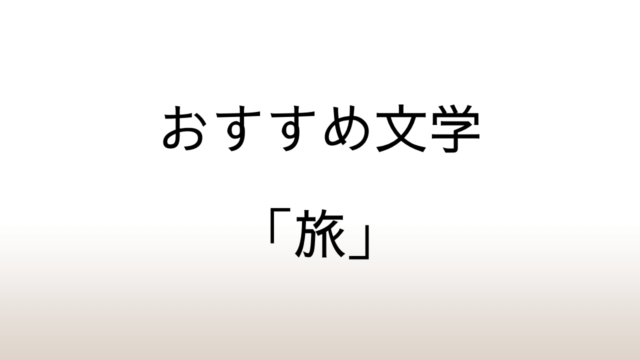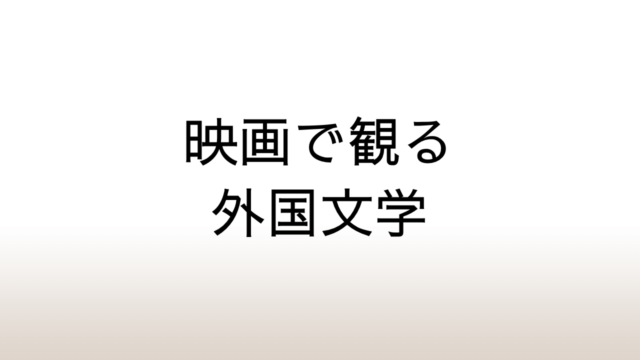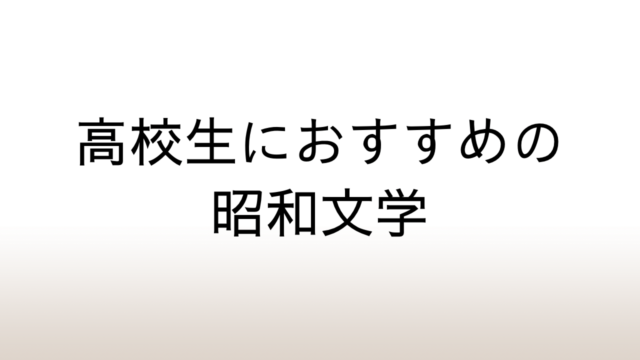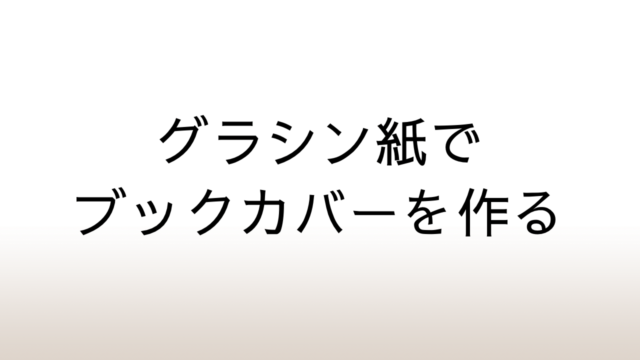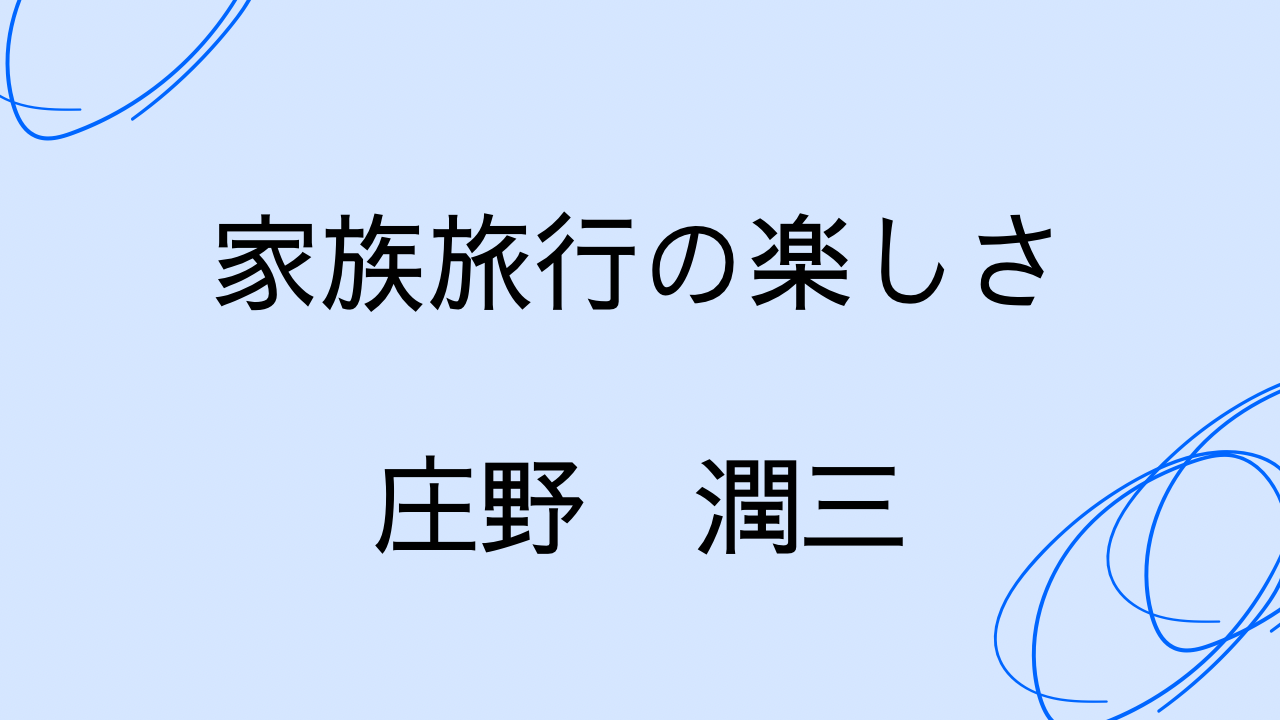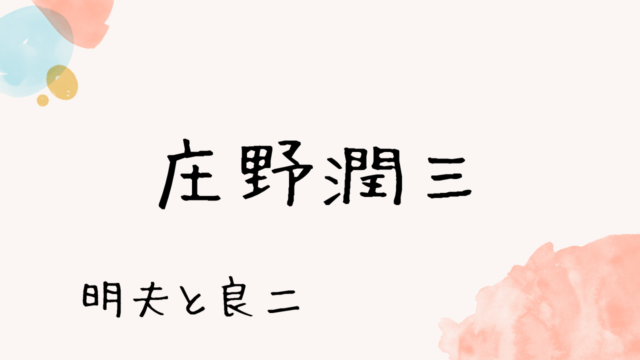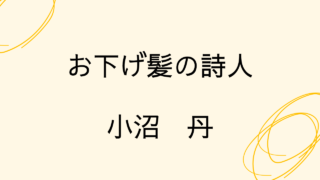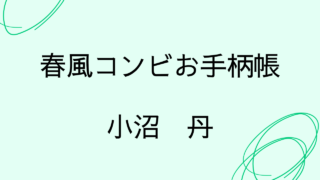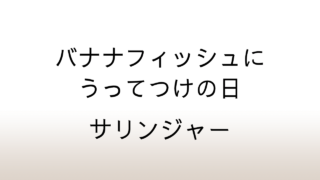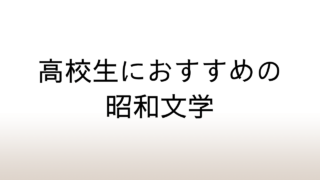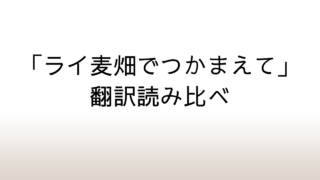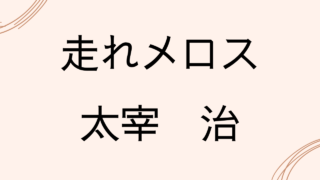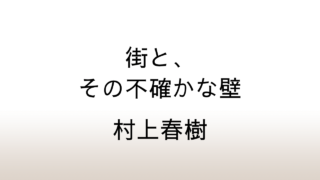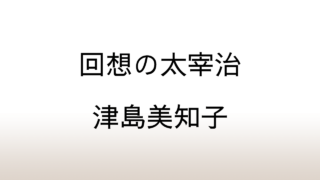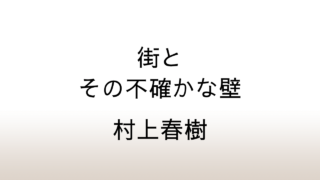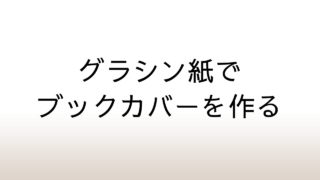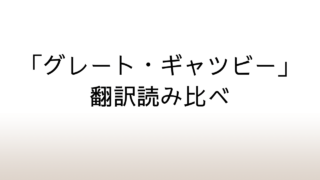庄野潤三「家族旅行の楽しさ」読了。
本作「家族旅行の楽しさ」は、1956年(昭和31年)12月『旅』に発表されたエッセイである。
この年、著者は35歳だった。
なお、作品集には収録されていない。
長女・夏子を連れた初めての家族旅行
本作「家族旅行の楽しさ」は、表題のとおり、家族旅行の楽しさについて綴ったもので、庄野家の例が紹介されている。
庄野家で最初に家族旅行をしたのは、結婚してから七年目のことだった。
庄野夫妻の結婚は、1946年(昭和21年)のことだから、七年目というと、1952年(昭和27年)ということになる。
私たちの家では長女が五つになり、二番目の男の子がヨチヨチ歩きが出来るようになっていた。それで下の子供は、家内の母親の家に預かってもらって、三人で出発した。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
長女・夏子は、1947年(昭和22年)10月生まれ、長男・龍也は、1951年(昭和26年)9月生まれである。
八月の初めであった。私たちが行ったのは三重県の青山高原である。私はその時まで大阪から二時間くらい離れたところに、そういう名前の土地があるということさえ知らなかった。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
青山高原行きを勧めてくれたのは、会社の同僚である。
私が前の年から勤めることになったその会社の同じ部に電鉄会社から来た人がいて、その人が非常に親切な世話好きの人で、私のために旅館もよく知っているところを取ってくれ、そこなら大丈夫だからと教えてくれたからだ。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
1951年(昭和26年)9月、庄野さんは大阪市立南高校を辞職し、朝日放送へ入社している。
ようやく生活が落ち着き始め、家族旅行もできるようになったということなのだろう。
もちろん、終戦後の混乱が収まり、社会全体が安定し始めていた時期でもあっただろうが。
妻子を放置して女性とダンス
庄野一家が泊まった旅館は温泉宿だったが、温度が低いので沸かし湯の温泉だった。
私は湯がいくらでも溢れて来るという感じがゆたかで好きだが、その点は残念であった。ふだん自分の家の一人用の湯槽に入っている人間は、こういう時には広々とした浴槽で思う存分身体を伸ばし他に客がいなければ静かに遊泳したい気持になるものである。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
夕食を運んできた女中は美人で、庄野さんは一人でかなり多くの酒を飲んだ、とある。
ホールがあると聞かされて行ってみると、蓄音機のそばに女性が一人いた。
私はこの女性と一緒に踊ったが、真夏のことであり、その上に大分お酒を飲んでいるので、汗が流れた。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
他に客はいないから、庄野さんと女性は二人だけで踊り続ける。
妻は、庄野さんが汗を拭くためのハンカチを、部屋まで取りに行かねばならない。
その間、妻と長女とは誰もいない広いホールの壁際の椅子に坐って、父のダンスを見物していた。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
家族旅行に出かけて、父親だけ酒を飲んで酔っ払って、ホールの女と踊り続けているんだから、現在だったら騒動になりそうな話である。
昭和20年代のこととはいえ、何とものんびりした話だ。
翌日、一家は赤目ノ滝を見学して帰阪する。
私たちはもうひと晩何処かに泊るだけの金を持っていたが、強行軍の勢いでそのまま大阪まで帰ってしまった。こうして話してみれば侘しい旅行のようであるが、それでも私たちには結構味わいのある旅行として未だに懐しく思い出される。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
その後、作家になるため上京した庄野さんは、子どもたちと一緒に、東京と大阪を何度も行ったり来たりするようになる。
親と違って子どもたちは、旅行に慣れた世代と言ってもいいだろう。
両親がもう生きていないので私のことを心配したりしないから、私は将来出来れば子供たちを連れて外国の土地を旅行してみたいと考えている。無論、万障繰り合わせての旅行であるが、夢は大きく持つ方がいい。(庄野潤三「家族旅行の楽しさ」)
ロックフェラー財団の招きを受けた庄野さんが、千壽子夫人と一緒にアメリカへ留学するのは、1957年(昭和32年)のことである。
子どもたちを連れての外国旅行は、どうやら実現することがなかったらしい。
作品名:家族旅行の楽しさ
著者:庄野潤三
誌名:旅
発行:1956/12
出版社:日本交通公社