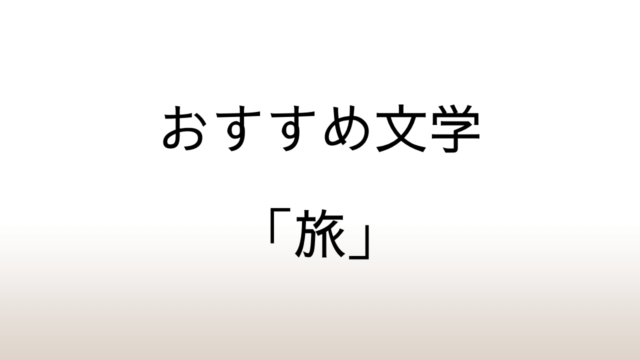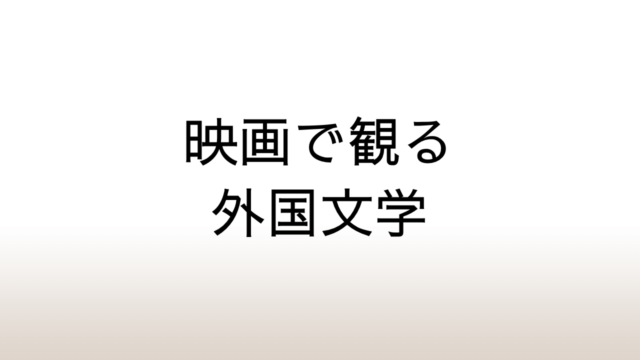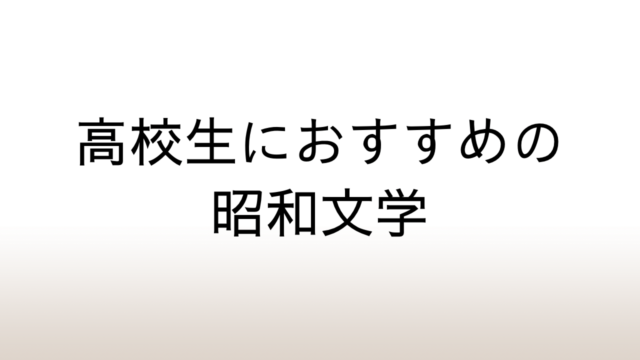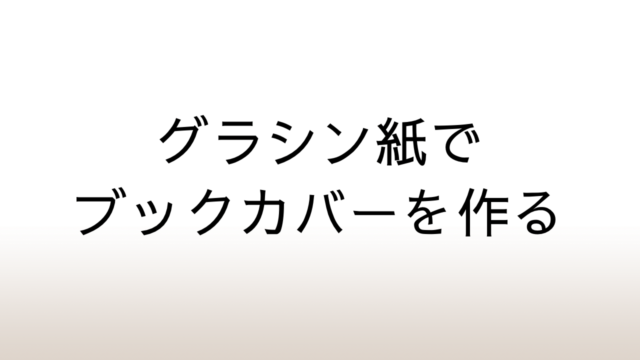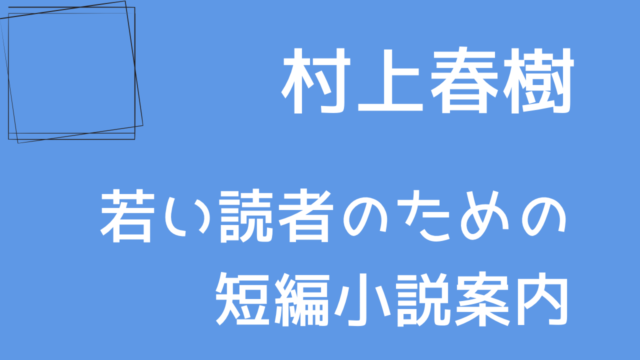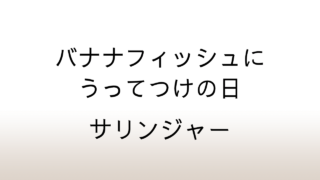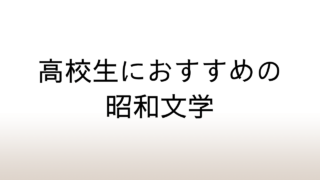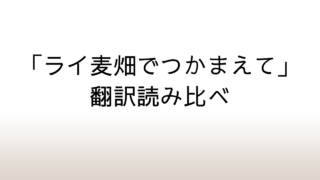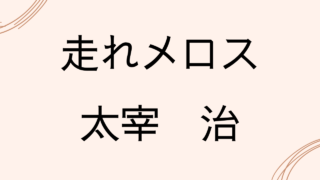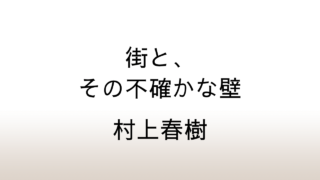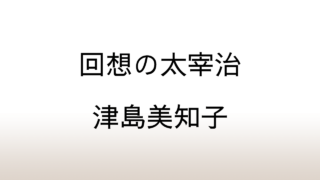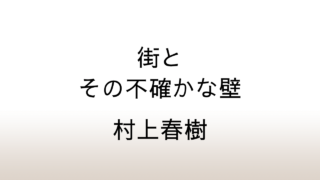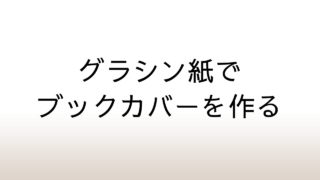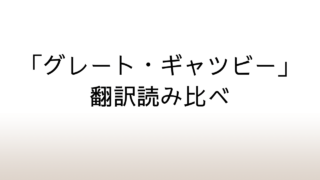庄野潤三『野鴨』の<十六>から<十八>まで。
連載で言えば六回目と思われるが、入学式が出てくるなど、季節は新しい春へと移った。
四季が繊細な感覚で描かれているところも、庄野さんの作品の楽しみのひとつ。
「貧乏だからね。こんなところで一生懸命、働いているんだよ」
『野鴨』の<十六>は、和子が住んでいる黍坂にいる鍛冶屋さんの話である。
会社の名前は鉄工所なのだが、近所の人は、みんな鍛冶屋と呼んでいる。
井村夫妻が、初めてだるま市へ行ったとき、お不動さんの境内へ上がる石段に近いあたりに、鍬や鋸、斧、火かき棒などを並べて売っている店があった。
親父さんとおかみさん、息子が二人に娘さんもいた。
ちょうど昼自分で、よく似た顔をした人たちが、重箱を開いてご飯を食べていた。
次に、井村夫妻が、子どもをおぶった和子を連れて、二度目のだるま市へ来たときも、同じ場所に同じ店が出ていた。
やっぱり家族で来ている。
そのとき、和子が突然「あ、鍛冶屋さん」と言ったので驚いた。
向うもびっくりしただろう。この一家が、和子の話に時折出て来る、近くの鍛冶屋とは思わなかった。「小父さん、来ているんですか」「貧乏だからね。こんなところで一生懸命、働いているんだよ」笑いながら、親父さんはそういった。そのあとでもう一回、「貧乏だから」といった。(庄野潤三「野鴨<十六>」)
この鍛冶屋の小父さんの「うちでは、飯は何杯食ってもいいが、噛んで食うな、呑んで食えといってるんだよ。時間がかかるから」という言葉がいい。
「鏡で自分の顔をみていたら、別の表情をしているように見えるの」
次の<十七>は、明夫と良二の話。
「良二が急に夜中に怖くなったといっていたな」という、井村の言葉から始まっている。
みんな寝てしまって、良二だけ、もと和子のいた部屋で机に向かっているとき、十二時を過ぎたころ、まったく何の理由もなしに、不意に怖くなってきたらしい。
「誰か、いや、誰かでなくて何かが、部屋にいて、見ているような気がした」と、良二は言った。
「鏡で自分の顔をみていたら、別の表情をしているように見えるの」「別の表情って、どんな表情だ」「自分と違うように見えるの」そんなときに鏡を覗き込むのがよくない。どうしてわざわざ鏡を見るのだろう。見る方が悪い。「何か分らないけど、そばへ来ていたような気がする」良二は、むしろしみじみとした声でそういった。(庄野潤三「野鴨<十六>」)
そんな良二の話から、井村は既に亡くなっている家族のことを思い出す。
それは、井村の両親と長兄だが、三人とも良二が生まれる前に亡くなっている。
しかし、もしも、それが「たましい」であるなら自由自在であって、計り知れない、精妙な動きをするだろう。
あるいは、亡くなった家族の誰かが、東京の我が家を訪れて、良二はそうした雰囲気を感じたのかもしれない。
<十八>は、パウンド・ケーキの話。
駅へ行く途中にある洋菓子屋でクッキーを二箱買ったら、おまけにパウンド・ケーキを一個くれた。
「パウンド・ケーキは、一ポンドの小麦粉に対してバター一ポンドを使うというところから、こういう名前が附いたらしい。つまり、それほどバターを多く使わないと、おいしいものが出来上がらない」という解説が、いかにも庄野さんらしい。
小さなケーキだから、和子にあげたら、和子は子どもと半分ずつ食べるといってふたつに割った。
その片割れをひとつ食べたところで、明夫が帰ってくる。
続いて、良二も帰ってくる。
二人とも予想より早く帰ってきたので、井村夫妻と和子は慌てた。
そもそも、小さなケーキひとつでは、家庭内で揉めごとになるだろうということで、和子に上げたものだったのだから。
まるで『サザエさん』のひとコマを見ているようで楽しい。
家庭内のユーモアな場面に惹かれた庄野さんらしい作品だと思った。
書名:野鴨
著者:庄野潤三
発行:1973/1/16
出版社:講談社