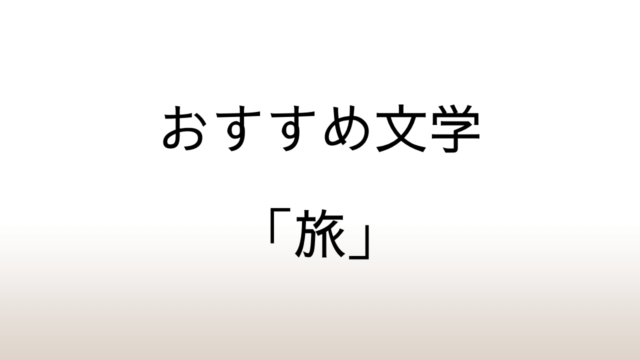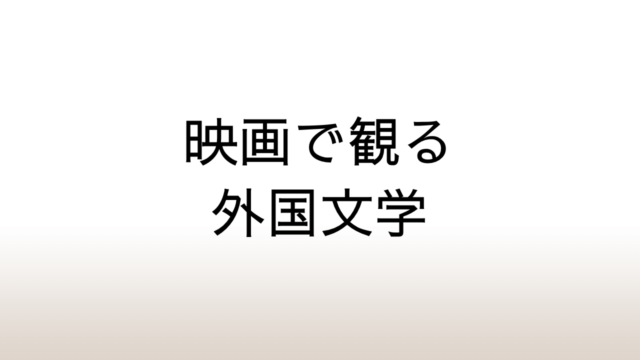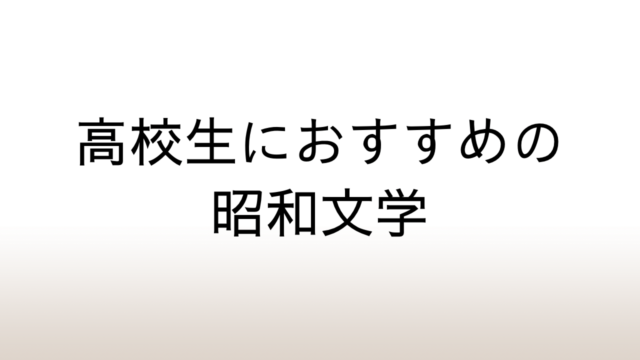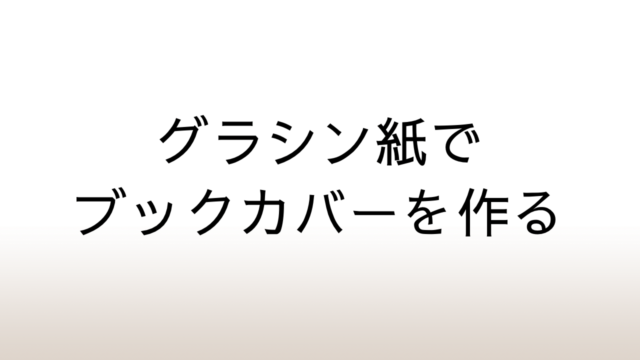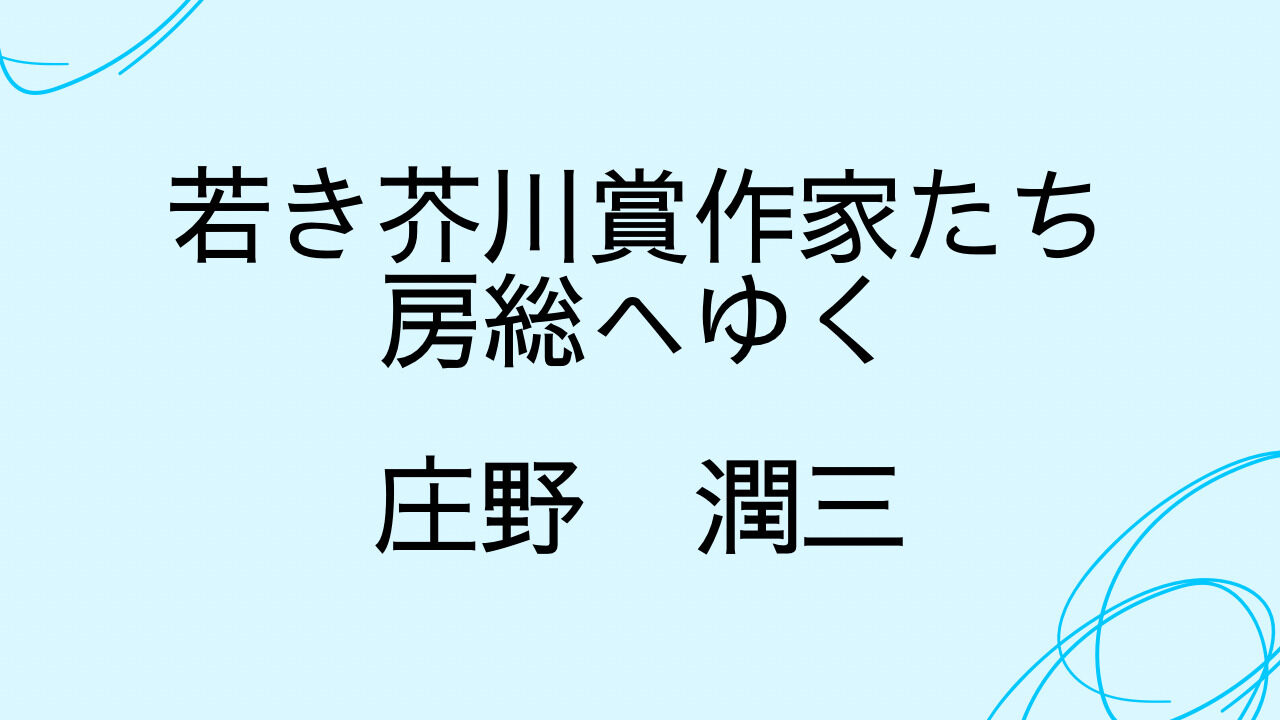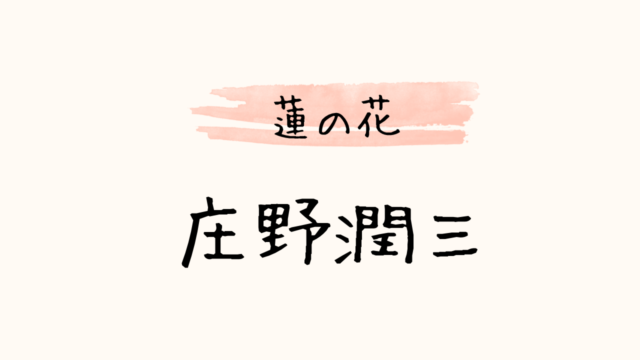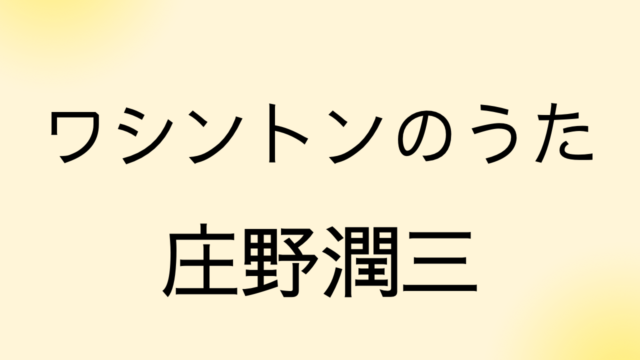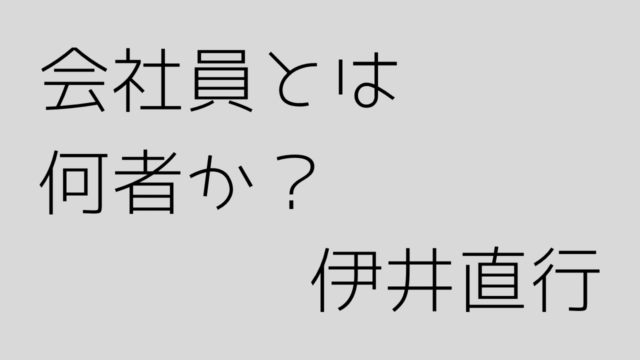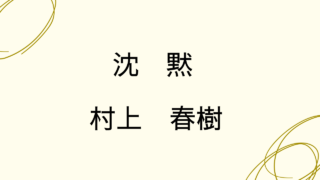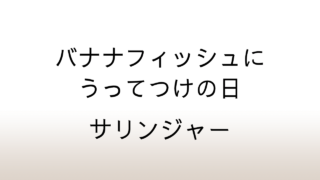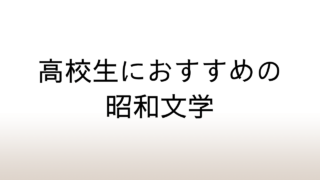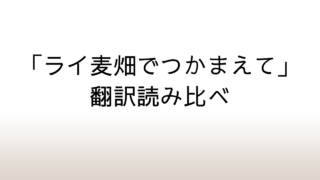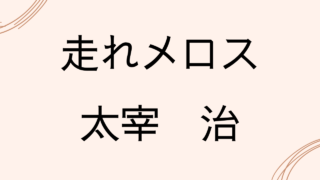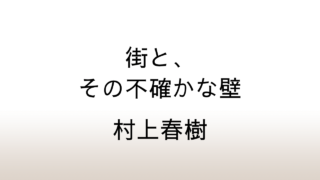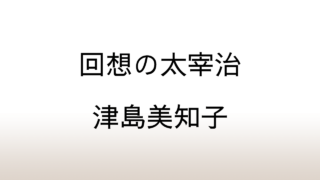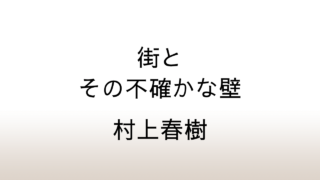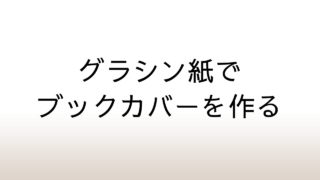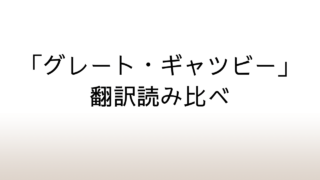庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」読了。
本作「若き芥川賞作家たち房総へゆく」は、1959年(昭和34年)3月『旅』に発表されたエッセイである。
この年、著者は38歳だった。
なお、作品集には収録されていない。
スティーヴンソン『旅は驢馬をつれて』
この時期、庄野さんは、多くの紀行文を書いている。
本人としても、紀行文を意識していた時期だったらしい。
ついでに云えば、現代の自分の文学が小説ばかり追い求めて、紀行文を忘れていることも私はかねがね不満に思っている。内容空疎な小説を読んでも、味気なくなるばかりだ。この文学界に活を入れるのは、すぐれた紀行文しかないと私は思っている。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
1959年(昭和34年)といえば、アメリカ留学の記録『ガンビア滞在記』を刊行した年である。
リアルな体験に、庄野さんが新しい道を見出していたことは想像に難くない。
私はスティーヴンスンの紀行文が好きだ。「旅は驢馬をつれて」などは大好きだ。中でもあの星空の下で野宿をするくだりは絶妙だと思う。あんな旅行を私はやってみたいと前から考えている。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
庄野さんの盟友・小沼丹が、R.L. スティーヴンソンの『旅は驢馬をつれて』の翻訳を家城書房から刊行したのは、1950年(昭和25年)のことである。
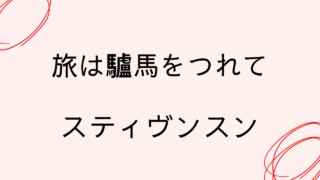
当然、庄野さんも小沼丹の『旅は驢馬をつれて』を読んでいたことだろう(なお、他に、吉田健一の訳あり。岩波文庫)。
旅に対する庄野さんの熱い思いが伝わってくるような文章だと思う。
一度も砂浜を踏むことなく、房総を去ってゆく
さて、本作は、そんな庄野さんの紀行文なのだが、このとき、雑誌の特集は「グループ旅行」だった。
庄野さんがグループ旅行をしたのは、一回だけしかないという。
それは、1953年(昭和28年)8月、ちょうど、安岡章太郎が「悪い仲間」で芥川賞を受賞したとした年の夏だった。
毎月一回集まって飲んでいた作家仲間たちが、千葉県鴨川に住んでいる近藤啓太郎の誘いで房総へ出かけた。
当日、両国の駅へ来たのは、安岡章太郎、島尾敏雄、三浦朱門、私の四人だけであった。行くと云っていた小島信夫はその頃教えていた高等学校の生徒の母親に頼まれて、その子の監督として軽井沢へついて行くことになり、欠席した。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
四人は、近藤啓太郎の案内で、鴨川の立派な旅館へと案内される。
窓の向こうは海だったが、誰も海岸へ出てみようという者がいない。
夕食の時間まで話をして、夕食とともに酒を飲み始めた。
このとき、仲間の吉行淳之介は、肺結核の外科手術を受けるために清瀬病院に入院していたが、友人たちのためにビール1ダースを寄贈してくれたという。
調子に乗った作家たちは、町へ飲みに出かける。
飲み屋には、近くの空軍基地にいるアメリカ兵たちと一緒になった。
ところが、不思議なもので、そういう意識が逆に作用して、みんなはとたんに卓をたたいて、「ハイ・ヌーン」などを歌い出した。外界の空気を吸ったせいもあるかも知れない。この卓を叩いて歌をうたう癖は、本来は安岡章太郎だけが持っている癖である。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
夜中になって宿に戻り、結局、彼らは一度も砂浜を踏むことなく、房総を去ってゆく。
紀行文というよりも、飲み会の記録だが、あいにく庄野さんに書けるグループ旅行というのは、この一回しかなかったのだから仕方ない。
最後に、庄野さんは、仲間たちに向けて、こんな言葉を綴っている。
荒々しい売文生活に負けずに作品の健康を守るためには、我々は旅に出なければならない。グループ旅行は難しいから、めいめい一人で、スティーヴンスンのやったように各自の驢馬を引き連れて旅行に出かけようではないか。(庄野潤三「若き芥川賞作家たち房総へゆく」)
当時、庄野さんは、作品を書くことができなくて苦悩の時期にあった。
名作「静物」を発表するのは、翌1960年(昭和35年)の6月のこと。
この紀行文には、文学に対する庄野さんのいろいろな思いを汲み取ることができるような気がした。
作品名:若き芥川賞作家たち房総へゆく
著者:庄野潤三
誌名:旅
発行:1959/03
出版社:日本交通公社