庄野潤三「蓮の花」読了。
本作「蓮の花」は、「文芸」昭和46年1月号に発表された短篇小説である。
作品集では『絵合せ』(1971、講談社)に収録された。
1960年代の後半、庄野さんは夏になると、家族を連れて広島の親戚のところまで海水浴に出かけた。
本作は、広島の海で遊んだときの体験を素材とした紀行小説である。
書き出しに「親戚の子供が三人、こちらの家族が四人、合せて七人」とあるから、庄野家の長女は参加できなかったのかもしれない(「そのころ会社勤めをしていて、今は結婚している姉」という表現が作品中にある)。
長女・夏子が結婚して庄野家を出ていくのは、1970年(昭和45年)5月のことである。すると、この小説は、1970年の夏が舞台になっているということだろう。
タイトルの作品名は、島へ向かう汽車の中で大きな蓮池を見たことに由来している。
「広い蓮池だな」「ほんとうですね」「これ、蓮根を取るための池だろうか」「そうかもしれませんね。こんなにたくさんあるのですから」と、庄野夫妻のゆったりとした会話が心地良い。
まるで日本昔話に出てくる、お爺さんとお婆さんの会話みたいだ。
その後に続く、<「お盆すぎると」ゆっくりした物いいの姪がいう。「新蓮根がとれる。いまごろの蓮根は、煮ると黒うなる」>という部分もいい。
短い散文と会話が、まるで詩のようなリズムを生み出している。
会話文の始まりの後に、いったん、話し手の描写を挿んで、それから会話文を続けるのが、庄野さんの文章の特徴のひとつだ。
汽車から乗り換えて、一行はバスに乗って海岸を走り続ける。
「よく浮びそうな潮水だな」彼は、ため息をつきそうになる。年を取ってゆくので、それでこんな海につかりたいと思うのだろうか。身体をやわらかな水にまかせて、沖の方をみたり、頭の真上の日を眩しく仰いでみたいと心がせくのはなぜだろう。(庄野潤三「蓮の花」)
物語の語り手が、こんなふうに「なぜだろう」とか「どうしてだろう」と、自分自身に問いかける文章も、庄野文学によく見られる手法だ。
そして、庄野さんは、その答えを書かないことで、読者の空想を膨らませようとしているらしい。
港に到着した一行は、渡し船で島へと渡り、釣りと海水浴を楽しむ。
夏休みの紀行小説の中に、突然、戦争の話が出てくる
彼らが宿泊した宿屋の入口には、古びた、目立たない表札がかかっていて、おとなしい字で「簡易旅館」と書いてあった。
この島で出会った人たちから、庄野さんはいろいろな話を聞きだしている。
宿屋のおばあちゃんからは、旅館を始めたときの様子について。
釣り船のじいさんからは、戦争へ行ったときの思い出について。
自分たちは工兵であった。工兵というのは、鉄砲よりつるはしの方が大事といわれるくらいで、土方のようなものだ。「ドカチン」と、この辺でいっている。ドカチンという言葉を聞いて、彼も細君ももうちょっとで笑いそうになった。(庄野潤三「蓮の池」)
じいさんは、戦争で召集になって、フィリピンへ行ったときのことを話してくれる。
「戦地へ行く船の中でも、向うに居る間でも」とじいさんはいった。「心に浮ぶのは、わが子のことだけです」どうしてそうなるのか分らない。いまもって不思議でならない。「親でもなければ、女房でもない」あれはどういうものですか、とじいさんはいいたげであった。(庄野潤三「蓮の池」)
夏休みの紀行小説の中に、突然、戦争の話が出てくる。
まるで聞き書き小説の一節のようだが、それが不自然な印象を与えないのは、こうした戦争体験でさえも、人々の肉体の一部となって、日常生活の中に溶け込んでいるためだろう。
日常の暮らしを描くことで、庄野さんは、人が生きていくうえでの悲しみや楽しみをあぶり出そうとしていたのかもしれない。
書名:絵合せ
著者:庄野潤三
発行:1971/5/24
出版社:講談社



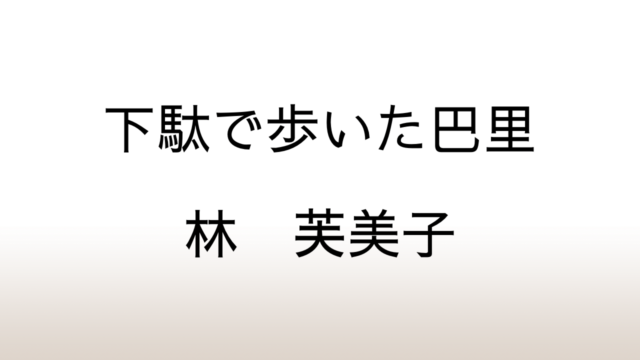


003-150x150.jpg)




