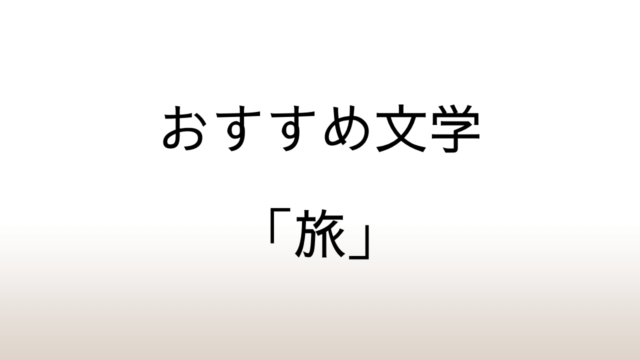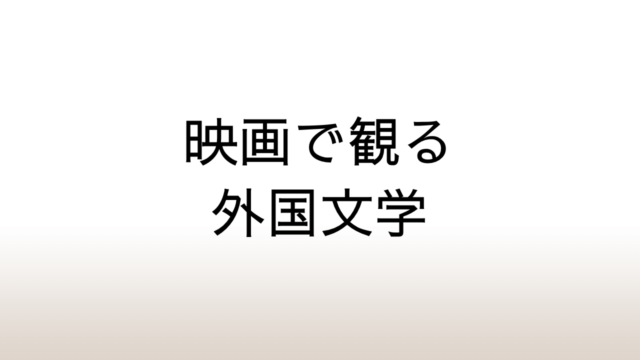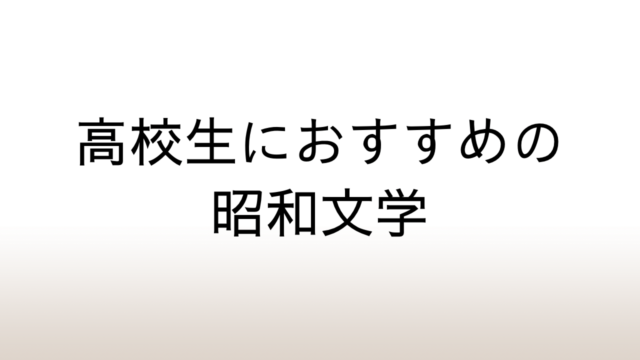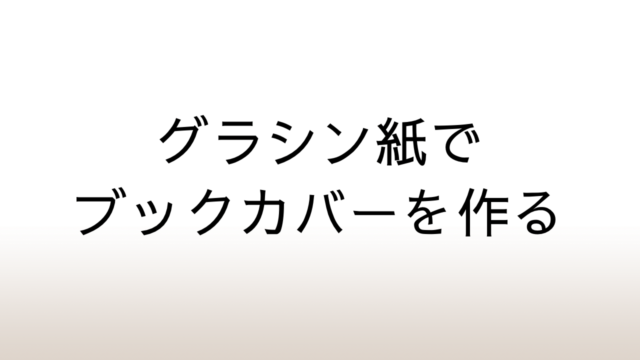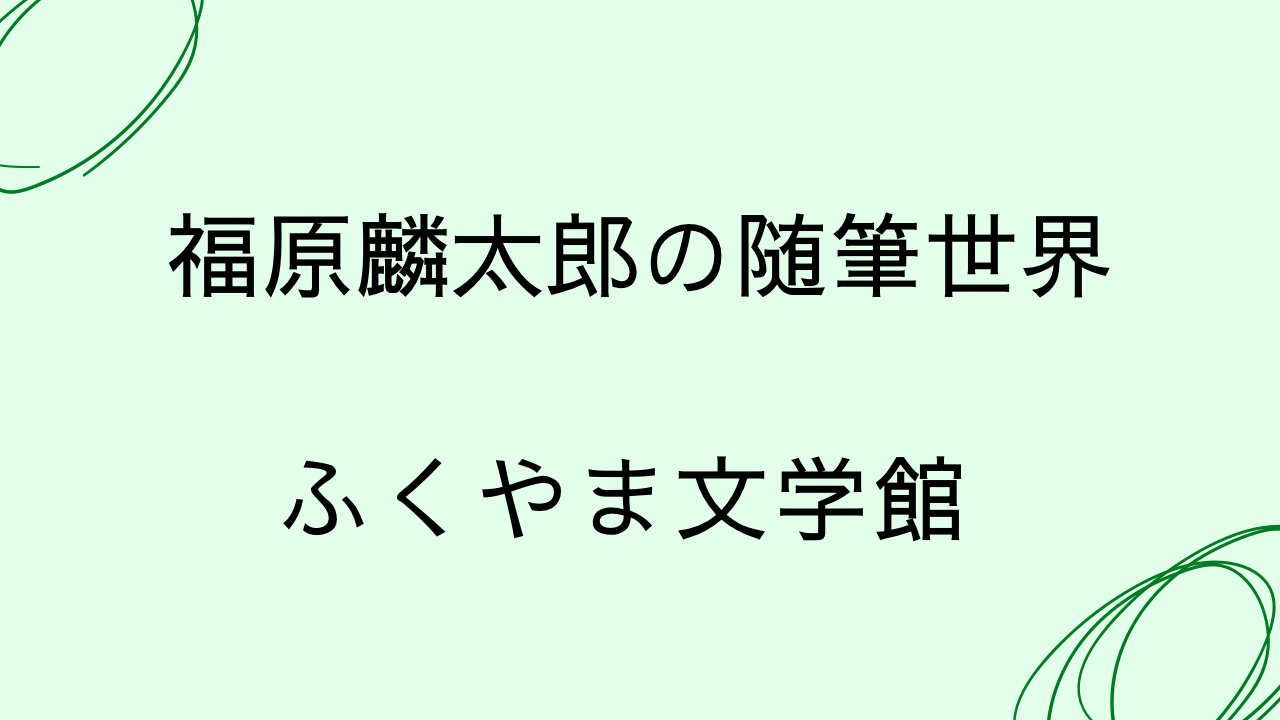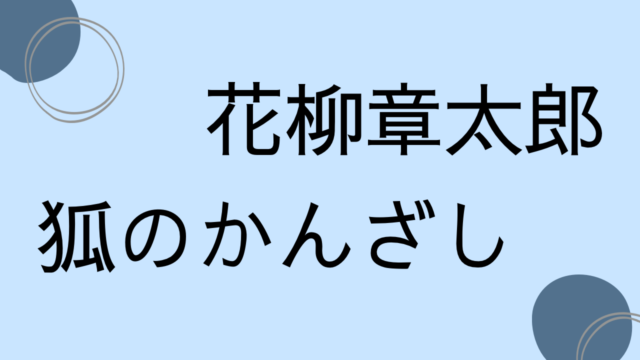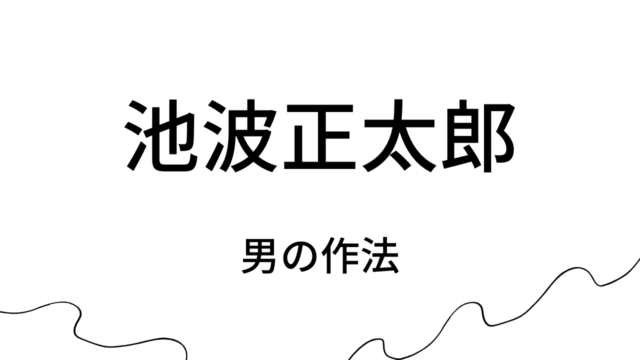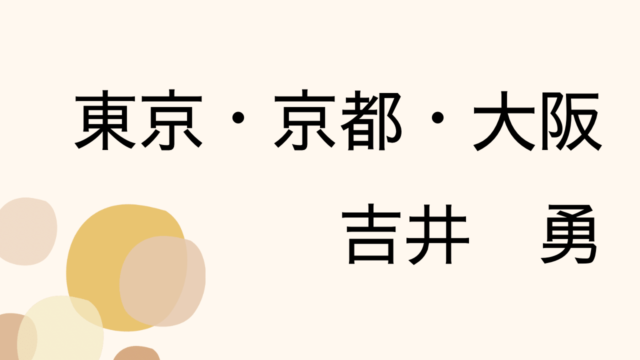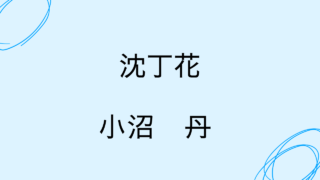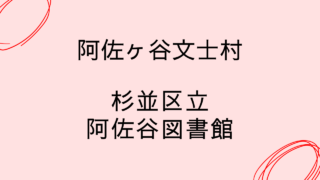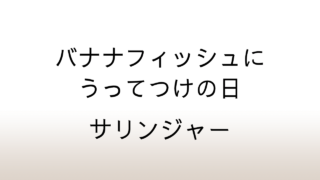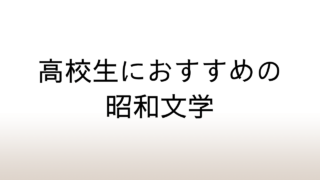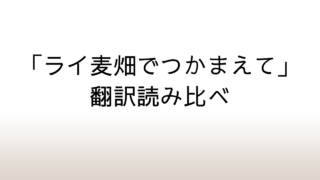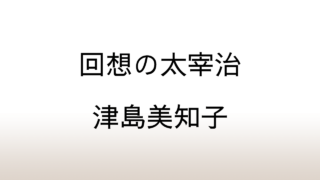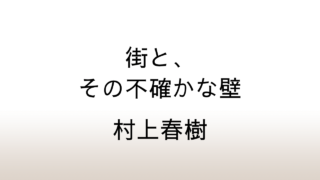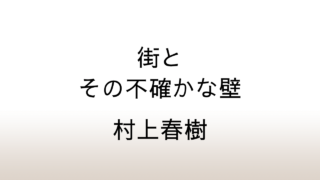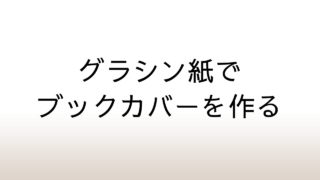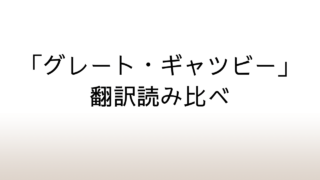ふくやま文学館「福原麟太郎の随筆世界」読了。
本作「福原麟太郎の随筆世界」は、2018年(平成30年)9月14日から11月25日までふくやま文学館で開催された特別企画展『福原麟太郎の随筆世界』の展覧会図録である。
なお、福原麟太郎は、1981年(昭和56年)1月、86歳で没している。
福原麟太郎という人間の魅力
久しぶりに、福原麟太郎の随筆を読んだ。
福原麟太郎の随筆は、こうして展覧会図録という形で、その断片に触れるだけでも、やはりいい。
人は、めいめいの一生を背負っている、その一生に出来ることを、着実に、正直に、親切に、やってゆけば良いのだ。他人の出来ることは他人の出来ることなのだ、自分に出来ることが自分に出来ることなのだ、ひとを羨むには及ばない、というようなことを私はいつのまにか考えるようになっていた。(福原麟太郎「この世に生きること」)
福原麟太郎の随筆は、とても分かりやすい。
主張がはっきりしているし、公明正大で堂々としている。
こういう文章は、自分に自信がなければ書けないものだろう。
つまり、人生に対して真っ正直なのだ。
最近、こんな随筆を書くことのできる大人はいないように思われる。
東京教育大学・東京文理科大学を停年退官したときの文章もいい。
大体は英文学の教師ということで通って来た。まことに怪しい英文学であった。しかしとにかく一所懸命、知っていることや考えたことを話して来たんだから、良いではないかと、一方では、自分を弁護したくもなる。しかし、ただ実際、力が及ばなかった。もっと秀れた人が、教師になるべきであった。学生諸君よ、許せ。(福原麟太郎「英文学に老いて」)
堂々と胸を張って「もっと秀れた人が、教師になるべきであった」と言える教師が、他にいただろうか。
こういう文章に触れたとき、福原麟太郎の随筆を好きだということは、福原麟太郎という人間そのものを好きなんだということに気付かされる。
福原麟太郎の随筆の魅力は、福原麟太郎という人間の魅力でもあるのだろう。
知的で、人間的で、面白くてたまらない
もちろん、福原麟太郎の随筆は、文章も素晴らしい。
福原は随筆を「まとまりのある人生観照から生れて居り、読んだ後に人生に対する慈しみを感じさせられるもの」(「随筆の文学」1926年10月)として捉えているが、福原の随筆は、年齢を重ねるにつれ、老いの自覚とともにしみじみとした味わい深いものが多く書かれていくことになる。(ふくやま文学館「福原麟太郎の随筆世界」)
福原麟太郎の随筆を読むと、年を取ることに怖いという感覚を持たなくなってしまう。
「早く老いたい」とまでは思わないまでも、老いることを楽しみたいという前向きな気持ちになることができる。
薄暗い住宅街の夜道、ところどころに街燈の立った淋しい道を、ぼんやりした老人の影法師が、犬をつれて、空を眺めながらゆるゆると散歩している。今夜も明日も。来年も再来年も。百年のさきにも、きっと。(福原麟太郎「散歩」)
「読んだ後に人生に対する慈しみを感じさせられるもの」とは、きっと、こういう文章を言うのだろう。
本作「福原麟太郎の随筆世界」では、福原麟太郎の生い立ちとともに、福原麟太郎をめぐる人々にも触れられている。
福原麟太郎が愛読したという夏目漱石も、その中にある。
『坊っちゃん』と『三四郎』をいちばんよく、何度となく、くりかえして読む。つまり、この二つが、私の愛読書である。『硝子戸の中』か何かに入っている、「クレーグ先生」も同様。つまり私は、自分が教師だから、教師の小説を喜んで読むのであろうか。それも深刻なのではなく、明るく皮肉で幸福なもの。『三四郎』のごときは、誰も悪人がいなくて、ぽかぽか小春日和で、知的で、人間的で、大学生活を中心の話で、面白くてたまらない。(福原麟太郎「漱石門外」)
「知的で、人間的で、」というところに、福原麟太郎らしいこだわりを感じる。
知的で、人間的であることが、何より福原麟太郎という教師にとって、大切なことだったのではないだろうか。
福原麟太郎の随筆もまた、知的で、人間的で、面白くてたまらないものだったからだ。
ところで、平田禿木の没後、福原麟太郎は『平田禿木追憶』(1943)に編集・刊行しているそうである。
いつか読んでみたいものだ。
書名:福原麟太郎の随筆世界
編集:ふくやま文学館
発行:2018/09/14