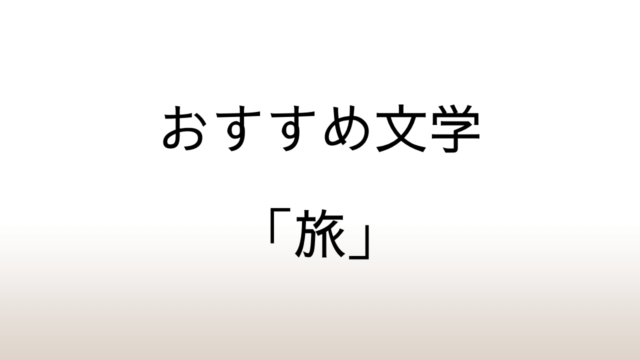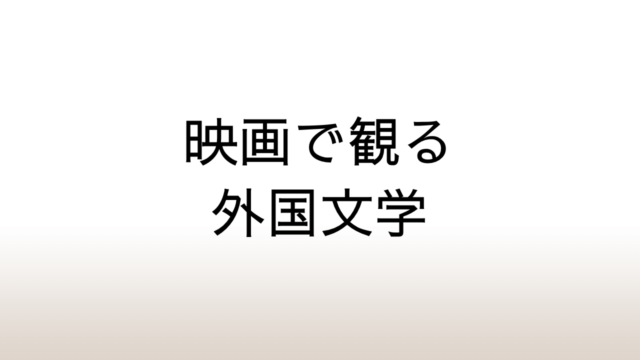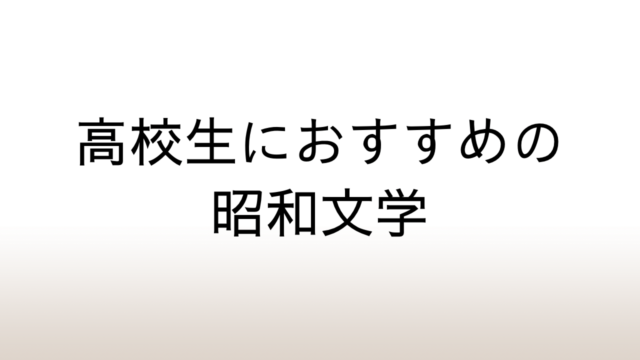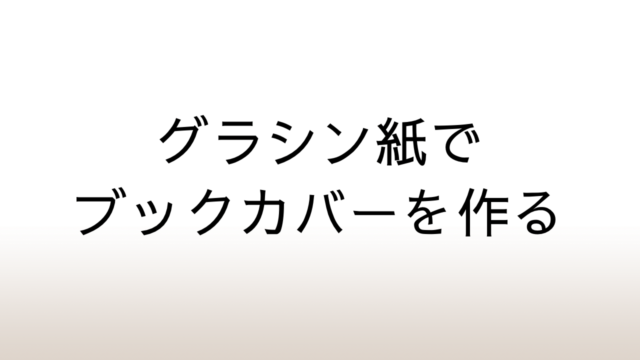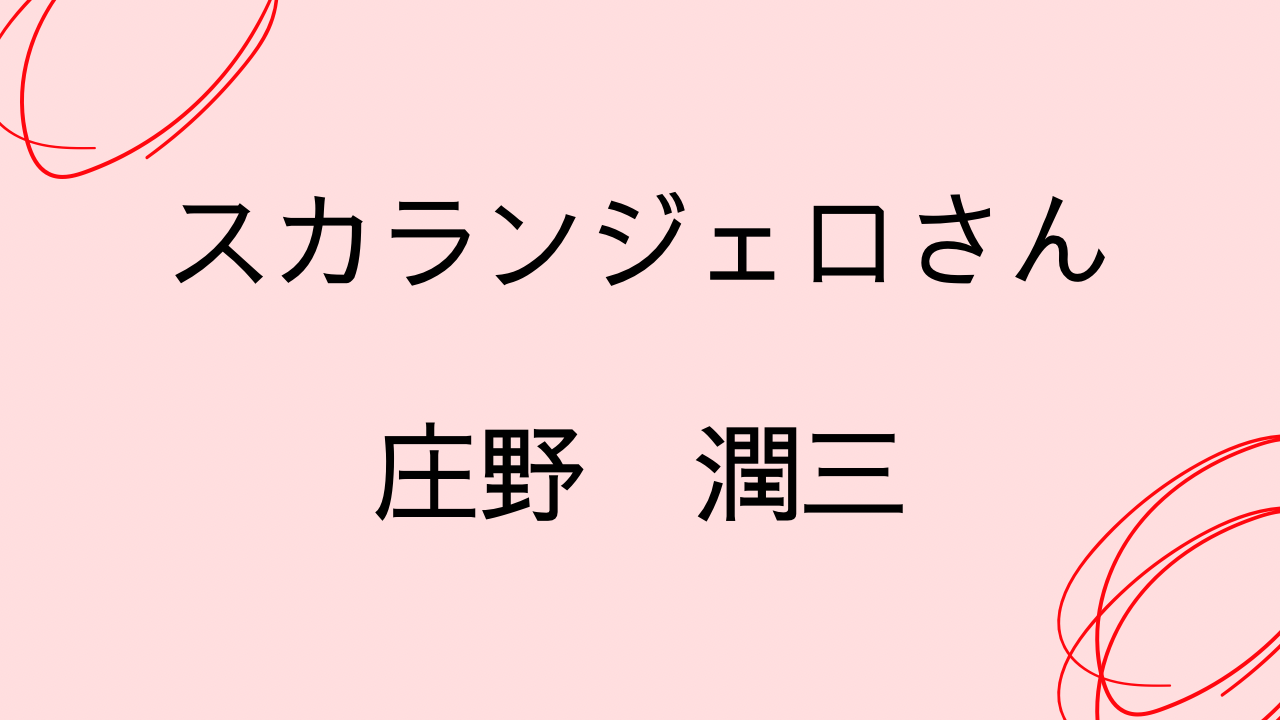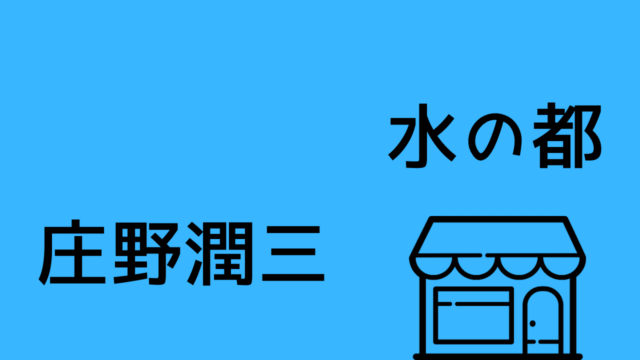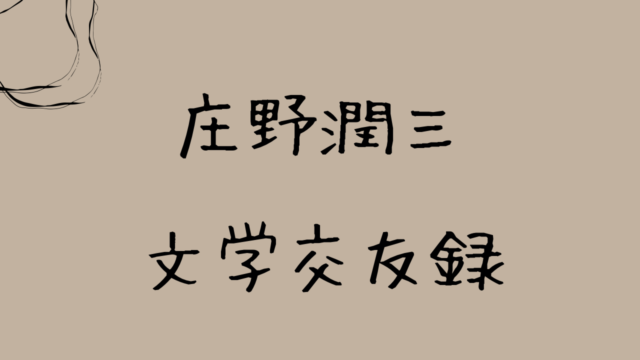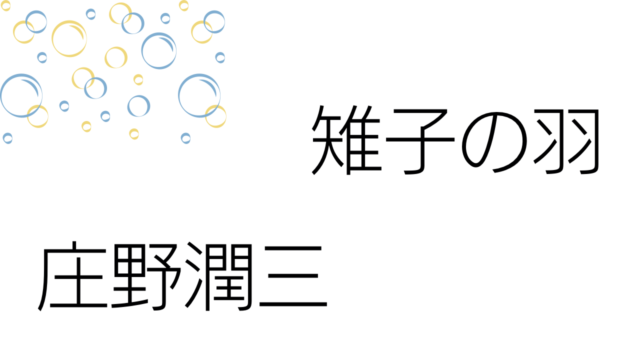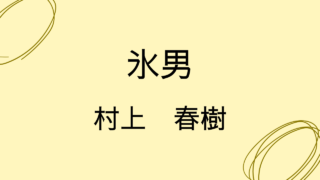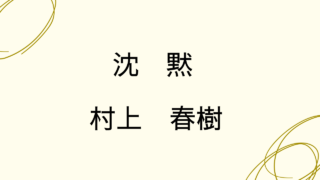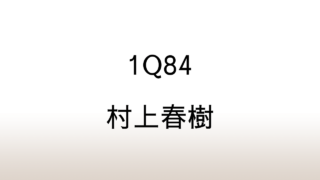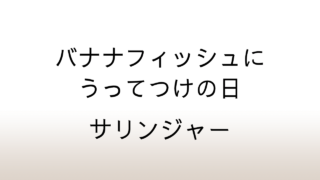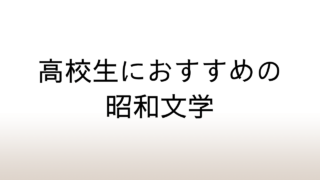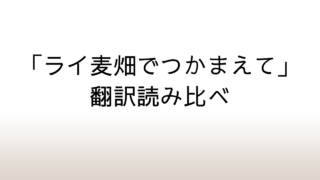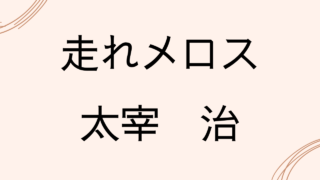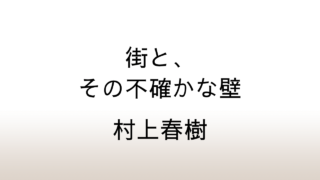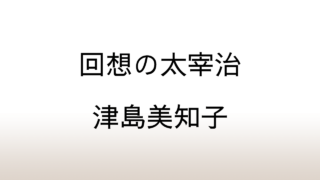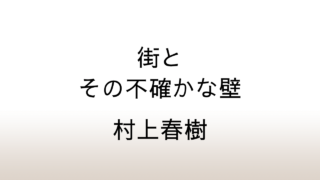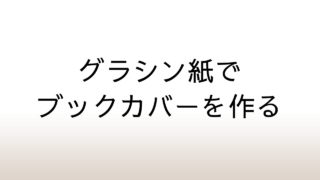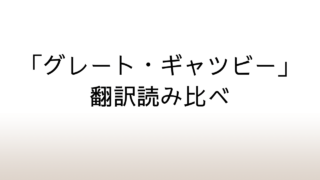庄野潤三「スカランジェロさん」読了。
本作「スカランジェロさん」は、1956年(昭和31年)5月『小学六年生』に発表された短編小説である。
この年、著者は35歳だった。
なお、作品集には収録されていない。
父親の心情が、娘の言葉によって語られる
本作「スカランジェロさん」は、家族小説である。
父と長女と長男の三人が、特急つばめ号に乗って大阪のおばあちゃんのところへ向かう。
特急列車の中で出会った外国人夫妻のことを書いた物語が、本作「スカランジェロさん」である。
ただし、この短編小説は、小学三年生の長女<あたし>の視点による一人称で書かれている。
庄野さんの家族小説のほとんどは、父親である庄野さん自身の目線から描かれているから、長女目線で描かれているということは、かなり大きな特徴と言えるだろう。
例えば、列車の中でお弁当を食べる場面。
あたしたちは持って来たおべんとうを食べました。おかあさんが入れてくれた折箱は、おとうさんのが大きくて、あたしと弟のは小さい折箱です。おとうさんはあせをいっぱいかきながら食べています。時々、ポケットからハンカチを出して顔のあせをふき、それから頭をくしゃくしゃとふいて、また食べています。そんなことをするので、おとうさんの髪の毛はぼうぼうです。ほのおがもえている時のように、全部の毛が上をむいています。(庄野潤三「スカランジェロさん」)
こんな姿を見られたら恥ずかしいから、食堂車に行った外国人夫妻が戻ってくる前に、お弁当を食べ終わってくれればいいのに、と願うところまで含めて、少女の言葉がおかしい。
おとうさんとスカランジェロさんが、英語で話をしているうちに、列車は大阪へ到着する。
おとうさんは握手をして、スカランジェロさんと別れました。あたしたちは前の駅からタクシーに乗りましたが、おとうさんは何時間も英語を話したので、すっかりくたびれてしまって、物をいう元気もなさそうに見えました。(庄野潤三「スカランジェロさん」)
普段は、あまり語られることのない父親の心情が、娘の言葉によって語られている。
娘の言葉を借りながらも、この物語は、やはり、父親目線で綴られた家族小説なのである。
家族が五人になった昭和31年
大阪へ向かう列車の中で、外国人夫妻と一緒になるエピソードは「イタリア風」という短編小説にも出てくる(1957年12月『文学界』)。
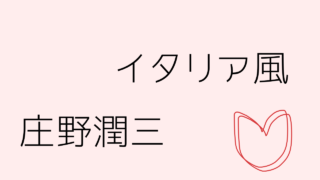
後に、アメリカへ留学したとき、庄野さんは、この外国人<アンジェリーニ氏>の家を訪ねるのだが、夫妻は既に離婚していた。
初期の庄野文学を思わせる、夫婦関係の崩壊を綴った物語である。
母親抜きで実家へ帰るのは、母親が次男の出産を控えていたからだ。
赤ちゃんは四月に生まれました。桃子という名前です。あたしは弟の信夫があまりいうことを聞かないので、女の赤ちゃんが生まれたらいいのになあと思っていたら女の赤ちゃんだったので、大よろこびでしたが、このごろではとてもやんちゃであたしは困っています。(庄野潤三「スカランジェロさん」)
実際の庄野家で、三番目の子どもは男の子なのだが、本作では<桃子>という名前の女の子が生まれている。
長女の願いを作品中に採り入れたということだろうか。
また、大阪へ行く特急の中で出会った「スカランジェロさん」という外国人の話は、『懐しきオハイオ』にも登場する。
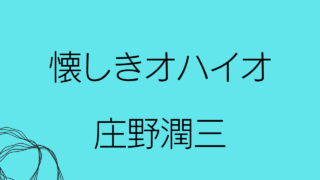
アメリカ留学しているとき、庄野さんは、スカランジェロさんの家を訪問しているので、このあたりのエピソードは「イタリア風」と同じときのものだろう。
ちなみに、家族三人で大阪へ帰郷するのは、1955年(昭和30年)の夏で、この年の1月、庄野さんは「プールサイド小景」で芥川賞を受賞したばかりだった。
あたしの家が大阪から東京へひっこしたのは、あたしが幼稚園にいた時分です。それから毎年、お正月の休みや春休みや夏休みには、家族全部で大阪のおばあちゃんのところへ帰ることにしているのです。(庄野潤三「スカランジェロさん」)
この夏、長女・夏子は小学三年生、長男・龍也は幼稚園(三歳)で、次男・和也は、翌1956年(昭和31年)の2月に誕生している。
本作「スカランジェロさん」が学習誌『小学六年生』五月号に発表されたとき、次男・和也は、まだ生まれたばかりだったのだ。
そういう意味で、本作は、家族が五人になったことを記念する作品ということも言えそうだ。
なお、庄野夫妻が、ロックフェラー財団の支援を受けてアメリカへ留学するのは、さらに翌年の1957年(昭和32年)の夏のことである。
作品名:スカランジェロさん
著者:庄野潤三
雑誌名:小学六年生
発行:1961/05
出版社:小学館