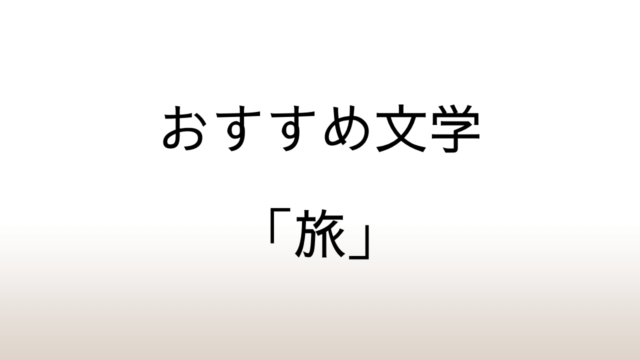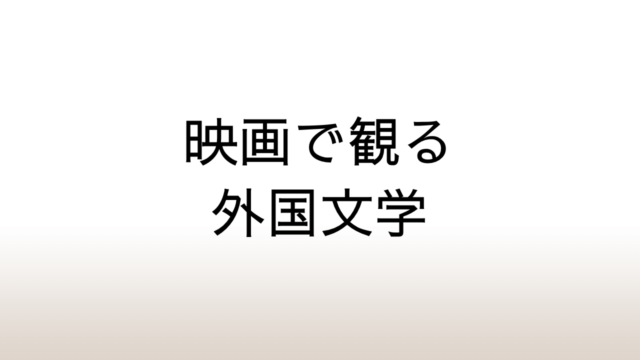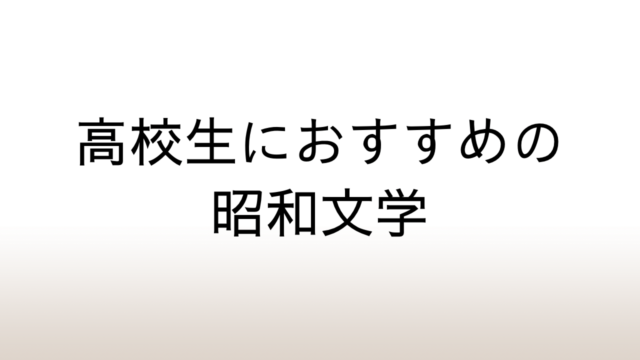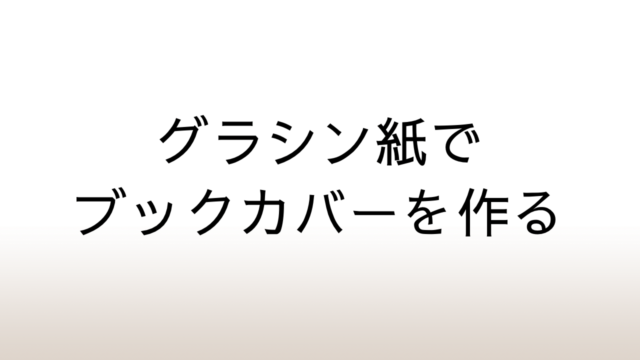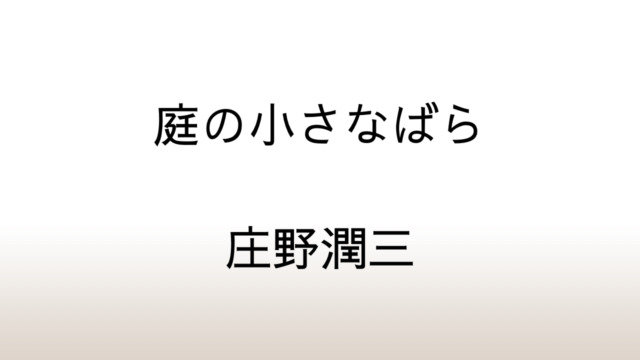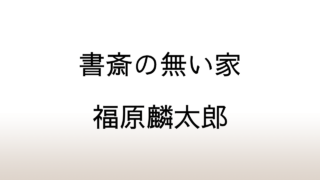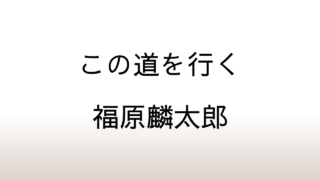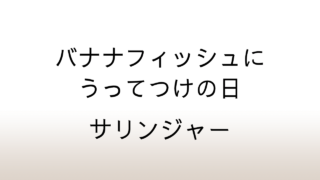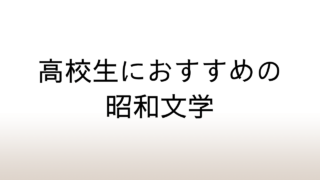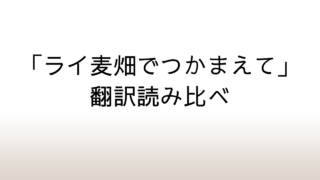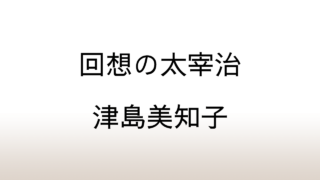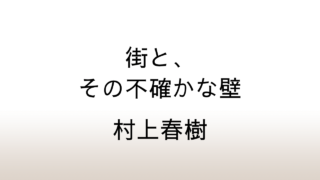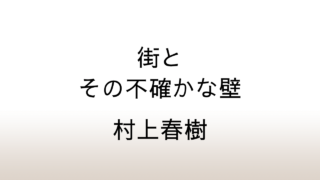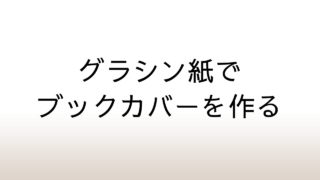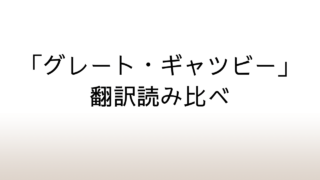庄野潤三「絵合せ」読了。
本作「絵合せ」は、1970年(昭和45年)11月『群像』に発表された短篇小説である。
この年、著者は49歳だった。
作品集としては、1971年(昭和46年)5月に講談社から刊行された『絵合せ』に収録されている。
1971年(昭和46年)、第24回「野間文芸賞」受賞。
五人家族の物語のクライマックス
絵合せというのは、一枚のイラストを3枚にカットした札で遊ぶカードゲームのこと。
3枚1組の絵を揃えたら得点となり、総合計点で勝者を決定する。
昭和時代には定番だったらしく、ヤフオクで探すと、当時の絵合せカードがたくさん見つかる。
この物語の一家が夢中になっている絵合せカードは、長女・和子が、お正月休みに駅の近くの本屋で本を買ったときに、おまけで貰ってきたものだ。
和子が買った『ニワトリ号一番のり』は、イギリスの詩人ジョン・メイスフィールドの書いた児童文学小説で、1967年(昭和42年)9月に福音館書店から刊行されている。
クリスマス・プレゼントとして和子は、この本を次男の良二に贈った(長男の明夫にはサッカーの靴一足分のお金をあげた)。
たくさんの帆に風を受けて海の上を進んでゆく船が、表紙に描かれている。海が好きで船の会社に入ったくらいの和子だから、「あ、これがいい」と思ったのだろう。(庄野潤三「絵合せ」)
良二は中学二年生で、明夫は予備校生になったばかり。
長女・和子の結婚を目前に控えて、五人家族は万障繰り合わせて、毎晩の絵合せゲームに参加している。
本作「絵合せ」は、そんな五人家族の暮らしを、父親である著者(庄野さんだろう)の視点から描いた家族物語である。
単行本のあとがきで、庄野さんは「取りとめのない、のんびりした話が次から次へと出て来る」と綴っているが、もちろん、この作品は、取りとめのないエピソードを無秩序に並べただけの作品ではない。
全部で二十の断章によって構成されている「絵合せ」は、それぞれのエピソードの組み合わせから、一人娘を嫁に出す父親の不安と寂しさを暗示的に浮かび上がらせている。
そして、その感傷は、決して主観的に描かれることがないというところに、この作品の優れたポイントがある。
例えば、大きすぎる上着を着て、中学校の制帽を被った和子がジェルソミーナの物真似をするのを見て、家族は盛り上がるが、そこに娘の将来を憂う父親の不安はなかっただろうか。
「その帽子に」と明夫がうしろからいった。「お金を入れてもらうんだよ」「あ、そうか」「ジェルソミーナだな」「そうそう、ジェルソミーナそっくり」(庄野潤三「絵合せ」)
ジェルソミーナは、乱暴者のザンパノと結婚をして哀れな末路を迎える不幸な女性の象徴だ(フェリーニ監督のイタリア映画『道』のヒロインで、フェリーニの妻ジュリエッタ・マシーナが演じた)。
ジェルソミーナの真似をして家族を笑わせる和子の姿に、父親が、ジェルソミーナの悲しい境遇を重ね合わせたとしても、決して不思議なこととは言えない。
それは、和子の会社にやって来たブラジル人夫婦のエピソードにも共通している。
帰国の船の件で相談に来た夫婦は、感情豊かな妻と、無関心の夫とのコントラストが顕著で、そこに、本来は他人である夫婦関係の不安が浮き彫りにされている。
「それで」と彼は聞いた。「主人の方は何をしているんだ」「だまっているの」と和子はいった。「離れたところの椅子に腰を下して」「何もいわないのか」「無表情なの。まるで無関係なひとみたいな顔をしているの」(庄野潤三「絵合せ」)
家族間の笑い話の陰で、娘を案ずる父親の不安が顔を覗かせている。
無論、そこには、初めての結婚を控えた長女自身の不安に対する共感もあっただろう(マリッジブルー)。
会社で見つけた小さな蓑虫をマッチ箱に入れて持ち帰った和子は、公園の葉桜の根元に、蓑虫をそっと置いてやる。
「からになったマッチ箱は」と和子は最後にいった。「家へ帰って、ごみ入れのバケツへ捨てたの」(庄野潤三「絵合せ」)
あと三日で会社を辞める和子は、小さな蓑虫に自分自身の姿を重ね合わせていたのだろうか。
あるいは、良二が歌った「赤い河の谷」という英語の歌のエピソード。
旅立つ若者がいる。もうすぐ出発しようとしている。あなたが行ったら、どんなにこの谷間はさびしくなるだろう。そんなに急いで別れを告げないでほしい。そういうふうに娘が頼んでいる。(庄野潤三「絵合せ」)
旅立つ若者に、両親と弟の良二は、もうすぐ嫁ぐ娘(姉)の姿を見ていたのだ。
和子が会社を辞めたとき、父親は、和子の入社が決まって、近くの小さな神社へ良二と三人でお参りに行った夕方のことを思い出す。
「雨でうすくけむった丘が、きれいだったな」あれから三年たった。ずいぶんあの時は、和子は喜んでいた。拝殿の前で長いこと、念入りに拝んでいた。だが、その会社勤めも、もう終りになった。(庄野潤三「絵合せ」)
新婚の家へ荷物を運び出した和子の部屋を見た両親が「ここは図書室になる」とか「誰か泊まって頂く時には、お客さんの寝室になりますわ」などと話しているのを聞いて、和子は「蚤が出るよ」とつぶやく。
まだ私はこの家の子供です。みんなと一緒に御飯も食べるし、片附けもするし、掃除もします。夜になると、このベッドで(もう九年も寝ている私のベッドで)心安らかに寝ているのです。どうか、そんな気の早いことを二人で話さないで下さい──和子のいった「蚤」とは、どうやらそういう意味もあるらしい。(庄野潤三「絵合せ」)
和子の結婚が近づく家族の日常は、おまけで貰った「絵合せゲーム」を舞台回しとして綴られていく。
父親の不安、母親の期待、弟たちの寂しさ。
「取りとめのない、のんびりした話」の組み合わせで描かれているのは、つまり、家族の絆の強さである。
『夕べの雲』に代表される五人家族の物語のクライマックスが、この「絵合せ」という短篇小説だったのだろう(実際に和子が結婚するのは、次作『明夫と良二』)。
取りとめのない話の中に含まれている象徴性
本作「絵合せ」は、娘を嫁に出す父親の不安を暗示的に描いた物語だが、その後の和子が幸せな道を歩むことは、現代の読者は既に知っているとおりである。
1996年(平成8年)7月に「神奈川近代文学館」に発表された随筆「『絵合せ』を読む」で、庄野さんは、結婚した和子の、その後を紹介している(随筆集『野菜讃歌』所収)。
「絵合せ」の長女は、はじめ私たちの家から歩いて三十分くらいのところにある借家にいたが、子供もふえたので、小田原に近い南足柄市の山の中腹に家を建てて移り住んだ。四人の男の子の母親で、今年、結婚二十五年の銀婚式を迎えた。あとの二人──長男と次男もそれぞれ二児の父となり、「絵合せ」の登場人物でもとの家に残っているのは、私と妻の二人となった。(庄野潤三「『絵合せ』を読む」)
南足柄市で暮らす長女は「なつ子」として、晩年の庄野文学に欠かすことのできないメインキャラクターとなるが、その原点が「絵合せ」だったと考えることは、極めて感慨深いことだと思う。
ちなみに、なつ子の結婚25周年のエピソードは、『貝がらと海の音』で読むことができる(お祝いに、庄野夫人の持っていた真珠のイヤリングをもらった)。
ここで注目したいのは、両親ともうすぐ結婚する長女と予備校生の長男と中学二年生の次男という五人家族が、毎晩欠かさず「絵合せ」というカードゲームに熱中しているという家族関係だ。
いくら山の上の一軒家で暮らしているといっても、昭和時代のすべての家族が、このように濃密なコミュニケーションを構築していたとは、到底思われない。
一家のコミュニケーション・ツールは、絵合せカード以外にもあった。
日曜日の晩、明りを消した書斎でレコードをきいていると、細君が「去年と同じね」といった。「四人がここでレコードをきいていて、明夫だけ向うで勉強している」(庄野潤三「絵合せ」)
明夫が勉強しているのは、高校3年生(受験生)だからで、すべての受験に失敗した明夫は、やがて、浪人生となるのだが、彼が、悲しき受験生となるまでは、つまり、五人家族が揃ってレコード鑑賞を楽しむというのが、一家のルーティン・イベントだった。
レコード鑑賞の習慣は、絵合せゲームのように一時的なものではなく、長く続いたものだったから、後の「夫婦の晩年シリーズ」で振り返られる場面も多い(「おともだーち」というオペラなど)。
山の上にある一家の住宅は、麓の駅から遠くて暗いので、明夫と良二が交替で、会社帰りの和子を迎えに行くルールとなっている。
絵合せカードを貰ったときに買った本(『ニワトリ号の一番のり』)には、日頃のお礼という気持ちも込められていたのだが、本作「絵合せ」を始めとする庄野文学を支えているのは、長い時間をかけて培われた家族間の強固な絆である。
1977年(昭和52年)1月に刊行された講談社文庫版『絵合せ』では、単行本『絵合せ』から収録作品が大きく変更された。
講談社文庫版『絵合せ』では、和子と明夫と良二という三人姉弟を中心とした五人家族の物語だけが、特にセレクトされて収録されたからだ(単行本『絵合せ』に入っていた「蓮の花」や「鉄の串」「グランド・キャニオン」などといった作品は、そのため文庫本で読むことはできない)。
『夕べの雲』以降の一家の日常を読むことができる文庫版『絵合せ』は、山の上の家で暮らす五人家族の物語を愛する読者にとっては、だから、欠かすことのできない大切な一冊となっている(この方針は講談社文芸文庫版でも踏襲された)。
とりとめのない日常生活の延長線上に、長女・和子の結婚があり、五人家族の一角が失われることの寂しさが、本作「絵合せ」の重要な主旋律となっているということを忘れてはならない。
なくなった絵合せカードを探していた明夫が、テレビの上にあるカードを見つけて安心する場面がある。
「では、かけます」と和子がいった。ふたたび部屋は暗くなり、音楽は始まった。その中で明夫のひとりごとが聞えた。「もう出て来ないかと、思った」(庄野潤三「絵合せ」)」
何気ない長男のつぶやきも、娘を嫁に送り出す父親には、重大な象徴性を持った言葉に聴こえてくる。
「もう出て来ないかと、思った」という短い台詞にも、娘の将来を案じる父親の不安が投影されているのだ。
複数の断片的なエピソードから父親の不安を浮かび上がらせたこの物語は、しかし、最後には、明るい兆しを見せて終わる。
彼は笑って、「お金、持って来たのか」その声は誰にも聞えず、ひとりごとをいったのと同じことになった。向うの部屋では、細君がアイロンを台に置く音がする。空が明るくなって来て、雨はもう殆ど上りかけた。(庄野潤三「絵合せ」)」
雨模様の空は、もちろん、父親の心境を象徴したものだが、「空が明るくなって来て、雨はもう殆ど上りかけた」という最後の一文が、娘の結婚を祝福する父親の喜びへと繋がっていく。
庄野文学では、庶民の日常生活が素材となっているから、取りとめのない話が多いように思われているが、取りとめのない話の中に象徴性が含まれていることに注意しなければならない。
むしろ、喜びや悲しみといった人間の普遍的な感情を、庶民の日常生活に昇華したところにこそ、庄野文学の重大な特徴があるのではないだろうか。
作品名:絵合せ
著者:庄野潤三
書名:絵合せ
発行:1989/06/10
出版社:講談社文芸文庫