庄野潤三「砂金」読了。
本作「砂金」は、「群像」昭和49年1月号に発表された短篇小説である。
作品集では、『休みのあくる日』(1975、新潮社)に収録された。
誰にも気付かれずに砂金を見つけた人のように
崖の坂道が出来はじめの頃は、少し勢いよく雨が降ろうものなら、土がえぐれて、どんなふうにそこを水が走っておりたか、一目で分るような跡が残った。
赤土の粘土があらわれ、河床そっくりなのを見ると、つい、「大峡谷じゃないか、まるで」といいたくなる。
物語の語り手である「私」(庄野さん自身だろう)は、しゃがみ込んで、水溜まりの底にある砂鉄を触ってみた。
誰にも気付かれずに砂金を見つけた人のように。
そして、ずっと以前に見た「シティ・オブ・ゴールド」という、不思議な味わいのある短編映画を思い出した。
それは、庄野さんがまだ、アメリカ中部の小さな大学町ガンビアに妻と二人でいたときのことだから、十五、六年前のことになる。
隣町マウント・バーノンにある映画館まで、庄野夫妻は、たびたび映画を観に出かけた。
人口一万五千人の町には、「マウント・バーノン劇場」という映画館がひとつあった。
客はあまり入っていなくて、大抵の場合、ひっそりとしていたらしい。
ここで庄野さんは、かつて我が家へ招待したことのある大学生と偶然に出会った。
この友達は勉強が嫌いで、寝るのと何かして遊ぶのが好きである。部屋で静かに本を読んでいることがない。試験になっても勉強しない。ロドニイがやかましくいうと、仕方なしにタイプライターに向うが、ラジオをかけっ放しにして打っている。それも、すぐにピンポンをしに行ったり、テレビをみに行ったりして、長続きしない。(庄野潤三「砂金」)
どうやら、彼は、マウント・バーノン劇場の映写技師が休暇を取るようなとき、代理の技師として映画館で働いているらしい。
庄野夫妻が「シティ・オブ・ゴールド」を観たのは、臨時の映写技師をしている、この風変わりな学生に出会う一月前—三月下旬の晩であった。
その夜、二人は「かくて神は女をつくり給えり」という、フランスの若い女優の主演映画を観に来たのだが、その前にあった短篇映画の方が良かった。
「私」の生れた何とかいう町が、先ず映る。
さびれた、小さな町だ。
「私」の父は、金を求めてこの町へやって来た、何百という男の中の一人である。
昔の町が映し出される。何という夥しい男の数だろう。通りに溢れ、カメラの方を見ているのは、みんな屈強な男だ。髭を生やしているのも、髭を生やしていないのもいるが、どれも面魂を持っている。(庄野潤三「砂金」)
金ははじめのうち出た。
やがて無くなり、男がひしめき合ったまま、この町は廃れていった。
小説ともエッセイとも受け取ることのできる作品
冒頭の雨上りの崖の坂道の場面を読んだとき、真っ先に思い出したのは、福原麟太郎の「治水」というエッセイである。
福原さんの、このエッセイを、庄野さんは好きだった。
似たような場面から入りながら、小説家である庄野さんの作品は、起伏に富んだ物語へと発展していく。
水溜まりの底に沈んでいた砂金を見つけた話から、ガンビア時代の思い出話へとつながっていく。
映画館で働いていた大学生の話から、妻と一緒に観た映画の話へとつながっていく。
この短篇小説は、そのような導入の仕掛けが巧みに計算された物語である。
このような構成は、庄野さんが好んだイギリスのエッセイ文学を意識したものだっただろうか。
「砂金」のように、小説ともエッセイとも受け取ることのできる作品が、庄野さんはきっと好きだったのだろう。
そのような作品には、やはり庄野さんらしい味わいがある。
書名:休みのあくる日
著者:庄野潤三
発行:1975/2/10
出版社:新潮社


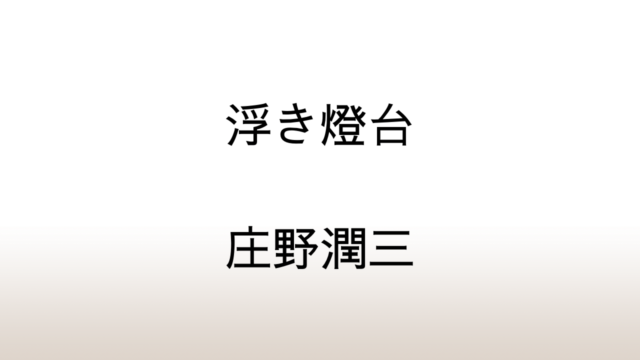

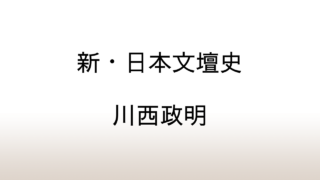
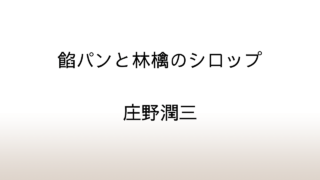
003-150x150.jpg)




