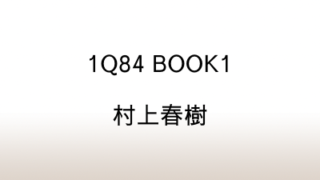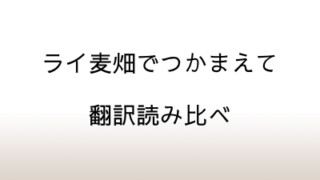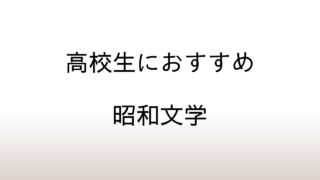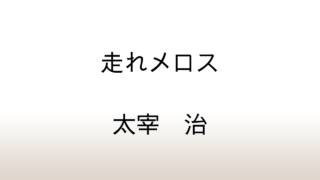野間正二「戦争PTSDとサリンジャー 反戦三部作の謎をとく」読了。
本書「戦争PTSDとサリンジャー」は、2005年(平成17年)に刊行されたサリンジャーの研究書である。
性的不能がもたらす家庭崩壊
本書「戦争PTSDとサリンジャー」は、戦争PTSDの観点からサリンジャー文学を読み解こうとする研究書だ。
考察の対象となる作品は、短篇集『ナイン・ストーリーズ』収録の「エズミに捧ぐ――愛と汚辱のうちに」「愛らしき口もと目は緑」「バナナフィッシュにうってつけの日」の3作品で、著者は、この三つを「反戦三部作」と位置付けている。
このうち「エズミに捧ぐ」は、戦争PTSDを主題とした作品として、よく知られているものだ。
「私」は戦争の野蛮さ残虐さ卑劣さを体験して、こころの均衡を失い、PTSDになった。その病気の苦しみのなかで、こころの失調から回復できないのは、愛するものを見つけられないからだと思っていた。ところがエズメの手紙と贈り物とによって、愛することができる対象がこの地上にあることを発見できた。この発見によって、こころの病からの回復を予感する。(野間正二「戦争PTSDとサリンジャー」)
「エズミに捧ぐ」においては、PTSDの診断基準にある「感情が制限されること」(例えば、愛情を抱くことができない)が、重要なテーマとなっていることが、論理的に考察されていて分かりやすい。
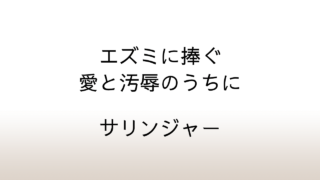
次に、「愛らしき口もと目は緑」において隠されたテーマとなっているのは、PTSDの代表的な症状の一つである「性的不能(インポテンツ)」であると、著者は指摘している。
つまりアーサーの性的な不能が、語り手によって皮肉な目で眺められているこの不倫関係の背後にあって、不倫関係にあるふたりのふるまいを見えないところで支配しているからである。そして、表だって語られることがない、帰還兵士の不能という残酷な事実が、苦いユーモアに満ちたこの作品を、洗練された恋愛物語から、社会的な問題をもふくんだ深みをもった作品に変質させている。(野間正二「戦争PTSDとサリンジャー」)
作品中に、アーサーが性的不能であるという明瞭な表現はない。
かなり深読みすぎる考察という印象は拭えないものの、PTSDが帰還兵士の家族崩壊を招いているという解釈には、一定の説得性がある(少なくとも「そうかもしれないなあ」と思わせる程度には)。
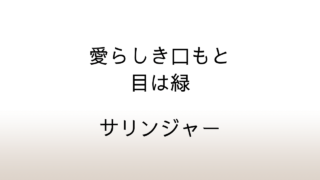
こういう解釈を続けていくと、何でもPTSDで解決してしまいそうで怖いけれど、まあ、読書の可能性は無限大である。
いささか強引ではあっても、あくまで論理的な考察を試みているところに、本書の特徴があることは確かだ。
社会復帰できない帰還兵士の絶望
最後の「バナナフィッシュにうってつけの日」が、社会復帰できない帰還兵士の絶望を描いた物語だという解釈は、ある程度定着したものであるが、著者は、ここでも、シーモアの性的不能を指摘している。
青白くて貧弱な肉体をした髪の毛の薄い男。しかも、やさしきインテリで、そのうえ神経質で几帳面で自意識の強い男。これはアメリカのマッチョ文化のなかでは、「弱い(weak)」男の典型的な姿である。(野間正二「戦争PTSDとサリンジャー」)
一方で、妻のミュリエルは、夜遅くまでホテルのバーで見知らぬ男と酒を飲み、昼間から雑誌のセックス記事を読んでいるような、性的欲求の強い女性である。
シーモアが、ミュリエルを性的に満足させることができる可能性は、かなり低いと推測できるだろう。
もっとも、シーモアを自殺へと追いやったのは、もちろん、性的不能による悩みだけではない。
シーモアは戦争によるPTSDに苦しむなかで、死にたいという願望/絶望をずっと抱いてきた。そういう願望/絶望を抱きつつも、妻と一緒にやって来た保養地で、シビルという可愛い少女に出会った。そのシビルに何かを感じたシーモアは、シビルに、生きつづけるための切っ掛けを見つけたいという、かすかな希望をもった。(野間正二「戦争PTSDとサリンジャー」)
しかし、シビルは、シーモアが期待するような純情無垢の少女ではない(シビルの言動は、ほぼ大人の女性のものだった)。
絶望したシーモアは、もはや自殺するしかなかったというのが、著者の考察であり、これは「バナナフィッシュ─」の解釈として穏当なものと言うことができるだろう(シーモアの謎の自殺については、批評家による独創的で勝手な解釈が多すぎる)。
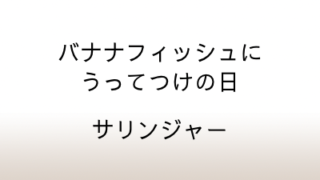
問題は、サリンジャーはなぜ、シーモアの自殺の原因を明確に書かなかったのか(謎の自殺として処理したのか)ということになるが、この点について、著者は、戦争PTSDに対する理解の欠如を浮き彫りにするためだったと指摘している。
戦争PTSDは、ベトナム戦争における帰還兵の精神的不調を、論理的に解明するために発明された病気であり、第二次大戦直後、アメリカ社会においても一般的に認知されている病気ではなかった。
戦争で神経衰弱になることは、むしろ「弱い男」として社会的失格の烙印を押されかねない状況だったのである。
自ら戦争PTSDを抱えていたサリンジャーは、そんな無理解な社会に対する怒りを抱えていた。
シーモアの自殺を「謎の死」と考えるなら、それは、戦争PTSDに対する無理解のためであると、サリンジャーは訴えたかったのかもしれない。
著者の言う「反戦三部作」は、戦争によるPTSDの影響を、三つの深刻度合別で段階的に検証した作品と言える。
PTSDからの回復を扱った「エズミ─」、家庭崩壊を描いた「愛らしき─」、自殺するしかなかった「バナナフィッシュ─」。
第二次大戦がサリンジャーに与えた影響は、もしかすると、我々が考えているよりも、ずっと大きなものだったのかもしれない。
考えようによっては、東洋思想への傾倒や、コーニッシュでの隠遁生活など、サリンジャーの人生そのものが、戦争PTSDからの逃避だったと説明することもできるのだから。
書名:戦争PTSDとサリンジャー 反戦三部作の謎をとく
著者:野間正二
発行:2005/10/10
出版社:創元社

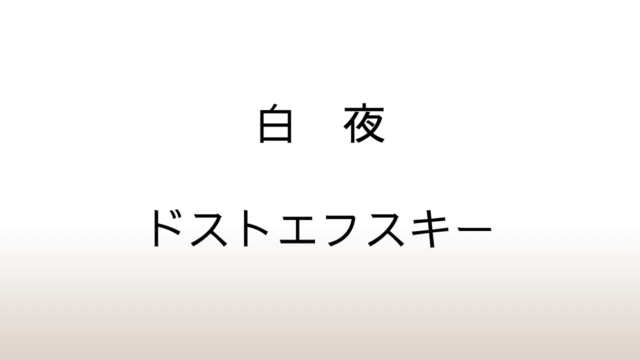
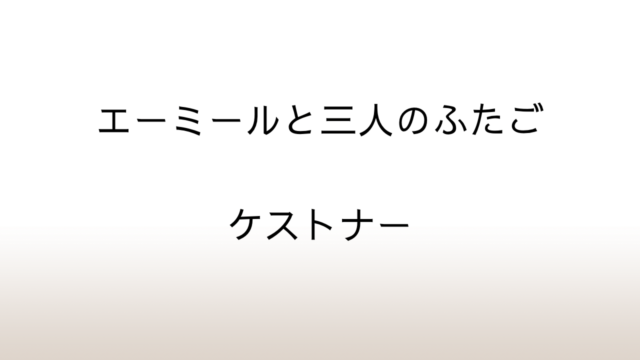
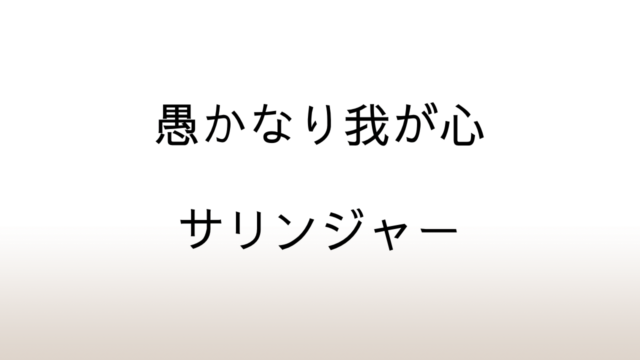
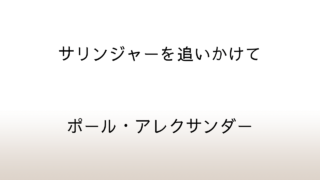
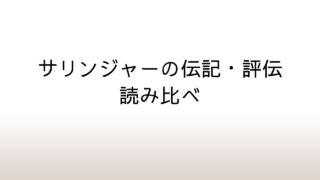
003-150x150.jpg)