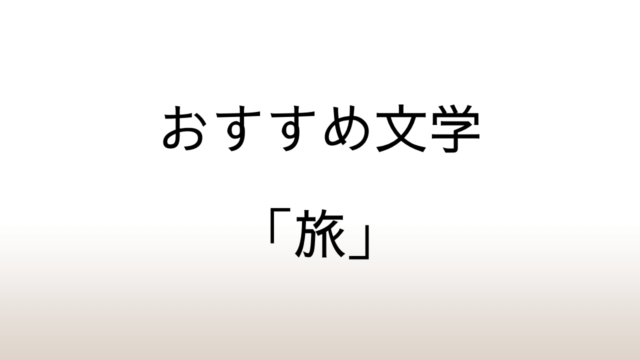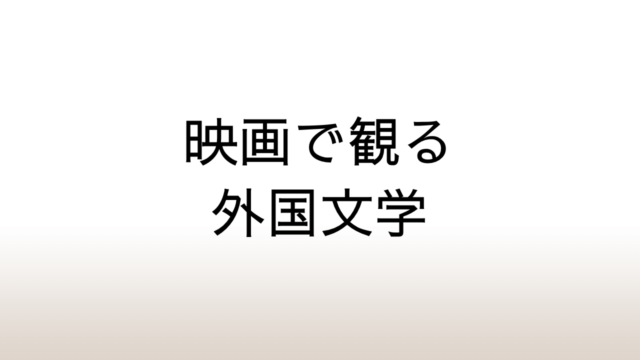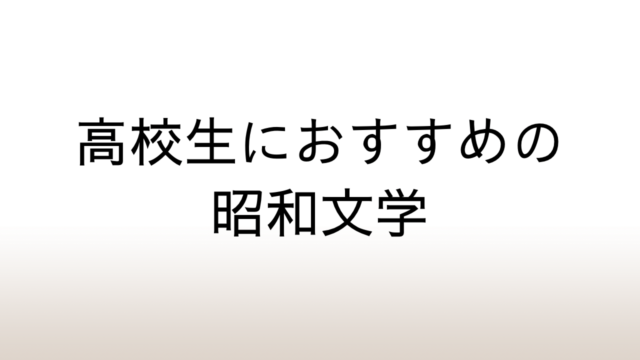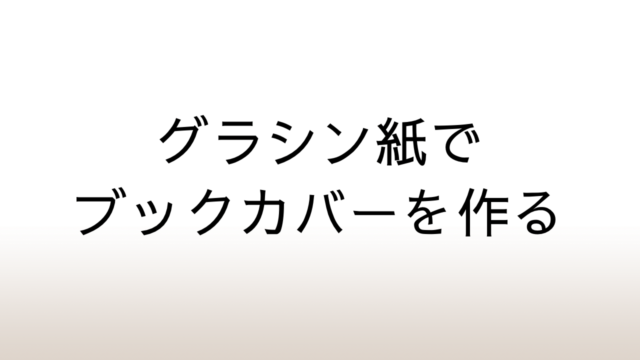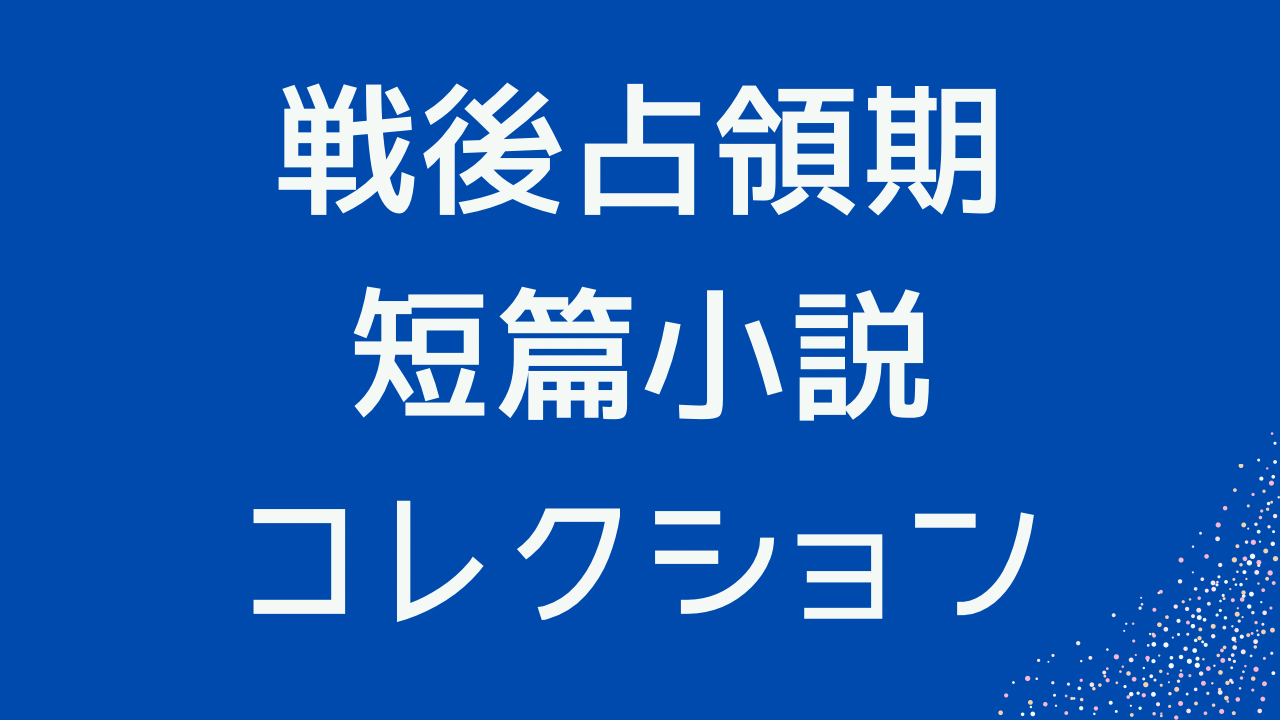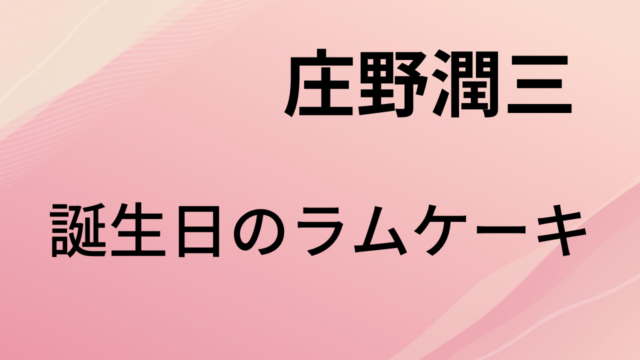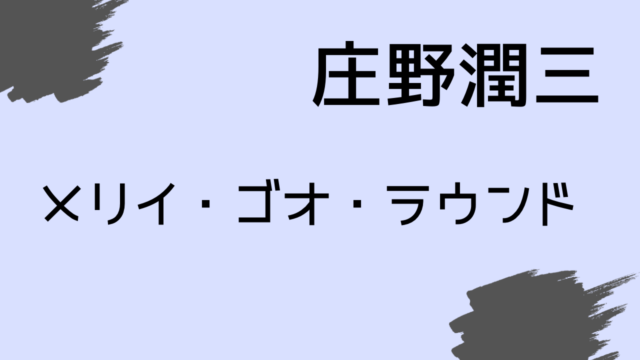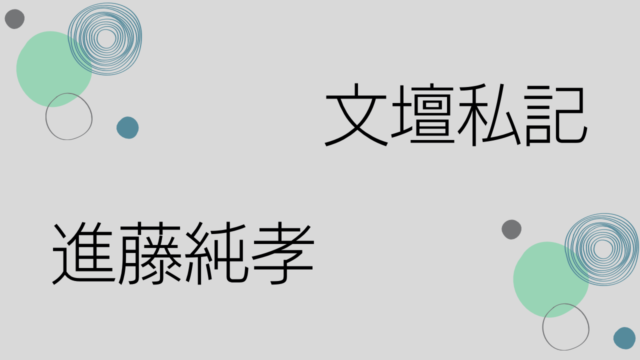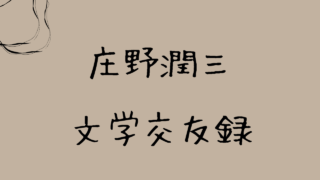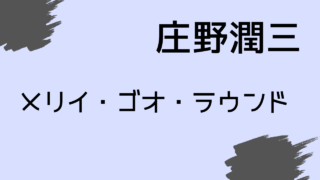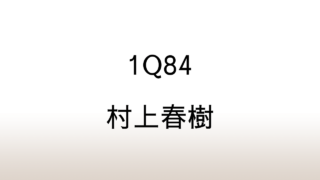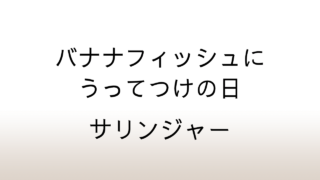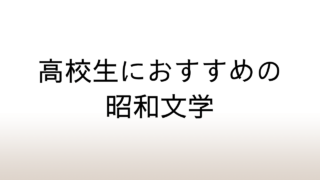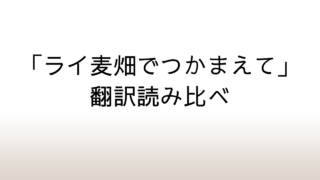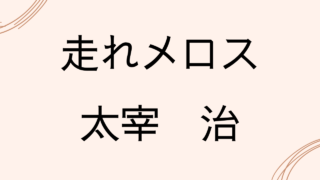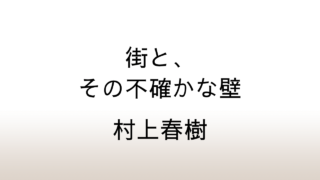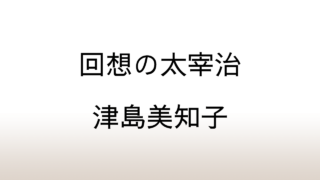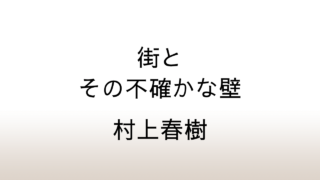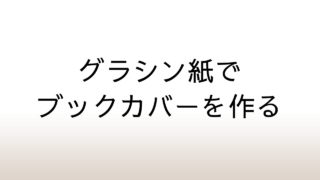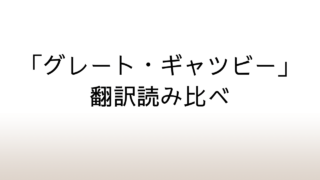(2024/04/25 22:35:07時点 Amazon調べ-詳細)
「戦後占領期短篇小説コレクション」シリーズの「第5集 1950年」に、庄野潤三の「メリイ・ゴオ・ラウンド」が収録されている。
庄野文学の長い歴史の中で、まさしく原点とも言える時期の作品だけに興味深いものがある。
敗戦日本にとって文学作品こそが復興の最初の兆候だった
敗戦から一九五二年にいたるこの未曾有の時期に、文学にたずさわるものたちは何を描き、何を見ていたか。何をとらえ、何をとらえそこねたのだろうか。小説はその時代に生きたひとびとの言葉と緊密な関係を結んでいる。きびしい制約のなかで書かれた短篇小説を通して戦後占領期をあらためて検証し、いまの私たちを問い返すため、ここに「戦後占領期短篇小説コレクション」全七巻をお送りする。(「刊行にあたって」)
「戦後占領期短篇小説コレクション」は、2007年、藤原書店から刊行された。
帯文には「”戦後文学”を問い直す、画期的シリーズ」「復活の最初の兆候」とある。
端的に言えば、1945年から1952年までの間に、日本国内で発表された短編小説のアンソロジーだが、すべての作品は、復興期にあった戦後日本を象徴するものとなっている。
日本の現代文学の中の「戦後文学」を包括的に読むことができるので、「戦後」を文学の観点から読み解きたい人には、便利なシリーズだと思う。
あるいは、日本の現代文学史の出発点を戦後に定めて、現在まで続く流れを辿るときのスタート地点としても使えるだろう。
もっとも、あまり難しいことを考えずに、単に小説として読むだけでも十分に満足することができる、上質の作品が揃っているので、「戦後文学」という言葉に惹かれた人は、躊躇せずに読むべきだ。
自由に表現できる時代の到来が、多様な文学的世界を創造した
この巻に収められた作者は本質的には戦後に作家としての歩みを始めた人たちである。それは年齢的に見ても、一番若い椎名麟三から、年長の大岡昇平に至るまでの人たちが揃えられていることからも見えてくる。しかし、言うまでもなく見事なほど、彼らの個性は異なっている。この点は至極当然過ぎるように思われるが、やはり敗戦前のわが国の近代文学の姿と較べると、そこに戦後文学の一つの特徴があると指摘してもいいのではないか。(「解説 さまざま萌芽」辻井喬)
シリーズ第5集の本書には、1950年(昭和25年)を代表する短編小説8篇が収録されているが、収録作品には、「1950年」という時間的な区切り以外には、特別の共通項はない。
にもかかわらず、ここに収録された作品には、1950年の日本に漂っていた空気感とも呼ぶべきものが、しっかりと反映されていることは不思議だ。
「言うまでもなく見事なほど、彼らの個性は異なっている」「そこに戦後文学の一つの特徴がある」という辻井喬の指摘は、だからこそ説得力があるのだと思う。
自由に表現できる時代の到来が、多様な個性を容認し、多様な文学的世界を創造したと理解しても良いかもしれない。
庄野潤三の『メリイ・ゴオ・ラウンド』には、解読を必要とするような喩はひとつもない
吉行淳之介と正反対の埴谷雄高という構図とは全く違う意味で埴谷文学と対峙しているのは、庄野潤三の『メリイ・ゴオ・ラウンド』である。この作品には解読を必要とするような喩はひとつもない。(「解説 さまざま萌芽」辻井喬)
「解説」の中で、辻井喬は占領期文学の特徴について、独自の分析を展開しているが、庄野文学に対する批評は、他の作品に比べると、ほとんど深掘りされていない。
批評というよりも、むしろ読書感想に近い簡単なコメントがあるだけで、「深読みを許さない」庄野文学の開放性が、難解な批評を拒んでいるのだろうか。
「この作品には解読を必要とするような喩はひとつもない」とあるが、主題となっている「メリーゴーランド」そのものが、大きな喩の一つだと解すると、この作品に対するスタンスも、随分と変わってくるような気がする。
解説者は「埴谷雄高とは、どこからどこまでも異質な文体で語っている」と、この作品に対する解説を締めくくっているが、作品理解を深めるための基準としての物差しを、あくまでも埴谷雄高に置いているところに、そもそものすれ違いがあったのかもしれない。
書名:戦後占領期短篇小説コレクション 5 1950年
編集:紅野謙介、川崎賢子、寺田博
発行:2007/7/30
出版社:藤原出版