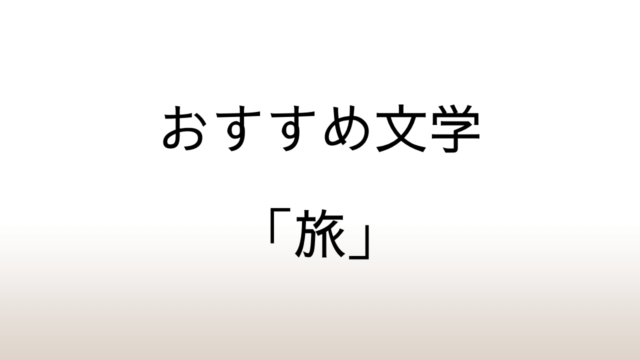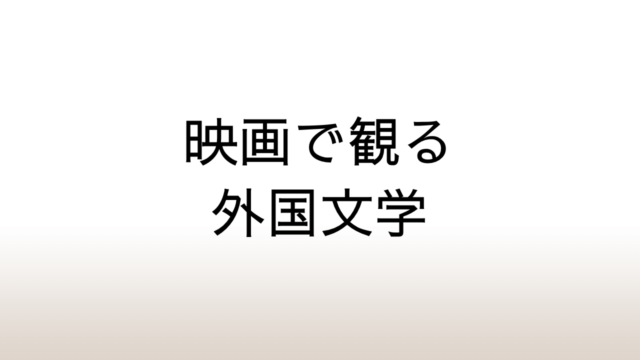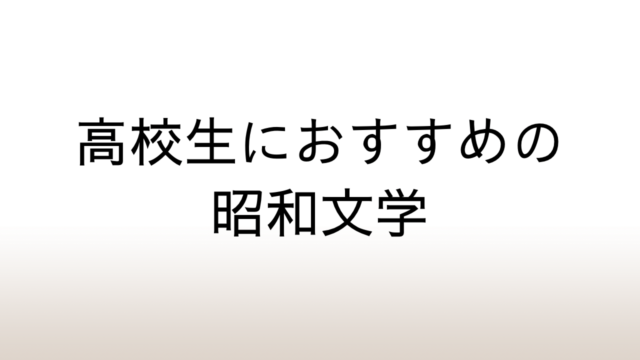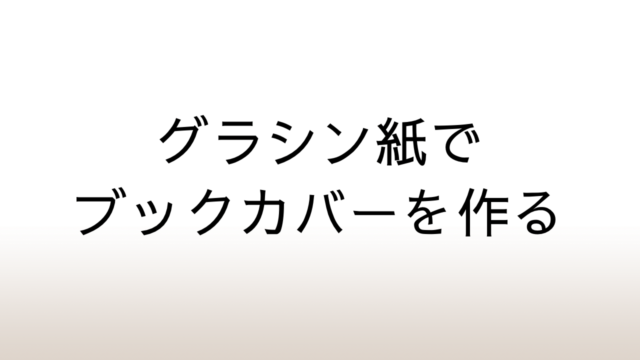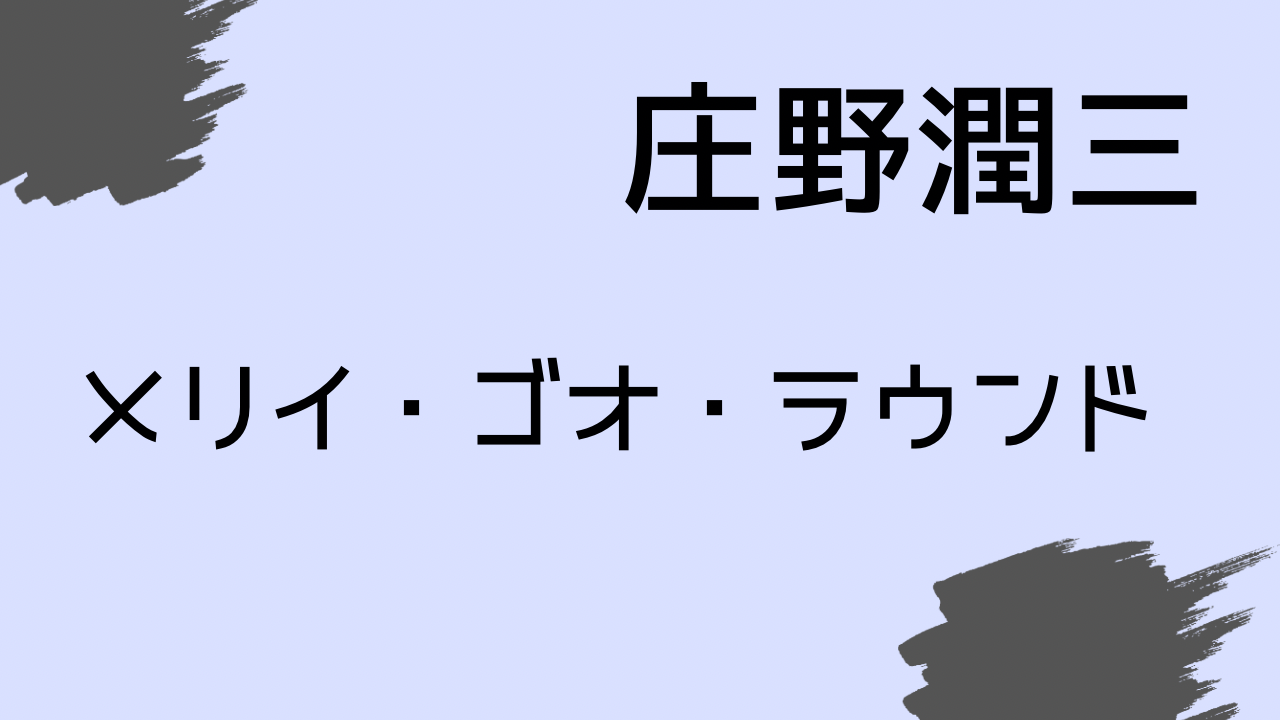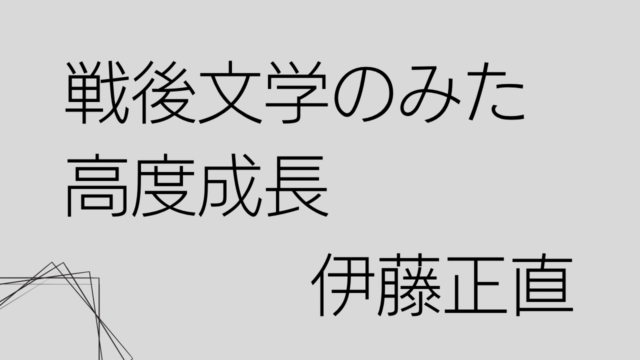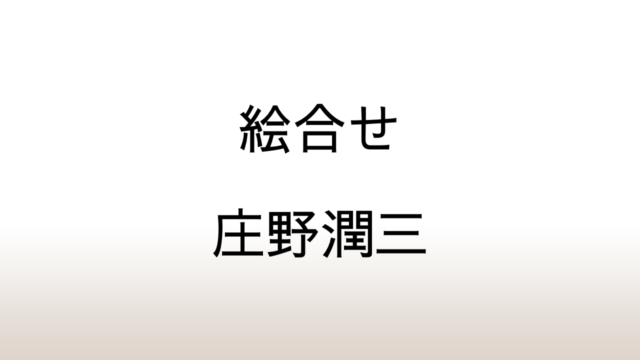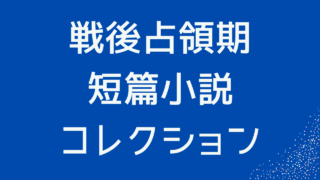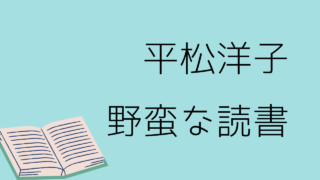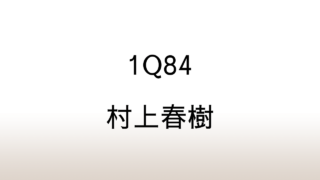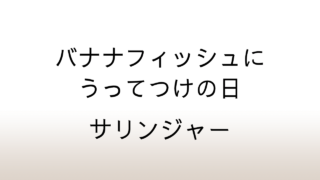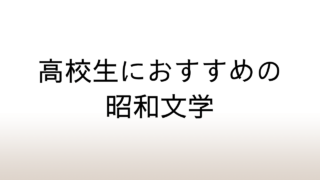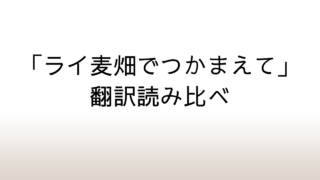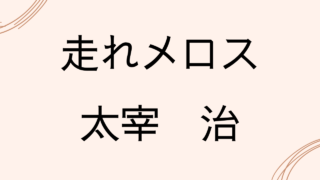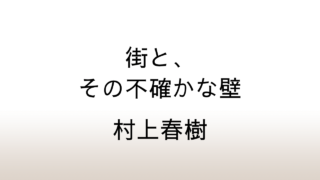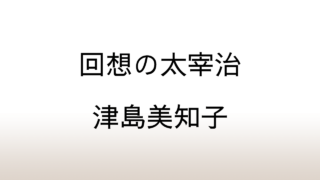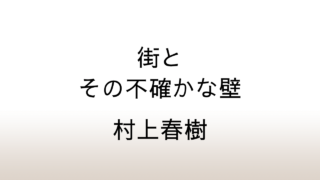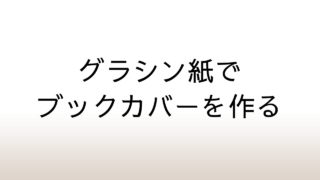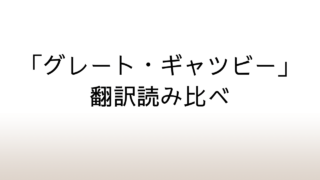(2024/04/24 04:31:02時点 Amazon調べ-詳細)
庄野潤三「メリイ・ゴオ・ラウンド」読了。
『戦後占領期短篇小説コレクション』に収録されていたもので、初出は1950年(昭和25年)の『人間』10月号。
結婚5年目の主婦「なつめ」の視点から、若い夫婦の葛藤を描いた夫婦小説で、初期の庄野文学の特徴が非常によく表れている。
刻々が無為とアンニュイのうちに過ぎ去っていく
彼女にとっては、人生はこんな単調極まるものである筈はないのだ。決して、こんな風な日常茶飯の繰返しであってはならないのだ。生きると云うことは、もっと何か別のものである筈なのである。しかも、現実は、いつでも彼女の期待を確実に裏切って、刻々が無為とアンニュイのうちに過ぎ去っていく。なつめが、少女時代からこの人生にかけていた憧れは、ちっとも満たされたことがない。(「メリイ・ゴオ・ラウンド」庄野潤三)
夢見る少女のままで大人となったなつめは、売れない童話作家である夫と結婚するが、毎日の暮らしは単調で、毎日が何事もなく、無為のままに過ぎ去っていくことを、たまらなく苦痛に感じている。
つまらない日常の中に何か夢を探そうとして、なつめは詩人のごとく生活の中に素晴らしく素敵なものを発見しようとしているが、夫はそんななつめの習癖に辟易していて、彼女の言うことに、まともに取り合おうとしない。
そもそも童話作家である夫以上に、なつめは童話の世界にでも暮らしているかのような夢を見続けていたのだ。
最終場面で、なつめは白い仔馬に乗る夢を見る。
そこは、フランスの小都会の広場で、女学生の彼女は白い仔馬に乗ったまま、広場を何周も何周も回っていく。
街中の人々が集まって来て、彼女は注目の視線を浴びながら、白い仔馬を走らせている。
それは、彼女が夢にまで見ていた、憧れの世界だ。
しかし、白い仔馬は広場を走り続けるうちに、まるで回転木馬のように素っ気なくなり、気付けば、彼女は、街の人々が自分を見ながら笑っていることに気が付く。
繰り返される単調な回転木馬を、彼女は遠い昔からずっと知っていたような気がする。
彼女が求めていた幸せとは、一体どのようなものだったのだろうか。
作品が読者に問いかけたところで、物語は終わる。
短くて、派手な場面のない小説だけれど、テーマも構成もしっかりしていて、間もなく芥川賞を受賞するという予感みたいなものが漲っている、充実の作品だと思った。
(金は幸福の源)ではなく、(金は幸福そのもの)なのである
たった一度きりしか、この世に生れて来ない我々が、生れてみたら、このちっぽけで、恐ろしく貧乏な日本の国に生れていたんだ。同じ時刻に、他のいくつかの生命は、金持のアメリカに生れている。眼の色も、皮膚の色も違って、彼等は、野放図に、思い切りぜいたくに生活をすることが出来、おれたちは、多分一生涯、みじめな、しみったれた暮しをして終わるんだ。何と、分の悪い話じゃないか。(「メリイ・ゴオ・ラウンド」庄野潤三)
夫は「金で幸福は買えないと云う風な言葉は、うそである。全く、今日では、(金は幸福の源)ではなく、(金は幸福そのもの)なのである」と主張するが、なつめは、幸福の条件は「愛」以外には信じられないと考えている。
自分が愛する人から愛されることこそが生きてゆくことだと言うと、夫は「愛し合っている家族だって、明日食う米がなければ、みんなで心中するより外ない」と言う。
この小説のひとつの大きな背景として、戦前と戦後の日本における価値観の大きな転換がある。
庄野さんは、それを「金」と「愛」という比較の中で、夫婦間の問題として物語の中に組み込んでいる。
大きく異なる価値観が衝突する現実こそが、昭和25年の日本という社会だったのではないだろうか。
「メリイ・ゴオ・ラウンド」は、必要以上に戦後を主張することもないし、社会的なメッセージを投げかけることもしていない。
しかし、物語の根底に流れるものは、紛れもなく戦後日本を生きる人々の葛藤である。
価値観が大きくねじ曲がる中で、単調な暮らしとの折り合いを付けなければならなかった庶民の戸惑いが、夫婦生活を舞台として描かれているのが、この短編小説なのだ。
初期庄野文学の本当の面白さを、僕はこの小説で知ったような気がする。
書名:戦後占領期短篇小説コレクション 5 1950年
編集:紅野謙介、川崎賢子、寺田博
発行:2007/7/30
出版社:藤原出版