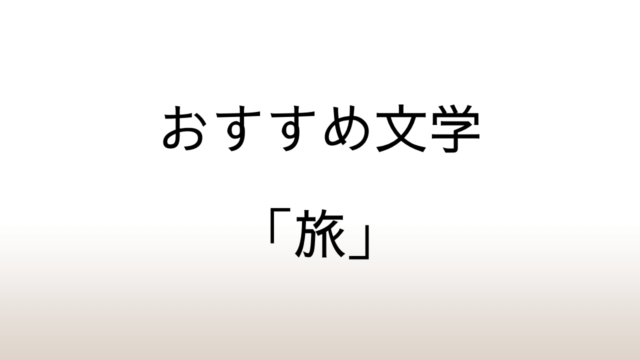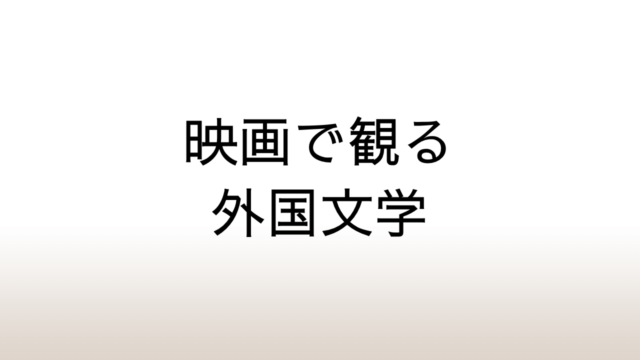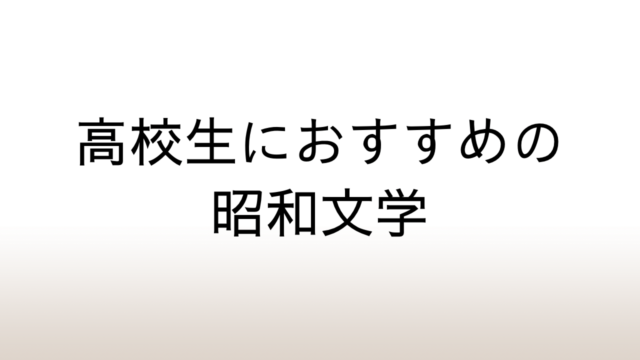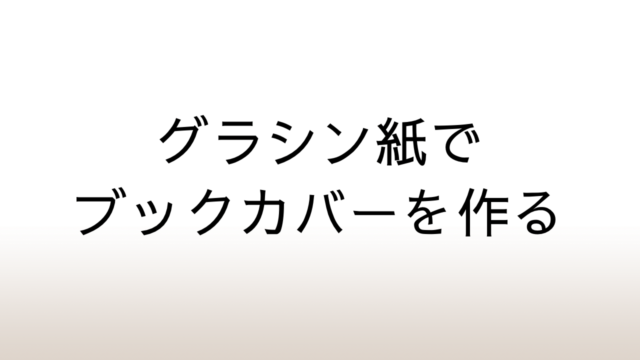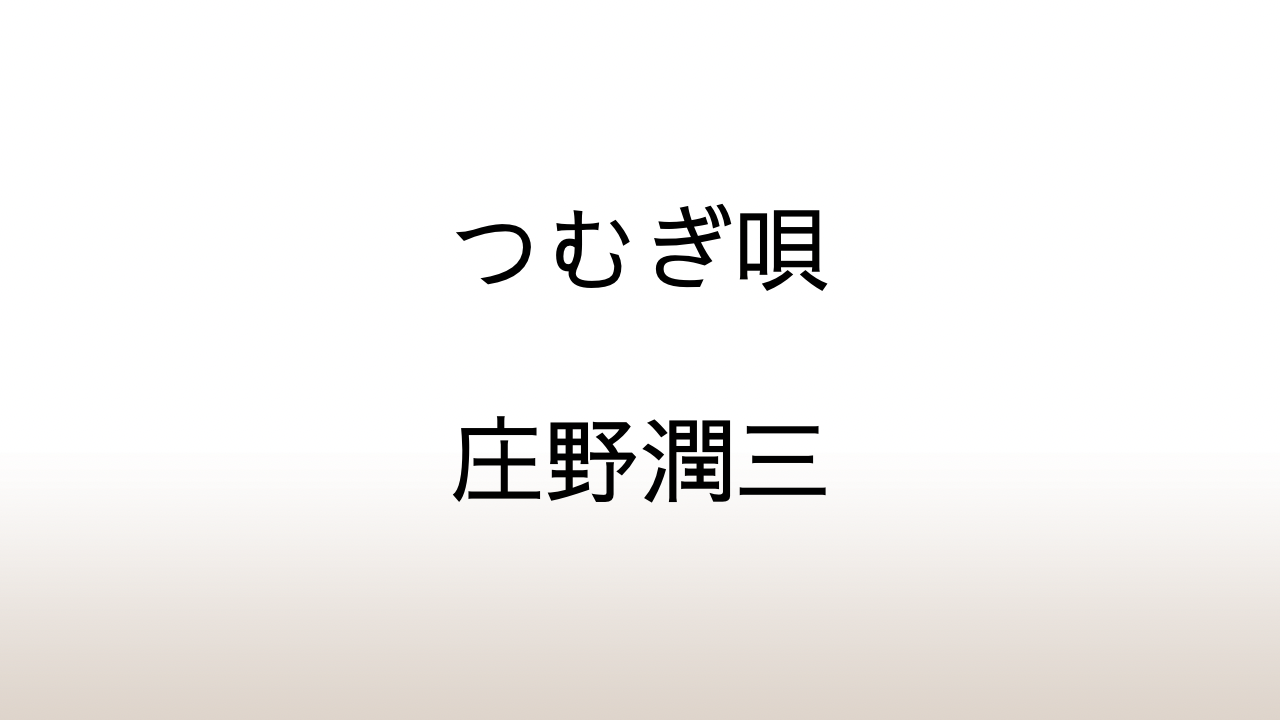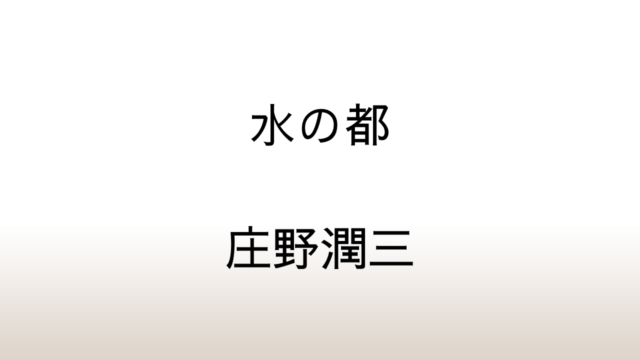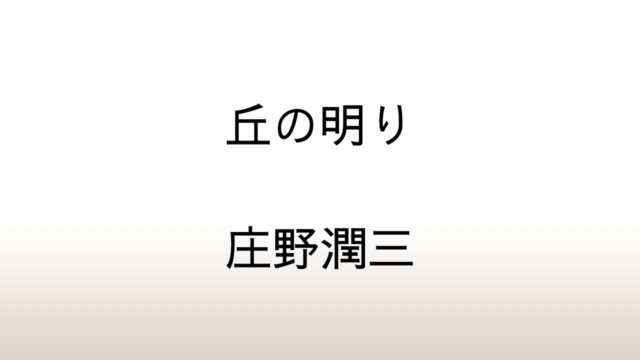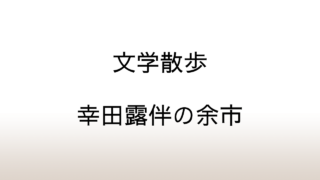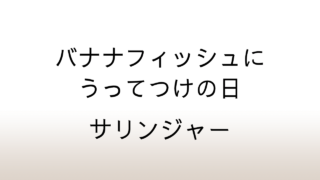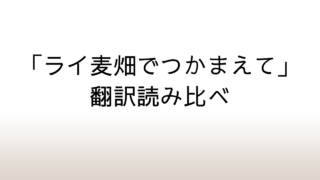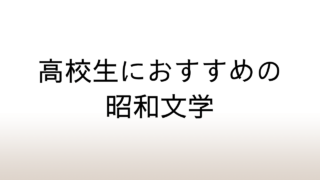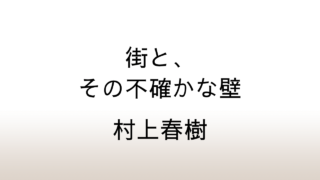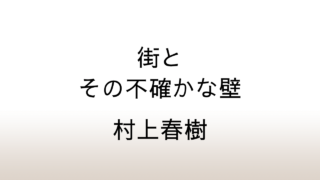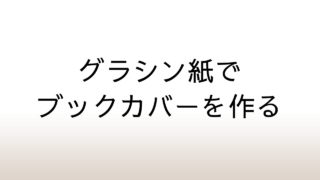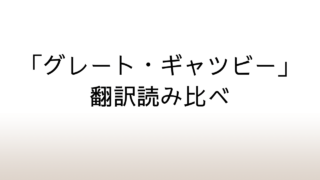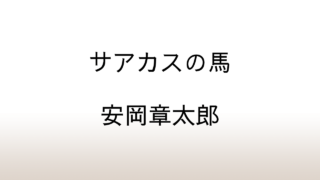庄野潤三「つむぎ唄」読了。
本作「つむぎ唄」は、1963年(昭和38年)7月に講談社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は42歳だった。
庄野潤三と小沼丹と吉岡達夫の「町内会」
本作「つむぎ唄」は、いずれも父親である三人の中年男性の目線から書かれた家庭小説である。
絵描きの「毛利」は、著者本人(庄野さん)がモデルになっているらしい。
毛利は三人の中では一番大きくて、肥っている。プログラムを持っている手も指も、まるくずんぐりしている。(庄野潤三「つむぎ唄」)
毛利には、中学三年生の長女(敦子)のほかに、小学五年生の長男(和男)と小学一年生の次男(正次郎)がいて、この家族構成は、1962年(昭和37年)の庄野家と同じものとなっている。
長女の敦子は受験生として苦労している。
「病気にならないか知ら」「大丈夫だよ」「そうか知ら。前はみんなで御飯食べてる時、よく馬鹿なこと云って笑わせていましたでしょう。それがこの頃は、何だかむっつりしてしまって」(庄野潤三「つむぎ唄」)
敦子の高校受験のエピソードは、志望校に合格して入学するまで、断片的に挿入されている。
来週になったら、高校へ願書を出しにいかなくてはならない。去年の夏休みもこんな風にして家にいたきりで、浮かない顔つきで勉強していたが、あれからもう半年経った。いつも夜は早く眠る毛利が、夜中に眼を覚ますと、敦子の勉強部屋で鉛筆削りを廻す音が聞えて来る。しんとした家の中で、その音はひとしきり続いて止む。(庄野潤三「つむぎ唄」)
庄野さんの長女・夏子は、1963年(昭和38年)4月に青山学院高校へ入学しているから、本作『つむぎ唄』は、長女の高校受験物語としての性格も備えていると言える。
大学の英文科の先生「大原」は、小沼丹だ。
大原の顔は求心力の働きをしている。眼鼻だちが引きしまっている。そのひきしまり具合は例えば胡桃のようであるが、眼もとにも口もとにも愛敬があって、ただ固いというのではない。それによくこの顔が笑う。(庄野潤三「つむぎ唄」)
大原には、美術大学の図案科に入学したばかりの長女(育子)と、中学三年生の次女(晴子)がいる。
「いや全く、うちのやつも背ばかり伸びやがって」と大原が云った。「上のと次のと競争するみたいに大きくなってゆくんだ」(庄野潤三「つむぎ唄」)
次女(晴子)の高校受験に附き添っていく話の主人公は大原だった。
娘の入学試験が終わるまでの間、大原は、何とかして時間を潰そうとするが、何をするにも気分が乗らない。
「さて、どうするか」彼は立ち止って、考えた。この映画なら始めから終りまで全部見なくたって構わない。どこで止めてもいい。こういう時には丁度ぴったりの映画だ。で、大原は始まるまでの間をどこか古本屋でも覗いてみようと考えて、さっきここへ来る途中で見かけた店の方へ歩き出した。しかし、不思議なことに、まだいくらも行かないうちに、自分がそれほどあの映画を見たいと思っていないことに気が付いた。(庄野潤三「つむぎ唄」)
結局、大原も、娘の受験が心配なのだ。
受験生の娘を持つ父親の不安が、父親の落ち着かない行動によって、さりげなく描かれているところがいい。
小沼丹の作品とリンクするようなエピソードもある。
「あれは何か知っているか」と今度は大原が、ちょっと枇杷のような葉をしたあまり大きくない木を指した。「いや、知らない」「あれはポポの木だ。南洋の木だそうだ」(庄野潤三「つむぎ唄」)
ポポの木については、小沼丹もエッセイに書いている。
大分前のことだが、知合の植木屋の親爺がポポの木を持って来て庭に植えた。(略)「──どこの木だい?」と訊くと、親爺もよく知らなかったらしい。「──多分、南方の木だと思いますが、当にはなりません」と心細いことを云った。(小沼丹「ポポ」)
放送会社勤務の「秋吉」は、吉岡達夫がモデルとなっている。
しかし、顔の大きさという点では、秋吉が一番であった。彼の顔は、どうかすると明りの加減でベートーヴェンのように見えることがある。(庄野潤三「つむぎ唄」)
秋吉にも高校二年生の長女(泰子)と、小学四年生の長男(弘夫)がいる。
物語は、三つの家族の日常風景をスケッチする形で構成されていて、素材の多くは、庄野家で実際に体験したことのように思われる。
例えば、秋吉家が家族で海水浴へ行く話は、いかにも庄野一家の物語だ。
いちばん最初に秋吉が細君と子供を連れてここへ来たのは六年前の夏であるが、その年の村の様子と今年の村の様子に少しも変りがない。同じところに同じ宿屋があり、同じ道ばたに漁師の網が乾してある。同じ井戸の横でお婆さんが洗濯をしているし、同じ家の卓袱台で裸の親父が立て膝をして夕飯を食べているという具合だ。(庄野潤三「つむぎ唄」)
あたかも、短篇小説「蟹」(1959)で描かれていたような風景である。
汽車に乗ってここへ来る途中には、海へ近づいてゆくあのときめきがもう一度蘇って来るように思える瞬間があった。窓の外にひろがる青い稲田や風にゆれる灌木の葉、海に出て行く小川、その上に照る陽には、夢の中のような美しさがあると思えた。(庄野潤三「つむぎ唄」)
「このときめきは、小学生の頃の夏休みにいつも待ち受けていてくれたあの喜びのかすかな名残であろうか」「父も母もとうに死んでしまって、もうこの世の中にはいない。昔のあの賑やかだった家は、どこへ行ってしまったのか」と考える秋吉の感傷は、庄野さん自身の感傷だったのだろう。
海に入った漁師たちが、海岸の石を沖へ捨てにいく作業風景を、秋吉は関心深く見つめている。
「何だろう」一人だけそちらを見ている秋吉は、自分に問いかけた。「どうしておれはこういう情景に惹かれるのだろう。何がおれをこんな風に立ち止まって見させるのだろう」(庄野潤三「つむぎ唄」)
秋吉が感じたものは、海辺の町で懸命に生きる漁師たちの生活への共感だったのかもしれない。
床屋さんのエピソードも、庄野さん自身の体験を素材としたものらしい。
「分けますか」「いや、バックにしてください」いつも散髪屋でこれを云う時、彼は気おくれがする。ふわふわと空に浮いたような彼の髪の毛は、分けるとか、バックにするとかいうような髪ではない。それはもっと分量の多い、艶のいい頭髪でなくてはぴったりしない言葉なのだ。(庄野潤三「つむぎ唄」)
床屋さんで「分けますか? それとも、バックにしますか?」と訊かれたのは若い頃の話で、中年になってからは、そんなことを訊かれることもなくなった。
そんな話が、庄野さんの随筆にもあった。
加齢は避けることのできないものだし、年月は、男たちの取り分を忘れたりはしない。
大学生や高校生の子どもたちを持つ父親世代への共感が、そこにはある。
そんな中年世代へのエールこそが、この物語のメッセージと言ってもいい。
小沼丹の好きだった「カプリ島」のエピソードもある。
「では、次にお送りしますのは」ラジオがかかっている。誰それの楽団と云ったが、その名前は聞き洩らした。「カプリ島」と云うのを聞いて、秋吉は、おや、と思った。カプリ島。懐かしい曲をやるなあ。(庄野潤三「つむぎ唄」)
放送会社に勤めている秋吉は、サラリーマン時代の庄野さんの姿を投影したものだろう。
毛利が、男の子たちの父親参観日に出かける話では、小学生時代の長男(龍也)と次男(和也)の日常が描かれている。
五年生の上の子は、いい加減、横着なことをやって羽根を伸ばしているようだが、一年生の下の子は、まだ頼りないところがあって、ランドセルと黄色い帽子が板に着いたという感じには、まだまだとある。
去年、最初の夏休みが終って、いよいよ今月から二学期が始まるという日の朝、細君に起こされて服に着換えて朝御飯を食べている時、不意に泣き出したのはこの子だ。これからまた毎朝、学校へ行かなくてはいけないのかと思ったら、耐らなくなったらしい。(庄野潤三「つむぎ唄」)
ちなみに、庄野さんが、小沼丹や吉岡達夫と「町内会」と称する飲み会を定期的に開いていたのは、石神井公園時代のことで、次男(和也)が小学校へ入学するのは、神奈川県の生田へ引っ越した次の年の春のことだった。
本作『つむぎ唄』では、庄野さんの体験が、時間を越えて立体的に組み合わされているということになる。
贔屓のプロ野球チームの調子が悪いとき、楽しい夢の話をして父親を元気づけてくれたのは、毛利の長女(敦子)だった。
あまりに父親が元気を無くしているので、彼女は気の毒に思ったのだろう。それが、そんな素晴らしい夢となった。一つのホームランでベースを一周して、なおも二周、三周と走り続ける打者は、本当は彼女自身であったのかも知れない。(庄野潤三「つむぎ唄」)
ホームランの夢で父親を元気づけてくれたときに小学三年生だった娘も、今では、中学三年生の高校受験生である。
今度は、父親が、彼女のホームランを期待して、大きな夢を見ているのだ。
庄野家のテーマソング「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート」
次女(晴子)と一緒に飛行機に乗って宮崎へ向かったのは、大原だ。
まだ珍しかった飛行機の旅で、遠く下界を見下ろしながら、大原は人生を考えている。
「われわれの毎日の暮しというものも、生活している当人に取っては、いやなことや情ないことや腹の立つことばかりで詰っているように思えるけれども、もう二度とそこで生きることが無くなって、はるか遠くから眺めるようになれば、こんな風にごく穏かな、いい色をして見えるのかも知れないな」(庄野潤三「つむぎ唄」)
こうした人生観は、1960年代あたりの庄野文学には、積極的に挿み込まれていたような気がする。
娘が志望校に合格した父親たちが「町内会」を催すラストシーンもいい。
そのうちに大原がバンジョーを弾くふりをしながら「スワニー河」を歌い、毛利は「カミング・スルー・ザ・ライ」を歌い、毛利の細君と敦子が「ふるさとを離れる歌」を二重唱でやり、小学六年になった和男が「燈台守」を歌い、二年生の正次郎が「子鹿のバンビ」を歌った。「さあ、そろそろ輪唱だ。ロウ・ロウ・ロウヤ・ボートだ」(庄野潤三「つむぎ唄」)
男たちの宴会に家族が参入して歌を披露するのは、庄野一家の習わしである(長男が「燈台守」を歌う場面は『山の上に憩いあり』にも登場する)。
これは「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート(漕げ漕げボート)」で滑り出して、「ライフ・イズ・バット・ア・ドリーム(この世は夢に過ぎない)」という終りの句まで来ると、また始めに戻るのだが、音楽が苦手の秋吉のところではいつも調子がちょっと外れ、四回続けて云う「メリー(楽しい)」が、あとから追っかけて来る組の声につられて、五回も六回も続くことがあり、その度に一緒の組である和男が困った顔をするのだった。(庄野潤三「つむぎ唄」)
結局、この作品の大きなテーマは「この世は夢に過ぎない」ということになるのだろう。
空から見た地上の光景が、穏やかな光景に見えるのと同じように、我々の人生も、終わってみれば、一つの夢のようなものだ。
娘たちの高校受験も、薄くなった髪の毛も、海水浴で見た光景も、すべては夢だ。
「生きていることは懐かしい」ということを書き続けた庄野文学の神髄が、ここにある。
きっと、庄野さんは、生きながらにして、生きていることは夢のようなものだと、常に感じ続けていたのではないだろうか。
ちなみに、「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート(漕げ漕げボート)」は、「夫婦の晩年シリーズ」最初の作品『貝がらと海の音』にも登場している。
それは、庄野さんの神奈川文化賞と勲三等瑞宝章のお祝いで、一族揃って箱根芦の湯へ一泊旅行したときの話だった。
広間での夕食の最後に進行係の「山の下」の長男が立って、「それでは、ここでロウ・ロウ・ロウヤ・ボートの輪唱をします」といい、はじめに私にこの歌の意味をみんなに説明してくれるようにと頼んだ。そこで、私は一通り歌って聞かせてから、「漕げ漕げボート ゆるやかに川を下って」と、長男に頼まれた通り、これからみんなで歌うボートあそびの歌の歌詞を紹介した。(庄野潤三「貝がらと海の音」)
『つむぎ唄』(1963年)から『貝がらと海の音』(1996年)まで33年の月日が経過しているが、時代は変わっても、庄野家は安泰だった。
「ロウ・ロウ・ロウヤ・ボート」は、そんな庄野家を象徴するテーマソングだったのかもしれない。
本作『つむぎ唄』は、文庫本になることもなく、オリジナル以外に再発されることもなかった。
それでも、この作品が、庄野文学を代表する重要な作品の一つであることに間違いはない。
書名:つむぎ唄
著者:庄野潤三
発行:1963/07/20
出版社:講談社