あとがきには「この三年あまりの間に発表した短編からこれだけを集めてみた」と書いた後で「昭和42年9月」とある。
全11篇の作品が収録されていて、一番古いものが昭和38年11月の「石垣いちご」、新しいもので昭和42年7月の「丘の明り」。
電車の乗客同士の会話に題材を得たものや、父や兄など家族の昔の思い出を描いたもの、あるいは、現在の家族の様子を描いたもの、友人との交流を描いたものなど、テーマは多彩だが、根底には一貫した庄野文学の水が流れている。
「冬枯れ」「まわり道」「行きずり」「つれあい」は、電車内など日常風景をスケッチした作品で、身辺に小説の題材を求める作家の姿勢が伝わってくる。
「秋風と二人の男」は、主人公の「蓬田」が、二年前に妻を亡くして、現在は高校三年生の娘と暮らしている友人「芝原」(小沼丹がモデル)と、二人で飲みに出かける話で、「細君」の作る巻き寿司を手土産に持っていくことや、秋風に吹かれながら上着を着て来なかったことを後悔することなど、中年男性の他愛ないスケッチが、味のある物語になっている。
「山高帽子」「石垣いちご」「曠野」「蒼天」は、亡くなった父や兄の思い出を書いた作品で、家族小説をライフワークとする作家の家族観が、粘着質でない程度に温かく描かれている。
「卵」と「丘の明り」は、和子と明夫と良二の3人の子どもたちが登場する「井村家」シリーズの物語で、この2作品は、後に文庫版「絵合せ」を再編集した際、「絵合せ」の中に収録された。
いずれの作品においても、決して派手なドラマは起こらないが、休日の午後、一文一文の流れに身を任せながら、ゆったりと読みたくなる短編集だ。
時の流れがゆったりと感じられるのは、現在と過去を行ったり来たりする作風のせいだけではないような気がする。
隠れたテーマは「時の流れ」
私はもう既婚者であり、年を取る一方であるが、この若い二人のようなことは、一度、真似してみたい気がする。しかし、そのためにはもう一回、時の針を逆に廻さねばならないとすれば、それは考えただけでも億劫である。いや、億劫というよりも、堪え難い苦痛であろう。決してもう一度、若くなりたいとは思わない。(「冬枯れ」)
「冬枯れ」は、蕎麦屋で一緒になった若い男女をスケッチした日常生活の断片だが、若い二人が食事をする風景を見ながら、物語の語り手である「私」は、「この若い二人のようなことは、一度、真似してみたい気がする」と思いつつも、「もう一回、時の針を逆に廻さねばならないとすれば、それは考えただけでも億劫である」「決してもう一度、若くなりたいとは思わない」と考えたりする。
この作品に限らず、本書に収録された作品では、「時の流れ」が隠れたテーマになっているようだ。
あとがきに「ひとつの場所からまだどこか、別の場所へ移って行く」「そこで「時間」ということを考える」「私は、そういうかたちで、自分がこの世に生きているという感じを、確かめようとしているのかも知れない」とあるのは、きっと、そういうことなのだろう。
時を超えて残る「家族の愛情」
父が五十代の初めの方で、丁度、戦争がはげしくなって来たのであった。父も母も若く、家族の出入りが(出征やら結婚やらで)頻繁であったあの頃が、いちばんの高みに立っていた時であったような気がする。(「山高帽子」)」
久しぶりの故郷を訪れた後で、「彼」は父の遺した山高帽子を土産に持ちながら、船の旅をする。
懐かしい風景が、亡き父の思い出へとつながり、亡き父の思い出が様々の思い出へとつながっていくというように、「彼」は旅をしながら、思い出の中で、もうひつの旅を楽しんでいる。
目の前の風景と過去の記憶とが交錯する不思議な感覚の中で、いつの間にか、物語が時間を超えていく。
時間を超えた先に残るのは、家族への愛情だ。
時間の流れに消えてしまわない普遍的なものだからこそ、著者(庄野潤三)は家族の姿を描き続けたのかもしれない。
書名:丘の明り
著者:庄野潤三
発行:1975/4/25
出版社:筑摩書房



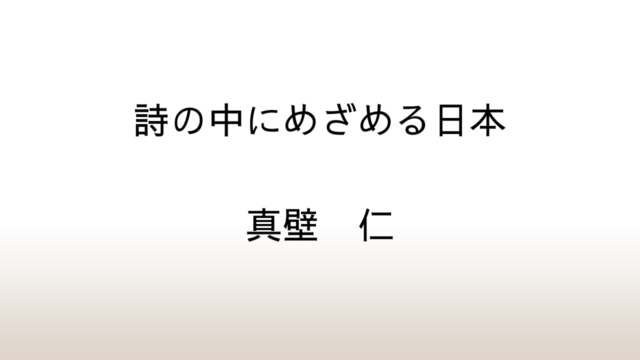
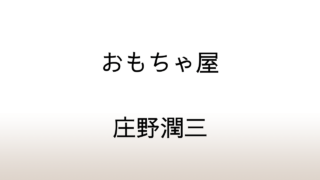
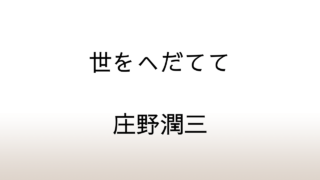
003-150x150.jpg)




