エーリヒ・ケストナー「飛ぶ教室」読了。
本作「飛ぶ教室」は、1933年(昭和8年)、ドイツの作家エーリヒ・ケストナーによって発表された児童文学小説である。
テーマは「子どものころのことを忘れないでほしい」
物語の後半、<禁煙さん(ウートホフト博士)>が、子どもたちにこんなことを言っている。
「いちばんたいせつなことを忘れないでほしい。過ぎ去ってほしくない、いまこのとき、きみたちにお願いする。子どものころのことを忘れないでほしい。きみたちはまだ子どもだから、いまそんなことを言われても、よけいなことのように聞こえるかもしれない。でも、これはけっしてよけいなことではないのだ。わたしたちの言うことを信じてほしい。わたしたちは年をとった。でも、若さは失っていない。わたしたちにはよくわかっている。わたしたちふたりには」(エーリヒ・ケストナー「飛ぶ教室」池田香代子・訳)
「子どものころのことを忘れないでほしい」は、この長篇小説の全体に通奏低音のように流れている、大きな作品テーマだろう。
それは「多くの人は、大人になったら子どもの頃のことを忘れてしまう」という歴史的事実に裏打ちされた、作者からのメッセージだ(大人にとっては切ないメッセージだが)。
ごく簡単に言えば、この小説は、五人の少年たちを中心とした友情と成長の物語である。
少年たちは、それぞれに困難を抱えているが、互いに支え合いながら、知恵と勇気と連帯を味方にして、自分たちなりに前へ進もうとしている。
そんな少年たちを陰ながらサポートしているのが、<正義さん(バク先生)>と<禁煙さん>という、二人の大人たちだ。
作品を読みながら、グッとくる場面が何度かあった(割と泣かせる物語なので)。
そのひとつが、実業学校生のグループに人質としてとらえられた仲間を救出するため、寮の規則を破って外出した夜に<正義さん(バク先生)>から諭される場面だ。
あらかじめ、子どもたちから相談を受けなかった<バク先生>は、「だとしたら、わたしも有罪だ。だって、わたしもきみたちのあやまちに一枚かんでいるんだからね」と、子どもたちの相談相手となることができなかった自分を責める。
実は、バク先生も、この寄宿学校の卒業生で、当時、信頼できる先生がいなかったために、辛い思いをしたことがあった。
今、バク先生が、この学校で舎監をしているのは、子どもの頃の辛い体験がバックボーンとしてあったからなのだ。
戦前ドイツでナチス政権が誕生したのは、この児童文学が発表されたのと同じ、1933年(昭和8年)のことである。
作者ケストナーもまた、自由主義の作家として表現の自由を奪われていたが、本作『飛ぶ教室』には、ナチス政権に対する無言の抗議とも読み取れる場面が少なくない。
「平和を乱すことがなされたら、それをした者だけでなく、止めなかった者にも責任はある」などの言葉は、全体主義国家へと突き進む祖国への警鐘だったのかもしれない。
少年たちの友情、大人同士の友情、少年と大人との交友、家族の愛情、人生の希望と困難、そして、自由で平和な社会への憧憬、、、
様々な読み方をすることができるというところに、この物語の深みがあるような気がする。
だからこそ『飛ぶ教室』は、大人にも読んでほしい児童文学の名作と言えるのだ。
ワクワクとするクリスマス物語
本作『飛ぶ教室』を、いっそう楽しいものにしているのは、この物語は、クリスマス休暇を目前にした寄宿学校が舞台になっている、ということである。
明るく照らされた店先は、モミの小枝とガラス細工でかざられていた。おとなたちは、いわくありげな顔で買い物の包みをかかえ、店から店へと走りまわっていた。あたりにはクリスマスのクッキー、レープクーヘンの香りがただよい、まるで道の敷石がレープクーヘンでできているみたいだった。(エーリヒ・ケストナー「飛ぶ教室」池田香代子・訳)
もうすぐ二週間の休暇が始まり、子どもたちは、家族の待つ家庭へと帰ることができる。
そのようなワクワク感が、物語に高揚感を与え、子どもたちのときめきを共有できる仕掛けとなっている。
ドイツのクリスマス菓子、レープクーヘンが食べたくなった。
書名:飛ぶ教室
著者:エーリヒ・ケストナー
訳者:池田香代子
発行:2006/10/17
出版社:岩波少年文庫

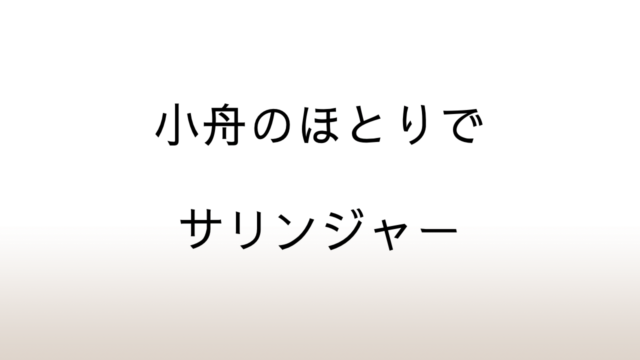
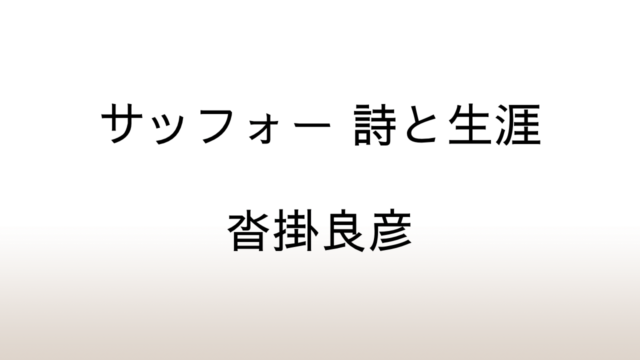
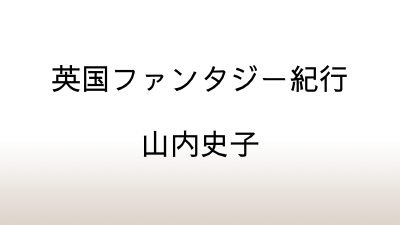
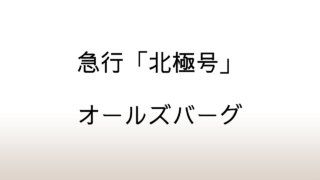
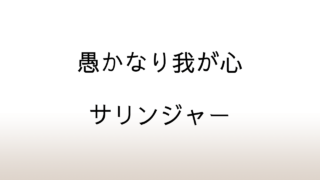
003-150x150.jpg)




