クリス・ヴァン・オールズバーグ『急行「北極号」』読了。
本作『急行「北極号」』は、1985年(昭和60年)にアメリカで刊行されたクリスマス物語の絵本である。
日本では、1987年(昭和62年)に、村上春樹の翻訳によって出版された。
2004年に公開されたアメリカ映画『ポーラー・エクスプレス』の原作である。
サンタクロースを信じる人にしか聞こえない鈴の音
サンタクロースの存在を信じている少年が主人公である。
友だちは「サンタクロースなんていない」と言うが、少年は、そんな言葉を信じたりしない。
クリスマス・イブの夜中、サンタの橇の鈴の音を待ち続けているとき、彼の耳に聞こえてきたのは、蒸気機関車の音だった。
少年は<急行・北極号>に乗り込み、たくさんの子どもたちと一緒に北極点を目指す。
北極点の街では、サンタクロースと小人たちが、クリスマス・プレゼントの準備をしていた。
プレゼント第1号の相手として少年を選んだサンタクロースは、「さて、君はクリスマスに何がほしいかね?」と訊ねる。
なんだって好きなものをもらえるんだ、と僕は思った。でも、僕がいちばんほしいものはサンタの大きな袋の中には入っていない。僕が何よりもほしいのはサンタの橇についた銀の鈴なのだ。(C・V・オールズバーグ『急行「北極号」』村上春樹・訳)
「サンタの橇についた銀の鈴」は、もちろん、サンタクロースの存在を信じることのできる、少年時代の純粋な心だろう。
翌朝、少年は妹サラと一緒に鈴を鳴らすが、父さんにも母さんにも、鈴の音は聞こえない。
サンタクロースの存在を信じている人にしか、鈴の音を聞くことはできないのだ。
以前は僕の友達はだいたいみんなその鈴の音を聞くことができた。でも年月が経ってしまって、もうその音は誰の耳にも届かない。サラはある年のクリスマスにそれを振ってみたが、彼女にさえその美しい音は聞こえなかった。(C・V・オールズバーグ『急行「北極号」』村上春樹・訳)
だけど、大人になった少年は、今もまだ、鈴の音を聞くことができた。
本当に信じていれば、それはちゃんと聞こえるんだよ──。
サンタクロースはイノセンスの象徴だった
幼少の頃、子どもたちは、誰もが無邪気にサンタクロースの存在を信じている。
年齢を重ねるうちに、少しずつサンタクロースの存在を疑問に思うようになり、やがて、サンタクロースなんて存在しない、ということを知る。
人は、それを「成長」と呼ぶのだ。
いつの時代も、サンタクロースはイノセンスの象徴だった。
サンタクロースの存在を信じることができるかどうかで、その人がイノセントな心を持っているかどうかを見分けることができる。
イノセンスの踏み絵が、まさしくサンタクロースだったのだ。
『急行「北極号」』の主人公の少年は、子どもから大人へと成長していく過程の、おそらく入り口にあったのだろう。
友だちが「サンタクロースなんて絶対にいない」と言い張っても、少年だけは、サンタクロースの存在を信じている。
イノセンスを失いつつある年代の中で、かろうじて、少年は踏み止まっていたのだ。
もしも、彼が、サンタクロースの存在を信じることのできない少年であったなら、そもそ<急行・北極号>は、彼の前に現われなかっただろう。
<急行・北極号>は、サンタクロースの橇の鈴と同じように、それを信じるものにしか見ることができないからだ。
興味深いのは、大人になった少年が、今でもサンタクロースからもらった橇の鈴の音を聞くことができる、ということ。
「本当に信じていれば、それはちゃんと聞こえるんだよ」という最後の言葉は、イノセントな心を失ってしまった大人たちへのメッセージだろう。
<北極点の街>は、あるいは、彼の心の中の自我ととらえることができるかもしれない。
しかし、そんな余計な深読みをなしにしても、本書は美しいクリスマス物語の絵本として、純粋に楽しむことができる。
むしろ、おかしな詮索をやめて、天真爛漫な気持ちで向き合うべき絵本なのかもしれない。
『急行「北極号」』を楽しく読むことができるかどうかということが、既にイノセンスの踏み絵になっているような気がした。
書名:急行「北極号」
著者:C・V・オールズバーグ
訳者:村上春樹
発行:1987/12/10
出版社:河出書房新社
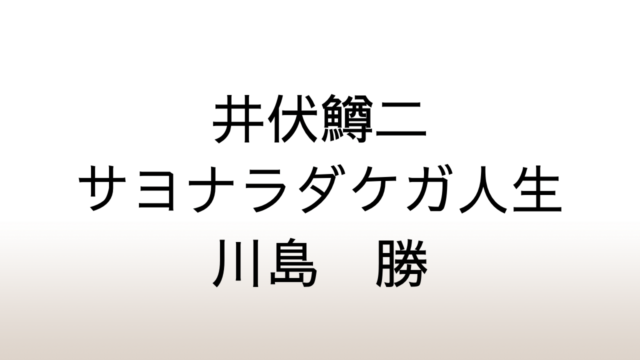
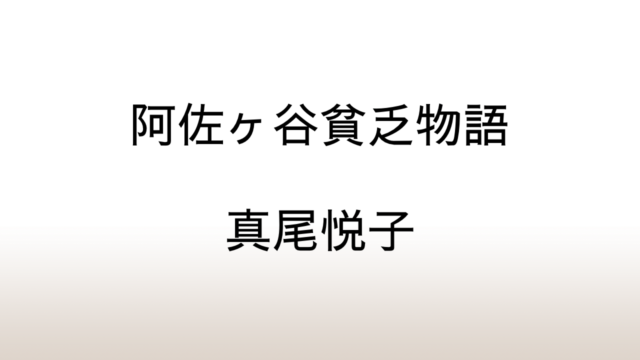

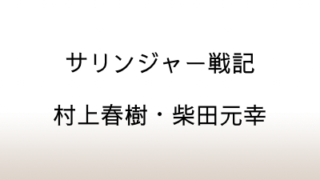

003-150x150.jpg)




