木山捷平「酔いざめ日記」読了。
本作「酔いざめ日記」は、1972年(昭和47年)11月から1974年(昭和49年)9月まで『浪漫』に連載された日記である。
著者は、1968年(昭和43年)8月に64歳で他界しており、妻の木山みさをが編集に携わっている。
単行本は、1975年(昭和50年)8月に講談社から刊行された。
井伏鱒二や太宰治との交遊
木山捷平29歳から、64歳で没するまでの日記である。
時代にすると、1932年(昭和7年)から1968年(昭和43年)までで、昭和初期(戦前)、戦中、戦後、高度経済成長期という、激動の昭和という時代を生きた一人の作家の姿が、そこにある。
概括してしまうと、飄逸なユーモア小説の書き手として知られる木山捷平も、やはり生々しい昭和文士の一人であり、時代に翻弄された一人の庶民であったということだ。
例えば、昭和8年1月1日(元旦)の文章。
いよいよ三十となったが立てもせず。失業中。文学がやり通せるか。又ツトメを心がけようかと考える。一日中炬燵でねてくらした。(木山捷平「酔いざめ日記」)
昭和12年2月10日。
仕事をしない自分。久しく仕事をしない自分をかなしく思う。「海豹」三人組と呼ばれた大鹿卓は「新潮」三月号に小説をかいてどんどん仕事をしている。太宰も正月号の「改造」に書き、名をひろめた。私一人がぶらぶら酒などのんで歩いている。嗚呼仕事に没入したい。(木山捷平「酔いざめ日記」)
文学仲間たちの中で出遅れている印象を感じていたらしく、「古い友人に逢うと皆偉くなっているので私は何故となく淋しい。仕事がしたい」ともある(昭和14年4月10日)。
当時の仲間うちでの評価は「木山は井伏のメイで中谷のオイだ」(外山繁)、「木山はかわいそうだ。父危篤はいいもんだ。しかしあれは、瀧井孝作だ、川崎長太郎だ」(林房雄)などだったらしい。
実際、井伏鱒二の名前は頻繁に登場していて、親しい飲み仲間であったことが分かる。
ハチマキして来訪の新庄、塩月と面談。風気ぬけず声かれてろくろく出ない。三人で高円寺を歩きお茶をのみダイバ通りより阿佐ヶ谷に出る道で井伏氏、太宰にあい、ピノチオで蜜豆を食い、中野のタンポポに行き、酒をのみ、昨夜高円寺で逢った女給の店ラインに行き失望し、電車にのりて帰る。(木山捷平「酔いざめ日記」)
太宰治が呼び捨てなのは、親しい同世代の友人だったからで、昭和11年には、太宰治『晩年』の出版記念会に出席、「へんな会であった」「一同そっぽを向いているふうであった」と記されている(7月11日)。
「虚無。朝床の中で、誰か首でもしめて呉れればそのまま死んでしまいたい。そんな気持、ぐんにゃり一日を送る」とあるのは、昭和13年1月9日で、相変わらず、仕事に行き詰っている様子が推測される。
昭和14年もそれは続いたらしく、1月31日のところに「人にものをたのむ苦しさ、三十六歳の一月もかくして今日で終わりぬ」「さびしさひしひしと胸をつく」とあった。
この年は、『抑制の日』が芥川賞候補になっていたが、受賞はならず。
僕は当選はしないと思っていたが、それでも、もしかという気も心の中のどこかにあったので、他人の前でこんな発表を見るのは嫌であった。お前の文学なぞ駄目だと、世間から言われているようで、自己嫌悪はなはだし。(木山捷平「酔いざめ日記」)
『文藝春秋』の芥川賞選評を読んだときの落胆は一層ひどくて、「選者たちは神様にでもなったつもりか」「腹がかきむしられるようだ」「こんなに書かれてはめいるばかりだ」と、口惜しさを文章に示している。
それでも、自分のペースで文学と向き合い、昭和16年4月30日の『昔野』『河骨』の出版記念会には、井伏鱒二、青柳瑞穂、太宰治、村上菊一郎、中谷孝雄、小田嶽夫など、多くの仲間が集まって、祝福してくれた。
太平洋戦争に突入すると、文学どころではない時代が続き、満州へ渡った木山捷平も、生きるか死ぬかの厳しい生活を強いられる(このあたりの経験が、戦後、文学作品として結実するのだが)。
この間の日記が残っていないのは残念。
芸術選奨受賞とがんとの闘い
昭和24年11月10日、戦前から続く阿佐ヶ谷に出席するも、「古谷(綱武)に満座の中で侮辱され、苦しむ。その夜は酔って、小田と青柳邸にとまった」「腸が煮えくり返るような気持」とある。
翌年(昭和25年)も、井伏鱒二の読売文学賞祝賀会の参加費を工面するため、質屋を訪れるなど、窮乏生活は続いた(7月21日に「収入少く死ぬほど寂莫」とある)。
一月七日にひいた風邪咳に苦しんだが、やっと元気になった。懐中時計を入質して三百円。嗚呼いやなさびしい人生、死にたいような気持でくらした。小山書店に二度電話をかけたが断られた。(木山捷平「酔いざめ日記」)
戦争直後は、多くの作家が生活に苦しんだが、ヒット作のない木山捷平の貧窮には、人並み以上のものがあったのかもしれない。
昭和27年8月10日に「木山捷平を激励する会」が、新宿樽平で催され、井伏鱒二、河盛好藏、外村繫、小田嶽夫、浅見淵、村上菊一郎、亀井勝一郎など、阿佐ヶ谷会のメンバーを中心に、親しい仲間が集まった。
小沼丹や吉岡達夫の名前もあり、この頃から三人の親交が始まったらしい。
特に、小沼丹は、井伏邸での将棋の会にも、ちょくちょく名前を見せるようになる。
庄野潤三の名前が現れるのは、昭和28年10月31日で、「留守中に庄野潤三氏来訪あった由、自動車にて。稿料持参されて恐縮」とあるのは、当時の庄野さんは、まだ放送局に勤める会社員だったからだ。
ラジオ放送の原稿を、庄野さんは、生活に困っている作家にお願いしては、原稿料を渡していたという。
二人が実際に対面するのは、昭和29年1月16日、庄野潤三『愛撫』・小島信夫『小銃』の出版記念会の会場だった(「庄野君とはじめて逢う」の記述がある)。
この年、木山捷平は51歳で、新進の若手作家が次々と登場してくる状況を、どのように受け止めていたのだろうか。
この年の12月30日には「収入の少ない生活がつづくと、いらいらして円形ハゲになるとは、笑い話のような、かなしいことである」と記している。
潮目が変わったのは、昭和38年3月26日。
文部省芸術課蛭間氏より電話あり。十一時半頃。『大陸の細道』が芸術選奨文部大臣賞と決定とのことなり。(木山捷平「酔いざめ日記」)
奇しくも、この日は、木山捷平60歳の誕生日で、この日を境に、木山捷平は人気作家の仲間入りをする。
マスコミの取材が相次ぎ、直木賞を受賞した山口瞳も「現存の作家では、木山捷平、庄野潤三さんが好きです。おやっと思うくらい、素晴らしい短篇を書きますから」と絶賛した(4月9日)。
5月21日に中野ほととぎすで開催された芸術選奨祝賀会には、井伏鱒二、青柳瑞穂、河盛好蔵、伊馬春部、谷崎精二、中谷孝雄、三好達治、檀一雄、亀井勝一郎、横田瑞穂、小沼丹、庄野潤三、吉行淳之介など、57人の仲間が出席。
昭和41年3月26日、62歳の誕生日には「よくも生きて来たと思うこともあった」と綴られている。
それにしても、日本武道館でのビートルズ公演の取材を担当するなど(6月30日)、芸術選奨受賞後は、いきなり多忙を極めているから、作家の世界というのはすごい。
昭和42年6月12日に『潮』から特集のための「私の貧乏生活六枚を書け」と言われたときも、「多忙のため」断っている。
華々しい作家生活の潮目が変わったのは昭和43年で、4月に入院して以降は、『酔いざめ日記』も闘病日記の様相を帯びてくる。
妻の言葉の中に「肝臓、その他に転移していないので手術が出来る」云々──ひどい言葉だ! 泣くにも泣けないほど悲しかった。怒鳴りちらした。茶碗も投げつけてやった。「これからすぐ帰れ帰れ」といって帰した。(木山捷平「酔いざめ日記」)
窮乏時代の日記も良かったが、晩年の闘病記も素晴らしい。
貧しい生活と病魔との戦いが、究極の人間らしさを表出させているのではないか。
昭和43年8月20日からは「今日より妻筆記」とあり、「もう死ぬかも知れん、えらいえらい(苦しいという方言)」「もう原稿は書けないよ」などの言葉が並ぶ。
臨終は8月23日1時23分。
病気は食道がんで、5か月に及ぶ入院生活だった。
一人の作家の日記が、こんなにも素晴らしいものであることを、初めて知ったような気がする。
随所に社会的事件の記述もあり、木山捷平という作家が、昭和史の中で生きてきたことが、リアルに理解できるところもいい。
そして、阿佐ヶ谷会を中心とする多くの文学仲間たちと過ごした、酒を酌み交わす日々。
窮乏記、交遊録、闘病記、そんなものが混然一体となった日記文学が、本作『酔いざめ日記』なのだ。
とどのつまり、それは、人間の記録ということなのだろう。
書名:酔いざめ日記
著者:木山捷平
発行:1975/08/20
出版社:講談社

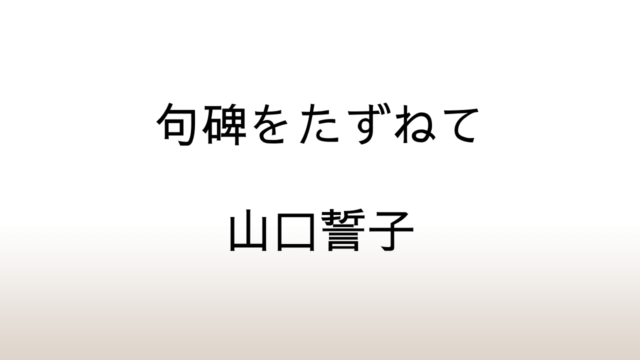


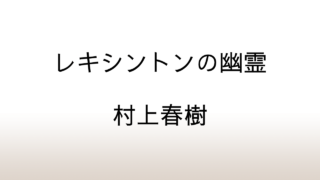
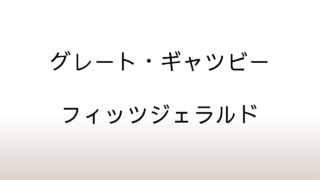
003-150x150.jpg)




