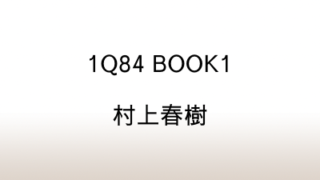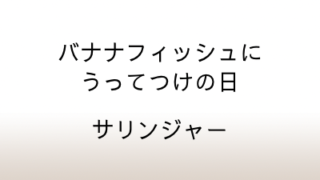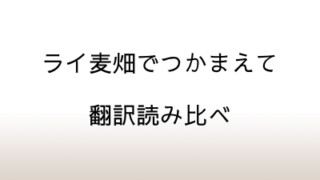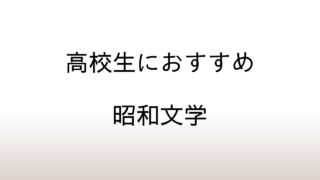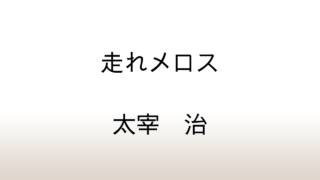小沼丹「藁屋根」読了。
本作「藁屋根」は、1972年(昭和47年)1月『文藝』に発表された短編小説である。
この年、著者は54歳だった。
作品集としては、1975年(昭和50年)10月に河出書房新社から刊行された『藁屋根』に収録されている。
長編『更紗の絵』のスピンオフ的な作品
本作「藁屋根」は、いわゆる<大寺さんもの>として第八作目の作品である。
1972年(昭和47年)6月に刊行された長編小説『更紗の絵』と同様に、終戦直後の著者の生活を題材に採っている。
その頃、大寺さんは大きな藁屋根の家に住んでいた。正確に云うと、郊外にある大きな藁屋根の家の二階を借りて住んでいた。大寺さんは結婚したばかりで、その二階が新居という訳であった。(小沼丹「藁屋根」)
この「大きな藁屋根の家」は、『更紗の絵』に登場するのと同じ家で、作品中に出てくるエピソードも、ほぼ『更紗の絵』を再現したものと言っていい。
ただし、本作「藁屋根」の主人公は大寺さん(つまり著者自身)ではなく、かつて「大きな藁屋根の家」に住み、現在はすっかりと落ちぶれてしまっている一人の老人である。
その大きな藁屋根の家が昔は銀行だった、と大寺さんに教えて呉れたのは家主の細君である。昔と云っても、いつ頃のことか大寺さんには判らない。家主の細君は、肥って眼玉のくりくりした女でよく喋る。そのお喋りに依ると、何でもその家には大金持が住んでいて、私設の銀行を開いて、取引は近県にも及んだと云う。(小沼丹「藁屋根」)
「藁屋根の家に住んでいた大金持」が、本作の主人公となるが、このエピソードは『更紗の絵』には出てこない。
つまり、本作「藁屋根」は『更紗の絵』のスピンオフ的な作品ということになる。
もしかすると、『更紗の絵』の単行本化の作業を進めているうちに、このような作品の構想が生まれたのかもしれない。
そういう意味では、先に『更紗の絵』を読んでいるので、物語の全体像がイメージしやすくて良かった。
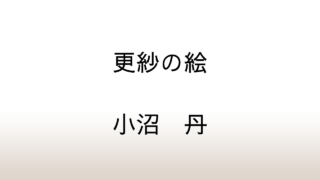
落ちぶれた男の人生への共感
もっとも、肝心の主人公の老人は、作品中にチラッと顔を出すだけである。
大寺さんが学校へ通う路の途中に、トタン屋根の小さな家が一軒あった。入口は硝子戸で、破れた硝子に紙が貼附けてある。天気の好い日だと、家の前に筵を敷いて爺さんが一人坐っていた。(小沼丹「藁屋根」)
大寺さんは、この爺さんが何者か気にも留めないが、ある日、細君が驚くようなニュースを持ってきた。
「そのトタン屋根の小さな家に住む爺さんが、嘗て羽振の良かった『銀行』の主の変り果てた姿である」という。
その事実を教えてくれたのは、細君が仲良くしている近所の「牛乳屋さん」の細君だった。
大寺さんは、爺さんの家に若い女がいるのを知っていた。それ迄は何とも思わなかったが、これは爺さんの孫娘で、夫が戦地に行っているので爺さんの世話をしているのだそうである。息子がいるが、これは爺さんの所に寄附かないらしい。(小沼丹「藁屋根」)
若い大寺さんは、落ちぶれた人物というものに関心を抱くが、老人と大寺さんとの交流が始まったりはしない。
爺さんに関する情報源は、家主の細君と牛乳屋の細君との世間話だけである。
しかも、家主の細君は、爺さんのことには触れたがらない様子だから、いよいよ妙な気がしてくる。
間もなく、落ちぶれた爺さんは死んでしまう。
大寺さんは、一人の男の人生というやつに、感傷的ではなく、冷静に共感しているのだが、そこにこの物語のテーマがある。
読み終わった後に、割り切れない何かが残る、そんな小説だった。
つまり、その割り切れないところが、人生の綾というものなのだろう(良くも悪くも)。
作品名:藁屋根
著者:小沼丹
書名:藁屋根
発行:2017/12/08
出版社:講談社文芸文庫

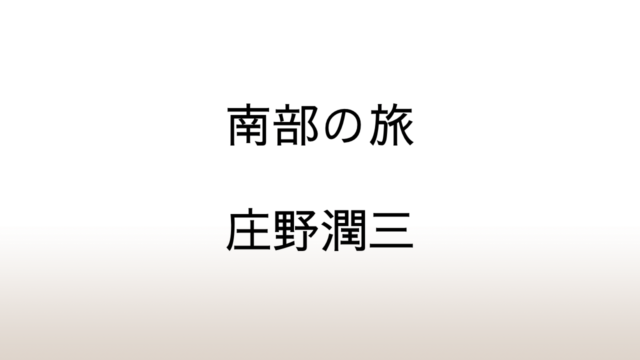
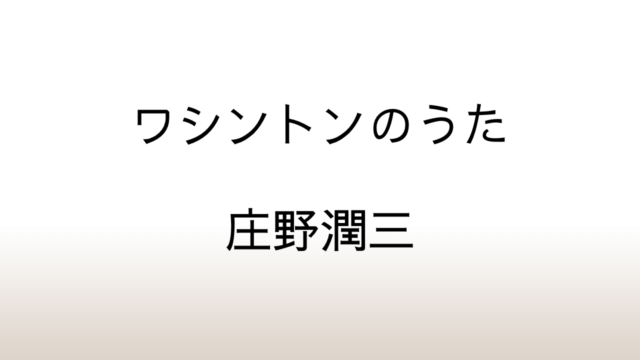
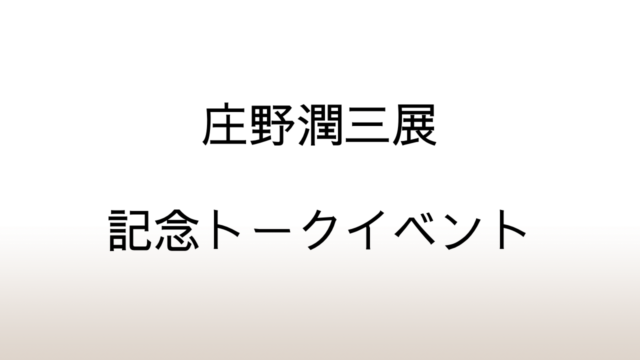
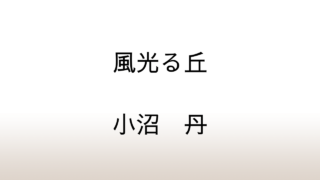
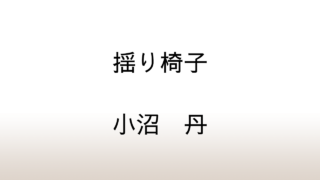
003-150x150.jpg)