「世をへだてて」は、1986年から1987年にかけて発表された連載エッセイで、庄野潤三生誕百年記念で、講談社文芸文庫から刊行された(初文庫化)。
カバー文には「闘病記」とあるが、第一話にあたる「夏の重荷」を読むと、ほとんど病気のことには触れていないので、おやっと思う。
それは、福原麟太郎が心臓病での長い病院生活から退院した後に発表した「秋来ぬと」に関する思いを著したもので、同じように闘病生活を送る著者(庄野潤三)が、福原さんの文章から大きな励ましを得たことが熱い筆致で綴られているもの。
第二話「杖」以降の話は、発病時から退院するまでの様子が非常に詳しく描写されていて、あたかもドキュメンタリーのようだが、味気ない記録文書ではもちろんない。
最大の特徴は、ほとんど意識のなかった入院当時の様子が、家族の述懐を通して丁寧に再現されていく、その手法で、「長女のはなし。」などと前置きした後に、長女の回想を記録する形で構築される物語は、いかにも庄野文学らしい。
また、入院生活の思い出を語りながら、福原麟太郎も愛用したポケット・オックスフォード辞典や「トム・ブラウンの学校生活」、小沼丹のエッセイ集「小さな手袋」、ガンビア留学時代の思い出、チャールズ・ラムの「エリア随筆」、ロシア伝説集など、話題があちこちに寄り道をしていくのも、庄野潤三らしい、物語の綴り方である。
もうひとつ、著者は闘病生活を描きつつ、入院時に交流のあった人々の様子を、いつものように飾らない文章で、さりげなくスケッチしていくが、「大部屋の人たち」や「同室の人」などのタイトルの付いた章は、著者がこよなく愛して描き続けてきた名もなき市井の人々の、入院生活を通して発見した暮らしの一端である。
書名の「世をへだてて」については、あとがきの中で、「恰も谷間をへだてるように今は向う側の国にいらっしゃる福原さんに対して感謝を述べるといった心持をこめて、通しの題名を「世をへだてて」としてみた」「谷間をへだてたあちら側にいる親しい人のなかに父母、長兄がいて、福原さん同様、励ましを受けた」と記されている。
幾層にも積み重ねられた証言
あとで葛代さんから聞いたんだけど、車のなかで「まだなんにもしてないのに」とそればかりいってたっていうの。まだなんにも、というのは(と長女は口ごもりながらいった)親孝行を、というつもりらしいけど。(「北風と靴」)
父が倒れて救急車で運ばれたという連絡を受けたとき、長女自身も気が動転していて記憶が定かではない。
そこで、長女も、自身の周りにいた親しい人々の記憶を引用しながら、そのときの様子を再現してみせる。
こうして、多くのひとたちの証言が幾層にも積み重ねられて、著者の入院当時の様子が多角的に描かれていく。
人生の大きな転換期の原因となる出来事と、著者は正面から向き合っていたのだ。
庄野文学の大きな転換点
当日はミサヲちゃん(十月に結婚した次男の嫁)もあつ子ちゃんも来て、みんなで引越しの荷物を纏めるのを手伝ってくれた。ミサヲちゃんがときどき生あくびをしている。お母さんがその様子に気が附いて、「ひょっとしたら、ミサヲちゃん、おめでた?」と訊くと、「はい、そのようです」とミサヲちゃんらしい口調で答えたので、みんなで、おめでとうといった。(「Dデイ」)
家族小説の名手として知られる著者だが、作家人生の中では、大きな波がある。
最初に書いた家族小説は、昭和31年の「ザボンの花」。
次に「和子と明夫と良二」という子どもたちを含めた五人家族が登場するのが、昭和39年の「鳥」で、この後、著者は毎年のように「夕べの雲」「雉子の羽」「絵合せ」「明夫と良二」などといった、5人家族の物語を発表し、昭和51年の「鍛冶屋の馬」まで続いた。
次に、こうした家族物語が登場するのは、昭和63年の「インド綿の服」で、その後、「エイヴォン記」などのフーちゃんシリーズや、「貝がらと海の音」などの夫婦の晩年シリーズが、亡くなるまで発表され続けていくことになる。
「ひょっとしたら、ミサヲちゃん、おめでた?」と話題に出ているのは、後の「文子(フーちゃん)」で、庄野文学の集大成とも言える晩年の作品群は、昭和62年に本書「世をへだてて」を発表した後から始まったと言っていい。
つまり、作家のターニング・ポイントを見届ける意味で、本書「世をへだてて」は、極めて貴重な作品であるということだ。
本書を単なる闘病記ではなく、そんな家族の物語として読んでいくことはできないだろうか。
書名:世をへだてて
著者:庄野潤三
発行:2021/2/10
出版社:講談社文芸文庫



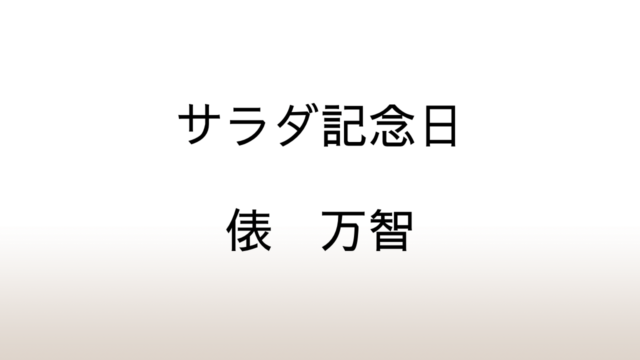
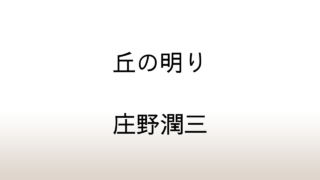
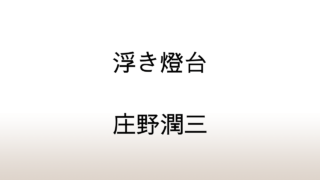
003-150x150.jpg)




