村上春樹「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」読了。
本作は、伊勢丹百貨店『トレフル』1981年(昭和56年)7月号に発表された短編小説である。
この年、著者は32歳だった。
作品集としては、1983年(昭和58年)に平凡社から刊行された『カンガルー日和』に収録されている。
山手線の広告ポスターで見かけた女の子
長篇小説『1Q84』を読んだとき、なんだ、これは「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」じゃないか、と思った。
村上春樹の作品には、時々そういうことがあるから楽しい。
あらすじは、極めてシンプルだ。
4月のある晴れた朝、原宿の裏通りで、<僕>は100パーセント好みの女の子とすれ違う。
<僕>は、なんと言って声をかけようか考える。
何も言えずに彼女とすれ違った後で、<僕>は、彼女に話すべき言葉を思いついた。
それは、「昔々」で始まり、「悲しい話だと思いませんか」で終わる、ちょっとした物語だったのだ。
「ねえ、もう一度だけ試してみよう。もし僕たち二人が本当に100パーセントの恋人同士だったとしたら、いつか必ずどこかでまためぐり会えるに違いない。そしてこの次にめぐり会った時に、やはりお互いが100パーセントだったなら、そこですぐに結婚しよう。いいかい?」「いいわ」と少女は言った。(村上春樹「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」)
しかし、悪性のインフルエンザで記憶を失った二人は、互いの存在を、もはや思い出すことはできない。
やがて、14年後の原宿の裏通りで、二人はすれ違う。
互いに「100パーセントの異性」だと、心の中で感じ取りながら──。
日常生活の中の妄想を小説に仕上げた作品だけれど、妄想にしては、とても良くできている作品だと思う。
そして、実際に、この作品は評判が良くて、山川直人監督によって映画化もされたし、外国でも翻訳紹介され、『1Q84』という大長編小説の源泉ともなった。
著者の村上春樹自身、この作品は『カンガルー日和』の中で最も好きな作品だと言っている。
この話は僕が満員の山手線の車中である広告ポスターを見かけたことが原形になっている。そのポスター(何の商品の広告だったのかどうしても思いだせない)のモデルになっていた女の子に、僕は理不尽なくらい激しく惹かれた。胸がいっぱいになって、脚が震えた。それは今思いおこしても本当に運命的な出会いだったのだ。(村上春樹「村上春樹全作品1979-1989(5)」)
短い作品であるだけに、様々な可能性に満ちた小説である、と言うことができるのかもしれない。
不思議な意味を持つ出会いと別れ
この掌編小説の根底にあるのは、運命への不信感である。
100パーセントの恋人同士が出会う。
それは、ある意味で運命的な出会いのようにも思えるが、一度離れてしまえば、二度と出会うことはない。
かつて、彼らを結び付けたものは、「運命」ではなく「ただの偶然」だったのだから。
それは、1960年代という学生運動の時代を生きてきた世代に、もしかすると共通する人生論のようなものなのかもしれない。
社会は、運命によって変革できるものではなく、無数の偶然の積み重ねによって大きく変動していくものなのだ、といったような。
そして四月のある晴れた朝、少年はモーニング・サービスのコーヒーを飲むために原宿の裏通りを西から東へと向い、少女は速達用の切手を買うために同じ通りを東から西へと向う。二人は通りのまんなかですれ違う。失われた記憶の微かな光が二人の心を一瞬照らし出す。(村上春樹「4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて」)
記憶を失った二人が、再び結ばれることはない。
ここに、運命論では語れない、人生の皮肉があり、男女関係の哀しさがある。
小説とも言えないくらいの短い話なので、4月になったら読んでみてはいかがだろうか。
出会いと別れの持つ意味が、少しだけ不思議なものに思えてくるかもしれないから。
作品名:4月のある晴れた朝に100パーセントの女の子に出会うことについて
著者:村上春樹
書名:カンガルー日和
発行:1986/10/15
出版社:講談社文庫

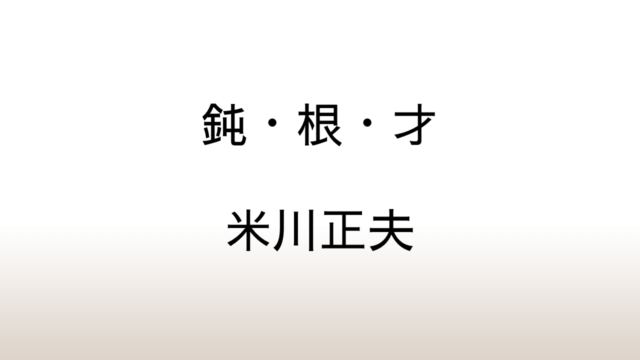
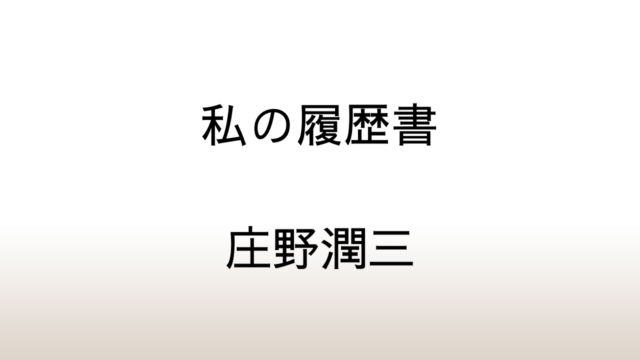
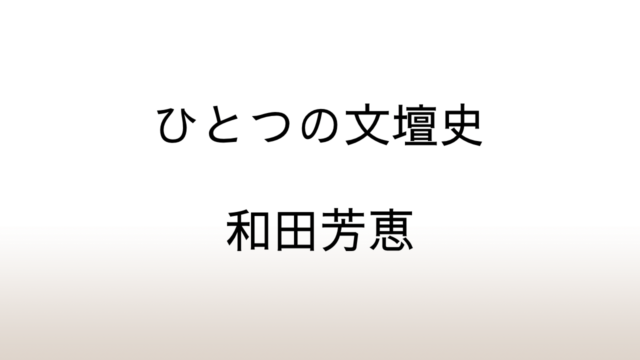
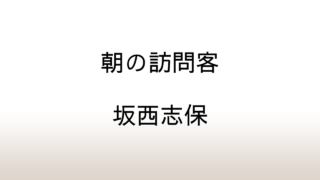
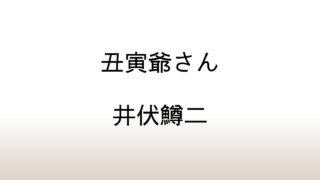
003-150x150.jpg)




