庄野潤三『庭のつるばら』読了。
『庭のつるばら』は「静かなブーム」と言われて久しい庄野文学晩年の代表作「夫婦の晩年シリーズ」の第4作目の作品である。
あとがきから引用する。
子供が大きくなり、結婚して、家に夫婦二人きりで暮すようになってから年月たった。そんな夫婦が毎日をどんなふうに送っているかを書いてみたい。その第一回が「新潮45」に連載した『貝がらと海の音』(新潮社)であった。この本が出たのが1996年。続いて「群像」に連載した『ピアノの音』(1997年、講談社)、「文學界」に連載した『せきれい』(1998年、文藝春秋)、今度の「新潮」連載の『庭のつるばら』(1999年、新潮社)ということになる。同じようなことばかり書き続けて飽きないかといわれるかも知れないが、飽きない。夫婦の晩年を書きたいという気持ちは、湧き出る泉のようだ。(「あとがき」)
連載小説『庭のつるばら』は、「新潮」1998年1月号から12月号まで12回にわたって発表されているが、物語は、1997年5月に始まって、同年の秋(10月か?)で完結する。
夏を愛する作家だった庄野さんらしく、一番好きな季節を書いたものと思われるが、「こどもの日」の話から開始した連載を「敬老の日」の話題で締めくくっているのはさすがで、季節の流れの中に、緩やかな世代交代の流れがしっかりと描かれている。
庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」は、「子供が大きくなり、結婚して、家に夫婦二人きりで暮すようになってから年月たった。そんな夫婦が毎日をどんなふうに送っているかを書いてみたい」という作家の思いを反映して、老夫婦のささやかな日常が淡々と綴られてゆくという、そんな物語だ。
普通の庶民である老夫婦の日常には、そうそう突飛な事件は起こらないから、自宅の庭に咲くバラの花や、妻との暮らしぶり、3人の子どもたちの家族の成長、近所の人たちとの交流の様子などが、主な内容となってくる。
しばしば「日記のようだ」と言われる庄野さんの作品だが、「夫婦の晩年シリーズ」は、老夫婦の日常を綴った日記のようなものなので、あながち誤った指摘とは思われない。
ただし、庶民の日記を小説化するにあたって、庄野さんは書き込むべき内容を徹底的に精選していると思われるから、正確な意味での日記ではないことに注意すべきである。
庄野さんは、日常のささやかな幸せ、楽しかったことや嬉しかったこと、感動したことなどに焦点を当てて作品を書いているから、不愉快だったことや嫌な気持ちになったことなどは、ほとんど描かれていない。
そういう意味で、庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」は完全なるフィクションだし、ある種の夢の世界を綴った「お伽噺」であるとも言える。
「そんな平和な暮らしがあるものか」と思われるような平和で穏やかな暮らしが、庄野さんの小説の世界にはあって、それがこの「夫婦の晩年シリーズ」の大きな魅力となっている。
私は以前、八十になるまで泳ぐといっていたが、どうやらそれはとり消しにした方がよさそうだと思うようになった。
何気ない日常生活の中にも起伏はあって、その大きな波のひとつが「伊良湖大旅行」だった。
これは、庄野さんの喜寿のお祝いに、3人の子どもたちの家族と一緒に、二泊三日で伊良湖ビューホテルへ海水浴に出かけたときのエピソードだが、若い頃から海が大好きで、賑やかな集いが大好きだった庄野さんらしい、楽しく愉快な旅行記となっている。
もうひとつの大きな波は、近所の清水さんが亡くなられてしまったことだろう。
丹精込めて育てたバラの花をくれる近所の清水さんは、『エイヴォン記』以降の作品で、実に重要な役割を果たしてきた登場人物の一人である。
『エイヴォン記』の作品名そのものが、清水さんから頂いたバラ(エイヴォンという)の名前に由来しているし、清水さんとの交流は、夫婦の晩年シリーズの中で大きな柱の一つとなっていた。
『庭のつるばら』では、清水さんのお通夜や葬儀の様子を通して、庄野夫妻の悲しみの大きさが、はっきりと伝わってくる。
考えてみると『庭のつるばら』では故人の話題が多い。
『早春』で神戸の案内役となった旧友の松井嘉彦の思い出話や、旧友の小沼丹の遺族から届いたスケッチ集「馬画帖」、第三の新人の仲間だった遠藤周作の一周忌、伊良湖旅行では「椰子の実」の作曲家である大中寅二を偲び、連載中には、一緒に中国旅行をして以来の付き合いだった福田宏年の訃報にも接している。
つまり、それが、間もなく喜寿を迎える老夫婦が生きている時代だということなのだろう。
伊良湖行きを前にして、庄野さんは「私は以前、八十になるまで泳ぐといっていたが、どうやらそれはとり消しにした方がよさそうだと思うようになった」「海が少し怖くなったのかもしれない」と綴っているが、老いることの不安が、海好きだった作家に、このような弱音を吐かせていたのかもしれない。
替え歌「松原とうちゃんきゆるかあちゃん」
一方で、未来に向けた世代交代の流れを捉えることも、庄野さんは忘れていない。
その象徴が、足柄山で暮らす長女のところの長男(和雄)の婚約だろう。
26歳になってお嫁さん探しを始めようと考えていた和雄は、庄野さんの妻の世話によって、23歳の幼稚園の先生と交際を始め、二人が婚約したところで物語は終わる。
「清水さんの死」と「和雄の婚約」が緩やかな世代交代の流れを誠実に描いているところが、この『庭のつるばら』という小説の大きなテーマになっていると感じた。
もっとも、それは、この作品を文学的に大きく考察した時に感じるものであって、『庭のつるばら』の本当の醍醐味は、数多く織り込まれている断片的なエピソードにこそあるのだと考えたい。
唱歌「海」をハーモニカで演奏しながら、幼いころ「松原とうちゃんきゆるかあちゃん」と替え歌を歌っていた子どもたちのことを思い出したり、同じくハーモニカで「まなびやとざして 真昼しずか」という歌詞のある「夏休み」を演奏しながら、かつて留学したケニオン・カレッジの夏の情景を思い出してみたり。
庭で雀がさえずるのを聞いた妻が「何か話しているようでしたね」「ドリトル先生なら分るんだけど」と言ったりする場面や、モンテーニュの「エセー」を読んだ妻が、庄野さんの作品「夕べの雲」に似ていると話す場面なども面白い。
庄野さんらしいと思ったのは、いつも方々へ佃煮を送ってもらっている根岸の三徳から入谷の朝顔市の朝顔の鉢が届いて喜んだ後で、「入谷の朝顔市が東京下町の風物詩であることはテレビなどで承知しているが、見に行ったことはない。これからもわざわざ見に行くことはないだろう」と綴っている場面。
純粋な意味で日常の暮らしを愛した庄野さんならではの言葉だと思った。
書名:庭のつるばら
著者:庄野潤三
発行:1999/4/25
出版社:新潮社





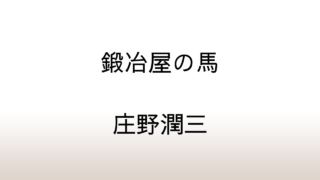
003-150x150.jpg)




