小沼丹「眼鏡」読了。
本作「眼鏡」は、1970年(昭和45年)9月『文芸』に発表された短編小説である。
この年、著者は52歳だった。
作品集としては、1975年(昭和40年)10月に河出書房新社から刊行された『藁屋根』に収録されている。
眼鏡の話をきっかけとして、昔のことを思い出す回想小説
本作「眼鏡」は、眼鏡の話をきっかけとして、昔のことを思い出す回想小説である。
老眼鏡が必要かどうかという話がきっかけだったが、今のところ、<大寺さん>に老眼鏡は必要がない。
それに、老眼鏡ではない眼鏡だったら、既に大寺さんは一つ持っていたのだ。
十年ぐらい前になるが、大寺さんは一時眩暈に悩まされたことがある。大寺山は学校の教師をしているが、その頃、教室から自分の部屋に戻って来て少し乱暴に椅子に坐ると、途端に部屋が廻転し始める。(小沼丹「眼鏡」)
友人の小説家に相談すると、それは「眼が悪いのかもしれない」ということになって、結局、大寺さんは、ひどい乱視だったことが分かる。
注文した眼鏡が出来上がるまで時間を潰そうと考えているところに、昔馴染みの「マダム」が、偶然に現われた。
一年前に「蘭」という名前の小さな酒場を辞めてしまったこのマダムと、大寺さんは何度か一緒に映画を観たことがある。
一度は「巴里祭」と云う古い映画で、何だか懐かしいから一緒に観に行った。(略)そのとき、大寺さんは色褪せた押花を見た気がしたが、マダムは、「──矢っ張り、いいわね……」と昔を懐しがっていた。(小沼丹「眼鏡」)
このとき、マダムは、館内が暗くなると眼鏡をかけて映画を観ていた。
眼鏡は、昔を思い出すきっかけであると同時に、美人マダムの思い出話に必要となる、大切なアイテムでもあったのだ。
小沼丹の小説には、死んだ人間がよく登場する
眼鏡を作って一か月ばかり経った頃、突然の報せがやって来る。
大寺さんが学校の自分の部屋で、窓の外の黄ばんだ銀杏の葉を見ながらぼんやり烟煙を喫んでいると、同僚の一人が這入って来て、「──あのマダム、死んだそうだね」と云った。(小沼丹「眼鏡」)
小沼丹の小説には、死んだ人間がよく登場する。
むしろ、死んだ人間を偲ぶために、小沼丹は小説を書いていたのかもしれない。
もちろん、マダムは、まだ亡くなるような年齢ではなかった。
しばらく忘れていた眩暈が、このとき久しぶりにやって来て、大寺さんはびっくりする。
「どこか遠くで古い懐かしい旋律が聞えるような気がした」のは、死んだマダムのことを、心のどこかで思い出していたためだろう。
大寺さんの頭の中には、古い唄とか旋律が消えずに残っていて、何かの切っ掛けでひょっこり出て来ることがあるのだ。
マダムが好きだったのは、「ロング・ロング・アゴオ」という古い唄だった。
酒場で合唱が始まると、マダムは「──ロング・ロング・アゴオを歌いましょうよ」と言った。
やがて、常連客の一人が、マダムに求婚をして断られたという噂が伝わり、それから間もなく、マダムは店を辞めた。
念願だった宝石店を始めるらしいということだったけれど、夢に破れてマダムは、既に、この世にいない。
そのとき、大寺さんは、マダムと二人で行った、小さな酒場のことを思い出した。
困惑する親爺を説き伏せて、マダムは小さな声でロング・ロング・アゴオを歌う。
暗い店で小さな歌声を聴いていると、何だかいろいろ忘れていることがぐるぐると動き出すようであった。マダムは遠い所を見ているような顔で歌っていたが、その唄と共にマダムに何が甦ったのだろう?(小沼丹「眼鏡」)
唄が終わったとき、親爺は中途半端な顔をして「──一体、何て云う唄だね?」と訊いた。
「──遠い遠い昔、って云う唄だ」と、大寺さんは答える。
マダムの中で、何が甦っていたのか、それは書かれていない。
きっと、大寺さんにも分からなかったのだろう。
こんな話は、年を取らないと、その良さが分からないのではないだろうか。
作品名:眼鏡
著者:小沼丹
書名:藁屋根
発行:2017/12/08
出版社:講談社文芸文庫

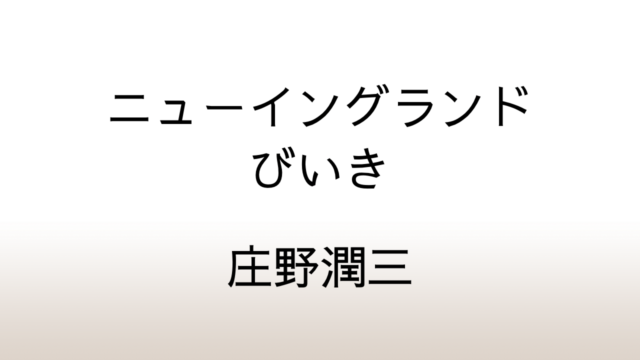
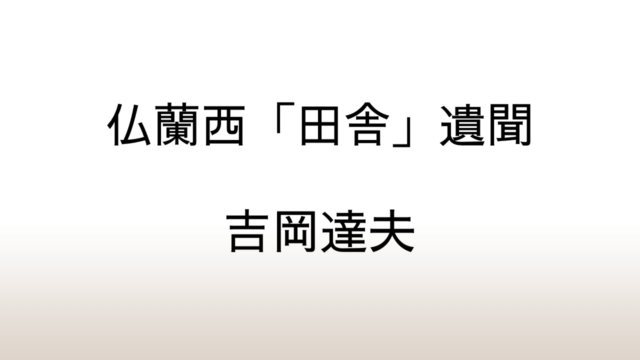
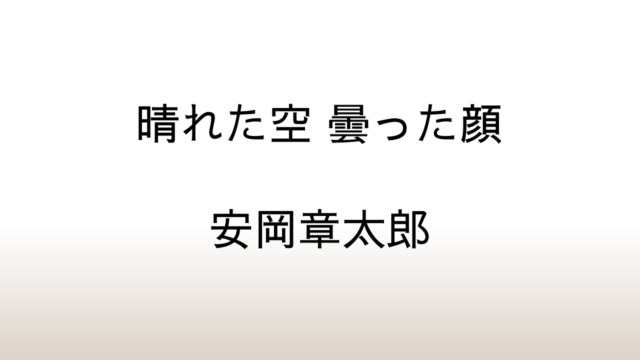

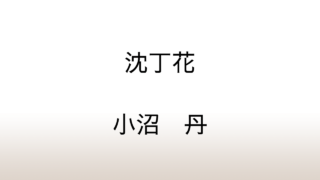
003-150x150.jpg)




