井伏鱒二「貸間あり」読了。
本作「貸間あり」は、1948年(昭和23年)1月から5月まで『週刊サンニュース』に連載された長篇小説である(タイトルは「貸間アリ」)。
この年、著者は50歳だった。
単行本は、1948年(昭和23年)8月に鎌倉文庫から刊行されている。
困窮する庶民生活の中から生まれてきた作品
本作「貸間あり」は、終戦直後の極端な住宅不足の時代を生きる庶民の姿を描いた人間ドラマの物語である。
実際、復員兵や外地引揚げなどで大量の人口が流入する中、住む場所を確保するということは、当時の人々にとって、かなり困難な問題だったらしい。
本作タイトルの「貸間あり」という言葉は、昭和20年代前半の都市生活を象徴するに、極めて強力なパワーワードだったのだ。
うら若き美女<ユミ子>がレンバン島(レンパン島)から復員してきたとき、自宅は焼け跡と化し、家族の行方は既に知れなかった。
戦争によって天涯孤独の身の上となったユミ子は、戦地で知り合った小説家<宇山>を、住宅確保の相談で訪れる。
酒と魚釣りの好きな小説家像は、もちろん、作者自身(井伏鱒二)がモデルとなっているものだろう。
本作では、青柳瑞穂がモデルと思われる骨董好きの仲間<市川瑞穂>など、井伏さんの人間関係が織り込まれているらしい(ちなみに、アパート屋敷の名前は「青柳邸」)。
宇山は、使わなくなった自分の仕事部屋をユミ子に提供し、ユミ子は、この<アパート屋敷>の一室で暮らし始める。
ユミ子の観察によると、そのアパート屋敷というところは、ことによったら貧民窟の一部分のようなものかもしれないのであった。そこには、ならずもののような若い止宿人もいた。(井伏鱒二「貸間あり」)
アパート屋敷というのは、一軒の家の一部屋ずつを賃貸住宅として提供している住宅のことで、本邸のほかに門長屋と別棟の書院を合わせて、全部で三棟の建物がある。
そして、このアパート屋敷の住民たち(小説家志望の若者や食料品加工業の男性、旦那持ちのお姉さん、闇屋のおばさん、ペンキ屋のお婆さん親子、骨董屋夫婦、盆栽屋の主人などなど)の生活を描いたものが、本作『貸間あり』という長篇小説なのである。
舞台は、井伏鱒二が暮らす荻窪の町で、敗戦直後の庶民文化も生々しいが、大変な生活なのに明るくのんびりしているところは、井伏文学らしい作品ということだろう。
「結構ですわね」ウタさんは書込みに気をとられながら、上の空のように云った。「筋書があれば、小説なんて筋書どおりですものね。でも、世の中のことだけは、そうは行かないわね」(井伏鱒二「貸間あり」)
長い物語の中で、特に印象的だったのは、闇屋女性のウタさんが、ユミ子につぶやいた言葉である。
ユミ子の恋愛相手の<五郎さん>は、小説の代筆なんかをやって生計を立てようとしているらしいが、実際の世の中は、小説の筋書きなんかのように簡単ではない、と彼女は言っているのだ。
これは、小説を書きながらも、井伏さんが常に意識していたことだったのではないだろうか。
本作『貸間あり』という作品は、困窮する庶民生活の中から生まれてきた作品という気がする。
自分が生き残るために、他の住民を不幸にする
生きることに大変な世の中で、生活は極限的なまでに苦しいはずなのに、アパート屋敷の人々は驚くほど生き生きとしている。
庶民の生きる力の強さが、この物語を支えていると言っていい。
そして、その生きる強さの根源にあるのは、戦争(あるいは国家)に対する怒りと恨みの念である。
「理由は、簡単です。僕は、桜の花それ自体は、きれいだと思います。しかし、よく一般に云いますね。花は何とか、とか、あしたに匂う何とかだとか、──ぞっとする──あの言葉には、妙な概念がつきまとう。僕は、それが不愉快です。花、それ自体ではない、それにつきまとう、概念のことです。全くあれは不愉快だ。あの概念が、三年間も僕を徴用して、マレーくんだりまで連れてったのだね。いまいましくって、仕様がない」(井伏鱒二「貸間あり」)
戦争に対する批判は、この物語において、さして重要なテーマとなっているわけではないだろう。
とは言え、戦争に対する怒りを抜きにして、戦後の庶民を語ることはできない。
そこに、昭和20年代前半の庶民像というリアリティがあったのではないだろうか。
そして、力強く生きるアパート屋敷の住民たちに、運命共同体的な意識が培われていたかというと、決してそうではなかったということも、また戦後社会の事実だろう。
ある住民は、自分が生き残るために、他の住民を不幸にすることを厭わない。
社会生活から消えていく人々を下敷きにして、戦後の人々は生きてきたと言っても過言ではないのだ。
そう思わせる社会の現実が、この物語の裏側にある。
宇山さんは木の札をとって、ちょうど短冊に揮毫でもするかのように膝をかまえた。そうして、ちょっと筆の穂さきを舐めてから「貸間あり」と少し書体をくずして書いた。その裏側には”A ROOM TO LET”と角張った書体で書いた。(井伏鱒二「貸間あり」)
新たに掛けられる「貸間あり」の札は、東京から一人の人間が消えていったことの証である。
生き残ることの難しさを教えてくれる物語だと思った。
個人的に言って、本作『貸間あり』は、『駅前旅館』や『珍品堂主人』と同じように、後世へ読み継がれていくべき井伏文学のひとつだと思う。
この作品が、現在では古い全集でしか読むことができないというのは、やはりちょっと寂しいような気がする。
作品名:貸間あり
著者:井伏鱒二
書名:井伏鱒二全集(第四巻)
発行:1974/07/23 増補版
出版社:筑摩書房

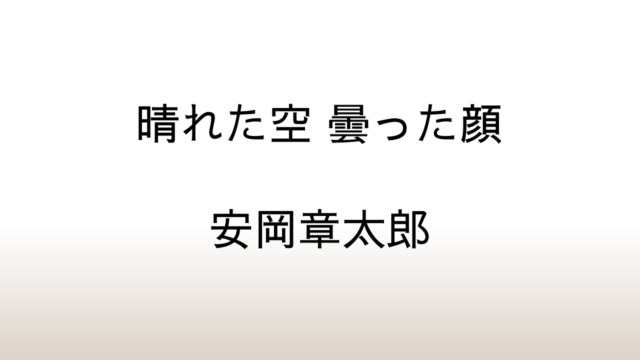

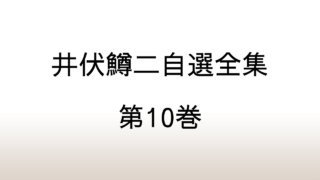
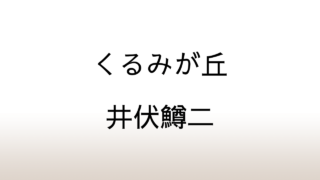
003-150x150.jpg)




