「井伏鱒二自選全集(第十巻)」読了。
本書「井伏鱒二自選全集(第十巻)」は、1986年(昭和61年)7月に新潮社から刊行されたものである。
この年、井伏鱒二は88歳だった。
人間が主役だった井伏鱒二の随筆
井伏鱒二の随筆はゆっくりとしている。
馴染みの店に腰を落ち着けて、さあ、朝までやろうじゃないかと、じっくりと盃を傾けているような、そんな時間の流れがある。
決して先を急いだりしない。
だから、「田中貢太郎先生のこと」を読んでいても、田中貢太郎とはまるで関係ない「田中さんのうちの斜向いの二階家は屑屋の家で、ここの六十前後の主人は雨の日には商売に出ないで殆ど一日じゅう時事新報を朗読した」というような、丸っきりの寄り道の文章が楽しい。
お経を誦むように抑揚をつけて、ゆっくりと読むのであった。それも新聞の題字から読みだして「東京時事新報、発行人何某、大正十何年何月何日発行」と、文字の印刷されている限り広告も職業案内も含めて隅から隅まで一字も漏らさず朗読した。(井伏鱒二「田中貢太郎先生のこと」)
井伏さんの随筆は、登場人物が生き生きとしている。
脇役なのに、全然脇役感というものがない。
井伏鱒二という作家が、いかに人間を描くことを楽しんでいたかということが、理解できるような気がする。
本編では主人公の田中貢太郎は、「お前は、どうして文壇へ出られんのじゃろうか」「わしは本当の小説はわからんきに、本当の小説のわかる人に紹介してやろう」と言って、佐藤春夫に宛てた紹介状を書いてくれたという。
こういう随筆を読むと、次は田中貢太郎という作家の作品を読んでみようという気持ちになる。
「中込君の雀」は、立川市錦町で鯛焼屋を営んでいる中込君の話である。
中込君は立川市錦町の鯛焼屋さんである。小豆と小麦粉に加工を施して、把手のついた鉄製器具で熱して鯛焼を拵えている。焼方は一個一個と焼く古いやりかただから今どきでは珍しい。別に職人気質で窮屈なことをしているのではなくて、一身上の都合から十八年前に買った鉄型をそのまま使っている。(井伏鱒二「中込君の雀」)
著名な作家も下町の鯛焼き屋も、同じ目線から描かれている。
井伏さんが見ていたのは、きっと、一人の人間だったのだ。
井伏鱒二の随筆は余韻を味わう
立川市の鯛焼き屋さんが飼っていた雀の話や、郷里の窪田さんという旧家の裏庭にあるムクの木の話などと並んで、「庄野君と古備前」という話がある。
『夕べの雲』などの作品にも登場する有名な甕を、庄野さんが入手したときのことを回想したもので、庄野夫人の手紙を引用しながら、庄野潤三という一人の人間の横顔を描いている。
いずれにしても庄野君は、身辺にあるものは些細なものまで生かして行く生きかたをしている人だ。大昔の焼物の破片まで生かしている。生かしているとは、詩にしているという意味である。(井伏鱒二「庄野君と古備前」)
巻末の「覚え書」には「庄野君の平和な生活と日常の記録を残したいと思った」とある。
庄野さんの生活を伝えるためには、家族(庄野夫人)の手紙を引用することが、きっと一番効果的だったのだろう(庄野さん自身が、家族のことを小説に書く作家だったから)。
佐藤古夢のことを綴った「『雨月物語』明治飜刻本」もおもしろい。
坪内逍遥の教え子だった佐藤古夢は、古本屋で上田秋成の『雨月物語』を見つけて、秋成研究に生涯を費やした人である。
佐藤古夢は、釣り友だち<佐藤三郎>の父親だったので、井伏さんは「三郎さんのお父さん」と呼んでいる。
当時の上田秋成は、『日本文学史』(三上参次)でも、「雨月物語」がわずか一行触れられている程度で、ほとんど無名の存在だったらしい。
ようやく、秋成の墓が京都南禅寺門前の西福寺にあることを知らされた三郎さんのお父さんは、これで研究の道が開かれると、大いに喜んだらしい。
三郎さんのお父さんは小躍りするばかりに喜んで、「日本文学史」下巻の上田秋成に触れている箇所を読んだ。もう何度も読んで暗記している文章だが、改めて嬉しく読みなおした。(井伏鱒二「『雨月物語』明治飜刻本」)
暗記している文章を改めて読み直すという描写は、いかにも井伏さんらしい表現である。
こういう人間らしい描写が、ともすると堅苦しくなりがちな歴史の話を、楽しい読み物へと昇華させてくれているのだろう。
井伏さんの随筆には、貴重な史実を扱ったものも多いが、いずれも読み物として楽しいから、史実としてのリアリティに乏しい。
むしろ、歴史的なリアリティを削ぎ落とした中に、人間としてのリアリティが浮かび上がってくるかのようだ。
古備前の鑑別について研究した桂又三郎のことを書いた「桂又三郎」も、人間としての「桂又三郎」が伝わってくる、そんな歴史随筆だ。
本書収録の中では、やはり「軍歌『戦友』」がいい。
<我々の友人奥山君>が主人公だが、奥山君は、海軍の輸送艦に乗って物資を硫黄島へ運んだ、元・海軍中尉である。
奥山君は、硫黄島で西大佐と交流を持った。
西大佐は、1932年(昭和7年)に行われたロサンゼルスオリンピックの乗馬障害競技で活躍した金メダリストである。
奥山君は、西大佐に請われて、金魚の入った金魚鉢をプレゼントする。
西大佐は「司令官閣下への土産にしたい」と言っていたそうだ。
「どうだろう。飢えた兵に、金魚鉢の水を飲ましてやったと思いますか」と奥山君に訊くと、「どんなものでしょう。しかし『戦友』という軍歌には、『煙草も二人で分けて喫み』と云ってありますがね」と云った。(井伏鱒二「軍歌『戦友』」)
つまり、この「軍歌『戦友』」は、奥山君を語りながら、硫黄島で戦死した西大佐のことを語る、そんな作品なのだ。
そして、作品中で二人を繋ぐ仕掛けを担っているのが、「戦友」という有名な軍歌である。
井伏さんの随筆は、終わり方もいい。
長かった飲み会の途中で、ふっと姿を消してしまったような、寂しい余韻がある。
井伏さんの随筆を読むときは、この余韻を味わわないと損をしたような気持ちになる。
「軍歌『戦友』」の終わり方は、そんな井伏さんの随筆を象徴するような終わり方だと思った。
書名:井伏鱒二自選全集(第十巻)
著者:井伏鱒二
発行:1986/07/20
出版社:新潮社

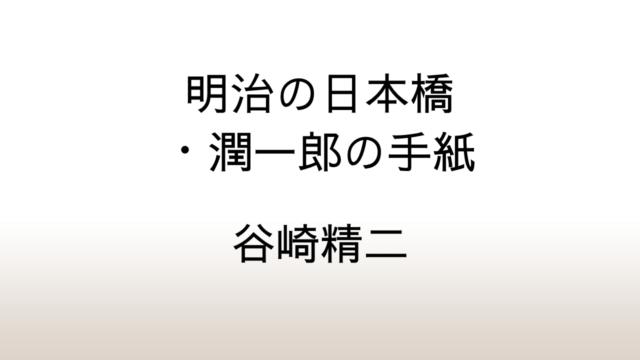


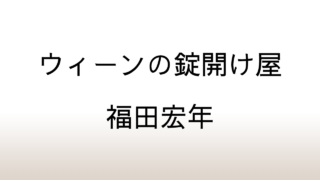
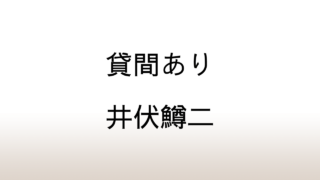
003-150x150.jpg)




