庄野潤三「石垣いちご」読了。
本作「石垣いちご」は、「文学界」昭和38年11月号に発表された短篇小説である。
作品集では、『丘の明り』(1967、筑摩書房)に収録された。
「ああ、そうだ。この前来た時には、この子らはいなかったんだ」
本作「石垣いちご」は、物語の語り手である「彼」(庄野さん自身のことだろう)が、静岡県清水市を訪れたときの様子を描いた作品である。
彼は、戦争中にも一度、この町を訪れたことがある。
昭和19年、12月のことだった。
当時、この町には、彼の九つ年上の兄が、中隊長兼砲台長として赴任していた。
そのとき、彼は、任官を目前にした海軍の予備学生であった。
墓参休暇で家へ帰るつもりだったところに地震が起きて、帰省することができなくなった。
それで、清水にいる兄のところまで行ってみることにしたのだ。
さっきのバスには、学期の始めで帰りの早い高校生の女の子が三人乗っていた。バスの乗り場で彼女たちに会った時、彼は始めは何気なしに見ていて、それから気が附いた。
「ああ、そうだ。この前来た時には、この子らはいなかったんだ」
いま眼の前にいる日に焼けて丈夫そうな少女は、あの時はいなかった。この世の中にいなかった。いや、生れてくるかどうかということも分らないものであった。(庄野潤三「石垣いちご」)
彼は、あの時と同じようにバスに乗って、かつて兄が暮らしていた隊の跡を訪ねる。
もっとも、当時を知っている人はほとんどいない。
かろうじて、当時、静岡県柑橘試験場の副場長を務めていた人が、彼の兄のことを覚えていた。
彼は、副場長に案内されて、かつての「大浦隊」(つまり「庄野隊」だろう)があった跡を見て回る。
彼の頭の中では、優しかった兄の記憶がまざまざと思い出されていた。
兄の部屋の窓には暗幕がかかっていた。そうして、陸軍式の毛布の寝床が、斜めに二つ、敷いてあった。火鉢には火がおこっていた。壁には兄の外套とマントが懸っていて、棚の上に軍装行李が載っていた。小さな机が壁際にくっつけてあり、その横には朱塗りの手箱がいくつも置いてあった。(庄野潤三「石垣いちご」)
この小説は、おそらく、若くして亡くなった、兄への弔いのために書かれたものだろう。
彼の記憶の中の兄は、どこまでも優しく、そして家族思いであった。
炊事の兵隊が買って来てくれた牡蠣で、夕食にすき焼きを食べる。
二人で家に充てた寄せ書きの手紙を書く。
南方派遣軍にいる二番目の兄から土産にもらったというジャワのコーヒーを飲む。
日本茶にどっさりとおかきを入れたのを飲む。
兄は、軍帽をかぶった彼を写生する。
実家に電話をかけて、家族みんなと話をする。
兄は、母と話している時、「うん、できるだけのことしてやるから、安心して」と言った。
兄は崖の中腹あたりを指して、「あれが石垣いちごだ」と云った。
これは、ひとつの戦争文学なのかもしれない。
けれども、それは、戦争の悲惨さや醜さを描いた作品ではなかった。
戦争の中にあって、互いに信頼し合い、助け合う、家族の強い絆が、そこには描かれている。
トーンで言うと、戦時中の学生生活を描いた長編小説「前途」に似ているだろうか。
大変な時代であったに違いないのに、その大変なところを浮きだたせるわけでなく、青春の日のひとつの思い出として、兄との再会を描いている。
ここで泊った翌朝、起きてすぐ兄と一緒に兵舎の前の道を上の方まで登って行った。すると、端は崖で、そこから海が見えた。すぐ下の田舎道をリヤカーを引いた自転車が通って行った。兄は崖の中腹あたりを指して、「あれが石垣いちごだ」と云った。(庄野潤三「石垣いちご」)
家族思いだった兄の爽やかさを、石垣いちごが象徴していたのかもしれない。
書名:丘の明り
著者:庄野潤三
発行:1975/4/25
出版社:筑摩書房
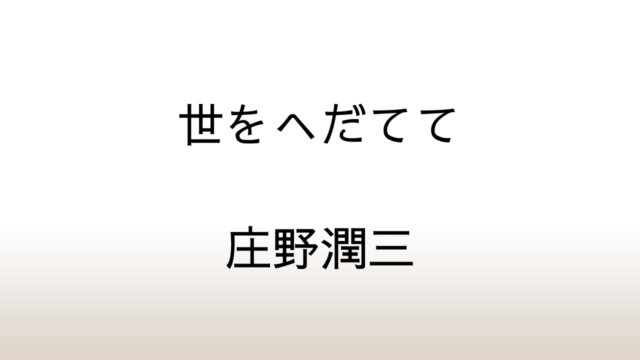
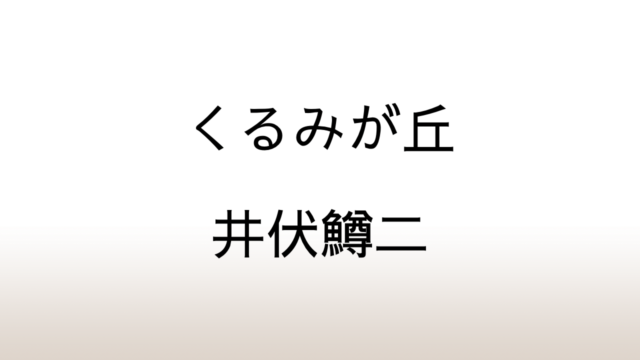


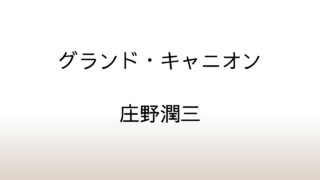
003-150x150.jpg)




