小沼丹「古い編上靴」読了。
本作「古い編上靴」は、1967年(昭和42年)9月『群像』に発表された短編小説である。
この年、著者は49歳だった。
作品集としては、1971年(昭和46年)5月に講談社から刊行された『銀色の鈴』に収録されている。
大寺さん自身が空襲被害に遭った体験
本作「古い編上靴」は、戦争中の体験を書いた、いわゆる戦時譚である。
そのためか、他の「大寺さんもの」とは、ちょっと違った印象を受ける。
もっとも、大寺さんものが、大寺さんの何気ない日常生活を描く物語だとしたら、本作もまた戦争中の大寺さんの何気ない日常生活を描いたものであることに違いはないだろう。
それが戦争中だったということが、そもそも非日常だった、というだけのことである。
最初は、大寺さんの細君が信州へ疎開したものの、退屈な田舎暮らしに耐えられずに帰ってくる。
次に、いよいよ空襲が激しくなってきたため、細君と子どもが二度目の疎開をしているときに、大寺さん自身が空襲被害に遭った体験が語られる。
大寺さんは睡気も一遍に醒めて、裏の壕に駆込んだ。ラジオのスイッチを入れ、パイプを咥えて編上靴の紐をホックに掛けた。壕の入口を開けて置くとたいへん明るい。覗いて見ると、探照燈の光が幾条も忙しそうに空を撫で廻している。(小沼丹「古い編上靴」)
この日の空襲で仕事場まで失った大寺さんは、妻子のいる信州へ疎開する。
ここまでが前半部分で、物語の多くは、疎開先の信州で務めた学校の話が中心となっている。
もっとも戦争中のことだから、学校でも学問を教えたりするわけではない。
田舎の百姓だって、そんなことは分かっている。
──へえ、いまじゃ教育なんて眼中にねえだ。教育なんてそっちのけよ。名前が学校だが教育なんてしやしねえだ。学校へ行ったと思えば、鍬担いで校門から出て来るだからなあ。情けねえ話だ。(小沼丹「古い編上靴」)
戦時における信州の田舎の日常をスケッチした場面は、この物語の大きなポイントかもしれない。
古い編上靴で語られていく大寺さんの戦争体験
戦争中であっても、本作「古い編上靴」に登場する若い大寺さんは、やはり大寺さんらしいところを随所で見せてくれる。
風に吹かれて展望台に立っていると、大寺さんはときにすべてを忘れてしまうような気のすることがあった。「──何故、茲に立っているのだろう?」と不思議に思う。空襲のあったことなど、遠い昔の夢のようにしか思えない。それから、想い出したように、草臥れた編上靴の埃を叩いたりした。(小沼丹「古い編上靴」)
ついこの間、ひどい空襲を体験したことさえ、大寺さんには「遠い昔の夢のようにしか思えない」。
戦争の悲壮感というよりも、人生のはかなさの方が、大寺さんには似合っているらしい。
学校の宿直中に、図書室から持って来た地理風俗体系を読みながら、パリの下町やベルリンの並木路、ライン河畔の古城、ロンドンの街の鼻垂小僧、ロシアの農民などが出てきたときにも、大寺さんは、人生のはかなさについて考えている。
──その連中の多くは疾に死んだろう。濃艶な微笑を送る美女も、今は皺だらけの婆さんだろう。
殊に、ベルリンの美しい並木路が、戦争で全滅したことを知っているから、大寺さんは、世の中全部が、はかない存在に思えてしまったのかもしれない。
やがて、戦争が終わり、信州の田舎の村にも平時が取り戻される。
「──一体、何があったと云うのだろう?」大寺さんの頭の中に「或る日」があって、その日が余りにも遠く思われたので、大寺さんは殆どその日を見ることは出来ないような気がしていた。それが、突然やって来た。大寺さんは、ぼんやりしてしまった。多分、そんなことだったろう。(小沼丹「古い編上靴」)
その後、しばらく働いた後、前任者が復員してきたところで、大寺さんは学校を辞めて東京へ帰る。
その学校で働いたのは、ざっと三か月ばかりだったが、学校を辞めたときに初めて「戦争は終わった」と、大寺さんは実感していた。
こうした戦争中の体験が、大寺さんの愛用している編上靴を中心に語られていく。
もしかすると、古い編上靴は、大寺さんにとって、戦争そのものであったのかもしれない。
作品名:古い編上靴
著者:小沼丹
書名:銀色の鈴
発行:2010/10/10
出版社:講談社文芸文庫

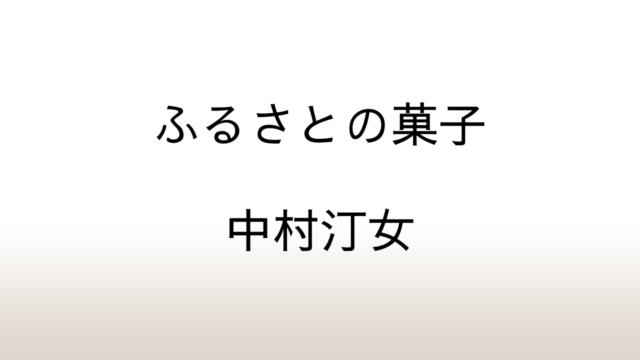


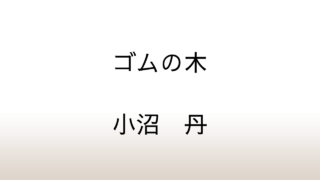
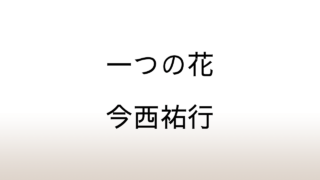
003-150x150.jpg)




