小沼丹「ゴムの木」読了。
本作「ゴムの木」は、1981年(昭和56年)3月『新潮』に発表された短編小説である。
この年、著者は63歳だった。
作品集としては、1986年(昭和61年)9月に講談社から刊行された『埴輪の馬』に収録されている。
過去の中にも過去があるという当たり前の事実
本作「ゴムの木」は、いわゆる「大寺さんもの」として最後の作品である。
大寺さんが初めて登場するのが、1964年(昭和39年)に発表された「黒と白の猫」だから、最後の作品まで、実に20年以上の時間が流れている。
この間に発表された大寺さんものは計12作品で、何とも息の長いシリーズだった。
本作「ゴムの木」では、複数のエピソードが密接に絡み合って構成されている。
一つは、大学で同僚だった<米原さん>の話である。
「──米原さんが亡くなったのは、何年前だったかしら?」「──もう十年ぐらいになるんじゃありませんか?」「──もうそんなになりますか……」河は日夜流れて、愁人のために少時も止ることが無い。米原さんに最后に会ったのはいつだったろう?(小沼丹「ゴムの木」)
この米原さんの思い出が、いつの間にか、大寺さんの次女<秋子>の思い出へとつながっていく。
かつて、米原さんは、秋子を養子にしたいと言い出したことがあったのだ。
どうやら、米原さんの奥さんが大寺さんの下の娘を養女に欲しいと云っていたらしい。何故、白羽の矢を立てられたのか見当も附かないが、その奥さんも死んで、大寺さんには遠い昔に思われる。米原さんがそんな話を持出したのは、或は奥さんのことでも想い出したのかしらん?(小沼丹「ゴムの木」)
思い出の中の米原さんは、その時点で既に思い出となっている昔のことを話してみせる。
ここで読者は、過去の中にも過去があるという当たり前の事実に気付かされて、ハッとするだろう。
思い出の中で語られていく思い出話。
時間軸を見失ってしまうはずである。
二つの話が時間軸を狂わせながら行ったり来たりする
米原さんの思い出と秋子の思い出を繋いでいるものは、作品タイトルにもなっているゴムの木だ。
大寺さんはゴムの木には格別の関心は無かった筈だが、現在大寺さんの家には二米ばかりのゴムの木がある。大寺さんの家では、それを「ウヱンズさんのゴムの木」と呼んでいる。(小沼丹「ゴムの木」)
かつて、米原さんの家を訪ねたとき、そこにもゴムの木があった。
米原さんも、教え子からもらったものらしいが、特別にゴムの木の話で盛り上がったわけではない。
大寺さんは、ただ、そのとき家にいた女のことが気になっているだけだった。
この物語では、米原さんの話と秋子の話が、時間軸を狂わせながら行ったり来たりする。
自分がいつの時代にいるのか、読者には分からなくなってくるが、これこそ、まさに、小沼丹の小説の醍醐味というところだろう。
物語は、最後まで現在には戻ってこない。
いつだったか、大寺さんの娘の秋子が、ちっぽけな男の子を連れて大寺さんの家に遊びに来たとき、何かの弾みで思い出したのだろう、「──ウヱンズさんに頂いたゴムの木、どうしたかしら? まだ、あります?」と訊いた。「──あれだ」と大寺さんが教えてやると、「──まあ、驚いた。あんなに大きくなったの?」と眼を丸くした。(小沼丹「ゴムの木」)
成長したゴムの木と小さな男の子(秋子の子どもだろう)が、時間の経過を示しているが、詳しいことには触れられていない。
昔話をしているのに、具体的な時間が示されていないのは、「あれは何年前のことだった」という話ではなく、「昔昔あるところに、、、」と言って始まる昔話のような曖昧さを感じさせることになる。
あるいは、読者はそんなところにも、不思議な割り切れなさを感じてしまうのではないだろうか。
そして、そんな割り切れないところこそが、小沼丹の小説の魅力ということなのだろう。
作品名:ゴムの木
著者:小沼丹
書名:埴輪の馬
発行:1999/03/10
出版社:講談社文芸文庫


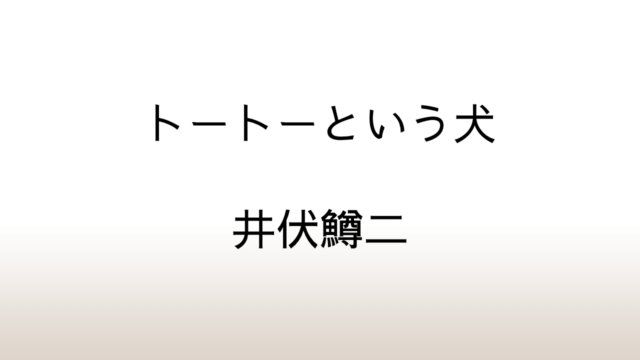
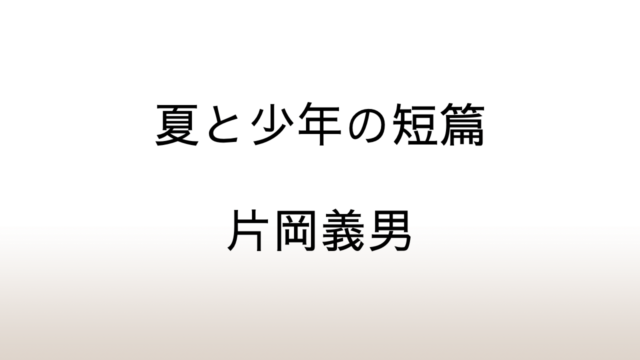
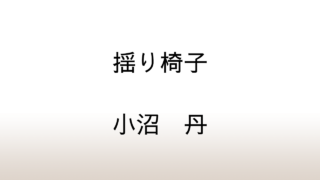
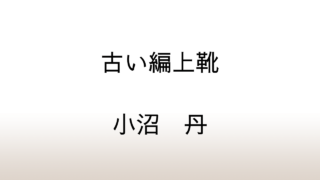
003-150x150.jpg)




