庄野潤三「ザボンの花」読了。
本作「ザボンの花」は、1955年(昭和30年)4月から8月まで日本経済新聞に連載された長篇小説である。
この年、庄野さんは34歳だった。
単行本は、1956年(昭和31年)7月に近代生活社から刊行されている。
生きている喜びを描く
庄野潤三『メジロの来る庭』に『ザボンの花』が登場している。
これは昔、芥川賞を受賞したあと、日本経済新聞からたのまれて、はじめて書いた新聞小説である。私たち一家が会社の転勤で大阪から東京へ引越し、石神井公園の麦畑のそばの家で暮すようになった最初のころの生活を描いたもの。父親の矢牧というのが私のことで、妻との間にまだ小さななつめと四郎のふたりの子供がいる。このなつめと四郎が活躍する。(庄野潤三「メジロの来る庭」)
正確に言うと、『ザボンの花』では、父親である矢牧のほかに、母親である千枝、長男・正三(小学四年生)、長女・なつめ(小学二年生)、次男・四郎(あと二年しないと幼稚園へ行けない)という五人家族が登場する。
ちなみに、朝日放送大阪本社に勤務していた庄野さんが東京支社へ転勤となり、「東京都練馬区南田中町453番地」へ移転したのは1953年(昭和28年)9月のことで、長女・夏子は6歳、長男の龍也が2歳になる年だった。
だから、『ザボンの花』に登場するなつめは夏子のことで、四郎は龍也がモデルになっている(当時の庄野家は、まだ四人家族だった)。
『鉛筆印のトレーナー』にも、『サボンの花』の回想がある。
『ザボンの花』を読んで、よかったという。「四郎が面白いね」といったら、笑っていた。『ザボンの花』に末っ子として登場する四郎というのは、その頃、四歳だった長男を素材として書かれたものである。これが活躍する。(庄野潤三「鉛筆印のトレーナー」)
『ザボンの花』を読んで「よかった」と言ったのは長男だから、「四郎が面白いね」という父親の言葉に苦笑したのだろう(なにしろ本人なので)。
物語の主軸に据えられているのは、妻であり母親の千枝である。
父親の矢牧はサラリーマンだから、平日の昼間は家にいない。
子どもたちの日常は、母親である千枝の目を通して語られていく。
と言っても、特別のドラマが起こることはなく、ごく普通の一家の、ごく普通の生活が、微笑ましいエピソードとともに綴られていく。
正三が主人公となっている「第一章 ひばり」は、長く国語の教科書に掲載されていた作品だから、『ザボンの花』を知らなくても「ひばり」という小説を知っているという人は多いかもしれない。
いじめっこと思しい見知らぬ少年が、ひばりの子に石を投げているのを見て、正三が憤慨する物語である。
それは、まるでひばりの子が、空から、地面のどこかで見てくれている親に向って、「お父さん、お母さん、もうこのくらい飛べば、及第でしょう。ぼくは、もう死にそうだ。ほら、降りますよ」と声をかけて、それを言い終らないうちに、すとーんと空から落ちたような具合であった。(庄野潤三「ザボンの花」)
勇敢な正三の行動の背景として、正義感の強い両親の影響を読み取ることができるが、物語の素材が、麦畑の中のひばりの子というところが、いかにものんびりしている。
こののんびりとした雰囲気こそ、『ザボンの花』という作品全体を覆っているトーンであり、まるでゆったりとした時間が流れていくような安らぎが、この物語にはある。
子どもたちには、隣人・村田さんの子であるユキ子ちゃんやタカ子ちゃんという遊び友だちがいて、千枝もまた、ユキ子ちゃんのお母さんと仲良しである。
休みの日には、村田さん一家が、矢牧の家まで遊びに来ることもある。
矢牧家と村田家の子どもたちが、この長篇小説を動かしていく推進力(いわゆる舞台回し)となっているが、特に力を入れて描かれているものは、大阪で暮らしている矢牧の家族や、死んだ家族など、身内の人々の思い出である。
例えば、「第六章 音楽会」に、大阪にいる矢牧の兄が植えてくれたライラックの樹が登場する。
夫は門の横にあるライラックが、小さい、うす紫いろの花を細い枝の先につけているのを見ていた。このライラックは、去年の四月に、大阪にいる矢牧の兄が上京した時、記念に買って植えてくれたものだ。(庄野潤三「ザボンの花」)
「第八章 はちみつ」で詳しく語られる龍二兄さんのモデルとなっているのは、夫婦の晩年シリーズに登場する「英二伯父ちゃんの薔薇」でお馴染み、児童文学者・庄野英二である。
龍二兄さんは、いつも王者の精神を心に持てといっている。それはどういうことかというと、人間が貧乏くさく見えるのは、お金がないからではなく、その人の精神が貧乏くさいからだというのだ。(庄野潤三「ザボンの花」)
物語の後半に行くほど、大阪で暮らしている家族の話が多くなるような気がするのは、夏休みの帰省で、物語の舞台が大阪へ移ったということも影響しているのだろう。
いとこのあけみちゃんとはるみちゃんは、死んだ長兄の子どもたちで、『野鴨』では民子と智子として登場している。
死んだ長兄と龍二兄さんに続いて、実家の母親が登場する。
この母は、プラタナスや父よりも長く生きて来た人だ。矢牧は、自分が育って来たこの古い家の中で、なくなった昔と、新しい生命をながめる。すると、矢牧の心にはかすかな悲しみが生ずる。それは、いったい何の悲しみだろう?(庄野潤三「ザボンの花」)
矢牧の心に生じた「かすかな悲しみ」は、自分という存在のはかなさだ。
それは、人間という存在のはかなさでもある。
大阪で暮らしている矢牧一族が出てくるようになると、いよいよこの小説も、矢牧一族の物語という印象が強くなってくるが、こうした一族の人々と共有しているものこそが、東京で暮らす矢牧一家の大きなバックボーンとなっていることは言うまでもない。
そして、その中心的な柱となっているのが、死んだ父親の思い出である。
「昔、このあたりにいたわしの親しい人は、みんな死んでしもうた。露木さんも、中谷さんも、浜田さんも。道を歩いても、さびしい」父がそういった。その顔は悲しげに曇って来た。「お父さん、そんなことを思ったらだめですよ。そんなこと、いわないで下さい」矢牧は父に向ってそういった。(庄野潤三「ザボンの花」)
夢の中に現われた父親や長兄は、現実世界では既に亡き人となっている。
親しい人々を失った寂しさに、読者は共感することができる。
こうした寂しさは、生きていて、なお、死を考える、人間の悲しさへと繋がっていく。
いずれは、おれもあの墓の下に入るんだな。そして、横に立てた石の表面に、父や兄などの名前のとなりにおれの名前も彫り込まれるんだな。そうすると、誰かがやって来て、やっぱりこんな夏の夕方に、おれの墓石の上からバケツの水を注ぐんだな。(庄野潤三「ザボンの花」)
生命のはかなさは、裏返すと、生きていることの喜びということになる。
つまり、本作『ザボンの花』は、生きていることの喜びを描いた小説だったということだ。
当たり前の暮らしを描いているようで、『ザボンの花』は深い。
この深いところに、庄野文学の魅力というものがあるんだろうなあ。
静かなる人生讃歌
NHKの『趣味どきっ(こんな一冊に出会いたい 本の道しるべ)』でナビゲーターを務めた菊池亜希子さんは、大切な本として『ザボンの花』を紹介している。
「大切な本は、そのときどきで変わりますが、今、選ぶなら」と前置きのうえ、紹介してくれた一冊。昭和30年代、3人の子どもがいて、東京郊外に暮らす家族の物語です。菊池さんが一言で説明すると、「すごく美しく情景を切り取った『サザエさん』」なのだとか。「今、こういう物語を自分はつむいでいる真っ最中と思わせてくれる大切な小説です。大きな事件が起こるわけではないんですが、幸福ってこういうことかな?って感じます」(「菊池亜希子さんの今、お気に入りの5冊と、大切な一冊」)
菊池亜希子さんは、『&Premium特別編集 あの人の読書案内。』でも、『ザボンの花』を取り上げている。
ずっとこの本の世界に浸っていたくなる『ザボンの花』。私の母世代が子どもだった頃の家庭の日常を描いている長編で、矢牧家の人々はみんな好きなんですが、特にお母さんの千枝がいいんです。千枝のような母親になりたいし、私の母もこうだったと思って。子育てが楽しいと思うのは、自分の子ども時代のみずみずしい記憶や豊かで優しい気持ちを再び体験できるところ。(『&Premium特別編集 あの人の読書案内。』菊池亜希子)
特に、女性としての感性が、母親・千枝への共感を呼んでいたのだろうか。
人は、毎日の営みの中で、自分だけの哲学を発見するものだ。
浮き沈みがあったというわけではなく、一日一日は全く同じことの繰返しのように思われた、変化のない暮しであったのに、こうして振り返って見ると、海の表面の色があるところでは水色に、あるところでは藍色に、またあるところではもっと違った色に見えるのに似ていた。(庄野潤三「ザボンの花」)
「全く同じことの繰返しのように思われた、変化のない暮し」の中に小さな変化を見つけて、その小さな喜びや小さな寂しさを描いてきたのが、つまり、庄野文学だった。
変化のない暮らしの中にこそ、庄野さんの関心があったわけで、激動のドラマを描くよりも、それはずっと困難で、高い技術力を求められる仕事であっただろう。
庄野潤三という作家が、何を書きたかったのかということが、『ザボンの花』の、この何気ない文章の中に表現されているような気がする。
『現代童話』(福武書店)を編集した今江祥智は、「わが国には珍しい極めて上質の家庭小説」と評した。
そういえば庄野(潤三)さんのものも長篇『ザボンの花』の第一章です。日本経済新聞に152回連載された長篇小説ですが、お読みいただければ分かりますように、これはわが国には珍しい極めて上質の家庭小説ではないでしょうか。冒頭の部分だけでもあえて収めたゆえんですが、これもぜひ全篇をお読み下さい。(今江祥智『現代童話』解説)
この長篇小説のクライマックスは、矢牧一家が夏休みで帰省する「第十五章 花火」にある。
『ザボンの花』は、「第十六章 夏の終り」で完結しているから、「第十五章 花火」は、静かなエンディングの前の、最後の盛り上がりだ。
矢牧はバケツの中の水を汲んで、まだ新しい、なめらかな光沢をもった墓石の上に注ぎかけた。すると、墓石の頂きの部分にたまった水が、夕べの空の色を映して、かがやいた。そこには、雲のかたちも映っているのであった。(庄野潤三「ザボンの花」)
墓石の上に溜まった水が空を映すところは、後の短篇小説「蒼天」(『丘の明り』所収)のテーマにもなった、重要なモチーフである。
「墓石の頂きの部分にたまった水」は、生と死の狭間にある境界線として、庄野さんには見えていたのではないだろうか。
懐かしいプラタナスの思い出も、矢牧にとっては、生と死を意識させるアイテムとなる。
なつかしいプラタナスの木は、それを植えた矢牧の父とともに、この家から姿を消してしまった。そして、いま家の中を声を上げて走りまわっているのは、戦争が終ったあとで生れて来た子供たちだ。矢牧は、なくなった昔と、この小さい子らとのちょうど真中に立っているのだ。(庄野潤三「ザボンの花」)
「矢牧は、なくなった昔と、この小さい子らとのちょうど真中に立っている」というところに、境界線を意識する主人公の(つまりは作者の)人生観が表現されていると言っていい。
ちなみに「戦後にビニールの表紙のアメリカのポケット叢書で父が見つけ出し、ひいきにしていたデエモン・ラニヨンの短篇集」とあるのは、後の長編随筆『エイヴォン記』の連載第一回「ブッチの子守唄」で紹介されているデイモン・ラニアンのことだ。
もっとも、庄野さんがデイモン・ラニアンを読むようになるのは、1980年代になって新潮文庫版の『ブロードウェイの天使』を買ってからのことになるのだが。
最終章「第十六章 夏の終り」で、なつめとユキ子の二人は「ゆりかごの唄」を歌う。
「ゆりかごのつなを 木ねずみがゆするよ」という、その歌は、1921年(大正10年)に『女学生』に発表された北原白秋の作品である(草川信が作曲)。
次に二人が歌った「若草もゆるおかのみち、心もはずむ身もはずむ」という唱歌は、昭和22年に作られた「散歩」(唱歌「散歩唱歌」を改作したもの)で、いずれも現代では、聴かれることも少なくなった、懐かしい唱歌である。
そして、作品タイトルにもなった「ザボンの花」は、北原白秋が詩を書いた「南の風の」という唱歌に登場する言葉だ。
千枝は自分もうたいたくなった。子供の時に家にあったピンク色のセルロイドのレコードに入っていた童謡だ。ピエロや踊っている人形の影絵をかいた盤で、「ザボンの花の咲くころは、空にはきれいな天の川」というのが、いちばんはじめの歌詞であった。(庄野潤三「ザボンの花」)
1921(大正10年)8月『赤い鳥』に発表された「南の風の」は、「ゆりかごの唄」と同じく、草野信が作曲をしている。
おそらく、現代ではほとんど聴くことのできない童謡だと思われるが、千枝が(つまり庄野千壽子夫人が)子どもだった時代には(大正末期から昭和初期)、この曲も、新しい時代の童謡として、子どもたちから親しまれていたのだろう(ちなみに、大正10年は庄野さんが生まれた年である)。
人生のはかなさと生きている喜び。
その生きている喜びが「南の風の」という童謡に象徴されている。
「ザボンの花」は、「南の風の」を、さらに象徴的にイメージ化した言葉だと言える。
我々の毎日は、変化のないように見えて、小さな変化が連続する毎日である。
その毎日は、決して永遠ではないけれど、生きているかぎりは、生きている喜びを感じていたい。
つまり、静かなる人生讃歌というのが、この物語の本質なのではないだろうか。
庄野潤三の盟友・小沼丹は、次のように書いている。
三十代にしか書けない小説がある。四十代には四十代の小説がある。「ザボンの花」は三十代の庄野が見た「ある家庭の生活」である。(小沼丹「夕べの雲」解説)
生田の丘の上で暮し始めたばかりの頃の庄野家を描いた小説が『夕べの雲』なら、『ザボンの花』は、石神井公園の麦畑の中で暮らし始めたばかりの頃の庄野家を描いた小説である。
どちらも、日本経済新聞に連載された新聞連載小説だったというところも面白いが、いずれにしても、『ザボンの花』と『夕べの雲』は、庄野潤三の原点となった作品と言える。
この作品を読まずして、庄野文学を語ることはできないだろう。
本作『ザボンの花』は、時代を越えて、繰返し出版されてきた名作である。
以下、『ザボンの花』の歴史にも触れておきたい。
近代生活社「ザボンの花」昭和31年
「ザボンの花」は、昭和30年4月から8月まで「日本経済新聞」に152回に渡って連載された。
庄野さんは、この年(昭和30年)1月に第32回芥川賞を受賞したばかりで、「ザボンの花」は、庄野さんにとって初めての新聞連載小説であり、初めての長編小説でもあった。
あとがきの中で、庄野さんは、英国の作家ヒュウ・ウォルポールの代表作「ジェレミイとハムレット」という長篇を引き合いに出して、「『ザボンの花』を書く時、私はたとえばこの『ジェレミイとハムレット』でウォルポールが英国の家庭の、部屋の中とか廊下などの空気を私たちに感じさせてくれたような具合に、私も自分の書くことが出来る範囲で、ある時代のある生活を表現してみようと思った」と綴っている。
ちなみに「ジェレミイとハムレット」は、『ジェレミー少年と愛犬ハムレット』(長尾輝彦・訳)で読むことができる。
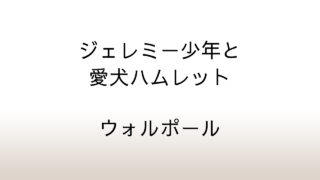
書籍の帯文には「芥川賞作家長編第一作」「現代文学中他に類を見ない、透明な詩情と哀感の文学」「日本経済新聞に連載されるや読者を感動の嵐に捲きこんだ名作長編小説」とある。
帯の推薦文を書いているのは、河盛好蔵と井上靖。
河盛好蔵は「庄野潤三氏には、戦後の作家がみなどこかへ置き忘れてしまった文学の核心になるべき純朴さがある。物ごとにこせこせしない大人の風格がある。すくすくと大樹に成長すべき豊かな樹液といったものを覚えている」と書き、井上靖は「庄野潤三氏は詩人である。氏が詩を書かれたかどうかは私は知らない。併し、氏の作品の尽くについて語る時、梶井基次郎の作品に対すると同様に感受性の純粋化という言葉を使っていいのではないかと思う。氏の作品の持つ澄明度はさしずめそうした言葉を使う以外ないと思う」と書いている。
著者の庄野さん自身、「人が読んでどの程度に興味のあるものであるかどうかは深く問わず、ただ私が一生のうちに書くとすれば一番いいと思われる時期にこれを書いた。私は自分にこの仕事をやらせてくれた日本経済新聞に感謝することを忘れてはならない」とあとがきに記しており、手応えのある作品だったことが伝わってくる。
「ザボンの花」は、新聞連載が終了した翌年の昭和31年7月に刊行されるが、版元である近代生活社の倒産によって、ほどなく絶版となってしまう。
印税さえ手にすることができず、庄野さんにとっては苦い思い出の残る作品となってしまった。
あかね書房「ザボンの花」昭和46年
出版元の解散という憂き目に遭った「ザボンの花」だったが、新聞連載時に好評を得ていたこともあり、第一章にあたる「ひばりの子」が中学校国語教科書に掲載されるなど、「ザボンの花」は根強い人気を維持していたらしい。
中学校国語教科書への掲載は、大修館書店(昭和33年~40年)三省堂(昭和35年~43年)、大日本図書(昭和36年~40年)、大阪書籍(昭和36年~43年)、学校図書(昭和41年~43年)、光村図書出版(昭和47年~55年)など、昭和30年代から50年代にかけて、各社に渡った。
ちなみに「教科書名短篇―家族の時間」(中公文庫)に収録されている「ひばりの子」が、「ザボンの花」の第一章に当たる部分の抜粋となる。
こうした人気を背景に「ザボンの花」があかね書房「少年少女日本文学」シリーズから刊行されたのは、昭和43年(1968年)のことである。
『ザボンの花』を最初に本にしてくれた小さな出版社は、間もなくつぶれて、私は印税をもらえなかった。ところが、何年かたって、児童文学の出版のあかね書房から「少年少女日本の文学」というシリーズの全集が刊行されることになり、うれしいことに私の『ザボンの花』がその一巻としてとり上げられた。文学全集で発行部数が多く、印税も大きかった。(庄野潤三「メジロの来る庭」)
ちなみに、あかね書房「少年少女日本の文学」には、井伏鱒二の『くるみが丘』も入っている(小沼丹が解説を書いた)。
巻末の作品解説に当たる「人と作品」を担当した十和田操は、近代生活社版のあとがきを全文引用して「庄野さんほど、誠実まっとうで心あたたかな信頼のできる作家は、めずらしいと思います」「どんな作品がいいだろうかと、いろいろ問題の多いこんにちの新聞小説を、庄野潤三—この芥川賞作家に書いてもらおうとくわだてた新聞(日本経済新聞)も、また心あたたかで、えらいものだと思います」などと綴っている。
また、この十和田操による「庄野さんの印象」は少年少女向けに書かれたものとは言え、昭和40年代当時の庄野さんを知るうえで、非常に精緻なものとなっていて注目される(庄野少年が綴り方の時間に書いた「折れたベーブルースの足」という作文が、大阪の大新聞に掲載されたエピソードなども興味深い)。
(2024/07/27 06:28:05時点 Amazon調べ-詳細)
角川文庫「ザボンの花」昭和47年
あかね書房が「ザボンの花」を復刻した翌年の昭和47年(1972年)12月30日、「ザボンの花」は角川文庫から刊行される。
カバー紹介文には「夫妻と子供3人が織りなす家庭生活を爽やかに描き、『ザボンの花の咲くころは、空にはきれいな天の川・・・』の童謡の余韻がひびく詩情あふれる庄野文学の名作長篇」と記された。
解説は、大阪朝日放送時代からの盟友であり、芥川賞作家でもある阪田寛夫。
阪田さんは「同じ年に庄野さんは『プールサイド小景』で芥川賞を受けたのだけれども、この明るい家族小説の方はあまり問題にされなかった」「だが『ザボンの花』が、あとに続く作者の中年期の仕事の大事な起点になっていることを、今はもう認めてもいいのではないか」と、一連の家族小説を発表している庄野さんにとって、『ザボンの花』が原点的な作品であることを指摘している。
昭和47年当時といえば「夕べの雲(昭和40年)」「丘の明り(昭和42年)」「小えびの群れ(昭和45年)」「絵合せ(昭和46年)」「明夫と良二(昭和47年)」などといった、和子・明夫・良二の3人の子どもたちが登場する一連の家族小説が発表されていた頃であり、原点を「ザボンの花」に求める阪田さんの指摘は、実にまっとうなものだった。
福武文庫「ザボンの花」平成3年
時代は変わって平成3年(1991年)、庄野さんの「ザボンの花」は、福武書店「福武文庫」から出版される。
カバーの紹介文を引用すると「東京郊外に移り住んだ家族は、四年生の男の子を頭に二年生の女の子、そして幼稚園前の男の子のいる賑やかな5人家族。奔放な3人の子供達を中心にに若々しい父母、近隣の人々、夕方になるとなぜか吠え出す愛犬ベルらの優しく温かな交流—子供達の華やぎと移りゆく自然の美しさの中に生の原風景を紡ぎ出す庄野文学の記念碑的長篇」となっている。
解説は、角川文庫版と同じく阪田寛夫。
他の文庫本や庄野潤三全集の解説を書くために、この作品を少なくとも10回は読んでいるはずだと言う阪田寛夫は「今度読み返して、こんなことが書いてある、少しも知らないでいた、と驚いた箇所がいくつもあった」「好きな交響曲や室内楽曲を何度も繰返して聴いて、そのつど新しい喜びを貰ったり発見を楽しんだりするように、私はこの作品から喜びや慰めを、繰返し貰ってきた」と綴った。
1980年代の庄野さんは「陽気なクラウン・オフィス・ロウ(1984年)」や「サヴォイ・オペラ(1986年)」などの大作を完成させた後、病期療養を隔てて、フーちゃん3部作と呼ばれるシリーズの最初の作品である「エイヴォン記(1989年)」を発表している。
つまり、福武文庫版「ザボンの花」が刊行されたのは、1990年以降に発表される晩年の家族小説シリーズの萌芽が登場していた時期ということになり、この時期に原点とも呼ぶべき作品が、世に再登場しているのはおもしろい。
阪田さんは「エイヴォン記」に登場する「デエモン・ラニヨンの短編集」が、実は「ザボンの花」で既に登場していたことを発見した驚きを率直に綴っているが、軸足のブレることのなかった庄野さんらしいエピソードだと思う。
みすず書房「ザボンの花」平成18年
さらに時代は変わって平成18年(2006年)、みすず書房の大人の本棚シリーズから「ザボンの花」が刊行される。
帯文では「麦畑に囲まれた一軒家で暮す五人と一匹。生活の情景、そこにある哀歓をのびやかに綴る、静かな明るさに満ちた長編小説。『夕べの雲』の前編、庄野文学の代表作」と記された。
1955年の日本経済新聞連載から実に半世紀以上の時間を経て世に再登場した、まさしく「庄野文学の代表作」と言っていい。
庄野さんの書いたあとがきを引用したい。
はじめての新聞小説で、どんなふうに書いていいか、分らない。文芸誌に書くのと同じように書いた。新聞ということを意識しないで、自分の好きなようにのびのびと書かせてもらった。大阪帝塚山の生家には、大病をしたあとの母がいて、日本経済新聞をとって「ザボンの花」を読んでくれ、切抜を作ってくれた。この切抜が単行本にするときに役立った。父に先立たれて淋しくなり、戦後に三十七歳という年で亡くなった長兄の妻と子供と一緒に暮していた。私はこの母に東京に引越した私たち一家がどんなふうに暮しているかを知らせるつもりで書いた。それが、「ザボンの花」であったといっていいだろう。(庄野潤三「あとがき」)
この時、庄野さんは85歳で、2009年に88歳で亡くなる、ちょうど3年前のことだ。
85歳になった息子が、とうの昔に亡くなった母を偲び、「ザボンの花」は「この母に東京に引越した私たち一家がどんなふうに暮しているかを知らせるつもりで書いた」と懐かしく思い出している。
その言葉を読むことができるという意味で、みすず書房「大人の本棚」版の「ザボンの花」は、非常に意義のある本だと思う。
講談社文芸文庫「ザボンの花」平成26年
そして、現在でも入手可能となっているのが、平成26年(2014年)に刊行された、講談社文芸文庫版「ザボンの花」である。
帯文は「家庭や生活のいとおしさ、『夕べの雲』へと続く庄野文学の魅力の長篇」。
著者である庄野さんは、既に2009年に逝去されているので、富岡幸一郎による解説も、庄野文学を総括する形で書かれているが、「『ザボンの花』に満ち溢れる言葉は、何かを指し示すことでその物を描いているのではなく、言葉自体がその物と化している」などの考察は、庄野文学の本質を探る上で興味深い。
『ザボンの花』から庄野潤三独特の家庭小説が始まる、というのはカバーの紹介文で、「生活を愛し育んでいく本質と主張を、完成度の高い文学作品にしあげている」と続いている。
原点という意味においても、また、ひとつの文学作品としての完成度としても、『ザボンの花』は間違いなく庄野潤三の代表作である。
書名:ザボンの花
著者:庄野潤三
発行:2014/04/10
出版社:講談社文芸文庫







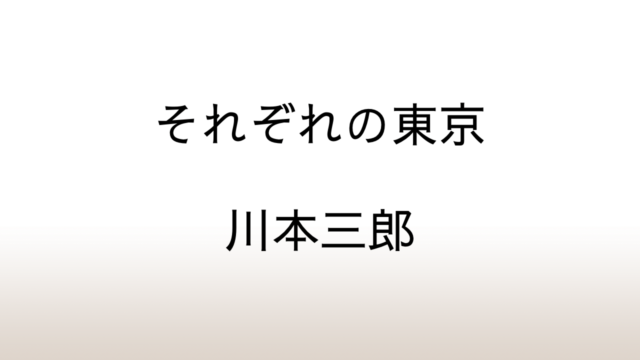
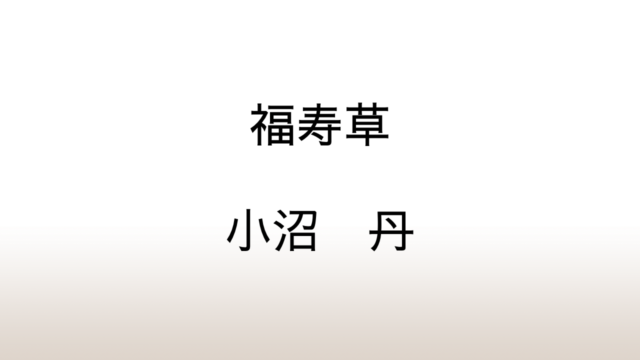
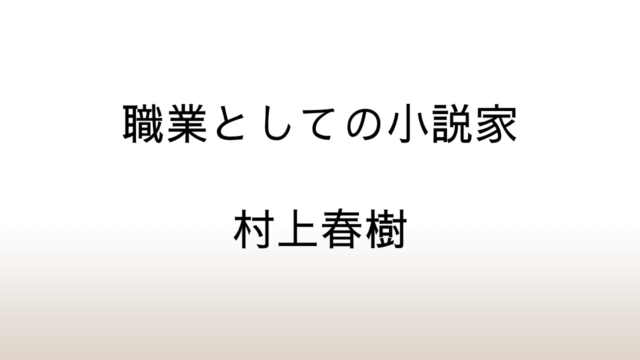


003-150x150.jpg)




