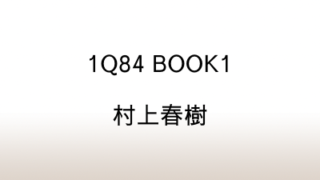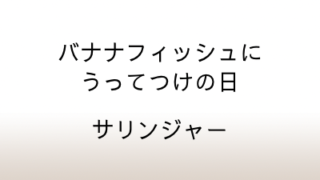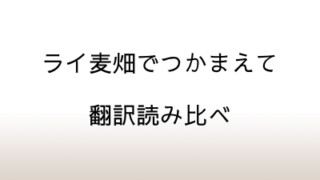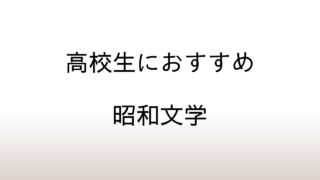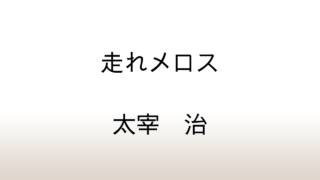庄野潤三「野菜讃歌」読了。
本作「野菜讃歌」は、1998年(平成10年)10月に講談社から刊行された随筆集である。
この年、著者は77歳だった。
福原麟太郎、井伏鱒二、庄野潤三
庄野潤三『鳥の水浴び』に、『野菜讃歌』が出るときのことが綴られている。
午後、講談社出版部の高柳信子さん来て、十月に出る私の随筆集『野菜讃歌』の装幀見本を見せてくれる。宮脇綾子さんのアプリケをあしらったもので、カバーは玉葱が三つ、表紙は枝豆。装幀は『ピアノの音』のとき、初めて担当してくれた野崎麻理さん。(庄野潤三「鳥の水浴び」)
庄野さんには9冊の随筆集があるが、『野菜讃歌』は、そのうちの8冊目で、晩年に書かれたエッセイがまとめられている。
作家の晩年に書かれた随筆というのは、人生の旨味がしみこんでいるような気がして、大体おもしろい。
本作『野菜讃歌』という随筆集も、庄野潤三という作家が辿ってきた人生の旨味を、たっぷりと吸いこんでいる。
「ラムの『エリア随筆』」は、若い頃から愛読していたチャールズ・ラムの『エリア随筆』について書かれたもの。
このティップは臆病な人で、露台の手すりによりかかったことがない。石垣の端を歩くとか崖の上から下をのぞくということはしない。この露台の手すりによりかかったことがないというところが、私は気に入っている。(庄野潤三「ラムの『エリア随筆』」)
『エリア随筆』の中の「南海会社」に出てくるティップという用心深い人が好きだというあたりに、庄野さんの生き方が滲み出ている。
若かった頃の思い出話もいい。
むかし、三人の子供が小さかったころ、私たちは夏休みが来ると、子供を連れて外房の太海海岸へ行き、子供らを泳がせた。おかげで三人とも小学生のうちにいくらでも泳げるようになった。(庄野潤三「この夏の思い出」)
1995年(平成7年)の夏、74歳の庄野さんは、長女夫婦の案内により、小田原の御幸ケ浜海水浴場で二年ぶりの海水浴を楽しんだという。
三歳の長女が登場するのは「お祝いの絨毯の話──『ピアノの音』」。
この「お祝いの絨毯」の委員長格の長女は、はじめて「群像」に載った「舞踏」のなかでは、頼りないお父さんに「ちょうちょ、とってえ」とせがむ三歳の女の子であったことに今、気が附いた。(庄野潤三「お祝いの絨毯の話──『ピアノの音』」)
「舞踏」は、1950年(昭和25年)2月『群像』に発表された短篇小説で、当時の庄野さんは、「夫婦の危機」を主なテーマとする若手作家だった。
「作者である私の興味は、自分と一緒に暮している年若い妻に向けられていた」と、当時を回想する文章に、作家の遠い目が感じられる。
代表作となる『夕べの雲』の頃を回想するエッセイもいい。
『夕べの雲』は私たち一家が多摩丘陵の一つの丘の上に移り住んだ最初のころの生活をそのまま描いた小説だが、この本が世に出てから三十年になり、主人公の大浦夫婦、つまり私と妻の二人は、今もこの『夕べの雲』の舞台である丘の上に住んでいる。(庄野潤三「『夕べの雲』の丘」)
生田へ引っ越した当時の話は、他にもある。
私たちが越して来たのは四月。家びらきに親しい友人を何人か招いた。その日、井伏さんの古いお友達で柿生に住む河上徹太郎さんもお招きした。会の途中で妻が庭に面した硝子戸をあけると、河上さんが、とたんに、「何だ、禿山の一夜じゃないか」と叫んだ。(庄野潤三「わが家の眺め」)
豊かな経験が、そのまま人生の旨味となって文章に出てくる。
『夕べの雲』以降の小説では、「絵合せ」を忘れてはいけない。
四十五年の五月に私の長女が結婚した。「群像」編集部で私の担当をしていた徳島君が来て、お嬢さんの結婚を主題にして一つ長い目の小説を書きませんかといった。私は何か書いてみましょうといって引受けた。それが始まりであった。(庄野潤三「『絵合せ』を読む」)
庄野さんのように、自分の家族を題材として小説を書いてきた作家にとって、過去の作品には、古い写真アルバムをめくるような懐かしさがあるのではないだろうか。
家族と同じように、文学仲間の名前も、あちこちに出てくる。
師匠格・井伏鱒二は、ことに登場回数が多くて、ちょっとした文章にも「井伏さん」という言葉が入る。
「わが家の眺め」では、「井伏さんがお祝いに郷里の福山の植木屋から送らせてくれた十本のウバメガシ」が出てくるし、「梅の実とり」にも、庭の梅の木を見た井伏さんが「庄野君、いい梅だね」と言ったというエピソードが紹介されている。
書評では「井伏さんの『徴用中のこと』」がある。
この夏は七月に講談社から出た井伏鱒二『徴用中のこと』をひまさえあればとり出して読んだ。はじめ頁を繰っていて途中から読み出し、大分進んでから最初に戻って読み返した。面白くて、やめられなかった。(庄野潤三「井伏さんの『徴用中のこと』」)
書評というよりも読書感想だけれど、「面白くて、やめられなかった」というところに、いかにも感じが出ている。
師匠の書いた本だからということではなくて、本当に好きな作家の本を読んでいるということが伝わってくる。
もっとも、井伏さんが、庄野さんの小説を読んだ感想を言うというようなことはなかったらしい。
そのころ井伏さんに会ったとき、『浮き燈台』を読んで下さったことが分った。井伏さんは、いいとも悪いともいわれず、「読んだよ。屋形船に大根積んだようなものだね」といわれた。(庄野潤三「井伏さんのお酒」)
『浮き燈台』は、石神井公園から生田の丘の上に引っ越してきた昭和36年の秋に出た本で、「出版社の書下しの企画で書いた小説であった」とある。
それ以前、『群像』に発表する一挙掲載の作品が書けないで苦しんでいるときも、井伏さんは励ましてくれた。
昭和34年頃のことで、このとき、ようやく書き上げた小説は「静物」となった。
長い作家人生を支えてくれた人が、井伏鱒二という年上の作家だった。
井伏さん夫妻は、甲州弁丸出しのこのヨッちゃんを何度も東京見物のため荻窪へ呼び寄せた。あるときヨッちゃんは「梅ケ枝」を訪れた飯田龍太さんに向って、「奥さんが歌舞伎座へ連れて行ってくれたですじゃん、困っちもう」と話したが、そういうヨッちゃんの顔は幸福そのものであったという。(庄野潤三「宝塚・井伏さんの思い出」)
作家として歩んできた人生の中で、様々な出会いがあったのだろう。
ロバート・ブラウニングの言葉に触れた随筆もいい。
私は昔から福原さんのお書きになるものがみんな好きであった。福原さんのお好きな言葉に私も惹かれるのである。(庄野潤三「「われとともに老いよ」──『ピアノの音』」)
「われとともに老いよ」という言葉の前に、「英文学者ですぐれた随筆家であった福原麟太郎さんのお好きな言葉であった」という文章がある。
ブラウニングの長い詩「ベン・エズラ法師」の最初の一行である、この言葉を、福原さんは好んで色紙などに書いていたらしい(福原さんの「老いの術」という随筆に出てくる)。
福原麟太郎、井伏鱒二、庄野潤三と、三人の作家の名前を並べてみると、何かしら共通点があるような気がする。
いずれも謙虚で、特別のことを避けたがる、大人の余裕を持った人たちばかりだった。
自分も年老いたら、そんな大人になりたいと思うのだけれど。
盟友・小沼丹を偲ぶ
1996年(平成8年)11月に、盟友だった小沼丹が他界した。
小沼丹が亡くなったという知らせを小沼の古い友人の吉岡達夫から受取った翌日、本棚から『村のエトランジェ』と『白孔雀のいるホテル』をとり出した。どちらも小沼と知り合ってからまだそんなに月日がたたないころに小沼から貰った本である。(庄野潤三「小沼とのつきあい」)
単行本が出版された時期的に、井伏鱒二や小沼丹の思い出を回想する文章が多いことも、本作『野菜讃歌』の特徴の一つだろう。
昭和30年10月に河出新書から出た『白孔雀のいるホテル』の口絵に載った著者の写真を見て、庄野さんは「はじめて知り合ったころの小沼は、こんな顔をしていたのか。それに男っぷりもいい」と驚いている。
『群像』に載った阪田寛夫の「七十一歳のシェイクスピア」を探して、小沼丹に関する文章を読む場面もいい。
私は「小沼さん」が出てくるところを探して読み返した。私たちも馴染の飲屋さんのつき当りの部屋の壁にもたれて小沼が、昔の宝塚歌劇の「モン・パリ」の歌を気持よさそうに歌う場面がある。(庄野潤三「庭のブルームーン」)
亡き友を偲んでから庭に出ると、ブルームーン(薔薇の名前)のもうすぐ開きそうな蕾を見つけた。
そんな随筆である。
ワーズワスの「水仙」という詩を思い出す場面でも、小沼丹の名前が出てくる。
いつもの散歩道を歩いていて、小学校の水仙を見て、ワーズワスの詩を思い出したまではいいが、あやふやな記憶で心細い。こんなときに友人の小沼丹がいてくれたら(小沼は英文学の先生をしていた)、はがきを書いて教わるのだが、残念なことに去年、小沼は亡くなった。(庄野潤三「わが散歩・水仙」)
おそらく、日常生活の様々な場面で、庄野さんは亡くなった小沼さんのことを思い出していたはずだ。
井伏鱒二について綴った文章を集めた、小沼丹の著書『清水町先生』のことを書いた随筆もある。
そこで、本の礼状を出すときに、「外函のあけびの絵もなかなかいい」と書いた。二回目に「むべ」を読んで、さては外函の植物はむべであったかと、おそまきながら気がついた。仕方がないから、また小沼に葉書を出すことにして、「さとりが悪くて、お粗末でした」と謝った。そんなことを思い出す。(庄野潤三「師弟の間柄」)
小沼さんの『清水町先生』が、ちくま文庫に入ったとき、解説を書いたのが庄野さんだった。
『清水町先生』を読んで、もっとほかに小沼丹の作品が読みたくなったら、随筆集『小さな手袋』と短篇集『懐中時計』がお勧めだと、庄野さんは最後に付記している(どちらも講談社文芸文庫に入っている)。
亡くなった友人を偲ぶ文章は、切なくて悲しいけれど、作家の気持ちが伝わってくる。
そんな庄野さんは、まだ存命中に、自分のお墓を建てた。
数年前の夏の日に、新しく建った墓の前にみんな集まった。私たちのご近所に伊予のお寺の生れの清水さんがいて、新しいお墓のために短いお経を唱えてくれた。ゲストに招いた私の作家仲間の阪田寛夫も、清水さんがコピーをとって配ってくれたお経を、清水さんについて唱えていた。あとで長女の家でお弁当とビールが出た。(庄野潤三「自然堂のことなど」)
このお墓は「小田原に近い南足柄に住む長女が近くの長泉院というお寺の先代の住職に頼んで、お寺の墓地の一画を分けてもらえた」ものだったという。
どの随筆にも、豊かな人生経験の旨味がしみ込んでいて味わい深い。
なお、本作『野菜讃歌』には、日本経済新聞に連載された「私の履歴書」が収録されていて、庄野潤三という作家を俯瞰する上で、非常にいい資料的作品となっている。
伊東静雄、島尾敏雄、林富士馬、佐藤春夫、中山義秀、吉行淳之介、安岡章太郎、真鍋呉夫、小島信夫、井伏鱒二、小沼丹、坂西志保、福原麟太郎、河上徹太郎、阪田寛夫と、親交の深かった仲間たちの名前が、次々と登場する。
まるで『文学交友録』のダイジェスト版みたいな作品だ。
子供は三人とも結婚した。長女は前にいった通り井伏さん夫妻のお世話で今村邦雄と(仲人は小沼丹)、長男は鈴木敦子と(仲人は阪田寛夫)、次男は冨田操と(仲人は藤野邦夫)。それぞれよきつれ合いを得た。長男のお嫁さんは「あつ子ちゃん」として、次男のお嫁さんは「ミサヲちゃん」として私の書く本に登場する。(庄野潤三「私の履歴書」)
庄野潤三という作家のことを知りたいと思ったら、まず、この「私の履歴書」を読むことをお勧めしたい。
庄野さんが、どのような文学的影響を受けているかが、一目で理解できると思うから。
書名:野菜讃歌
著者:庄野潤三
発行:2010/01/08
出版社:講談社文芸文庫

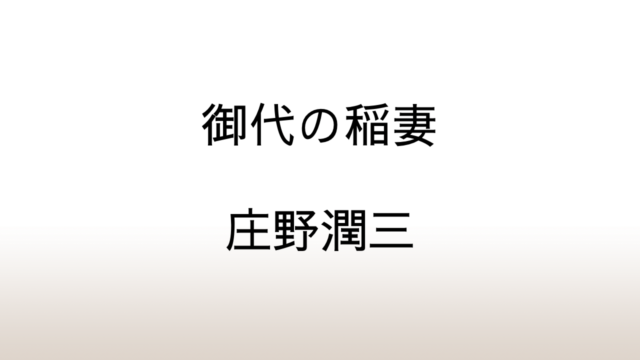
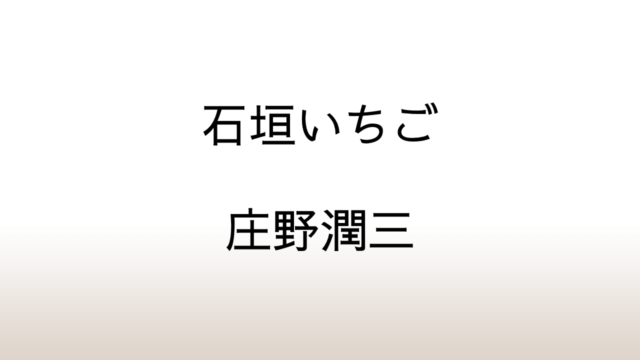
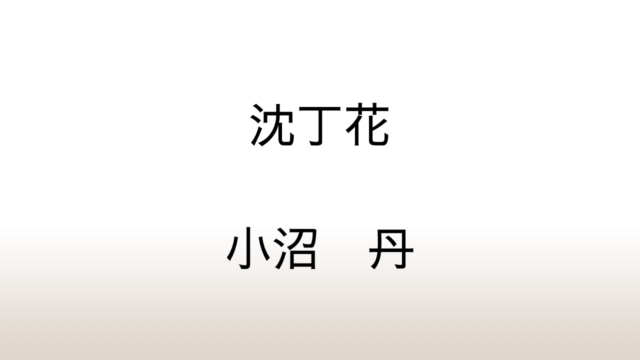
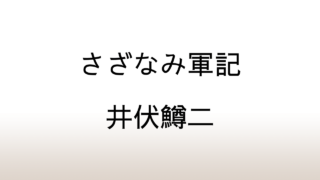
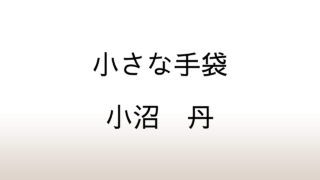
003-150x150.jpg)