小沼丹「竹の会」読了。
本作「竹の会」は、『群像』1972年(昭和47年)6月号に発表された短編小説である。
この年、著者は54歳だった。
谷崎精二を慰める会だった「竹の会」
谷崎精二を読んでいたら、小沼丹を読みたくなった。
1940年(昭和15年)、早稲田大学文学部英文科に入学したとき、小沼丹は谷崎精二の講義を履修している。
『早稲田文学』に小説を発表したときの同誌主幹も谷崎精二だった。
小沼丹が、井伏鱒二の薫陶を受けていることを知っていた谷崎精二は、小沼丹の作品を積極的に『早稲田文学』に採用するようになる。
そんな縁があって、大学を卒業した後、早稲田大学への就職を推薦してくれたのも、この谷崎精二だった。
本作「竹の会」は、1971年(昭和46年)に谷崎精二が80歳で亡くなったときに書かれた、追悼の回想記である。
「竹の会」というのは、終戦後、三、四年経って、『早稲田文学』が廃刊になったとき、井伏鱒二の提案により開催された、谷崎精二を励ます会の名称である。
思い浮ぶ儘に最初の会の出席者の名前を列記すると、谷崎精二、青野季吉、保高徳蔵、井伏鱒二、浅見淵、逸見広、小田嶽夫、木山捷平、村上菊一郎、吉岡達夫の諸氏に僕の十一名で尾崎一雄氏は体の具合が悪くて欠席だったと思う。出席者は須く酒飲みであることと云う条件があったから、広津も来るといいんだが彼は酒が飲めないんでね、と谷崎さんが残念そうな顔をしたのを憶えている。(小沼丹「竹の会」)
この「竹の会」は、その後、会員を増やしながら、十数年も続いていくことになるのだが、上林暁や新庄嘉章、結城信一、江戸川乱歩、火野葦平、横田瑞穂、岩淵鉄太郎、三浦哲郎なども参加していたらしい。
もっとも、後年は、谷崎精二を慰めるという会の趣旨は薄まり、井伏鱒二を囲む会のように勘違いしているメンバーも現れるようになってしまった。
本作「竹の会」では、この「竹の会」の人間模様を中心に、谷崎精二との交流を仔細に振り返っていく。
なにしろ、学生の時の出会いから亡くなるまでを思い出しているから、その時間軸はおそろしく長い。
早稲田大学に入学したとき、谷崎精二は、まだ50歳だった。
80歳で亡くなるまで、30年間の付き合いである。
思い出すこと、書かなければならなかったことは、いくつもあったに違いない。
現れては消えてゆく人たちとの出会いと別れ
谷崎精二はお酒が好きだったが、酒場で深酒することはなかった。
ビールは飲まずに、もっぱら日本酒だったが、銚子に三本ほど飲むと、もう適量だからといって、盃を伏せてしまう。
帰宅して必ず銚子二本の酒を飲むことを、こよなく楽しみにしていたらしい。
酒の席で、この話を井伏鱒二にしたところ、井伏さんは「君は谷崎さんの教え子だろう?」と言った。
「教え子としては、先生のそう云う点は大いに見習うべきじゃないのかね……」なんだか思い当ることもあるから、早速見習うことにして、ではそろそろお先に失礼します、と云うと、井伏さんはそっぽを向いて、ふうん、君はそう云う男か、と云った。(小沼丹「竹の会」)
井伏さんの酒は長っ尻で有名だったから、井伏さんと一緒に飲んでいて、さっと切り上げるなんていうことは、なかなかできなかったに違いない。
学校での谷崎精二しか知らなかった小沼丹が、初めて酒場で谷崎精二に会ったのも、井伏鱒二といっしょのときだった。
早稲田文学に短篇が載って間も無く、清水町の井伏鱒二氏のお宅を訪ねたら、今夜は早稲田文学の会があるから一緒に行こうと云われて、清水町先生に随いてその会に出たことがある。会場は東海道の「末広」の並びにあった、昔の「樽平」の二階であった。多分、月に一度そこで例会があったのだろう。会費は一円だったと思う。(小沼丹「竹の会」)
ここで小沼丹は、学校では謹厳実直な姿しか見せたことのない谷崎精二が、「よう、よう」「大家の御入来とは恐れ入りました。また一段と恰幅が良くなって、押しも押されぬ大家だな」などと軽口を叩く姿を目にしてびっくりする。
酒場での谷崎精二は、冗談を言って周りを笑わせたり、ときには「ひゃあ」などと突拍子もない声を出したりして、教壇の先生とはまったくの別人であったらしい。
ちなみに、本編主人公の谷崎精二は1890年(明治23年)生まれ。井伏鱒二は1898年(明治31年)生まれだから、谷崎精二の方がずっと先輩だった。
まるで、次から次へと溢れるように、谷崎精二の思い出が語られ、やがて「谷崎さんが亡くなられたという電話があって」というところまで、文章は続く。
小沼丹は、豪徳寺の駅で友人と待ち合わせて、谷崎精二の自宅を訪問することにするが、約束の時間よりだいぶ早く着いてしまう。
この作品のクライマックスは、この駅のプラットホームで、通り過ぎていく人々を、じっと見送る場面である。
短い路に姿を見せては直ぐに消えてしまう通行人が、此方のそのときの気分に似つかわしい感じがしたのはどう云う訳かと思う。あんまり見ていると、谷崎さんがステッキを振って出て来そうだから戻ってきたら、着いた電車から降りて来た友人が、いや、どうも、と谷崎さんのような口を利いた。(小沼丹「竹の会」)
このラストシーンは、永井龍男の短編小説を思い出させる余韻を与えている。
「短い路に姿を見せては直ぐに消えてしまう通行人」は、そのときの小沼丹に、人生の寂しさを感じさせたのだろう。
現れては消えてゆく人たちとの出会いと別れ。
もちろん、そんなことまで書かずに、「此方のそのときの気分に似つかわしい感じがしたのはどう云う訳かと思う」とぼやかしてしまうのが、小沼丹の作品の素晴らしいところである。
作品名:竹の会
著者:小沼丹
書名:藁屋根
発行:2017/12/8
出版社:講談社文芸文庫

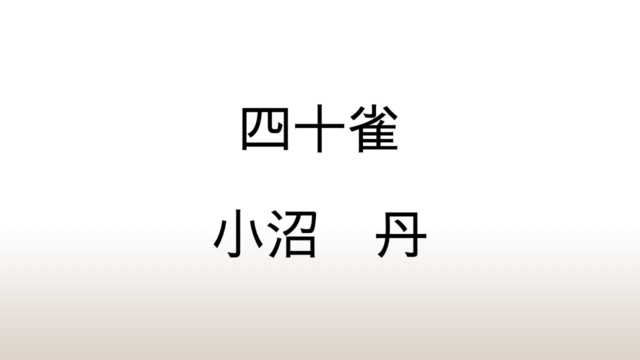
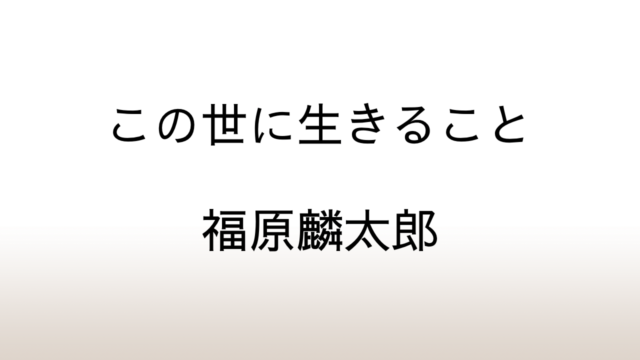
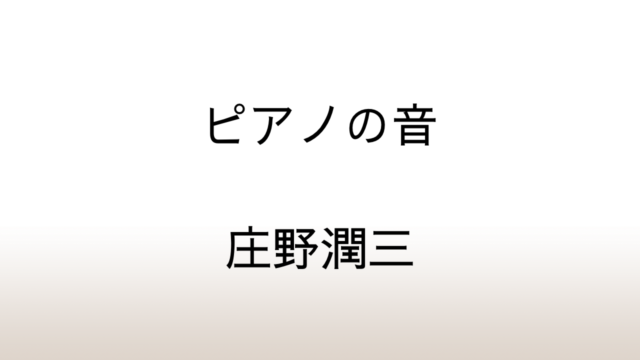

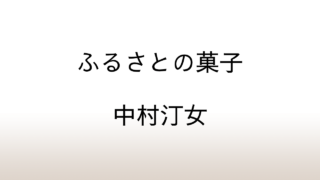
003-150x150.jpg)




