小沼丹「四十雀」読了。
本作「四十雀」は、1978年(昭和53年)1月『群像』に発表された短篇小説である。
この年、著者は60歳だった。
作品集としては、1978年(昭和53年)6月に講談社から刊行された『木菟燈籠』に収録されている。
生きていくことの難しさと寂しさ
本作「四十雀」は、鎌倉の<林さん>の思い出を綴った、追憶の短篇小説である。
全集の年譜で1949年(昭和24年)5月のところに「林房雄の勧めで「ガブリエル・デンベイ」(『歴史小説』7月)」とあるから、小沼さんが最初に林房雄に会ったのは、この時期のことだったのかもしれない。
林さんに或る雑誌に短篇を書くように云われて、ロシアの漂民のことを書いた原稿を持って林さんのお宅に行ったことがある。失態を演じてから、二、三ヶ月経った頃だったと思う。暑い日で、汗を拭きながら径を上って林さんの家の前迄行くと、芝生の庭越しに、パンツ一枚の裸の林さんが縁側に立って、手紙だか何だか読んでいる姿が見えた。(小沼丹「四十雀」)
「失態」というのは、林さんの家で飲んでいるうちに記憶をなくし、気が付いたら林さんのお宅で寝ていたという事件のこと。
このエピソードは、「のんびりした話」(『小さな手袋』)でも紹介されていて、「鎌倉の林房雄氏のお宅で御馳走になったことがある」と、林房雄の名前が綴られている。
林さんの希望で、井伏鱒二を林さんのお宅まで連れて行ったのは、1954年(昭和29年)9月と年譜にある(吉岡達夫も一緒だった)。
林さんは、永井龍男を電話で呼び出した後、井伏さんを鎌倉ペン・クラブの例会へと引っ張っていく。
久保田万太郎や久生十蘭などが参加していたらしい。
吉岡達夫の話によると、料亭では芸者も何人か来ていたというが、小沼さんは「全然記憶に無いから驚いた」と回想している。
後で、井伏さんに訊いてみると、井伏さんも「──芸者? さあ、知らないよ。そんなの来たかね?」と不思議そうな顔をしたという。
多分、この后で、酒を飲みながら井伏さんから林さんに就いての昔話を聴いたと思うが、そのとき井伏さんは、林君はいい男なのに誤解ばかりされて気の毒だ、誤解を招く言動もあるが、本当はいい人なんだ、と云う意味のことを云われた。(小沼丹「四十雀」)
この小説の中で、井伏さんのこの言葉は、ひとつの大きなキーワードとなっている。
「林君はいい男なのに誤解ばかりされて気の毒だ、誤解を招く言動もあるが、本当はいい人なんだ」という言葉の中に、生きていくことの難しさと寂しさが示されているような気がした。
懐かしい人へ送る追悼文のような小説
本作「四十雀」は、林房雄の思い出を軸としているが、井伏鱒二や吉岡達夫など、脇の登場人物によって、作品としての厚みを増している。
その意味で重要なもう一人の登場人物が、吉田健一である。
話をしながら何となく薄の方に眼をやっていたら、一人の男が薄の前を横切って客間の外に立った。半ば潰れた古ぼけた中折帽子を被った中年男で、兵隊の着るような襯衣を着ていたような気がするが、はっきり想い出せない。どういう人物なのか見当が附かなかったが、林さんの懇意な人だったと見える。(小沼丹「四十雀」)
吉田健一は、林房雄の紹介状を持って、鎌倉に住む「白樺」派の小説家の某氏を訪ねてきたところらしく、「──怕い人かと思っていたら、ちょっと親爺に似ているんで、それで親しみが持てました」と言ったという。
林さんが「──うん、似てますかね……。そう云えばお二人共小柄だし……」と応えているから、これは、志賀直哉ではなく武者小路実篤だったのだろうか。
吉田健一は、この後も登場して、内幸町にある出版社の前で会ったときには「──貴方も原稿料の前借ですか?」と挨拶したというからおかしい。
この男性が、吉田健一という小説家だということを、小沼さんが知るのは、その後、しばらく経った後のことである(新聞か雑誌の写真で見た)。
林房雄の物語としては、完全にサブキャラである吉田健一の印象が強く残るあたり、小沼さんの小説の面白さというところだろう。
大切なところを微妙にはぐらかしながら、林房雄との付き合いを回想していく。
林房雄が亡くなったのは、1975年(昭和50年)10月9日。
1978年(昭和53年)1月に発表されたこの作品は、やはり、懐かしい人へ送る追悼文のようなものだったのかもしれない。
或る朝、栗の実を拾っていたら、家の者が顔を出して、「──林さんが亡くなりましたよ」と云ったから吃驚した。栗拾いは中止にして、家に這入って新聞を見ると、林さんの写真が載っていた。眼が細くて、笑っている顔だなと思う。新聞を読んで、ぼんやり庭の方を見ながら、いろいろ昔のことを想い出していたら、四十雀が一羽飛んで来て、木蓮の枝にちょんと止った。(小沼丹「四十雀」)
四十雀を見ているとき、「不意に「──みんなみんないなくなった」と云う悉皆忘れていた懐かしい詩句が甦ったから不思議である」と、最後に著者は綴っている。
思えば、小沼丹の小説には、いつでも「みんなみんないなくなった」というチャールズ・ラムの「古なじみの顔(Old Familiar Faces)」の心境が織り込まれていたような気がする。
林房雄という馴染みのない作家の物語さえ、読後感には切ない余韻が混じったくらいだ。
これが、文学の普遍性というものなのだろうか。
そして、この小説を書いた小沼丹も、もうとっくにいない。
今も残るのは、50年近くも昔に書かれた作品だけだ。
そこに、僕は、小沼丹という作家が描いた「人生」というやつを感じ続けている。
作品名:木菟燈籠
著者:小沼丹
発行:2016/12/09
出版社:講談社文芸文庫

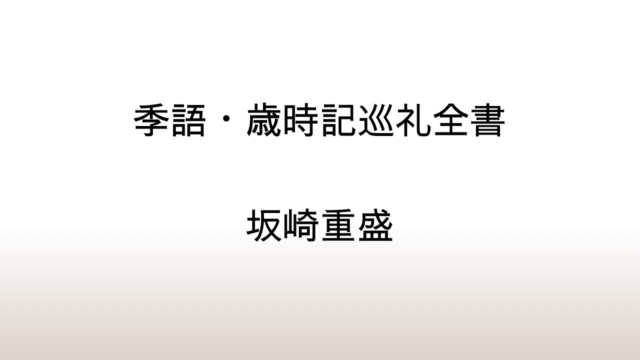
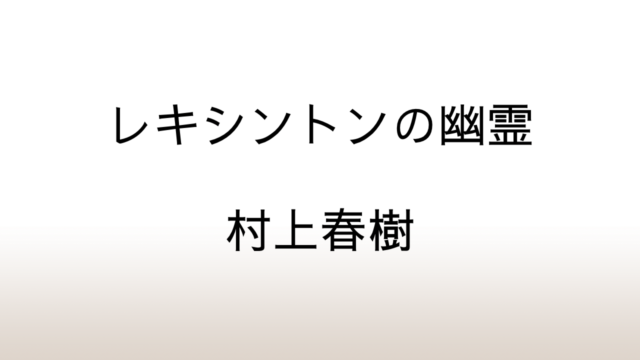
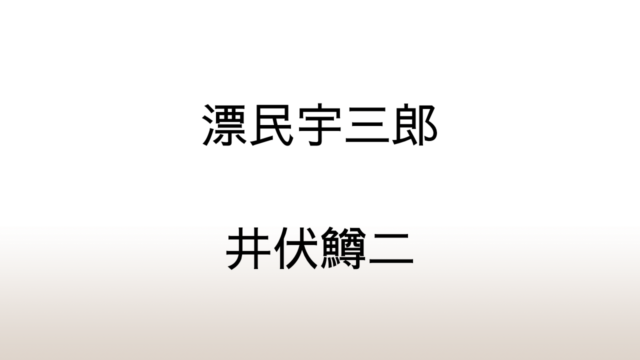
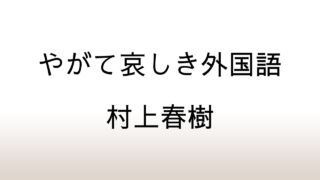
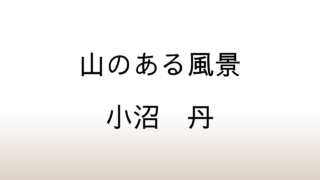
003-150x150.jpg)




