富島健夫「喪家の狗」読了。
本作「喪家の狗」は、『新潮』1953年(昭和28年)12月号に発表された短編小説である。
この年、著者は22歳だった。
1953年(昭和28年)、第30回芥川賞候補作。
嫁が強姦される瞬間を盗み見る夫の心境
富島健夫の初期作品を読むのは、多分これが初めてだけど、率直な感想として、高度経済成長期に若者の支持を得た一連の青春小説よりも、ずっと好きになれそうな作風だった。
暗くて重い作品だけれど、錆び付いた蓋を無理やりこじ開けて真実を引きずりだそうとするかのごとく、執念めいたものが感じられる。
敗戦間もない頃、一人の在日朝鮮人<金秀承>が、日本人の妻<里子>や幼い子ども<義弘>と、三人で貧しく暮らしている。
金秀承に定職はなく、福神漬け工場で働く嫁に養ってもらっている毎日だ。
李にはわかるものか。耐えきれなくなった里子が、夜中、彼のからだにからみついてくる。身をねじって、喘いで、そして求めてくるのを、彼はつめたく押しやるのだ。洗っても落ちぬ福神漬の浅い酸味を帯びた匂いに、ひやりとなるのだ。(富島健夫「喪家の狗」)
ある日、金秀承は、同胞の<李>に誘われて、アメリカ兵相手のポン引きに参加するが、運悪くMPに捕まってしまう。
何とか釈放されて「もう二度とポン引きなどやるまい」と思いながら家に帰ると、ちょうど嫁の<里子>が、李にレイプされようとしているところだった。
烈しい暴力で襲う李と、必死の抵抗を試みる里子。
息子の義弘が眠っているその横で、二人は無言の争いを続けていたが、とうとう里子は李に犯されてしまう。
制止しなければならないと思いながら、二人の争いを息を潜めて盗み見ていた金は、妻が犯された瞬間、我が家を離れる。
彼は先刻帰って来た道をもどり始めた。俺は何処へ行こうとしたのだろう。つい今まで判っていて、それで歩き出したのだがな。そうだ。もう一度、あの鉄条網の下に立ってみるつもりなんだ、そうだったかな。大体似ているが、少しちがうようだ。でもいいや。もう一度、カムオン、チャンスと呼んでみよう。(富島健夫「喪家の狗」)
嫁が強姦されるのを見た瞬間、それまで卑屈だった在日朝鮮人の男の心が、勢いよく暴走し始める。
「里子は好い女だったな。が結局好い女だったというだけさ」という金秀承の言葉は切ない。
異国の日本で貧しい生活を強いられ、同胞の男にまで妻を寝取られてしまう。
それでも、金秀承は生きなければならない(それも、この日本で)。
嫁を強姦された金秀承が、ひとつ強い男になったような気がするのは、決して偶然ではないだろう。
戦後社会の闇を切り取った作品として、自分としては好きな作品になると思えた。
ちなみに、タイトル「喪家(そうか)の狗(いぬ)」は、『孔子家語(こうしけご)』からの引用で、喪中の家の犬のこと。
喪中の家では誰も犬に餌を与えないので、犬は飢えてやせ細る。
つまり「哀微(すいび)の人」という意味を持つものらしい。
主人公の金秀承もまた、喪家の狗のごとく、哀微の男だったのだ。
庄野潤三や小島信夫と争った芥川賞
もっとも、この作品、芥川賞の選考会では散々の評価だったらしい。
宇野浩二のコメントなどは「もっと勉強しなさい」で、早稲田大学に在籍中だった富島健夫としては、荒削りの野心作というところだっただろうか。
ちなみに、同じ第30回芥川賞(1953年・下期)では、庄野潤三や小島信夫、小山清などの作品が、候補作としてノミネートされているが、受賞作はなしだった。
作品名:喪家の狗
著者:富島健夫
書名:考えない人
発行:1976/07/30
出版社:角川文庫

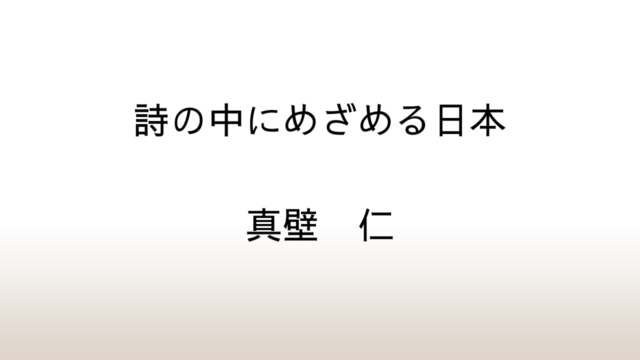
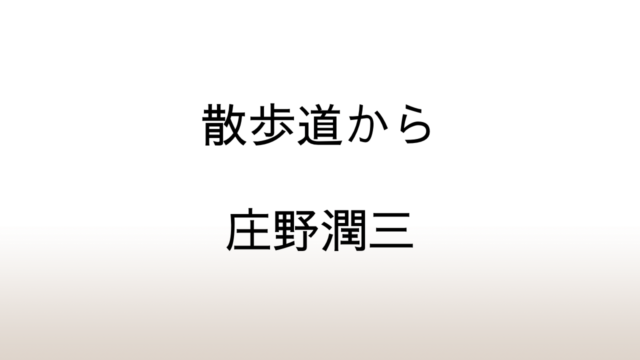
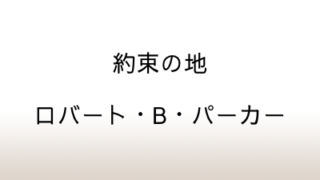

003-150x150.jpg)




