庄野潤三の「道」は、昭和37年に刊行された短編集である。
「この三年ほどの間に書いた作品からこの八篇を集めたが、「道」以外の七篇はすべて旅行中の見聞によるもので、一種の紀行小説集のやうな本が出来上った」とあとがきにある。
著者(庄野潤三)は、昭和32年から翌33年まで妻を同伴してアメリカのガンビアへ留学しているが、本短編集にも、当時の体験を元にした作品が収録されている。
「南部の旅」「静かな町」「二つの家族」「ケリーズ島」「マッキー農園」の五篇がそれで、結局全八篇のうち五篇がガンビアシリーズということになるから、本短編集はアメリカ留学の結果生み出されたものという印象が強い。
後の「ガンビア滞在記」のように包括的なものではないが、それだけにひとつひとつのエピソードにしっかりと焦点を当てて構成されていて、短編ながら小説としても読み応えは十分に大きい。
一方で、「なめこ採り」と「二人の友」は、日本に帰ってからの紀行の所産であり、表題作である「道」はある一人の女性の結婚の記録を綴ったものであるが、著者は「人生を旅と見るなら、これも旅中所見の如きものではないかと考へて、この作品集の題名にした」と綴っている。
人生そのものを旅のようなものだと感じたり、人はいつでもどこかに滞在しているのだと考えたりするのは、ある意味で庄野文学の根幹に繋がるものである。
だから、「道」というタイトルのこの短編集は、庄野文学のエッセンスを詰め合わせたものであるということができそうだ。
アメリカ旅行の不安を描く
私は妻を待たせておいて、先に便所へ行った。この時、私は便所の入り口で誰かに出会って、不意に咎められはしないかという危惧の念を感じた。しかし、便所には誰もいなかった。私はほっとして、用を足した。(「南部の旅」)
ガンビアシリーズの「南部の旅」は、グレイハウンド・バスでメンフィスを訪れた際の物語だが、バスの中で黒人はみな後ろの席へ座っていたり、バス・ターミナルの待合室は「白人用」と「黒人用」に分かれていたりと、アメリカの人種差別社会が色濃く描かれている。
著者は気付かぬままに「白人専用」の待合室を利用してしまい、何かトラブルに巻き込まれてしまうのではないかという大きな不安を感じるが、こうした不安的要素は「ガンビア滞在記」の中では、ほとんど触れられなかったものである。
昭和34年に発表された「南部の町」では、まだ「不安を描く作家」と呼ばれていた庄野潤三の作風が、如実に浮き彫りになっているのだ。
おそらく、この南部への旅を題材にするだけで、著者は他にいくつもの物語を完成させることができるに違いない。
ほとばしり出る不安が、アメリカ南部の熱さをリアルに描き切っている。
人生の頼りなさや夫婦の絆の不確かさ
私の主人は、「飽いたからお古をくれた」と云ひます。それがいちばん腹が立つたと云ひます。さう取られても仕方ありません。或は実際その通りであつたのかもしれません。主人はまた、自分に結婚の話をしておきながら一方で私と関係を続けてゐたという点がいちばんいやだと云ひます。「(道)」
表題作「道」は、初期庄野文学で見られる夫婦の不安を題材としたものである。
パン屋で知り合って結婚した二人だが、妻とパン屋の主人との間には不倫の関係があり、それが結婚直前まで続いていたことが、結婚後に発覚してしまう。
小心の夫は、離婚を匂わせたり、家出をしたりするものの、夫婦の中は境界線ギリギリのところで保たれていく様子が、妻の目線から描かれている。
パン職人である夫の仕事が安定しなかったり、住居がなかなか定まらなかったり、不安を抱えながらの結婚生活は、妻の不倫の過去を背景として、なかなか思うようには進んでくれない。
夫は、いつかまた妻が元の不倫相手とヨリを戻すに違いないと疑心暗鬼になっているし、妻は自分の過去に責任を感じているから、夫婦の関係はどこまでも不安定に、緊張感を持って進んでいく。
紆余曲折を繰り返しながら過ぎていく日々は、まさしく「道」のようであって、人生の頼りなさや夫婦の絆の不確かさが、物語に陰影を与えて立体的な作品として示された。
生きることには、常に不安がつきまとうものである。
その不安を、庄野潤三は小説という形でくっきりと浮き彫りにしてみせたのだ。
書名:道
著者:庄野潤三
発行:1962/7/15
出版社:新潮社

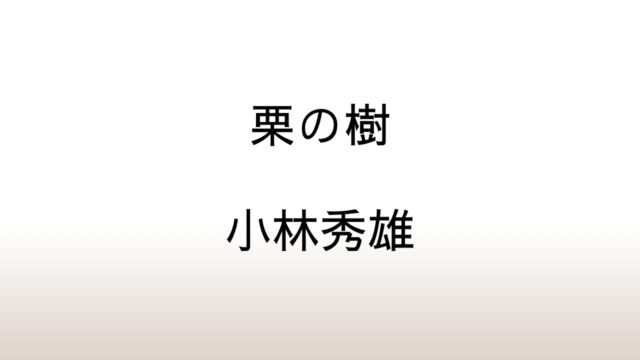
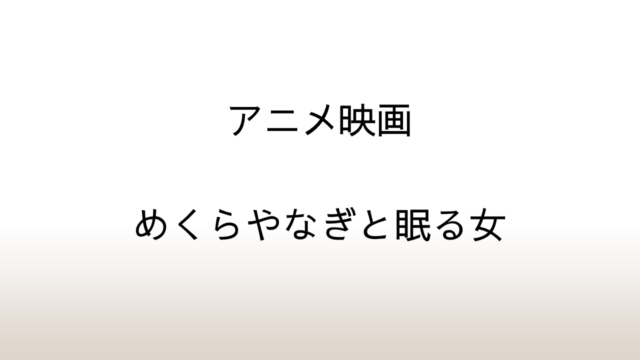
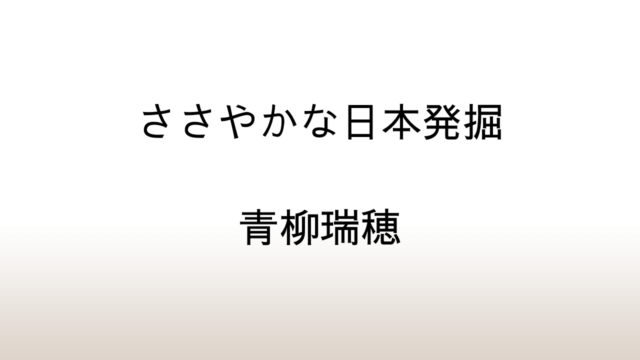
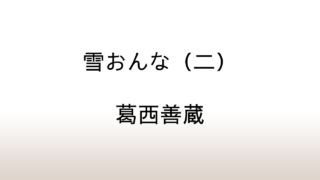
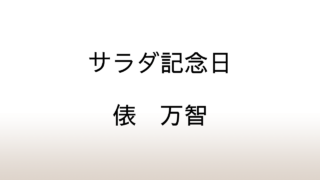
003-150x150.jpg)




