庄野潤三「餡パンと林檎のシロップ」読了。
本作「餡パンと林檎のシロップ」は、「文学界」昭和47年1月号に発表された短篇小説である。
作品集では『休みのあくる日』(1975、新潮社)に収録された。
「お前の餡パン、無くなった、といってるの」
本作「餡パンと林檎のシロップ」は、明夫と良二の兄弟が登場する、いわゆる「明夫と良二」シリーズの作品である。
本作で、明夫は予備校生、良二は中学三年生として登場している。
庄野家の長男・龍也が、高校を卒業して予備校に入学したのは、1970年(昭和45年)4月のこと。長女・夏子が結婚して家を出てゆくのは、同じ年の5月のことである。
全部で8篇のエピソードから構成されているが、いずれも家庭内の何気ない日常の断片を切り取ったスケッチである。
それぞれのエピソードに直接的なつながりはなく、起承転結の明確なストーリーがあるわけではない。
例えば、作品タイトルの餡パンと林檎のシロップが出てくる第五章は、風呂上がりに家族でお茶にする場面が描かれている。
その夜のおやつは、良二が見つけてきたパン屋の餡ぱんと、細君がつくった林檎のシロップと、せんべいの入ったお菓子のかんからであった。
良二が風呂から上がるのを待ちきれなくなった三人は、餡パンを先に食べ始めてしまう。
風呂の戸があいて、「出まーした」という良二の声が聞えた。「良二」明夫は大きい声を出した。「はあ」「餡パン、なくなったぞ」「え?」「お前の餡パン、無くなった、といってるの」哀れな叫び声が聞えた。(庄野潤三「餡パンと林檎のシロップ」)
明夫は、良二の分を取って、蜜柑を入れてある鉢のうしろへ隠した。
そして、ちょうど半分だけ食べた自分の餡パンを、良二の席の前へ置いた。
慌てて入って来た良二は、半分になった餡パンを見て「あ、済んましぇん」と、うれしそうに言った。
明夫は、話にならないというふうに、父親と細君の顔を見て笑った。
「もう無くなったかと思ったら、あったから」と良二は言った。
なくなったと思っていた餡パンが、半分とはいえ残っていた。
そのことがうれしかったのである。
いずれ間もなく終わってしまうだろう、四人家族の物語
長女の結婚前夜の日常生活を描いた「絵合せ」の頃から、庄野さんはこうした家族をモチーフとした物語を「家族日誌」と呼ぶようになった。
そこには、「それひとつでは名づけようのない、雑多で取りとめのない事柄」が描かれていて、庄野さんは、そうした<雑多で取りとめのない事柄>について「或は結婚よりももっと大切であるかもしれない」と述べている。
なぜなら、こうした<雑多で取りとめのない事柄>は、「いま、あったかと思うと、もう見えなくなるものであり、いくらでも取りかえしがきくようで、決して取りかえはきかない」ものだからだ。
庄野さんが、こうした<雑多で取りとめのない事柄>に、特に着目した背景には、「どんなに楽しく過しても、それは一瞬のもの」という、人生に対する基本的な姿勢があるからだろう。
本作「餡パンと林檎のシロップ」に描かれる家族スケッチは、いずれも、のんびりとしていて、ちょっと愉快なエピソードばかりだが、こうした家族の日常も永遠に続くものではない。
やがて子どもたちは、みな家を出て独立し、夫婦ふたりきりの暮らしがやってくる。
老夫婦は、いつか必ず、かつて賑やかだった日々を懐かしく思い出す日が来る。
そう考えると、人生ははかないし、当たり前のように思える日常生活の一瞬が、貴重な思い出の一つとなるような気がしてくるのではないだろうか。
庄野さんは、愉快な子どもたちの会話を人生の断章としてとらえて、ひとつの物語を作り上げることに腐心した作家だった。
この家族日誌は、いずれ間もなく終わってしまうだろう、四人家族の物語なのである。
書名:餡パンと林檎のシロップ
著者:庄野潤三
発行:1975/2/10
出版社:新潮社

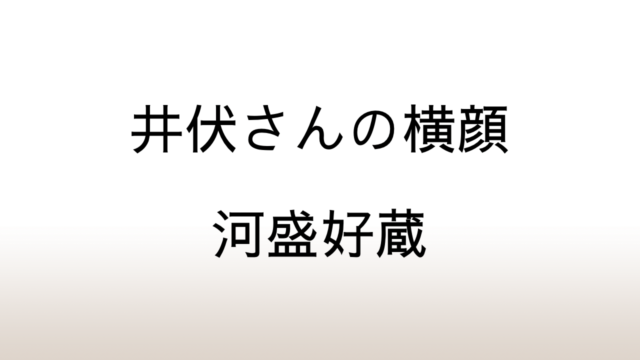




003-150x150.jpg)




