小沼丹「翡翠」読了。
本作「翡翠」は、1982年(昭和58年)5月『海燕』に発表された短篇小説である。
この年、著者は64歳だった。
作品集としては、1986年(昭和61年)9月に講談社から刊行された『埴輪の馬』に収録されている。
石川隆士と玉井乾介(金井)
本作「翡翠」は、学生時代の友人<石川隆士>の思い出を綴った物語である。
想い出すと古い話だが、或る大学に入学することに決ったから、清水町先生の所へ行ってその旨を報告すると、石川隆士と云う男と友達になるといい、と先生が云った。「──石川君も今度、予科から文学部に行く」「──小説を書いてるんですか?」「──いや、小説は書かないが、なかなかいい詩を書く。詩人だから、ちょっと気取っているかもしれないよ」そう云って、先生は面白そうな顔をした。(小沼丹「翡翠」)
小沼丹が早稲田大学に入学したのは、1940年(昭和15年)4月で、22歳になる年だった。
初めて石川隆士に会ったとき、小沼さんは、井伏さんの言葉を思い出して、「成程、大分気取っているな」と思ったそうである。
憶えているのは、よく晴れた日で、リラの淡紫の花が満開だったことである。当時はどう云うものか、詩人とは気難しいものだと思い込んでいた。石川を見ると、眼鏡を掛けた真面目そうな男で、一方ならず気難しそうな顔をしている。二十世紀の憂鬱を独りで背負い込んだ顔だったかもしれない。(小沼丹「翡翠」)
「二十世紀の憂鬱を独りで背負い込んだ顔だったかもしれない」がおかしいが、親しくなってみると、石川は決しておとなしい人間ではなくて、小沼さんのいくつかの作品の中で、武勇伝を披露することになる。
大学生となった小沼さんは、石川隆士にも声をかけて、新しい文芸雑誌を始める。
雑誌の名前は、最初「海燕」という名前に決まっていたが、ロシア人のブブノワさんに書いてもらった表紙絵を紛失したことで、雑誌の名前は「胡桃」に変更される。
このとき、ブブノワさんの絵を失くした友人というのが、小沼さんの小説では、しばしば<金井>として登場している玉井乾介だった。
(この辺の話は、短篇小説「胡桃」(『木菟燈籠』所収)に詳しい)
石川隆士と玉井乾介(金井)は、学生時代の思い出を綴った一連の作品の中で、重要な役割を果たす登場人物だ。
小沼さんの作品を読んでいくと、同じ登場人物がたびたび登場する場合があって、まるで連作短編シリーズのように楽しむことができる。
以前に読んだ作品の登場人物と、別の作品の中で再会したりすると、懐かしい友人に会ったような気持ちになって、気分が盛り上がる。
そんなところも、小沼文学を楽しむポイントの一つなのではないだろうか。
作品タイトルの「翡翠」は、石川隆士の書いた詩に由来している。
石川の詩では、「渓流」と云う題の詩が記憶にある。多分、「早稲田文学」に載ったような気がするが自信は無い。作品が手許に無いのではっきり想い出せないが、谷川に向って書き損じた手紙を千切って捨てる、捨てながら紙片に、「──翡翠になれ、翡翠になれ」と呼び掛けるのである。(小沼丹「翡翠」)
「翡翠」という漢字のルビに、石川は「とり」と書いていたらしいから、この短篇小説のタイトルも「翡翠(とり)」ということになる。
清水町先生は「石川は詩を書いているかしら?」と心配していて、最近は小説を書いていると聞くと、「──ふうん、そうかね? 詩人が堕落したね」と言ったそうである。
石川隆士は、井伏鱒二と同郷で、戦後に結婚したときも、井伏さんが仲人になった。
井伏さん自身、「仲人」という文章を書いていて、<房木君>という名前で石川隆士が登場している。
「清水町先生の漢詩訳に、「──アサガヤアタリデ大ザケノンダ」と云う一行があるが、石川は阿佐ヶ谷へ来ると、必要以上にこの一行を意識して大酔に及んだのではないかしらん?」とあるのも、石川と清水町先生の親しい関係を現している感じが出ている。
1981年(昭和56年)の1月、小沼さんの出版記念会(『小沼丹作品集』か『山鳩』だろう)で久しぶりに再会したとき、石川は何となく元気がないように思われた。
ちなみに、随筆「長距離電話」(『小さな手袋』)で、石川は、名古屋の新聞社に勤務していることが綴られている。
小沼さんの出版記念会のために、名古屋から荻窪までやってきたらしい。
石川と会って話をしたのは、それが最後になった。
今年の正月の二日、石川の奥さんから電話があって、石川が死んだと知らせて来たからたいへん驚いた。何でも去年の夏ごろから入院していたらしい。病気は脳出血で、元日に死んだそうだが、「──元旦にお知らせするのもどうかと思いまして……」と奥さんが云った。(小沼丹「翡翠」)
「どこか遠くの方から、翡翠になれ、翡翠になれ、と云う声が聞えて来るような気がした」と続いているところが、小沼スタイルというやつだろう。
ただし、最後は湿っぽく終わらないのも、また、小沼文学のスタイルだ。
ブラジルのサン・パウロにいる金井からの手紙に、ブラジルはやぽたんとか云う大木が一杯に花を付けていて、紫がかった夾竹桃も満開だと書いてある。
「一体、紫色の街とはどんな感じがするものかしらん? やぽたんの花とは、どんな花なのだろう?」と、まるで石川の死をはぐらかすようにして、物語が終わる。
あたかも、友人の死を儚む小説を書いたことが恥ずかしいとでも言うように、最後はふっと話題を逸らす。
この辺りの絶妙なバランスが、小沼文学にとって、ひとつの生命線となっていることは間違いないだろう。
本作「翡翠」もまた、訃報に接した旧友に送る追悼の物語だった。
生きるということは、親しかった人々を見送るということでもあるのかもしれない。
そして、いつかは、自分が見送られる番がやってくるのだとしても。
作品名:翡翠
著者:小沼丹
書名:埴輪の馬
発行:1999/03/10
出版社:講談社文芸文庫

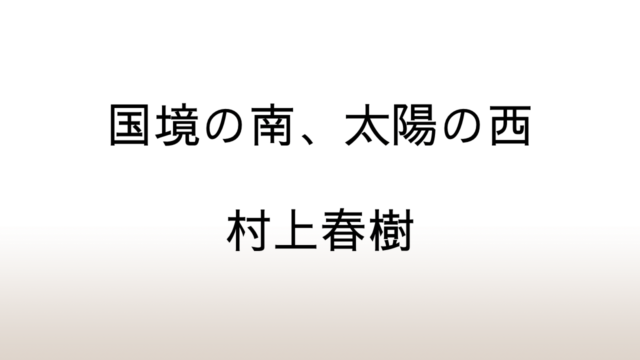

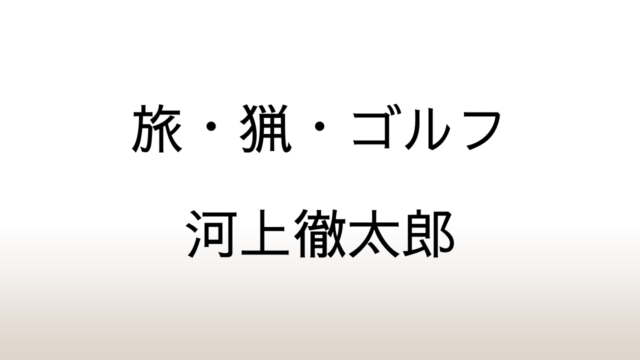
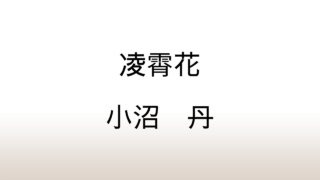
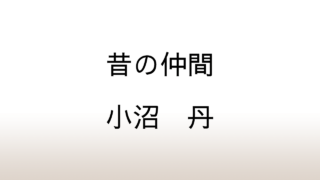
003-150x150.jpg)




