小沼丹「銀色の鈴」読了。
本作「銀色の鈴」は、1971年(昭和46年)2月『群像』に発表された短編小説である。
この年、著者は53歳だった。
作品集では、1971年(昭和46年)5月に講談社から刊行された『銀色の鈴』に収録されている。
すべてを書き切らない小沼文学の魅力
小沼丹の小説は、どうしてこんなにおもしろいのだろう。
特に、著者自身がモデルになっていると思われる<大寺さんシリーズ>はすごい。
本作「銀色の鈴」も、六、七年前に妻を亡くした<大寺さん>が主人公の短編小説である。
ベッドの傍の本棚に載せた銀色の鈴から、大寺さんは、亡くなった細君のことを思い出す。
細君が生きていた頃、大寺さんは、目を覚ますと、この銀色の鈴を鳴らして、細君を呼んだものだった。
物語は、そんな死んだ細君の思い出から始まる。
銀色の鈴は、物語を死んだ妻の思い出へと導くための小道具だが、小沼さんは、こういう小道具の使い方が滅法にうまい(そして、作品タイトルもいい)。
細君が死んだ後、二人の娘とともに遺された大寺さんの再婚が、友人たちの間で話題となった。
淡々とした文章で、前の細君が亡くなってから、現在の細君と再婚するまでのことが綴られていく。
しかし、物語は、あくまでも、死んだ最初の細君に焦点が当てられている。
その翌年の春、大寺さんは細君と一緒に上野の娘の結婚式に出た。ぼんやり花嫁姿の娘を見ていると、いつの間にか時間の歯車が逆に廻転し始めて、春子がだんだん小さくなって行ったかと思うと、その上に母親の顔が重なって見えた。(小沼丹「銀色の鈴」)
春子の母親は、死んだ前の細君である。
前の細君は、大寺さんに何か言ったようだったが、それは声にはならなかった。
「何と云う心算だったのだろう?」と、大寺さんは考えるが、答えは出てこない。
ここに、小沼文学のひとつの特徴がある。
小説の中で、著者はすべてを書くことをしない。
まるでぶつ切りのようにして、著者は答えを出すことを強く拒絶するのである。
ちなみに、著者の小沼丹が妻を突然死で失ったのは、1963年(昭和38年)のことである。この年、小沼さんは45歳だった。
じわじわと胸を濡らしてくるような余韻
同じような場面が「銀色の鈴」の中に、もう一つある。
それは、片付ける仕事があって、夏の終わりの東北まで出かけたときのことだ。
夕食に酒を飲んで眠り、夜中に目覚めると激しい雨が降っていた。
仕事をする気にもなれなくて、大寺さんは、持参のウイスキイを取出して水で割って飲むことにする。
ウイスキイを飲みながら激しい雨の音を聴いていると、その中からいろんな声が聞えて来るから不思議であった。それに混って、或る旋律を繰返し演奏しているのも聞えた。突然、雨の音が歇むと嘘のように静かになって、それと同時に声も旋律も消えてしまう。──どうだろう?(小沼丹「銀色の鈴」)
激しい雨の音の中、果たして大寺さんはどんな声を聞き、どんな旋律を聞いたのだろうか?
その答えは、どこにも書かれていない。
大寺さんは、ただ、「うん、もう一杯飲もう」と言って、ウイスキイの水割りを飲み続ける。
まるで余白のたっぷりと残されたスケッチブックのように、小沼さんの小説は淡白でさっぱりとしている。
そのくせ、取り残された寂しさの中で、じわじわと何かが胸を濡らしてくる。
この余韻が、小沼文学の最大の魅力なのではないだろうか。
もちろん、この余韻は、本文中で描かれている様々なエピソードの後からやって来るものである。
読者は、春子の結婚式のときに現われた死んだ細君の言葉や、激しい雨の中で大寺さんが聞いた声や旋律を想像することができる。
そして、その想像に共感することができる。
それは、余計なことが一切書かれていない、この小説の中に、余韻を残すだけの物語がしっかりと書かれているからだ。
小沼さんの小説を読むたびに「不思議だなあ」と感じる理由は、そんなところにあるのかもしれない。
短い物語の中に、大きな時間の流れとヒューモアが溢れている。
作品名:銀色の鈴
著者:小沼丹
書名:銀色の鈴
発行:2010/10/10
出版社:講談社文芸文庫


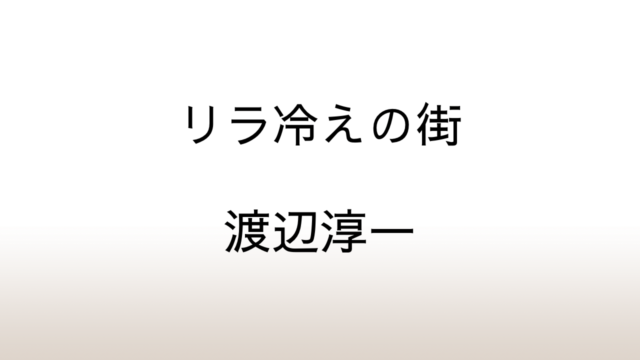
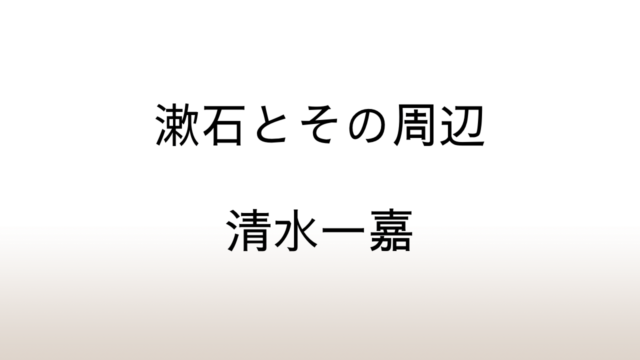


003-150x150.jpg)




