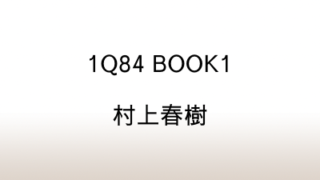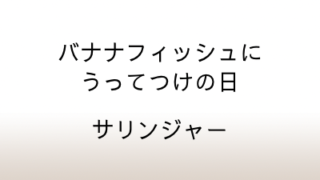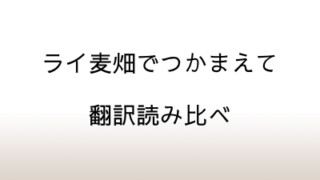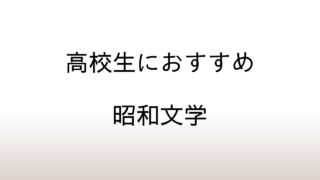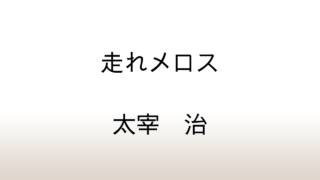トルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を」読了。
本作「ティファニーで朝食を」は、1958年(昭和33年)『エスクァイア』に発表された中篇小説である。
原題は「Breakfast at Tiffany’s」。
この年、著者は34歳だった。
生きづらさを抱える不器用な女の子
庄野潤三は、『ガンビア滞在記』(1959)のあとがきに、こんな文章を綴っている。
私は滞在記という名前をつけたが、考えてみると私たちはみなこの世の中に滞在しているわけである。自分の書くものも願わくばいつも滞在記のようなものでありたい。(庄野潤三「ガンビア滞在記」)
一方で、本作『ティファニーで朝食を』の主人公として登場する女性<ホリー・ゴライトリー>の名刺には、常に「旅行中(トラヴェリング)」の文字があった。
私がその家に移ってから一週間ばかりたったある日のこと、二号室に属する郵便箱の名札さしに、奇妙な名刺がさしこんであった。しゃれた字体で印刷してある文字を読むと、「ミス・ホリディ・ゴライトリー」とあり、その下の隅っこに、「旅行中(トラヴェリング)」と記してあった。(トルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を」龍口直太郎・訳)
もちろん、ホリーは、実際に旅行へ出かけていたわけではない。
彼女の人生は、常に「旅行中」だったのだ。
ある小説家は、人生を「滞在」のようなものだと書き、ある女性は、人生を「旅行」のようなものだと考えている。
僕は、この小説を、そのような観点から読んでいった。
眠りたくもなし、死にたくもなし、ただ旅して行きたいだけ、大空の牧場通って──この歌がいちばん彼女のお気に入りだったらしい。というのも、彼女は髪がかわいてしまったずっとあとまで、夕陽が沈み、たそがれの窓べに灯がチラホラ見えても、なおそれを歌い続けていたからだ。(トルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を」龍口直太郎・訳)
「ただ旅して行きたいだけ」というこの歌は、ホリーにとって、人生のテーマソングである。
多くの人間が、平穏な安住を求める世の中にあって、ホリーは、常に夢を追いかけ続けた。
だから、ある意味で、この作品は、夢を追いかける若者へ送る応援歌のような物語としても読むことができる。
もっとも、「あたしはちがう、どんなものにも慣れるってことないの。そんな人間がいたら、死んだほうがましなくらいよ」と主張する彼女のような生き方を、実際にしようと思ったら、かなり消耗するに違いないだろう。
世の中と折り合いをつけることさえ、彼女にとっては「あのいやな赤」と同じようなものだったのだから。
ホリー・ゴライトリーもまた、生きづらさを抱える不器用な女の子だったということなのだろうか。
ティファニーに象徴される秩序の空間
彼女の生き方を象徴するのが、<私>が持っている「宮殿みたいな鳥籠」と、ホリーの飼っている一匹の猫だ。
骨董屋のウインドーに飾ってあった鳥籠をプレゼントしてくれたとき、ホリーは「でも約束してね、そん中には生きものを絶対に入れないって──」と、<私>に念を押す。
旅するように生きる彼女にとって、鳥籠は、人生の終着点のように思われたのかもしれない。
そして、ホリーの飼っている猫は、ホリーが旅立つという瞬間に、街の中へ放される。
彼女は身ぶるいし、危うく倒れそうになって、私の腕につかまった──「ああ、しまったことしちゃった。あたしたちはどうしても離れらない間がらだったのよ。あの猫はあたしのものだったんだもん」(トルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を」龍口直太郎・訳)
動物のいない鳥籠と、名前のない猫は、自分探しを続けるホリー・ゴライトリーにとって、象徴のような存在だったに違いない。
そして、そんなホリーが求める安住の地がティファニー宝石店だった。
「いったいあたしって女は、あたしとほかのものがちゃんと一緒にいられるような場所をはっきりみつけるまでは、どんなものにしろ、所有したいなんて思わないのよ。ところが、まだ今のところでは、そういう場所がどこにあるかはっきりしないの。でもね、それがどのようなところか、あたしにはよくわかってるわ」そこで彼女はニッコリと口もとをほころばし、猫を床の上に落した。「それはティファニーの店みたいなところ。といっても、宝石なんかどうだっていいのよ」(トルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を」龍口直太郎・訳)
もちろん、ティファニーは、一つの比喩に違いない。
彼女が求めているのは、莫大な財産でも豪華な生活でもないからだ。
「結局、自分でみつけたいちばんいい方法というのは、タクシーに乗ってティファニーの店に出かけること。そうすると、すぐに気分が落着いてくるのよ──あたりのシーンとした静けさや、誇らしげなお店のようすでね。あの立派な洋服を着た親切な人たちを見たり、銀とワニ革の財布の気持のいい匂いをかいだりしてると、ひどく悪いことなんかとても起りそうもないのね。だから、あたしをティファニーの店にいるような気分にしてくれる本物の生活のできる場所が見つかりさえしたら、あたしは家具でも買い入れ、この猫に名前をつけてやるわ」(トルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を」龍口直太郎・訳)
「ひどく悪いことなんかとても起りそうもない」ティファニーの店は、「あのいやな赤」に対するアンチテーゼとして作用している。
一言で言うと、それは「秩序」だ。
結局のところ、ホリーの自分探しの旅は、彼女の個人的な問題であったと同時に、社会的な問題でもあったと言える。
若い女性の極めて個人的な生き方を描きながら、この作品は、現代アメリカという非常に大きな世界を描いていたのかもしれない。
この点、何となくだけれど、J.D.サリンジャーが『ライ麦畑でつかまえて』(1951)で描いた、<ホールデン・コールフィールド>の不安を思い出してしまった。
いずれも、若者の不安を丁寧に描き出している作品だからだろう。
ホリーが逃がした猫は、物語の最後で見つかる。
両わきに小ざっぱりしたレースのカーテンが下がっている、鉢植えの草花のあいだに、彼はうずくまっていた。見るからに温かそうな部屋の窓わくの上であった。彼にどんな名前がつけられたのかしら、と私は思った。(トルーマン・カポーティ「ティファニーで朝食を」龍口直太郎・訳)
安住の地を見つけた猫の姿には、ホリー・ゴライトリーの幸運を祈る気持ちが示唆されている。
そして、その祈りを具象化した場面こそ、冒頭に出てくるアフリカの写真だったのだろう。
人生とは、旅のようなものだ。
若い世代にとっては、特に。
「ティファニーで朝食を食べる」というのは、もちろん比喩表現である。
人生をこんなふうに表現できるというだけで、ホリー・ゴライトリーは素晴らしい女性なんだということが分かる。
人生においては、センスが大切っていうことかもしれない。
余談だけれど、物語の語り手<私>には、作者であるトルーマン・カポーティの影が感じられた。
センシティブで、ちょっと気難しくて(逆切れしてホリーをボコボコにしてしまう)、中性的ゆえに女性とも友人関係を保つことができる<私>は、もしかすると、カポーティ自身だったのかもしれない。
作品名:ティファニーで朝食を
著者:トルーマン・カポーティ
訳者:龍口直太郎
発行:1968/07/30
出版社:新潮文庫

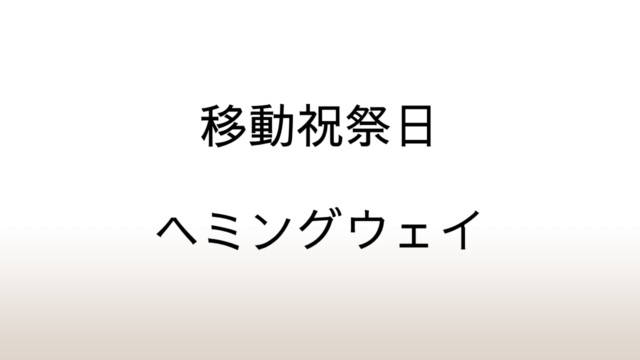
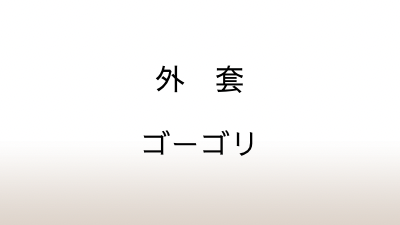
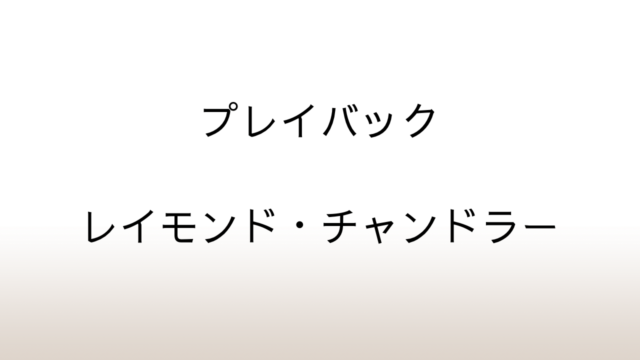
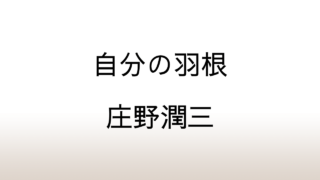
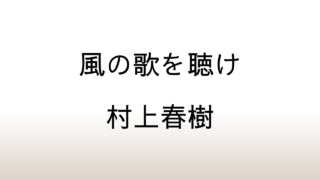
003-150x150.jpg)