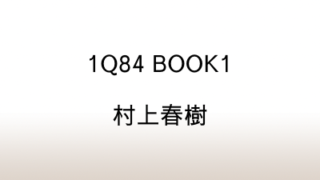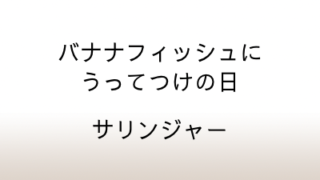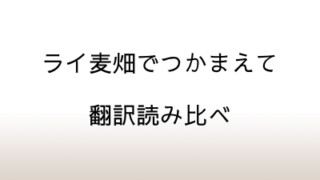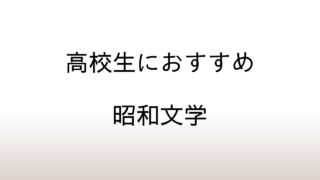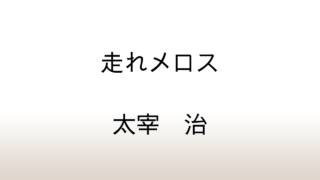庄野潤三「早春」読了。
本作「早春」は、1980年(昭和55年)6月から1981年(昭和56年)9月まで16回にわたって「海」に連載された長編小説である。
連載開始の年、著者は59歳だった。
単行本は、1982年(昭和57年)1月に中央公論社から刊行されている。
登場人物の人生を通して「都市と人間の移ろい」を描く
単行本の帯には「私の神戸物語」「青春の地、神戸を旧友、叔父夫婦の案内で妻と再訪する。都市と人間の移ろいを描いて静かな感動を誘う長篇」「神戸の今昔を描く最新長篇小説」とある。
現代の神戸を訪ねながら、神戸の街の歴史を振り返る構成になっているので、旅行記のような雰囲気を持った歴史案内書と言うことができそうだ。
特徴的なのは、神戸の街の案内役として、旧友の「太地一郎」と、芦屋にいる「叔父夫婦」、そして、ガンビアにあるケニオン・カレッジ繋がりの「郭ジェーン」が登場することで、それぞれの登場人物が、自分の言葉で思い出の神戸を語ることで、ストーリーを生み出す仕組みとなっている。
「それからラムネね。十八番いうのはラムネを製造したところです。球入れたラムネあったでしょう、昔。いまもありますけど。あれを日本で初めて製造したのが十八番の家です。十八番のラムネいうてこれも居留地にあったんです」(庄野潤三「早春」)
『早春』が、ただの神戸ガイドブックではなく、文学作品として完成されているのは、こうした登場人物の人生を通すことで、「都市と人間の移ろい」を描いているからに他ならない。
生身の人間への取材を作品として生かす手法は、大阪の街を描いた『水の都』と同様で、実際、芦屋で暮らしている叔父夫婦は、『水の都』『早春』のいずれの作品にも登場しているし、むしろ『水の都』を書きながら、同時に庄野さんは『早春』の構想も固めつつあったのだろうという感じがする。
作品が次の新しい作品を生み出した、ということかもしれない。
題名の「早春」は伊東静雄の詩集『夏花』から
作品名の「早春」は、庄野さんの師である詩人・伊東静雄の作品に依っているようだ。
学生ぶりに再会した旧友の太地は、その昔、庄野さんから伊東静雄の詩集をもらったことがあるという話をする。
聞き終った太地は、それで思い出したけど、僕はあなたから伊東静雄の詩集を貰っているんだといった。それは覚えていないというと、「あなたが僕の差上げた本を持っているのと同じようにね。『夏花』という詩集」(庄野潤三「早春」)
太地は、その中の「早春」という作品が特に好きだと言い、私たちも早春の頃が一番好きだと、庄野夫妻が答える。
早春の瑞々しさは、青春の日の初々しさに通じるものがあり、あるいは、明治以降に栄えた神戸の街の輝きを意味するものでもあったかもしれない。
ところで、昭和50年代の庄野さんは、それまでの日常のスケッチを離れた、取材に基づく作品を書き続けている。
『引潮(1977年)』『水の都(1978年)』『早春(1982年)』『陽気なクラウン・オフィス・ロウ(1984年)』『サヴォイ・オペラ(1986年)』といった作品は、まさしく作家として円熟期にあった時期の作品と言っていい。
こうした一連の大きな仕事の中、庄野さんは病に倒れ、闘病記とも言える『世をへだてて(1987年)』で復活した後は、『エイヴォン記』などのフーちゃんシリーズや、『貝がらと海の音』で始まる夫婦の晩年シリーズといった「家族小説」に注力していくことになる。
『早春』が連載されていた頃、50代後半だった庄野さんは、まさしく作家として円熟期に入りつつあったわけで、どこまでもどこまでも書いていけそうなエネルギーを、この小説からは感じた。
書名:早春
著者:庄野潤三
発行:1982/1/20
出版社:中央公論社

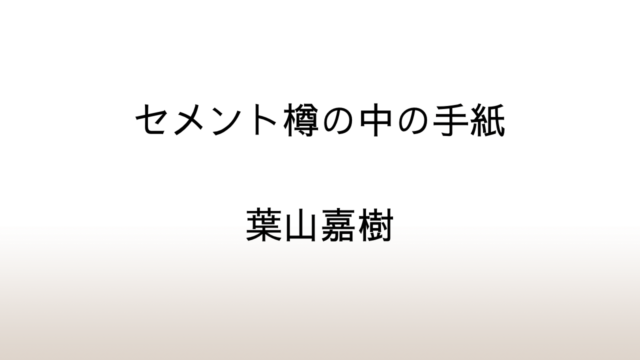
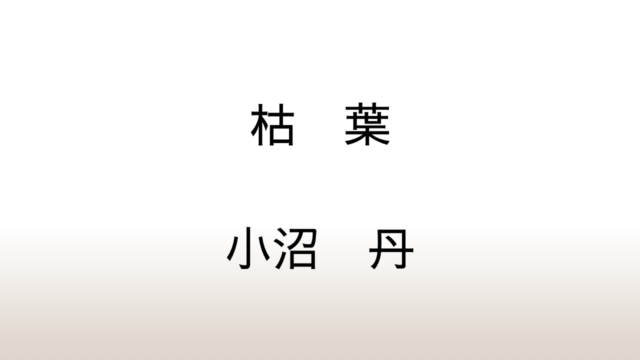
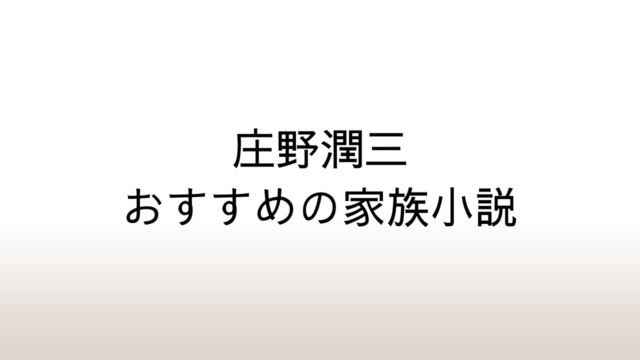
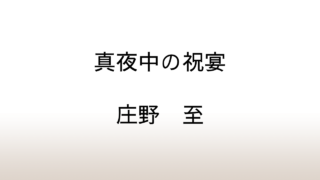
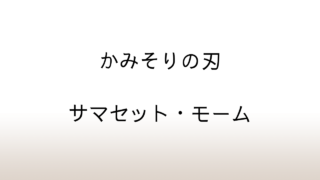
003-150x150.jpg)