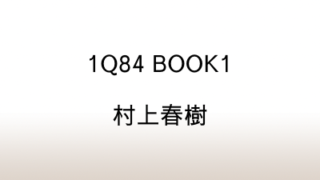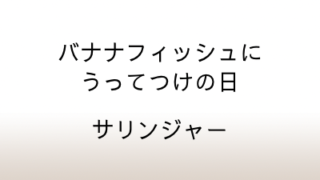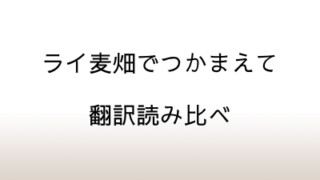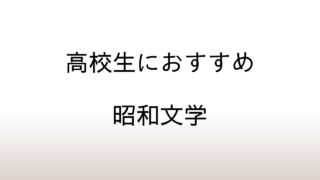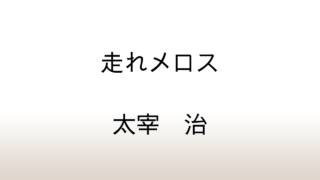太宰治「お伽草紙」読了。
本作「お伽草紙」は、1945年(昭和20年)10月に筑摩書房から刊行された短編小説集である。
この年、著者は36歳だった。
人生のはかなさや人の世の皮肉を伝える
戦争中、多くの文学者たちの活動が停滞する中、太宰は淡々と自分の小説を書き続けたという。
新潮文庫版「お伽草紙」には、戦時中に書かれた短編5編が収録されているが、その中核となっている作品が「新釈諸国噺」と「お伽草紙」の二つである。
この頃、太宰は、日本や中国の古典や民話を素材として、自分なりの解釈で物語を発展させていく手法を多用しており、「新釈諸国噺」や「お伽草紙」はもちろん、「盲人独笑」「清貧譚」「竹青」のいずれも、元素材のある作品となっている。
現代でも人気があるのは、「ムカシ ムカシノオ話ヨ」で始まる「お伽草紙」で、子どもの絵本に出てくる昔話を、太宰流に再解釈してみせる物語だが、狸を醜悪な中年男に、兎を十六歳の処女に見立てた「カチカチ山」は傑作として知られている。
個人的には「浦島太郎」に登場する亀がいい。
子どもにいじめられているところを助けてやった浦島太郎に対して、「せっかく助けてやったは恐れいる。紳士は、これだから、いやさ。自分がひとに深切を施すのは、たいへんの美徳で、そうして内心いささか報恩などを期待しているくせに、ひとの深切には、いやもうひどい警戒で、あいつと同等の附合いになってはかなわぬなどと考えているんだから、げっそりしますよ」などと亀は毒づき、「しかし、まあ、五文とは値切ったものだ。私は、も少し出すかと思った。あなたなのケチには、呆れましたよ。私のからだが、たった五文かと思ったら、私は情け無かったね」とにべもない。
現代社会でも、どこかで聞いたような話になりそうな気がする。
井原西鶴を下敷きにした「新釈諸国噺」では「人魚の海」を推したい。
荒れ狂う海に現われた人魚を弓で撃ち殺した武士が、噓つき呼ばわりされたことに立腹し、人魚の死骸を探して回るが見つからず、ついには衰弱して死んでしまう。
怒りに狂った仲間と娘が仇討ちを果たした後で、人魚の骨が発見されるという話だが、打ちあがった人魚の骨に武士の矢が刺さったままだった、というラストシーンは忘れがたい。
近世文学の面白さをしっかりと再現しているだけでなく、人生のはかなさや人の世の皮肉を伝えるに十分な作品となっている。
世の中に迎合した作品を量産する売れっ子小説家は正義か?
今回読んで面白かったのは「清貧譚」である。
菊の花の美しさに魅せられている男が、菊の花を売って金銭を得るなど邪道で卑しい行為だと主張して譲らない。
かたや、江戸へやってきたばかりの姉と弟は、美しい菊の花をいくつも育てて、経済的にも豊かになってゆく。
私は、君を、風流な高士だとばかり思っていたが、いや、これは案外だ。おのれの愛する花を売って米塩の資を得る等とは、もっての他です。菊を凌辱するとは、この事です。おのれの高い趣味を、金銭に換えるなぞとは、ああ、けがらわしい。(太宰治「清貧譚」)
これに対して、隣人の三郎は、「天から貰った自分の実力で米塩の資を得る事は、必ずしも富をむさぼる悪業では無い」と真っ向から反論するのだが、これは、もはや芸術論の争いと言っていい。
自分の信念を守って無名のままに死んでゆく詩人と、世の中に迎合した作品を量産する売れっ子小説家のどちらが正しいか、ということに正解はない。
ただ言えることは「天から貰った自分の実力で米塩の資を得る事は、必ずしも富をむさぼる悪業では無い」ということだろう。
書名:お伽草紙
著者:太宰治
発行:1972/2/21
出版社:新潮文庫

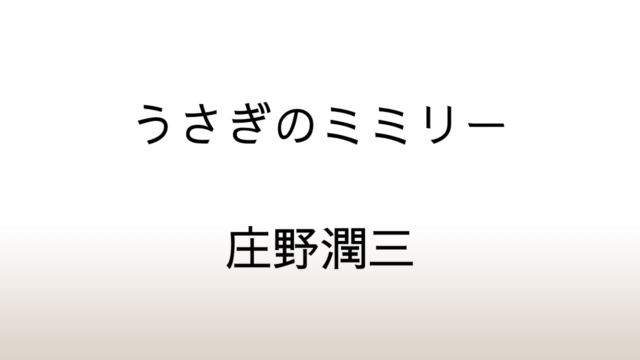
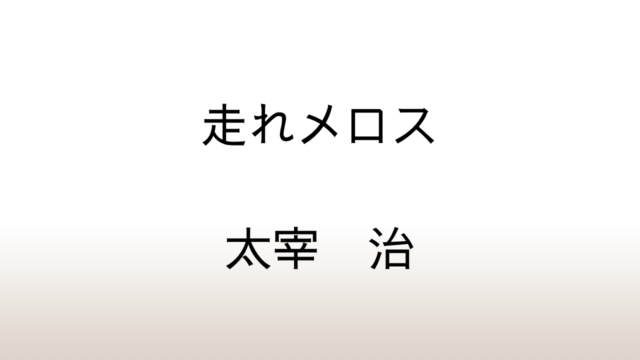
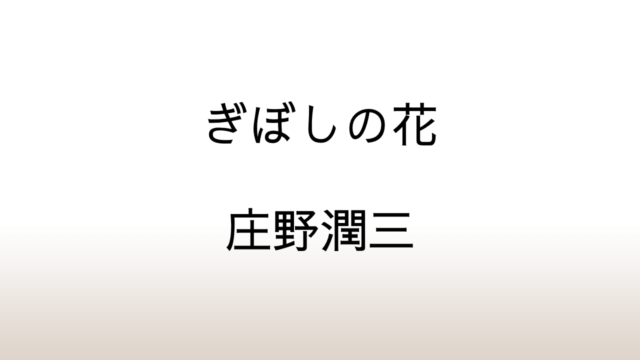
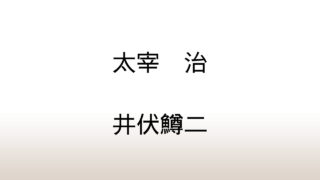
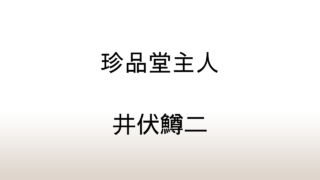
003-150x150.jpg)