「ここが私の東京」は、上京の瞬間に着目した、文化人たちの評伝物語である。
「ここが私の東京」という題名からは、既に地方出身者の悲哀が感じられるが、昭和という時代、日本で成功するということは、東京で成功するということと同義であった。
将来を夢見る若者たちの多くは、「上京」というステップを経た上で、チャレンジングな人生と向き合っていたのである。
本書に登場するのは、東京に人生を賭けた、そんな文化人たちばかりで、漫画家の藤子不二雄Aのほか、ミュージシャンの友部正人や松任谷由実も含まれているが、その他はすべて文学者たちといった構成だ。
上京する若者のエピソードは、それだけでドラマ性を秘めているような気にさせてくれる。
例えば、俳人の石田波郷は、師である五十崎古郷の紹介状を携えて、東京の水原秋櫻子を訪ねるが、昭和恐慌の中、まともな食いぶちも見つからず、浮浪者収容施設で働きながら、「ティータイム茶をのみに行く雷の下」などといった、和製英語を使ったモダンな俳句を作り続けた。
1958年に上京した富岡多恵子は、翌59年に池田満寿夫と出会い、一夜のうちに恋に似た状態に落ちて同棲生活に入ったが、激動の1960年代を二人で迎えて間もなく、池田のブレイクを呼び込み、あたかも「ミューズ」のごとき存在となったという。
地方出身者の成功の道のりには、必ず東京があった。
著者(岡崎武志)もまた、一人の地方出身者だったからこそ、こんな発想が生まれたのだろうか。
成功しなかった東京物語
「柳荘」は、高校同期の北村巌がひと足先に上京し、住んでいたアパートで新井薬師近くにあった。ここは「函館時代の仲間や後輩たちのたまり場になっていて、昼夜なくそこに集まっては議論を闘わせたり、デモ帰りの格好の寝床になっていた。その頃、近くのブロードウェイの明屋書店でアルバイトをしていた泰志も、ちょくちょく顔を出し始めるようになった」という。(佐藤泰志 報われぬ東京)
地元の函館西高校を卒業した佐藤泰志が上京するのは、1970年のことである。
函館で2年浪人していた佐藤は、大学入学時は既に21歳で、最初に暮らした街が、中野区上高田だった。
この「柳荘」の一室を発行所として、佐藤たちは「黙示」というガリ版刷りの同人誌を作るようになり、一年半の間に六号までを発行したという。
五度も芥川賞候補となりながら、商業的に成功を収めることのなかった佐藤にとって、上京物語は決して成功の物語ではなかった。
神戸から上京して成功した同い年の作家・村上春樹の影には、そんな佐藤の呻きが埋もれているような気がする。
庄野文学は石神井公園から始まった
一九五三年九月、家族とともに特急「はと」に乗り上京。妻のほか、もうすぐ六歳になる長女・夏子、二歳の長男・龍也がいた。庄野は三十二歳になっていた。(略)東京駅に着くと、プラットフォームに吉行、安岡、遠藤、島尾といった「第三の新人」のメンバーがニコニコしながら立っていたという。(「庄野潤三 石神井、そして生田」)
庄野潤三というと、神奈川県川崎市多摩区の生田というイメージが強いが、上京したときに暮らしたのは、練馬区南田中町で、最寄り駅は西武池袋線の「石神井公園」だった。
当時、野中に建つ吹きさらしの一軒家で、庄野は、後に名作と呼ばれることになる「ザボンの花」を日本経済新聞に連載する。
石神井の小さな家に住む矢牧一家の物語は、元気のありあまった子供たちが日々起こすできごとや、新しい生活になじみながら近所の人々と交流する母親の姿などが、それらを温かく見守る父親の目線によって綴られている。
この石神井の家で、まだ会社勤めをしていた庄野は、毎朝、通勤前の起き抜けに、妻と綴ったノートを元手に、日課として新聞連載一回分である三枚の原稿を書き上げたという。
やがて、庄野家の物語は、生田の丘の上へと舞台を移し、「夕べの雲」を始めとする数々の名作をものにした。
彼らにとって、上京はひとつのスタートであり、多くの物語は東京から生まれたらしい。
東京に着目した評伝シリーズには、今後も期待をしたいと思う。
書名:ここが私の東京
著者:岡崎武志
発行:2016/4/15
出版社:扶桑社

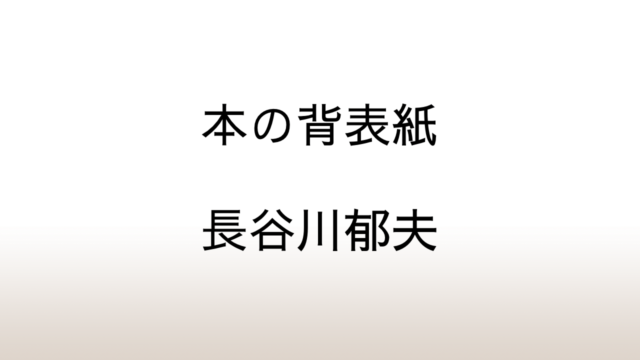

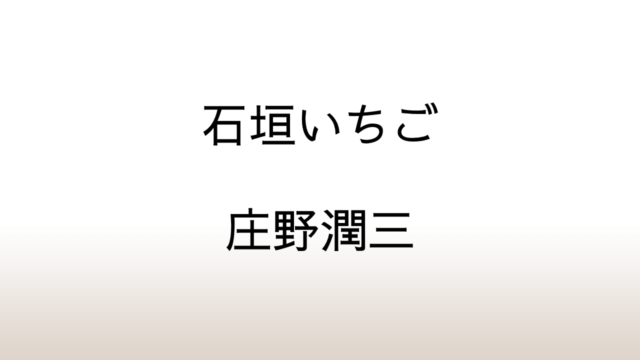
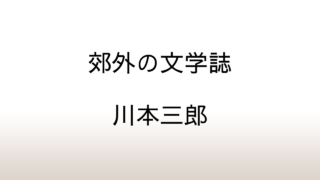
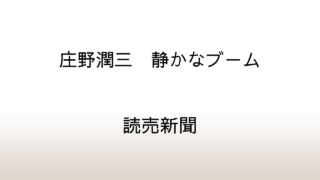
003-150x150.jpg)




