村上春樹「ノルウェイの森」読了。
本作「ノルウェイの森」は、1987年(昭和62年)9月に講談社から刊行された長篇小説である。
この年、著者は38歳だった。
「死」を描きながらにして、生きている者を描く
本作『ノルウェイの森』は、「セックス(性行為)」と「死(自殺)」についての物語である。
当時、単行本の帯には「待望の書下ろし・長篇九〇〇枚、限りのない喪失と再生、今いちばん激しい一〇〇パーセントの恋愛小説!!(上巻)」「新しい世界に挑む・書下ろし長篇、激しくて、物静かで、哀しい、一〇〇パーセントの恋愛小説!!(下巻)」というキャッチフレーズが記されていたが、「恋愛小説」と呼ぶには、あまりに露骨な(「気持ち悪い」とさえ言われる)表現(性描写)が多く、驚いた読者も少なくなかったらしい。
僕はペニスをいちばん奥まで入れて、そのまま動かさずにじっとして、彼女を長いあいだ抱きしめていた。そして彼女が落ちつきを見せるとゆっくり動かし、長い時間をかけて射精した。(村上春樹「ノルウェイの森」)
主人公(ワタナベ・ノボル)が、いろいろな女の子とセックスをする場面にばかり気を取られると、『ノルウェイの森』という小説は、いったい何を言いたいのだ? という迷宮に迷い込んでしまうかもしれない(「意味不明」という読後感)。
何を言いたいのかといえば、『ノルウェイの森』は、セックスと死について伝えたかったのだということになるが、「セックス(性行為)」を、生きていることのシンボリックな行為として変換すると、この小説は「生と死についての物語」として読むことができる。
生きていることと死んでしまったことについての物語。
おそらく、それが、この『ノルウェイの森』という小説の、基本的なプロットである。
最初に死んだのは、高校時代の親友(キズキ)だった。
彼はその夜、自宅のガレージの中で死んだ。N360の排気パイプにゴム・ホースをつないで、窓のすきまをガム・テープで目ばりしてからエンジンをふかせたのだ。死ぬまでにどれくらいの時間がかかったのか、僕にはわからない。(村上春樹「ノルウェイの森」)
キズキの死は、主人公に大きな教訓を残す。
死は生の対極としてではなく、その一部として存在している。(村上春樹「ノルウェイの森」)
『ノルウェイの森』という小説が、本質的に伝えたかったメッセージが、ここにある。
つまり、『ノルウェイの森』は、「親しい者の死」を抱えたままで生きている人間の物語なのである。
様々な「死」が、現在は37歳になった主人公の心に留まっている。
例えば、たった一度しか会うことなく(エウリピデス)、病気で亡くなった緑(小林緑)の父親の死。
僕は彼がキウリを噛むときのポリ、ポリという小さな音を今でもよく覚えている。人の死というものは小さな奇妙な思い出をあとに残していくものだ、と。(村上春樹「ノルウェイの森」)
あるいは、結婚後に自殺した年上の女性(ハツミさん)の死。
ハツミさんは──多くの僕の知りあいがそうしたように──人生のある段階が来ると、ふと思いついたみたいに自らの生命を絶った。彼女は永沢さんがドイツに行ってしまった二年後に剃刀で手首を切った。(村上春樹「ノルウェイの森」)
そして、本作で最大の悲劇となった最愛の恋人(直子)の死。
「淋しい葬式でしたね」と僕は言った。「すごくひっそりとして、人も少なくて。家の人は僕が直子の死んだことをどうして知ったのかって、そればかり気にしていて。きっとまわりの人に自殺だってわかるのが嫌だったんですね。本当はお葬式なんて行くべきじゃなかったんですよ」(村上春樹「ノルウェイの森」)
直子の死は、「尊いものの喪失」という意味において、ハツミさんの死と通じるものがある。
尊いからこそ失われてしまったのだ、直子も、ハツミさんも、あるいはキズキさえも(逆に言うと「尊いものの喪失」の象徴として、キズキやハツミさん、直子の自殺があるのかもしれないが)。
多くの死が、主人公の中に留まっているからこそ、主人公は、この物語を書かなければならなかった(生きている者の資格として)。
僕は顔を上げて北海の上空に浮かんだ暗い雲を眺め、自分がこれまでの人生の過程で失ってきた多くのもののことを考えた。失われた時間、死にあるいは去っていった人々、もう戻ることのない想い。(村上春樹「ノルウェイの森」)
主人公の言葉を借りると、この物語は、「失われた時間、死にあるいは去っていった人々、もう戻ることのない想い」についての物語である。
同時に、それは「今も生きている人々」を書くことでもある。
なぜなら、「死」は生きている者の中にこそ留まっているのであり、「死」を描くことは、同時に、生きている者を描くことでもあるからだ。
「死」を描きながらにして、生きている者のことを描く(それが、つまり、主人公のワタナベ君だ)。
そして、生きている者を象徴する行為として描かれていたのが、数々の「セックス(性行為)」だったのだろう。
死者に捧げられる言葉は、生きることへの決意だった
本作『ノルウェイの森』でセックス(性行為)は、生きている者を象徴する行為として読むことができる。
自殺する直前、直子は、レイコさんに、ワタナベ君とのセックスの思い出を語っている(生涯でたった一度だけのセックスの思い出)。
「それから急にあなたの話を直子が始めたの。あなたとのセックスの話よ。それもものすごくくわしく話すの。どんな風に服を脱がされて、どんな風に体を触られて、自分がどんな風に濡れて、どんな風に入れられて、それがどれくらい素敵だったかっていうようなことをまあ実に克明に私にしゃべるわけ」(村上春樹「ノルウェイの森」)
ワタナベ君とのセックスの思い出は、おそらくは「直子が生きていた証」として伝えられたものだ。
直子が自殺した後で、バツイチの中年女性(レイコさん)と、主人公はセックスをする。
「ねえ、ワタナベ君、私とあれやろうよ」と弾き終ったあとでレイコさんが小さな声で言った。「不思議ですね」と僕は言った。「僕も同じことを考えてたんです」(村上春樹「ノルウェイの森」)
なぜ、レイコさんは、ワタナベ君と寝たのか?
唐突とも思える二人の性行為は、療養所(阿美寮)から抜け出したレイコさんが、現実に生きていることを確認するための神聖な行為だったのだ。
『ノルウェイの森』における性行為は、欲望の処理という以上に(あるいは、愛情の証という以上に)、「生きていることの証明」を意味する重要なメタファーとして読むべきなのである。
そう考えると、この物語で最も生命力に溢れているのは、70人以上の女性と性交した伝説を持つ先輩(永沢さん)と、想像力豊かにエッチな話をするガールフレンド(小林緑)の二人だろう。
「俺とワタナベの似ているところはね、自分のことを他人に理解してほしいと思っていないところなんだ」と永沢さんが言った。(村上春樹「ノルウェイの森」)
かつて、直子は、主人公(ワタナベ君)に「井戸」の話をしたことがある(「それは本当に──本当に深いのよ」)。
「でも大丈夫よ、あなたは。あなたは何も心配することはないの。あなたは闇夜に盲滅法にこのへんを歩きまわったって絶対に井戸には落ちないの。そしてこうしてあなたにくっついている限り、私も井戸には落ちないの」(村上春樹「ノルウェイの森」)
「井戸」とは、つまり、人生の「落とし穴」のことだろう。
人生の「落とし穴」とは、山中にある療養施設(阿美寮)であり、突然の「死(自殺)」である。
井戸に落ちるか落ちないかという境界線上で、人は、長い人生を渡り歩いているのだ。
京都の阿美寮(直子の暮らしている療養施設)から東京へ戻った主人公は、しばらく街の光景になじむことができない(「いったいこれらの光景はみんな何を意味しているのだろう」)。
それは、直子の暮らす阿美寮が、「向こう側の世界」であることを暗示している(つまり「井戸の中」だ)。
どうしてかはわからないけれど、この部屋の中で横になっていると、これまであまり思いだしたことのない昔の出来事や情景が次々に頭に浮んできた。あるものは楽しく、あるものは少し哀しかった。(村上春樹「ノルウェイの森」)
あるいは、阿美寮は、主人公の内面(潜在意識下)という機能をも、併せ持っていたのかもしれない。
「向こう側の世界」に引き付けられた主人公を「こちら側の世界」へ引き戻すのが、たくましい生命力を持つ小林緑だった(「でも私、ポルノ映画って大好きなの」)。
緑と二人でウィンドウ・ショッピングをしながら歩いていると、さっきまでに比べて街の光景はそれほど不自然には感じられなくなってきた。「君に会ったおかげで少しこの世界に馴染んだような気がする」(村上春樹「ノルウェイの森」)
恋愛小説という形を取りつつ、『ノルウェイの森』もまた、『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』と同じように、「壁の中の世界」を描いていたのかもしれない(それが阿美寮だった)。
ただし、『ノルウェイの森』は、あくまでも「こちら側の世界」で生き続けていくことの物語である。
直子は死を含んだままそこで生き続けていた。そして彼女は僕にこう言った。「大丈夫よ、ワタナベ君、それはただの死よ。気にしないで」と。(村上春樹「ノルウェイの森」)
「我々は生きることによって同時に死を育んでいるのだ」とは、キズキが死んだときに、主人公が学んだ教訓の一つだった(「死は生の対極にあるのではなく、我々の生のうちに潜んでいるのだ」)。
死者が生きている者の中に留まっている(我々の生のうちに潜んでいる)と考えたとき、死者は、生きている者の分身としての役割を果たすのかもしれない。
17歳で死んだキズキも、21歳で死んだ直子も、彼らは、永遠に主人公の一部として、主人公の中に留まり続ける(潜み続ける)からだ。
彼らは、主人公がとうに失ったアドレセンスの象徴でもある。
僕にとってキズキという男の存在はいったい何だったんだろうと考えてみた。でもその答を見つけることはできなかった。僕にわかるのはキズキの死によって僕のアドレセンスとでも呼ぶべき機能の一部が永遠に損なわれてしまったらしいということだけだった。(村上春樹「ノルウェイの森」)
誰かが死ぬたびに、主人公は、青春の喪失を思い出している。
そんな圧倒的な夕暮の中で、僕は急にハツミさんのことを思いだした。そしてそのとき彼女がもたらした心の震えがいったい何であったかを理解した。それは充たされることのなかった、そしてこれからも永遠に充たされることのないであろう少年期の憧憬のようなものであったのだ。(村上春樹「ノルウェイの森」)
この物語は「失われた時間、死にあるいは去っていった人々、もう戻ることのない想い」についての物語だったが、あるいは、「失われた時間、死にあるいは去っていった人々、もう戻ることのない想い」を象徴するものが、「青春」という言葉だったのかもしれない。
つまり、この小説は、失われた青春に捧げられる鎮魂歌だったのだ(エピグラフ「多くの祭り(フェト)のために」は、「多くの若者たちの失われた青春のために」と読むことができる)。
それは、単行本だけに収録された「あとがき」からも明らかだ。
この小説は僕の死んでしまった何人かの友人と、生きつづけている何人かの友人に捧げられる。(村上春樹「ノルウェイの森」あとがき)
『村上春樹全作品1979-1989(第6巻)』の「自作を語る」の中にも、同様の表現がある。
この話は基本的にカジュアルティーズについての話なのだ。それは僕のまわりで死んでいった、あるいは失われていったすくなからざるカジュアルティーズについての話であり、あるいは僕自身の中で死んで失われていったすくなからざるカジュアルティーズについての話である。(村上春樹「100パーセント・リアリズムへの挑戦」)
「僕がここで本当に描きたかったのは恋愛の姿ではなく、むしろそのカジュアルティーズの姿であり、そのカジュアルティーズのあとに残って存続していかなくてはならない人々の、あるいは物事の姿である」という文章は、つまり、「主人公は、死んだ人々を描くことによって、生きている自分を描いた」という理解へとつながっていく。
おいキズキ、と僕は思った。お前とちがって俺は生きると決めたし、それも俺なりにきちんと生きると決めたんだ。お前だってきっと辛かっただろうけど、俺だって辛いんだ」(村上春樹「ノルウェイの森」)
そして、死者に捧げられる言葉は、常に、生きることへの決意である。
僕はレイコさんの目を見た。彼女は泣いていた。僕は思わず彼女に口づけした。まわりを通りすぎる人たちは僕たちのことをじろじろと見ていたけれど、僕にはもうそんなことは気にならなかった。我々は生きていたし、生きつづけることだけを考えなくてはならなかったのだ。(村上春樹「ノルウェイの森」)
本作『ノルウェイの森』は、青春を失った後もなお生きることの覚悟を描いた、ひとつの青春小説である。
生き続けていくことの覚悟を書くために、主人公は、多くの死(自殺)を描き、セックス(性行為)を描いたのだ。
青春の多くは、主人公から失われてしまったけれど、その一部は、「死」という形を取って、主人公の中に留まり続けている。
突撃隊のくれた蛍は、青春の光だ(短篇小説「蛍」からの発展)。
瓶の底で蛍はかすかに光っていた。しかしその光はあまりにも弱く、その色はあまりにも淡かった。(村上春樹「ノルウェイの森」)
蛍の光は、ジェイ・ギャツビイが毎夜見守っていた「対岸の小さな光」と同じ輝きを放っている(スコット・F・フィッツジェラルド『グレート・ギャツビー』)。
ギャツビイが見守っていた「対岸の小さな光」もまた、彼にとっての青春の日の輝きだったからだ(かつての恋人デイズィが暮らす家の明かりだった)。
『ノルウェイの森』では、村上春樹の小説らしく、多くの外国文学が、作品に深みを与えている。
レイコさんは僕が読んでいた本に目をとめて何を読んでいるのかと訊いた。トーマス・マンの「魔の山」だと僕は言った。「なんでこんなところにわざわざそんな本持ってくるのよ」とレイコさんはあきれたように言った。(村上春樹「ノルウェイの森」)
トーマス・マンの『魔の山』は、山の上にあるサナトリウムを訪ねる物語だから、京都の山中にある療養施設(阿美寮)を訪れた主人公が読んでいる本としては、あまりに相似性が強すぎるが、作中アイテムがストーリーにコミットしてくるのは、村上文学における常套手段だと言っていい(そして、そこに村上文学の魅力がある)。
あるいは、サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』。
「あなたって何かこう不思議なしゃべり方するわねえ」と彼女は言った。「あの『ライ麦畑』の男の子の真似してるわけじゃないわよね」(村上春樹「ノルウェイの森」)
『ライ麦畑』の主人公(ホールデン・コールフィールド)の姿は、ワタナベ君よりも、むしろ、緑に投影されていると考えたい。
「そのとき思ったわ、私。こいつらみんなインチキだって」(村上春樹「ノルウェイの森」)
現代社会の欺瞞を糾弾する緑の言葉は、あるいは、ホールデン・コールフィールドにインスパイアされたものではなかったか(「私が赤い帽子をかぶってたら、道で会っても声をかけずにさっさと逃げればいいのよ」)。
そして、過去の村上文学作品からの引用も、村上春樹の長篇小説では、定番となりつつある手法だった(『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』に続く)。
「さっき一人でいるときにね、急にいろんな昔のこと思い出してたんだ」と僕は言った。「昔キズキと二人で君を見舞いに行ったときのことを覚えてる? 海岸の病院に。高校二年の夏だっけな」(村上春樹「ノルウェイの森」)
阿美寮で思い出した懐かしい高校時代の記憶は、やはり、青春の日の輝きだったのだろうか(短篇小説「めくらやなぎと、眠る女」からの引用)。
最後に、主人公は「生きている」緑の元へと戻っていく。
「あなた、今どこにいるの?」と彼女は静かな声で言った。僕は今どこにいるのだ? 僕は受話器を持ったまま顔を上げ、電話ボックスのまわりをぐるりと見まわしてみた。僕は今どこにいるのだ?(村上春樹「ノルウェイの森」)
彼は、今、「こちら側」でも「向こう側」でもない世界の境界線上にいる(「僕はどこでもない場所のまん中から緑を呼びつづけていた」)。
そして、ワタナベ君が「こちら側」の世界で生き続けて来たことを証明するのが、冒頭に登場する37歳の主人公の姿だった。
飛行機が完全にストップして、人々がシートベルトを外し、物入れの中からバッグやら上着やらをとりだし始めるまで、僕はずっとあの草原の中にいた。僕は草の匂いをかぎ、肌に風を感じ、鳥の声を聴いた。それは一九六九年の秋で、僕はもうすぐ二十歳になろうとしていた。(村上春樹「ノルウェイの森」)
「1969年の草原」は、主人公(ワタナベ君)の心の中にある(おそらくは、潜在意識下に潜んで、死んだキズキや直子たちと一緒に)。
我々の人生において「生きる」ということは、つまり「生き残る」ということなのだ。
書名:ノルウェイの森
著者:村上春樹
発行:1991/04/15
出版社:新潮文庫


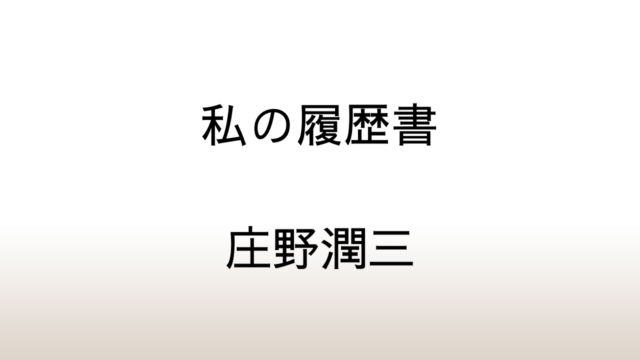
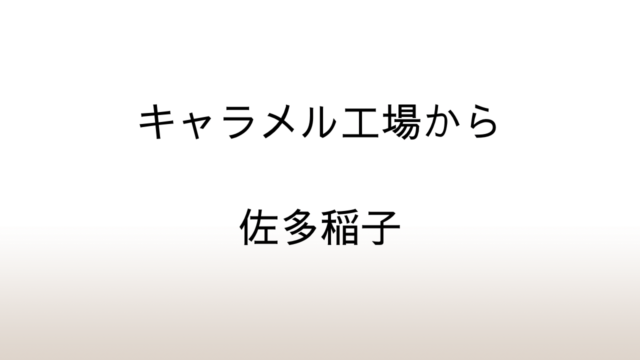
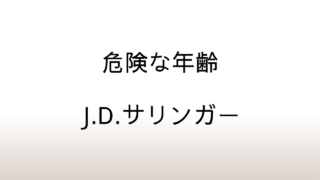
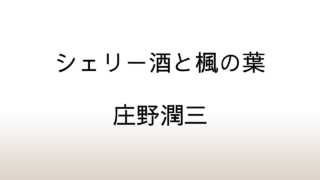
003-150x150.jpg)




