小沼丹「村のエトランジェ」読了。
本作「村のエトランジェ」は、1954年(昭和29年)1月『文藝』に発表された短編小説である。
この年、著者は36歳だった。
作品集としては、1954年(昭和29年)11月にみすず書房から刊行された『村のエトランジェ』に収録されている。
三角関係のもつれから発生した殺人事件か?
久世光彦『ひと恋しくて』に「村のエトランジェ」が出てくる。
ちょうどそのころ、小沢書店から五巻の『小沼丹作品集』が出た。この人は、私が落ち着きをなくしていた間、ずっと書いていたのだ。昭和五十年代の『藁屋根』や『沈丁花』が淡々と澄んでいて私は少し泣いた。『村のエトランジェ』が懐かしくて、またちょっと泣いた。そのうち、表紙の<小沼丹>という字を眺めているうちに涙が止まらなくなった。この人恋しさに泣いたのではない。自分が歩いてきた五十数年の道が、一瞬白々と見えたような気がしたのである。(久世光彦『ひと恋しくて』)
昭和20年代の終わり頃に文学青年だった久世光彦は、当時台頭してきた「第三の新人」の中でも「私はなんと言っても小沼丹だった」らしい。
小説家20人ぐらいの住所を『文学年鑑』で調べて年賀状を出したところ、返事が来たのは、小沼丹と川端康成の二人だけだった。
「村のエトランジェ」は、そのころに初めて読んだ小沼丹の作品だったのだ。
最初に気が付くことは、ストーリー構成上の巧みな工夫である。
この物語は、<詩人>と呼ばれる一人の若者が、大雨で増水した川で溺死する場面から始まるが、それは「戦争の終った年の十月初めのこと」だった。
助役の家の離れに東京から「凄い女」が疎開してきたのは、「戦争の終る少し前」である。
中学一年生だった<僕>と<センベイ>は、この都会的な女性たちに大きな好奇心を抱き、二人に内緒で<カプリ>と<睡人形>という名前を付けて呼んだ。
日傘を差し、二人共青い洋服を着ていた。よく肖ているように見えた。しかし、年上の方は少しほっそりしていたし、妹の方は幾らか肉附が良かった。(本作「村のエトランジェ」)
<僕>が、東京の父の許を離れて、この村の伯父の家に疎開してきたのは、彼女たちよりも少し先の「六月」のことだった(時系列でいうと、物語はここから始まっている)。
少年たちは、当初、姉のカプリと詩人が二人きりでいるところを発見するが、やがて、詩人は、妹の睡人形と一緒にいることの方が多くなる。
詩人はいつも、黄色い麦藁帽子を被って歩いていた。詩人が歩く度に、黄色い麦藁帽子は上ったり下ったりした。と云うのは、詩人は跛だったから。(本作「村のエトランジェ」)
そして、戦争が終わり、彼らが間もなく東京へ帰るというあの日、事故は起きた。
この小説は、姉のカプリが、詩人を濁流の中へ突き落す瞬間を目撃した、一人の少年の回想の物語である。
若い男女三人の三角関係の物語
この作品は、一人の少年の目を通して描かれた若い男女三人の三角関係の物語である。
姉の白い手が伸びた。何をするのだろう、と思ったとき、その白い手は男の肩を突いたのである。男は奇妙な動作をした。それは、何か眼に見えない綱にでも掴まろうとしているかのように見えた。(本作「村のエトランジェ」)
しかし、事件を目撃した少年たちは、警察の事情聴取に「詩人は足を滑らせて川に落ちた」と説明する。
少年たちは、嘘をついたのである。
この物語の最大のテーマは、なぜ、彼らは嘘をつき、姉のカプリをかばったのか?というところにあるだろう。
二人の少年たちは、三人の若者と交流しながら、詩人の心が姉から妹へと移っていったことを暗に理解している。
彼らの中には、詩人に失恋した(かもしれない)姉への同情の気持ち(共感)があったのかもしれない。
少年たちは、姉の奏でるマンドリンの音色が好きだった。
「──いま歌ってるのは、何て云う歌だや?」姉はちょっと黙り込んだ。「──ああ、これ?」それからもう一度口誦むと、笑った。「カプリの島って云うのよ。教えてあげましょうか?」(本作「村のエトランジェ」)
姉を「カプリ」と呼ぶ彼らの約束は、このときに付けられたものであるが、もしかすると、この辺りから、少年たちの心は姉に寄り添っていたのかもしれない。
本作「村のエトランジェ」は、小沼丹の文壇デビュー作として高い評価を得た作品である。
昭和二十八年夏の終り、突然、電話がかかってきた。「この夏休みをかけて、小説が出来た。ようやく、出来たよ」明るく弾んで、ちから強いひびきがあった。これは傑作にちがいない、と咄嗟に信じた。(略)それが「村のエトランジェ」だった。(結城信一「唯一度の電話」)
ちなみに、エトランゼとは異邦人という意味のフランス語だそうである。
これも、戦争によって都会を追われた女性たちの悲劇の物語なのだろうか。
作品名:村のエトランジェ
著者:小沼丹
書名:村のエトランジェ
発行:2009/07/10
出版社:講談社文芸文庫

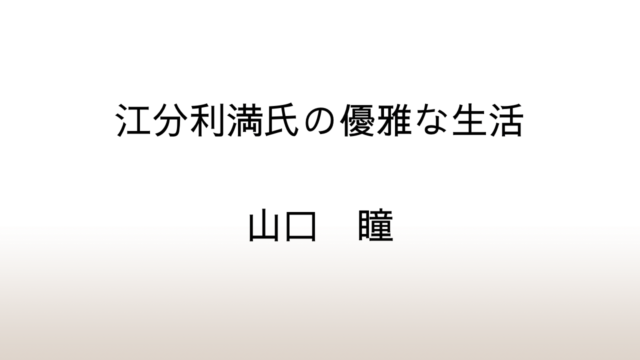
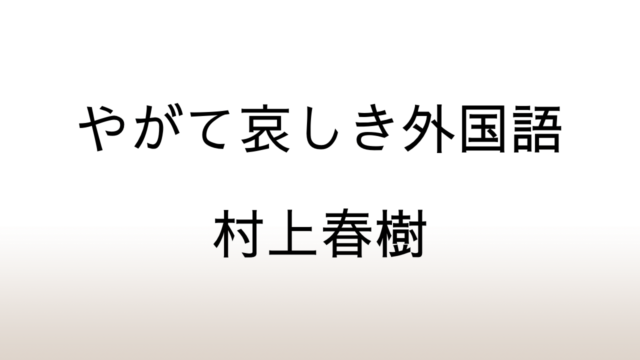

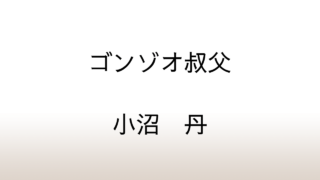
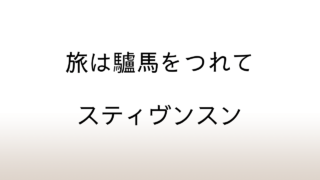
003-150x150.jpg)




