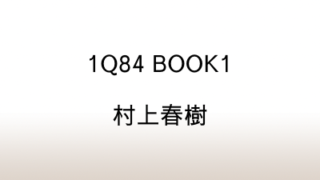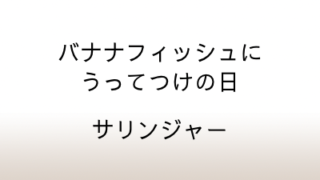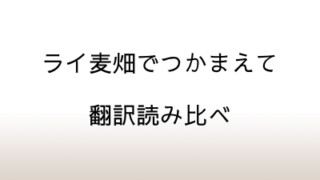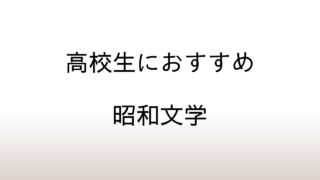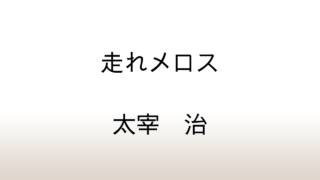太宰治「女生徒」読了。
本作「女生徒」は、1939年(昭和14年)4月『文學界』に発表された短編小説である。
この年、著者は30歳だった。
作品集では、1939年(昭和14年)7月に砂子屋書房から刊行された『女生徒』に収録されている。
日本という国が抱えた自己矛盾
本作「女生徒」は、戦前の文学女子が、父親を亡くした悲しみの中で綴った日記という体裁で書かれている。
出来事を記録しているというよりも、朝から夜に至る少女の心理描写が、細かな独白形式で綴られていることが、大きな特徴だろう。
そして、この独白の中で、少女の内的心理は、めまぐるしい変化を見せる。
さっき、好きだと思ったものが、今は嫌いだと思ったり、肯定と否定が彼女自身の中でさえ一定しない。
思春期に特有と思われるこの微妙な心理描写が、まずは、この物語の大きなテーマになっていると見ていいだろう。
しかし、主人公である<私>の真骨頂は、現状を否定する言葉の中にある。
ああ、汚い、汚い。女は、いやだ。自分が女だけに、女の中にある不潔さが、よくわかって、歯ぎしりするほど、嫌だ。(太宰治「女生徒」)
こうした自己否定は、もちろん、自己愛と表裏一体のものである。
愛憎が同時に存在し得る自己矛盾こそが、本作「女生徒」が描き出す、大きなテーマとなっているのだ。
作者の太宰治は、若い女性からのファンレターを素材として、この小説を書いたと伝えられている。
おそらく、太宰は、好きと嫌いの矛盾に満ちた手紙の中に、若い女性に特有の美と醜を同時に感じただろう。
そして、世代や性別といったフィルターを越えたところに、人間としての本質的なものを発見したはずである。
この作品は、女生徒を主人公として描くことによって、若い女性の共感を呼び起こす作品となっているが、根底にあるのは、人間としての自己矛盾であるからだ。
学校の修身を絶対に守っていると、その人はばかをみる。変人といわれる。出世しないで、いつでも貧乏だ。嘘をつかない人なんて、あるかしら。あったら、その人は、永遠に敗北者だ。(太宰治「女生徒」)
若い女性を主人公にしているとは言え、作者の正義感は顕著だ。
内面に抱えた自己矛盾は、女生徒一人のものではなく、すべての日本人、もっと言えば、日本という国そのものに対して向けて発せられていたのではないだろうか。
矛盾を抱えて生きる人間の自己肯定
彼女の自己矛盾は、同時に、作者自身の自己矛盾でもある。
変に笑ったり、先生のくせに恥ずかしがったり、何しろサッパリしないのには、ゲッとなりそうだ。「死んだ妹を、思い出します」なんて、やりきれない。人は、いい人なんだろうけれど、ゼスチュアが多すぎる。(太宰治「女生徒」)
ジェスチャーやポーズの多すぎる<伊藤先生>は、作者が憎んだすべての人々であり、同時に、作者自身の姿でもあっただろう。
「女生徒」には、作者・太宰治を思い出させる場面が多い。
なぜ、このごろの自分が、いけないのか。どうして、こんなに不安なのだろう。いつでも、何かにおびえている。この間も、誰かに言われた。「あなたは、だんだん俗っぽくなるのね」そうかもしれない。私は、たしかに、いけなくなった。(太宰治「女生徒」)
思うに、本作「女生徒」は、女学生の姿を借りた、作者・太宰治の自己開示の小説である。
太宰は、若い女性の手紙の中に共感するものを得たからこそ、このような小説を書こうと思い立ったのだ。
もちろん、作品の中の太宰は、あざといまでに女学生に姿を変えて登場しているから、この主人公は、もしかすると作者自身ではないかしら、などと怪しまれることもない。
そんな心配をする必要がないくらい、本作「女生徒」の中の<私>は、若い女性らしさに満ち溢れている。
しかし、この作品が一番に伝えたかったもの、それは矛盾を抱えて生きる人間の自己肯定である。
すべての人は、自己矛盾に満ちており、自分の中に美と醜の両面を抱えて生きていくのだ。
そんな普遍性こそが、この小説が長く読み続けられる背景となっているのではないだろうか。
作品名:女生徒
著者:太宰治
書名:教科書で読む名作 走れメロス・富嶽百景ほか
発行:2017/04/10
出版社:ちくま文庫
(2024/07/27 06:24:04時点 Amazon調べ-詳細)

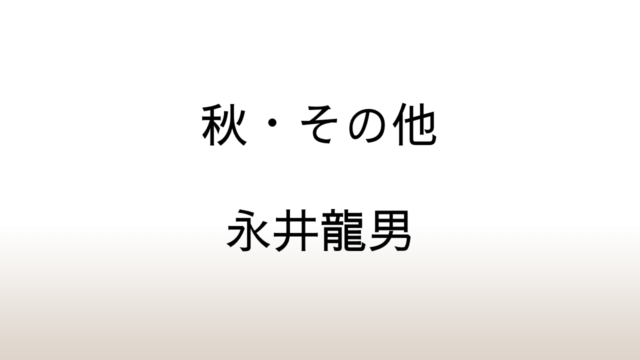
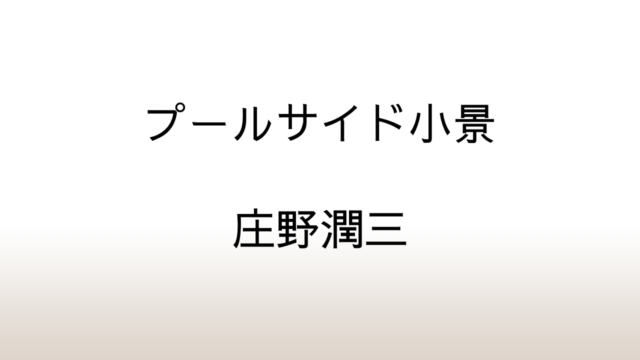
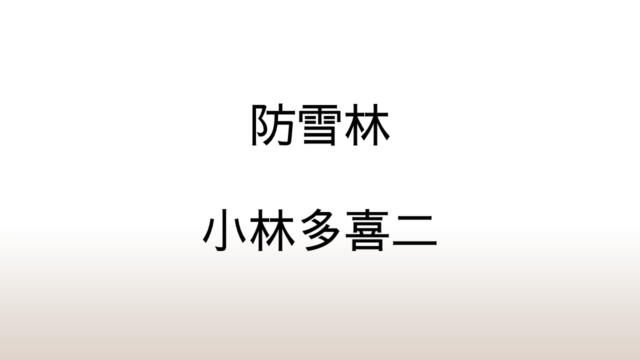
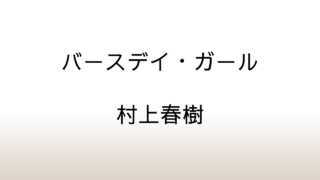
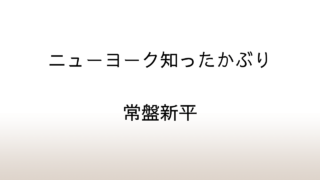
003-150x150.jpg)