花森安治「一銭五厘の旗」読了。
本作「一銭五厘の旗」は、1971年(昭和46年)に刊行された自選エッセイ集である。
この年、著者は60歳だった。
1972年(昭和47年)、第23回読売文学賞随筆・紀行賞受賞。
日本を良くするための提案
松浦弥太郎が編集長をしていた頃の『暮しの手帖』には、自分の暮らしを良くするための提案がたくさんあった(ブルックス・ブラザーズとかマーガレット・ハウエルとか)。
今回『一銭五厘の旗』を読んで感じたことは、花森安治の文章には、社会を良くするための提案がたくさんあるということである。
例えば、1962年(昭和36年)に書かれた「酒とはなにか」というエッセイでは、酒を飲んで酔っ払って人を殺しても無罪放免になる日本という国はおかしい、という内容のものだ。
恨まれるようなこと、殺されるようなことはなにひとつしなくて、しかも、人は殺されることがある。ひとつは、戦争である。ひとつは、酒である。(花森安治「酒とはなにか」)
著者は、1956年(昭和31年)の京都地裁の判決を引用して、自分の意思で酒を飲んで酔った人間が、心神喪失で罪に問われない社会はおかしいと主張する。
酒を飲むのは個人の問題だが、酔っぱらいに寛容であることは社会の問題である。
いま、私たちに必要なものは、車内で泥酔して乱暴を働く人間に立ちむかってゆく勇気ではない。酔っている人間を、特権者扱いしない勇気である。酒は麻薬でも毒薬でもない。ふつうの飲みものの一つだからである。(花森安治「酒とはなにか」)
主張が明確で、論理的であるというのが、花森安治が書くエッセイの特徴の一つだろう。
書名の『一銭五厘の旗』は、1970年(昭和45年)に書かれた「見よぼくら一銭五厘の旗」から取られている。
戦争中、郵便葉書は一枚「一銭五厘」だった。
日本の若者たちは、一銭五厘の葉書一枚で軍隊に徴用されたから、軍隊では「貴様らの代りは一銭五厘で来る」と罵倒された。
終戦直後に高揚していた民主主義の空気は冷めて、今また「一銭五厘」の時代が近づいてきているのではないかと、著者は危惧している。
ぼくらの旗はこじき旗だ。ぼろ布端切をつなぎ合せた暮らしの旗だ。ぼくらは家ごとにその旗を物干し台や屋根に立てる。見よ。世界ではじめてのぼくら庶民の旗だ。ぼくら、こんどは後へはひかない。(花森安治「見よぼくら一銭五厘の旗」)
徹底した庶民主義である。
終戦から25年が経過して、それでもまだ戦争が終わっていない。
戦争の日々の怒りが、今もまだ、身体の中で煮えくり返っているかのようだ。
『暮しの手帖』の原点は敗戦後の貧しい暮らし
『暮しの手帖』の「暮し」とは、庶民の暮らしのことである。
花森安治のエッセイには、飾らない庶民の暮らしがある。
リンゴ箱というのは、とにもかくにも木製の箱であった。しかも値だんは二十円か二十五円で、いくらでも果物屋で分けてもらえた。私たちの身辺で一番たやすく手に入る家具のユニットだった。おそらく、あの頃を生きてきた人ならたぶん、このリンゴ箱のいくつかにお世話にならなかった人はいないだろうと思うくらいである。(花森安治「なんにもなかったあの頃」)
『暮しの手帖』第一号(1948年)に掲載された田宮虎彦の「地獄極楽」というエッセイの中にも、理想の暮らしの風景として「家具調度の類いは書籍をミカン箱につまず」という一文が出てくる。
「なんにもなかったあの頃」は、1969年(昭和44年)4月の『暮しの手帖(100号)』に発表された文章だが、花森安治の視点はブレることなく、終戦直後の誰もが辛かった、あの日々にある。
むしろ、敗戦後の貧しい暮らしこそが、戦後に創刊された『暮しの手帖』を支えてきたのだと言っていい。
庶民代表。
みんな忘れても、自分だけは忘れまいという気概が、花森安治に『暮しの手帖』を続けさせた原動力だったのだろうか。
我々が忘れてはいけないものが、この本の中には残されているような気がする。
終戦直後の貧しい暮らしは、未来にまで続く日本人の体験的遺産なのだから。
書名:一銭五厘の旗
著者:花森安治
発行:1971/10/10
出版社:暮しの手帖社

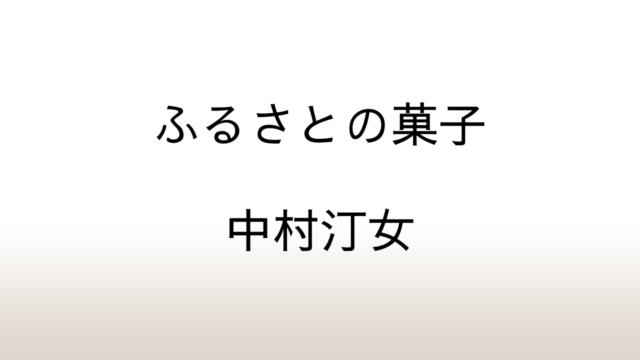

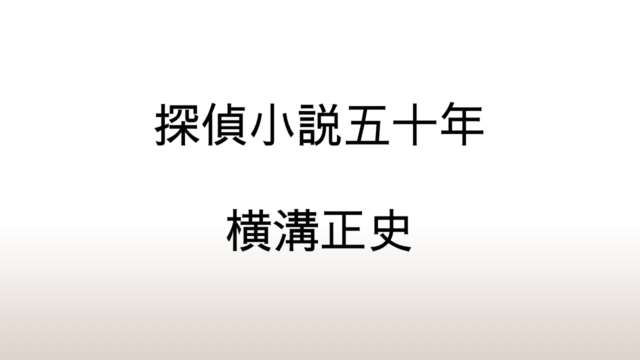


003-150x150.jpg)




