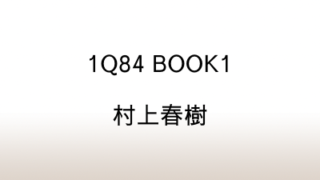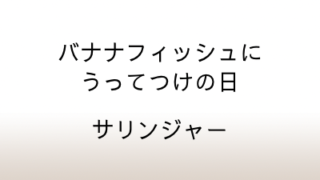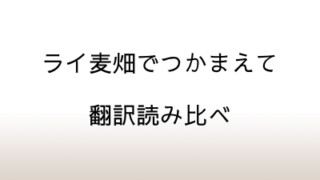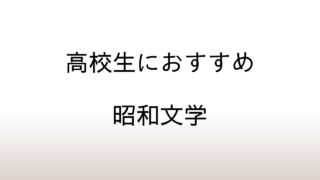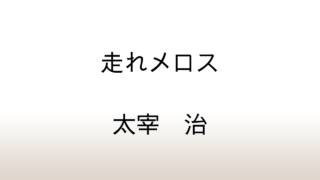レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女(ひと)よ」読了。
本作「さらば愛しき女よ」は、1940年(昭和15年)にクノップフ社から刊行された長篇小説である。
原題は「Farewell, My Lovely」。
この年、著者は52歳だった。
無償の愛の美しさに惹かれた男
果たして、人間は、遠く離れた人間を、8年間も愛し続けることができるものだろうか。
本作「さらば愛しき女よ」のテーマは、人を愛することについて、である(あるいは、愛し続けることについて、かもしれない)。
作者のレイモンド・チャンドラーは、きっと、愛し続けることの力を信じていたのだ。
少なくとも、主人公である私立探偵フィリップ・マーロウは。
「ずいぶん、彼女を愛していたのね」と、アンは静かに言った。「マロイのことよ。六年間手紙をよこさなくても、監獄に一度も面会に行かなくても、彼女を愛している気持は変らなかったんだわ。彼女が賞金をもらって密告したことも赦すつもりだったんだわ。そして、出獄すると、すぐ美しい服を買って、彼女を探しはじめたのに、久しぶりで会ったときの彼女の挨拶は五発のピストルの弾丸だったのね。マロイも彼女のために二人殺しているけれど、最後まで彼女を愛していたんだわ。世の中って、不思議なものね」(レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」清水俊二・訳)
あるいは、それは、男の弱さだったのかもしれない。
しかし、マーロウは、元カノ・ヴェルマを愛する大鹿マロイの純粋な心に惹かれて、稼ぎにならない事件へと深く入り込んでいく。
そういう意味では、マーロウもまた、賢い人間ではなくて、純情な心を持ち続ける少年のような大人だったと言えるだろう。
私は赤い髪に紫色の眼の大男を頭に浮べた。この男はおそらく、私が会ったもっとも美しい心の持主だった。(レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」清水俊二・訳)
僕たちが、この物語に惹かれる理由は、この少年のような大人たちの純粋さにある。
作品タイトルの「さらば愛しき女よ」は、もちろん、大鹿マロイが最愛の女性ヴェルマに捧げる言葉だ。
この邦題は、古風なところまで含めて「さらば愛しき女(ひと)よ」以外にはないと思う。
日本語タイトルが、作品に付加価値を与えているとまで言ったら、言い過ぎになるだろうか。
そのくらいのインパクトが、この題名にはある。
もっとも、大鹿マロイがヴェルマに射殺された今、この別れの言葉を代弁したのは、もしかすると、フィリップ・マーロウだったのかもしれない。
「お前の声をまだ覚えていたよ」と、彼はいった。「八年間、その声が聞きたかったんだ。それに、その赤い髪にも、たまらねえ想い出がある。ほんとうに久しぶりだったなあ」(レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」清水俊二・訳)
マーロウ・シリーズの作品で、マーロウと同じくらいに存在感を持つ登場人物は、決して多くはない。
本作の大鹿マロイは、『長いお別れ』のテリー・レノックスと並んで、マーロウ・シリーズにおける優秀なバイプレイヤーと言えるだろう。
フィリップ・マーロウの小説では、なぜか、男たちが、いい働きをしてくれるのだ(もちろん、マーロウの協力者となったアン・リアードンも、十分に魅力的な女性として描かれているが)。
大鹿マロイの心の美しさに呼応するように描かれているのが、賭博船へ乗り込むマーロウの恐怖心である。
「ぼくは死と失意が怖い」と、私はいった。「暗い海と溺れた人間の顔と眼玉のあとがからっぽのしゃれこうべが怖い。死ぬことと、すべてがむだになること、ブルネットという男に会えないことを怖れる」(レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」清水俊二・訳)
マーロウに、ここまで正直な告白をさせているのは、見返りを求めることのない大鹿マロイの無償の愛だ。
そして、その街で、その言葉は、口に出して言うだけの価値のある言葉だったに違いない。
不器用な男の愛情が、世の中の仕組みを変える
大鹿マロイの無垢な愛情を引き立たせているのは、ベイ・シティという腐敗した社会だ。
賄賂が横行するベイ・シティでは、金が幅を利かせ、自惚れと自己満足が優先される。
「正直に暮したいと思っても、暮せないのさ」と、ヘミングウェイはいった。「それがこの国の病気なんだ。手を汚さなければ、食っていけないんだ。糊のついたシャツを着てスーツケースを提げた連邦警察官が九万人いれば、それで泰平無事だと思ってる奴が大勢いる。そんなわけにはいかないよ。奴らだって、俺たちと同じような立場になるにきまってる。俺はこう考えてるんだ。世の中を、もう一ぺん建てなおさなければ、どうにもならない。道徳的再武装という奴さ。あれをやらなければ、どうにもならないんだ」(レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」清水俊二・訳)
無器用な警察官に「ヘミングウェイ」というあだ名をつけ、社会改革を「道徳的再武装」と呼んでいるあたり、村上春樹への影響が感じられる(特に『ダンス・ダンス・ダンス』)。
それは、ともかくとして、ベイ・シティは、純粋に生きることの難しさを教えてくれる街だった。
大鹿マロイの純粋な愛は、腐敗したベイ・シティへのアンチテーゼであり、マーロウの不器用な生き方も、また、同種のメッセージを持つものだっただろう。
「ベイ・シティだといったな」と彼は一言一言考えるようにいった。「その名は唄のように聞こえる。汚ない浴槽の中の唄のように」(レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」清水俊二・訳)
ベイ・シティが汚いほどに、大鹿マロイとフィリップ・マーロウが、美しく見える仕掛けだ。
そして、それは、現実社会でも殊更に珍しいことではない。
作品の随所でシェイクスピアが引用されているところも、この物語に深みを与えてくれている。
「署長は休職になった。刑事の半数が平巡査に格下げになった。そして、ぼくをモンテシト号に連れてってくれたレッド・ノーガードという立派な男が復職することになった。みんな、市長がやったことなんだ。ボロを出さないように、一時間ごとにズボンを取り替えてるんだ」「そんなことまでいう必要があるの?」「シェイクスピアの筆法さ。ドライヴに行こう。もう一杯ずつ飲んでから」(レイモンド・チャンドラー「さらば愛しき女よ」清水俊二・訳)
魅力的な女性アン・リアードンも、麻薬と暴力でボロボロにされたマーロウを見たときに、「まるで、ハムレットの父親みたいよ!」と叫んでいる(暗殺された国王の幽霊のこと)。
マーロウには、「シェイクスピアの『リチャード三世』に出てくる第二の殺人者のような男だった」と、殺されたリンゼイ・マリオを皮肉る場面もあり、この物語において、シェイクスピアは効果的な小道具として活用されていることが分かる。
そして、大鹿マロイの死と引き換えに、世の中が少しだけ変わった。
もちろん、それが根本的な解決ではないということは、マーロウが、いちばんよく分かっていたはずだ。
「道徳的再武装」には時間がかかるし、人間の欲望を止めることは誰にもできない。
それでも、大鹿マロイの登場と死は、腐敗した社会に投じた一つの石のようなものだったと、僕は思いたい。
大鹿マロイがマーロウの心に火を点け、「道徳的再武装」に火を点けたのである。
本作「さらば愛しき女よ」は、不器用な男の愛情が、世の中の仕組みを変えていくまでの経過を描いた、壮大なハードボイルド・ミステリーである。
大鹿マロイのような人間こそが、本当に人間らしい人間だったのかもしれないな。
書名:さらば愛しき女よ
著者:レイモンド・チャンドラー
訳者:清水俊二
発行:1976/04/30
出版社:ハヤカワ文庫
(2024/07/26 20:35:03時点 Amazon調べ-詳細)

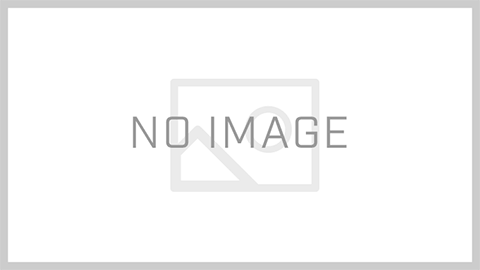
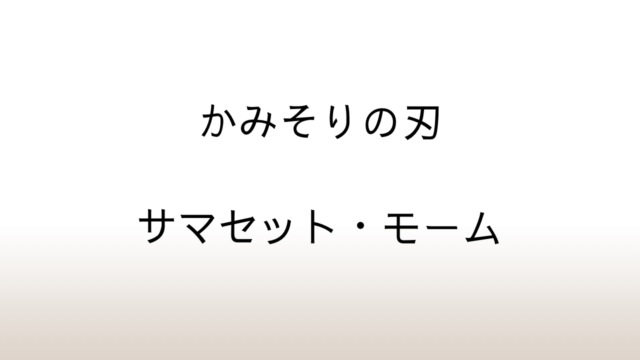
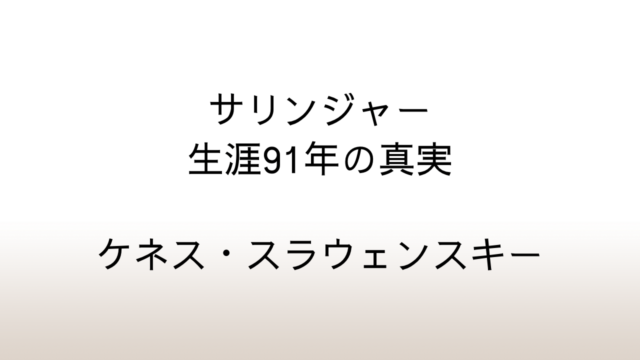
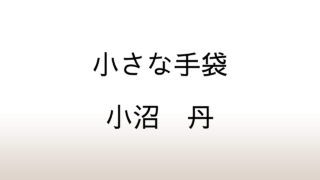
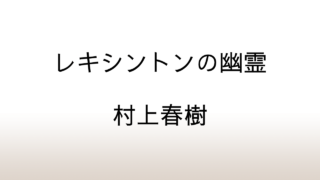
003-150x150.jpg)