小沼丹「珈琲挽き」読了。
本作「珈琲挽き」は、1994年(平成6年)1月にみすず書房から刊行された随筆集である。
この年、著者は76歳だった。
故人の魂を弔う文学
小沼丹の随筆は短い。
素材やテーマも、小説と同じようなものなので、ショートバージョンの小説を読んでいるかのような趣きがある。
最近の流行で言えば、ショート動画のようなものかもしれない。
短いけれども、しっかりと内容があって、小説に負けないくらいの情感が伝わってくる。
小説でも随筆でも、小沼丹の作品から立ち上る情感は、時間の巻き戻しによって得られるものだ。
近況報告のような作品であっても、そこには過去の思い出が介在する。
例えば、盟友の庄野潤三と鰻屋で待ち合わせをする「鰻屋」は、ロンドン滞在時に庄野潤三から届いた手紙の話から始まり、駅のプラットフォームで「──ひとつ、蕎麦でも食ってやろう」と思ったときに、ここがイギリスだったと気づいて「これは早い所帰国した方がいいかもしれない」と考えた話へとつながっていく(『椋鳥日記』にも登場する場面だ)。
「──ひとつ、蕎麦でも食ってやろう」どう云う料簡だったか忘れたが、そう思って、思った途端に茲は英吉利だと気が附いた。軽食堂はあるが、無論、蕎麦なんかある訳が無い。何だか味気無い気分になって、これは早い所帰国した方がいいかもしれない、そのとき、本気でそう考えたのを憶えている。(小沼丹「鰻屋」)
肝心の鰻屋は臨時休業で、昔、井伏鱒二を案内したときにも定休日だったために、面目を失くしたというエピソードも出てくる。
村上菊一郎が登場する「つくしんぼ」も、昔話型のエッセイだ。
念のため、杉菜と土筆の関係を村上さんに訊ねると、──あれは違うものらしいですね、と云う答であった。同席した矢張り仏文学の室さんも、「──杉菜と土筆は別ものだよ」と自信あり気に判定した。(小沼丹「つくしんぼ」)
思い出話が、近況報告みたいに自然の形で語られている。
つまり、追憶の文学ということが、小沼文学の最も基本的な主旋律であることに間違いはない。
追憶の文学において、もっとも定番の物語といえば、死んだ人間の回想である。
小沼丹の趣味として有名なコースター蒐集は、「コップ敷」という作品で詳細に語られている。
村上菊一郎や伊馬春部にもらったコースターの話の後に、「昔よく通った酒場の御粗末なコップ敷が出て来て何だか懐かしかった」という文章から始まるエピソードがある。
マダムは自殺して、その店は疾うに無い。もう二十数年前のことになるかもしれない。そのコップ敷を見たら、マダムの好きだった「遠い遠い昔」と云う唄が不意に甦って、その旋律が暫く耳を離れなかったのを想い出す。(小沼丹「コップ敷」)
「遠い遠い昔」という歌(イギリス民謡の「Long, Long Ago」)が、短い物語の中で効果的なBGMとして生きている。
「蕗の薹」は、死んだ山川さんの思い出を綴ったもの。
それから何年経ったか忘れたが、確か山川さんの奥さんが死んだ翌年だったと思う。久し振りに山川さんが訪ねて来て、「──今日も蕗の薹を貰って帰るよ……」と云った。(小沼丹「蕗の薹」)
「かたかごの花」では、亡くなった甲野夫妻の話が綴られている。
植物好きの知人の甲野さんに会って酒を飲んだとき、その話をしたら、甲野さんは笑って、「──片栗なら、うちにもあります、今度、お頒けしましょう」と云った。(小沼丹「かたかごの花」)
初めて片栗の花を見たのは「或る年の四月、井伏さんのお伴をして、三、四人で仙台の近くの小原温泉に行った」ときのことだった。
小沼丹の作品では頻繁に登場する植木屋の親爺も故人となっている。
上の娘が夏蜜柑の種子を捨てたのは小学生の頃だが、その娘がいまは二人の小学生の男の子の母親になっている。こんな場合は、ことに月並の感想しか浮ばないが、その間に何だかいろんなことがあったと思い出す。植木屋の親爺は去年死んだ。生きていて、夏蜜柑の花が咲いたと知ったら、何と云ったかしらん?(小沼丹「夏蜜柑の花」)
「『塵紙』」には、亡くなった浅見淵が登場している。
もう二十年ぐらい前のことだが、熱海の双柿舎で会があって、帰りに小田原で下車したら、同行の浅見(淵)さんが、川崎長太郎の行く店に案内してやる、と云うので四、五人で随いて行った。(小沼丹「『塵紙』」)
最後の一文に「訂正したいが、浅見さんは既にこの世に亡い」とあるところが、いかにも小沼丹らしい。
文学仲間では、上林暁の思い出もある。
初めて短篇集を出して、昭和二十九年末に中野の「ほととぎす」でその出版記念会があったとき、上林さんも出て下さった。そのとき、息子が学校で教えて貰って、と話をされたが、それでわざわざ出て下さったのかもしれない。(小沼丹「追憶」)
上林暁の自邸を訪ねたときは、井伏鱒二や吉岡達夫も一緒だったらしい。
お酒の思い出を綴った「酒のこと」は、学生時代の友人だった石川の話から始まり、井伏鱒二や谷崎精二の回想へと繋がっていく。
酒は愉快に飲むのが好きだが、偶に深夜独りで飲んでいると、先に逝った遠い昔の仲間が姿を現すことがあって、暫くその連中と話をすることもある。(小沼丹「酒の」こと)
回想の中で生きていると言いたいくらい、小沼丹の話は、昔話へと繋がっていくのだが、この追憶が、小沼文学を支えていることは言うまでもない。
学生時代の友人・矢嶋の思い出は、「『町の踊り場』」という作品に出ている。
学校の親しい友人に矢嶋と云う男がいて、これは秋声の親戚だと聞いていた。親戚だからと云う訳でもなかったろうが、秋声の作品が好きで読んでいたらしい。(小沼丹「『町の踊り場』」)
小沼丹が持っていたのは、改造社版の現代日本文学全集『徳田秋声集』だったが、師の谷崎精二は「──秋声は知性が無いから嫌いです」と言っていたらしい。
余談として、山田順子の『神の火を盗んだ女』を買った話が出てくるが、著者近影を見た井伏さんが「──実物はもっと色気があって良かった」と言う場面がいい。
「日夏先生」にも、学生時代の友人が出てくる。
友人の一人に日夏先生の崇拝者で、卒業すると直ぐ兵隊に取られた男がいた。この友人に阿佐ケ谷で日夏先生に会った次第を手紙に書いてやったら、莫迦に歓んだ返事を寄越した。(略)その后間も無くこの男は戦地へ送られて戦死した。昔の色褪せた記念写真を見ると、この友人は腕組をして、天の一角を睨む恰好で写っている。(小沼丹「日夏先生」)
旧友として忘れられない男として、玉井乾介がいる。
この玉井は大学の頃からの古い友人だが、去年の十二月に何の挨拶も無く死んだ。ちょうどそのとき、此方は入院していて、病床でその報を聞いてがっかりしたり腹を立てたりしたのを想い出す。(小沼丹「筆まめな男」)
亡き友の思い出は、小説として、随筆として、小沼作品の中で繰り返し語られている。
まるで、故人の魂を弔うかのように。
小沼丹というタイムマシーン
書名の「珈琲挽き」は、フランス土産にもらったコーヒーミルを舞台回しに使って、コーヒーの思い出を綴った作品である。
昔、「メリイ・ウィドウ」と云う映画があった。モウリス・シュヴァリエとジャネット・マクドナルド共演の映画で頗る面白かったが、このなかで、酔ったシュヴァリエに執事だったか誰かが無理に珈琲を飲ませようとする場面があった。(小沼丹「珈琲挽き」)
小沼丹は、舞台回しの使い方が絶妙に優れている作家で、「赤蜻蛉」では、信州の叔父や高崎の美人の思い出が、「自転車」では松木老人の思い出が綴られている。
「窓」は、勤務先の七階の部屋の窓から見える光景を素材としたもの。
あれはいつだったか、昔の或る雨上りの午后だったと思う。窓から外を見ていたら、不意に時計台の鐘が鳴った。空気が湿っていたせいかもしれない。鐘の音はいつになく大きく聞えた。遠く続く背の低い町には淡い夕靄がかかっていて、これもいつになくしっとり落ち着いた姿に見える。そのせいかしらん?(小沼丹「窓」)
「「──鐘の音に 胸ふたぎ」云云の昔懐かしい詩の文句を想い出したりしたが、どう云うものか、窓の記憶はそこで切れてしまって后が続かない」という文章へとつながって、短い物語は幕を閉じる。
「秋の日の/ヴィオロンの/ためいきの/身にしみて/ひたぶるに/うら悲し。/鐘のおとに/胸ふたぎ/色かへて/涙ぐむ/過ぎし日の/おもひでや」という上田敏・訳のヴェルレーヌ(「落葉」)を、さりげなく引用しているところに、作家の技を感じる。
ストリンドベリイの戯曲「稲妻」を思い出す話もいい。
どう云うものか、ここの所は妙に印象に残っていて、確か戦後間も無い頃だと思うが、オウルド・ラムプ・ライタアとか云う唄を聞いたとき、思い掛けず「稲妻」のこの場面が甦った記憶がある。或は、点燈夫が気に入っていたのかもしれない。(小沼丹「虫の声」)
文学の話題ということでは、戸川秋骨の「ケエベル先生」を読んだ話に惹かれる。
秋骨の「ケエベル先生」を読んだら、見たことも無い昔の人が、急に身近に感じられて面白かった。(略)秋骨は「先輩」と云う文章のなかで、漱石の想い出話も書いている。(小沼丹「古本市の本」)
このとき、小沼丹が読んでいたのは、現代ユウモア全集の『戸川秋骨集』だった。
何気ない文章のひとつひとつに情感があるのも、小沼丹の作品の大きな特徴だろう。
あの頃はみんな若かったが、いまはみんな変ってしまった。何でもみんな変ってしまう。無論、新宿も例外では無い。(小沼丹「昔の西口」)
「何でもみんな変ってしまう」という言葉の中に、過ぎ去った時間に対する郷愁が含まれている。
こういう例はたくさんあって、「古いランプ」という作品にも注目すべき表現があった。
近頃偶に電車で三鷹台を通るとき、窓から外を見ると、全然知らない賑やかな町が並んでいて、昔の三鷹台は、あれは夢だったのではないかしらん? そんな気がすることがある。(小沼丹「古いランプ」)
もしかすると、小沼丹という作家は、自分の中にタイムマシーンを持っていたのかもしれない。
庭で焚火をしていると、旅先で出会ったいろんな人が、思い掛けずひょっこり煙のなかに浮んで消える。格別心に留めた訳でも無いのに、何故記憶に残っていたのかしらん?(小沼丹「遠い人」)
もちろん、焚き火がなくたって、小沼丹のタイムマシーンは発動するわけだ。
所在無い儘、ぼんやり庭を見ているときとか、或は茶を飲もうと茶碗を取上げたりするとき、ひょっこり、何の関連もなく、昔旅先で見掛けた光景とか人間が眼の前に浮んで来ることがある。浮んだからと云って、格別のことは何も無い。その儘また消えてしまう。どういう訳か知らない。(小沼丹「丘の墓地」)
感傷に流されがちなノスタルジーが、「浮んだからと云って、格別のことは何も無い」「どういう訳か知らない」といった素っ気ない言葉で抑制される。
そこに、小沼丹という作家にしかない、優れた技術が感じられるのだろう。
本作『珈琲挽き』には、『椋鳥日記』で描かれたイギリス滞在のスピンオフ的なショート作品が、数多く収録されている。
ヒイスを散歩して上って来ると、この店の赤い灯が点点と見える。その灯を見ると妙に懐かしい気がしたものだが、いまも赤い灯を想い浮べるとロンドンの風物が次次と甦って懐かしい。この儘一眠りして、眼が醒めたらロンドンにいた、となると嬉しいが真逆そうは行かない。(小沼丹「ロンドンの記憶」)
『椋鳥日記』の余韻に浸りたい人には(つまり僕のような人には)絶対にお勧めで、小沼丹のイギリス滞在時の話を素材とした作品だけを集めたアンソロジーがあったらいいのに、とさえ思う。
小沼丹の随筆は、どれも短いものばかりだが、しっかりとした物語が、そこにはある。
この世界の虜になったら、簡単には抜け出せそうにない(つまり、沼だ)。
書名:珈琲挽き
著者:小沼丹
発行:2014/02/10
出版社:講談社文芸文庫


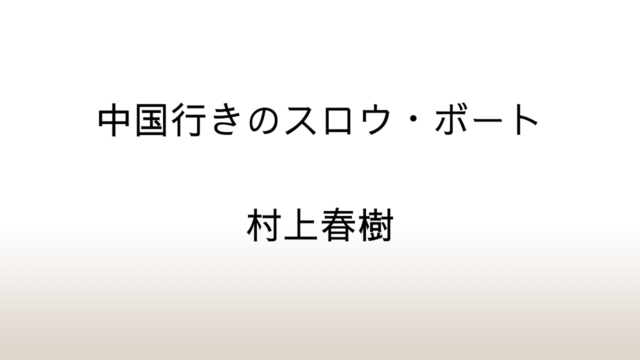
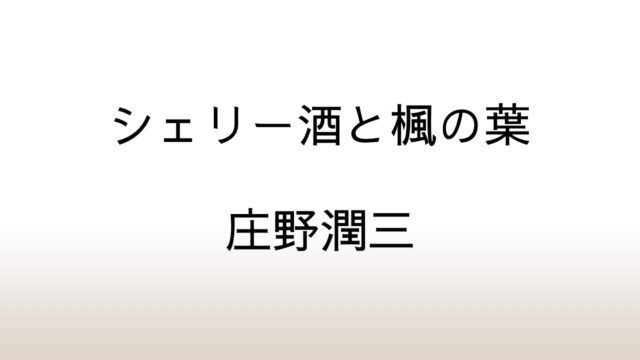

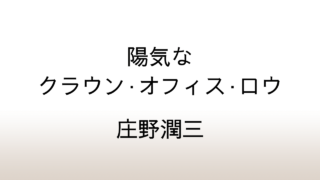
003-150x150.jpg)




