キャサリン・マンスフィールド「入江にて」読了。
本作「入江にて」は、1922年(大正11年)1月『ロンドン・マーキュリー』に発表された中篇小説である。
この年、著者は34歳だった。
原題は「At the Bay」。
マンスフィールドは、翌年の1923年(大正12年)1月、34歳で病死している。
身勝手な男たちと振り回される女たち
庄野潤三の最初の随筆集『自分の羽根』に「マンスフィールド」(1966)という一篇がある。
大阪外語時代、友だちに勧められて初めて読んだマンスフィールドの作品が、研究社の小英文学叢書に入っている「湾頭小景(At the Bay)」だったという。
やがて、マンスフィールドの作品が好きになったことについて、庄野さんは「多分、私は散文で書かれた詩、というような印象を受けたのかも知れない」と、当時を回想している。
本作「入江にて」は、夏の別荘地であるクレッセント湾で過ごす<バーネル一家>の様子を、一日の流れに沿って断片的に描いた物語である。
特定の主人公はなく、時間と場面の転換によって、登場人物は目まぐるしく変わっていく。
印象的なのは、こうした家族の様子が、様々な対立の観点から描かれていることである。
マイペースに生きる男たちと、身勝手な男たちに振り回される女たち。
年老いた女と若く美しい女。
心の闇を抱える大人たちと今を生きることに精一杯の子どもたち。
そして、そんな子どもたちでさえ、男と女は、しっかりと対立という構図の中で描かれていく。
このとき、読者は、この作品の著者が、まだ若い(アラサー)の女性であったことを思い出すのだ。
「わたしはその時々を楽しんでる綺麗な娘を崇拝するわ」ミセス・ハリー・ケンバーは言った。「そうしちゃいけない理由なんてないのよ。楽しむ機会があったら、見逃しちゃいけない」(キャサリン・マンスフィールド「入江にて」西崎憲・訳)
悪妻として近所では敬遠されている<ミセス・ハリー・ケンバー>の魅力に、若くて美しい<ベリル>は惹かれていく。
ベリルは、現状の平穏な生活に満足できていない。
しかし、その夜遅く、夫人の夫である<ハリー・ケンバー>に口説かれたとき、ベリルは、彼の要求に応えようとしない。
「冷たく、かわいい女、冷たく、かわいい女」声は憎しみに満ちていた。けれど、ベリルは強かった。後ずさりし、屈み、体を捻り、その腕から逃れた。「あなたは下劣よ、下劣」彼女は言った。(キャサリン・マンスフィールド「入江にて」西崎憲・訳)
確かに、ベリルは現状の平穏に満足していなかったかもしれない。
しかし、それでも、ベリルは、身勝手な男に体を任せることを拒んだのだ。
ミセス・ハリー・ケンバーは、夫以外の男たちと遊び歩くことで女性の強さを証明してみせたかもしれないが、ベリルは違った。
ベリルは、男の指図に従わないことで、女性の強さを示してみせようとしたのである。
様々な世代の女性たちが抱える心の闇
若い母親の<リンダ・バーネル>は、自分が母親という存在であることに苦悩している。
夫である<スタンリー・バーネル>との結婚生活に疲弊し、その上、彼女は小さな赤ん坊の母親であるという自分自身に疲弊していた。
「なぜ、おまえはずっと笑ってるの?」彼女は厳しい声で言った。「わたしが心のなかでなにを思っているか知ったら、きっとそんなふうには笑わないわよ」(キャサリン・マンスフィールド「入江にて」西崎憲・訳)
あるいは、これは育児ノイローゼなのだろうか。
それとも、家庭からの独立を願う女性の祈りだったのだろうか。
心の闇を抱えているのは、ベリルやリンダだけではない。
年老いた祖母<ミセス・フェアフィールド>は、亡くなった<ウイリアムおじさん>を思い出しながら死と向かい合い、お手伝いの<アリス>は、台所からの自由という葛藤を抱えている。
様々な世代の女性たちの苦悩が、美しい夏の海を背景に描かれていく。
夏の季節だけ訪れる人たちの家はみんな緑色のブラインドを下ろしていた。ヴェランダや囲い地の柵や庭の柵のうえにくたびれ果てたような水着と梳毛の縞のタオルが見える。家々の裏手の窓の窓枠には砂浜用のゴムの靴や岩の塊やバケツ、パワ貝の殻がいくつか干してあった。(キャサリン・マンスフィールド「入江にて」西崎憲・訳)
あるいは、我々の人生というのは、こんな夏の一日のようなものなのかもしれない。
作品名:入江にて
著者:キャサリン・マンスフィールド
訳者:西崎憲
書名:郊外のフェアリーテール キャサリン・マンスフィールド短篇集
(ブックスならんですわる02)
発行:2022/04/03
出版社:亜紀書房
(2024/07/26 20:34:28時点 Amazon調べ-詳細)

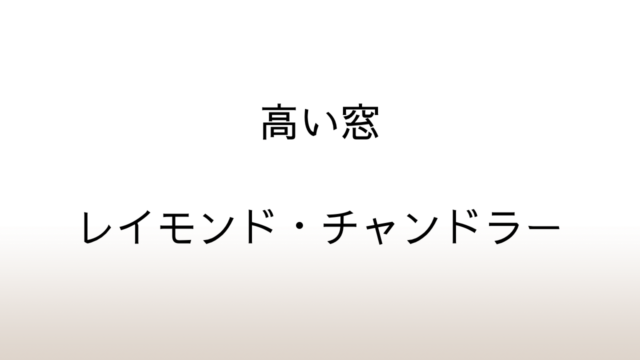
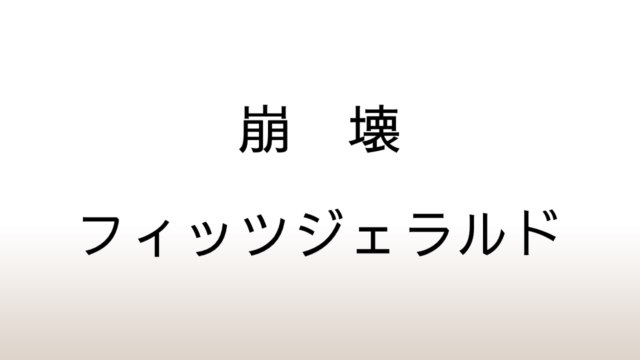
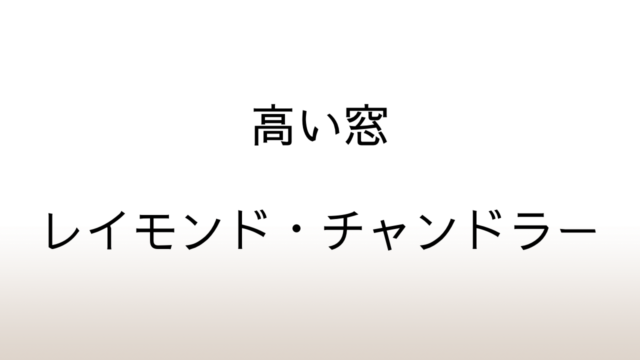
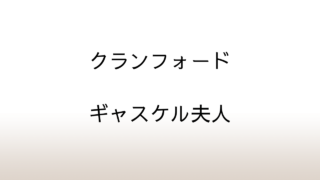

003-150x150.jpg)




