スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」読了。
本作「スタンド・バイ・ミー」は、1982年(昭和57年)8月にヴァイキング・プレスから刊行された作品集『恐怖の四季』に収録された中篇小説である。
原題は「The Body」。
この年、著者は35歳だった。
センチメンタルな少年時代
スティーヴン・キングの「スタンド・バイ・ミー」は、原作小説よりも、リヴァー・フェニックス主演の80年代映画として有名な作品だ。
映画タイトルとなった「Stand by Me」は、主人公ゴーディ(ゴードン・ラチャンス)と親友クリスとの友情に由来している。
わたしたちは深い水の中で、たがいにしがみついていたのだ。(略)もしクリスが溺れたら、わたしの一部も彼とともに溺れてしまうだろう。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
二人を固く結び付けているのは、「父親の不在」という不幸な家庭環境だ。
ゴーディの父親にとって、次男ゴーディは「見えない人間」であり(彼の父親は死んだ長男を溺愛していた)、クリスの父親にとって、大学進学を希望するクリスは、目障りな存在でしかなかった(彼の父親はただの飲んだくれだった)。
「父親の不在」という不幸な家庭環境を、二人は互いに励まし合って克服しようとする(二人は互いに「とうちゃん」と呼び合っている)。
この二人の絆が、「Stand by Me」という短いフレーズによって象徴されているのだろう(そして「Stand by Me」は、ベン・E・キングの名曲のタイトルでもある)。
本作「スタンド・バイ・ミー」は、作家になったゴーディが綴る、センチメンタルな回想記である。
随所に登場する60年代カルチャーが、主人公の感傷を盛り上げる。
ザ・フリートウッズが歌う『カム・ソフトリイ・トゥ・ミー』とか、ロビン・リュークが歌う『スージー・ダーリン』、それにリトル・アンソニーのボーカルの『アイ・ラン・オール・ザ・ウェイ・ホーム』。これはみんな一九六〇年の夏のヒット曲ではなかったか?(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
そして、センチメンタルな皮を一枚剝いだところに、少年たちの複雑な家庭環境と、それによってもたらされる彼らの不幸な人生とが描かれている。
まるで、ロルフ・ハリスが歌った「TIE ME KANGAROO DOWN SPORT」(悲しきカンガルー)のように。
チコは古い、珍しい歌の一行を思い出している。”おれが撃つまで遊びつづけろよ、相棒……おまえの仲間たちと”。ロルフ・ハリスの『タイ・ミー・カンガルー・ダウン』だ。チコはにやりと笑う。かつてジョニイがよくうたっていた歌だ。こういうふうに終わる。”あいつが死んだら皮をなめすさ、クライド、そいつを小屋につるすんだ”。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
感傷的な小説だけれど、最も感傷的な部分は、作家になったゴーディの作品『スタッド・シティ』からの引用という形で描かれている。
大人になったゴーディが書くべき作品(つまり『スタンド・バイ・ミー』)としては、書くことができなかったからだ。
だから、劇中劇である『スタッド・シティ』では、主人公の少年時代が、生々しく(そしてひたすらメロドラマティックに)再現されることになる。
『イージー・ライダー』と死んだ兄貴と父親に対する激しすぎる嫌悪感と。
「スタンド・バイ・ミー」で伝えるべきメッセージは、作家ゴードン・ラチャンスの発表した作品の中にこそ、顕著なのかもしれない。
そういう意味で、ゴーディのもう一つの作品『でぶっ尻ホーガンの復讐』も重要な意味を持っている。
「うんにゃ、おもしろかったぜ」テディは言った。「最後までちゃんと聞いたら、おもしろかった。反吐ってのは、ほんと、クールだったな」「うん、クールで、まったく汚らしい」バーンもうなずいた。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
いじめられっ子ホーガンが、グレトナ・パイ食い大会(パイ食い競争)で壮絶な反吐(ヘド)を吐くことによって、街の人々に復讐する物語は、「反吐が出そうなくらいにくだらない社会」を、強烈に批判している。
「反吐が出そうな」社会に対して、ゴーディは、文字どおり「反吐を吐きかけてやった」のだ。
この劇中劇は、一緒に旅をするテディとバーンの二人が、物語を理解する想像力に欠けているというエピソードへと繋がっていく。
「センチメンタルな少年時代」という思い出の皮を一枚剥いだところにあるのは、そんな少年たちの未来(末路)だ。
キャッスル・リバーの流れの底に消えた仲間たち
誰が食料品店へ買い出しに行くかを決めるため、少年たちはコインを投げる。
とつぜん、わたしは恐ろしくなった。太陽に影がさしたような気持だった。彼らは依然としてグーチャーのままなのだ。二度目は、悪い運が彼ら三人だけを指したかのようだった。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
一度目のコイン投げは、全員が「裏」だった(グーチャー)。
グーチャーは、非常に運が悪いことを意味しており、臆病なバーンは「グーチャーってのは、本当によくないんだ」と怯える。
少年たちの未来が、ここで一つ示唆されている。
なぜなら、「コインを投げた四人のうち、実際に生き残っているのは、たった一人しかいない」からだ(それが、34歳で小説を書いている主人公のゴーディだ)。
ささいな出来事が、時間を経るうちに、だんだん大きな反響を呼ぶものだとしたら、そう、わたしたちがあっさり行動を起こし、ヒッチハイクでさっさとハーロウに行っていたら、彼ら三人は今日もまだ生きていただろう。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
すべての結果には、原因がある。
仲間たちの早すぎる死は、あの死体探しの旅の時、既に決まっていたのだと、主人公は考えていたのかもしれない。
もしかすると、「死体探しの旅」という、この物語の大きなテーマそのものが、少年たちの未来を暗示していたのではないか。
まるで、死ぬために生き続けているかのような、彼らの人生を示唆するかのように。
そして、彼らの不幸は、彼らが生まれた家庭環境から既に始まっていた。
最近の言葉で言う「親ガチャ」が、彼らの運命を支配していたとも言える。
運命から逃れることのできた二人が、ゴーディとクリスの二人であり、そのクリスでさえ、最後には支配された運命から逃れることができなかった。
グーチャーは、その一つの象徴だったと言えるだろう(少なくとも主人公ゴーディにとっては)。
親ガチャという運命から逃れることを、クリスは早くから意識していた。
「おまえの友達はおまえの足を引っぱってるよ、ゴーディ。おまえにはわからないのか?」クリスはテディとバーンを指さした。(略)「おまえの友達はおまえの足を引っぱってる。溺れかけた者が、おまえの足にしがみつくみたいに。おまえは彼らを救えない。いっしょに溺れるだけだ」(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
死体探しの旅の途中で、少年たちはキャッスル・リバーに架かるトレッスルを超える。
このキャッスル・リバーは、まるで主人公の人生そのもののような川だ。
いくつものトレッスルを越えるようにして、少年ゴーディは大人になった。
作品の最後の文章に、すべてが綴られている。
左手を見ると、今はもう川幅が狭くなっているが、少しは水がきれいになったキャッスル・リバーが、キャッスル・ロックとハーロウを結ぶ橋の下を流れているのが見えた。上流のトレッスルはなくなったが、川はまだ流れている。そしてわたしもまた、そうだ。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
「川はまだ流れている。そしてわたしもまた、そうだ」とあるように、ゴーディは、まだ生きて、小説を書いている。
しかし、少年時代に仲間たちと越えたトレッスルは、もうない。
足を引っぱる仲間たちが、キャッスル・リバーの流れの底へと消えてしまったように。
友人というものは、レストランの皿洗いと同じく、ひとりの人間の一生に入りこんできたり、出ていったりする。そこにお気づきになったことはないだろうか? しかし、水中の死人たちが無情にもわたしの足を引っぱっていた、あの夢のことを思うと、そうなるべくしてなったのだという気がする。ある者は溺れてしまう、それだけのことだ。公平ではないが、しかたがないのだ。ある者は溺れてしまう。(スティーヴン・キング「スタンド・バイ・ミー」山田順子・訳)
グーチャー、死体探しの旅、キャッスル・リバーの流れ。
「あの夢のことを思うと、そうなるべくしてなったのだという気がする。ある者は溺れてしまう、それだけのことだ。公平ではないが、しかたがないのだ。ある者は溺れてしまう」──この小説で、僕のいちばん好きな文章が、ここにある。
映画のように、爽やかでノスタルジックなだけの作品ではないかもしれない。
映画を観た後で原作小説を読むと、がっかりしてしまうこともあるだろう(それは、特別に珍しいことではないし、その逆もまた同じだ)。
しかし、映画では再現することのできないものが、文学にはある。
作家ゴードン・ラチャンスの信念は、「なににもまして重要だというものごとは、なににもまして口に出して言いにくいものだ」だった(作品中で何度も繰り返される)。
だからこそ、読者は、文脈の間に隠れているものを探さなければならない。
作者は、何を伝えたかったのだろうかということを見つけるために。
本作『スタンド・バイ・ミー』は、そんな読書の楽しみを思い出させてくれる、実に素晴らしい作品だと言えるだろう。
作品名:スタンド・バイ・ミー──秋の目覚め──
著者:スティーヴン・キング
訳者:山田順子
書名:スタンド・バイ・ミー 恐怖の四季秋冬編
発行:1987/03/25
出版社:新潮文庫

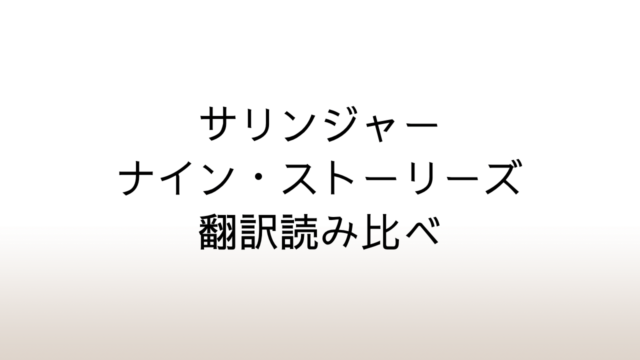
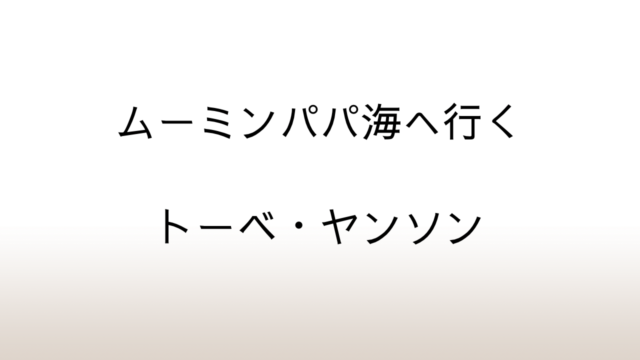
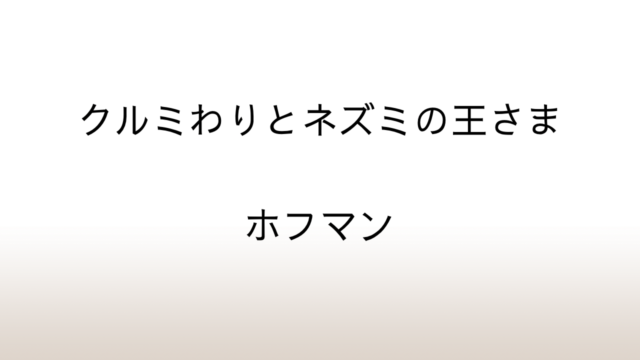
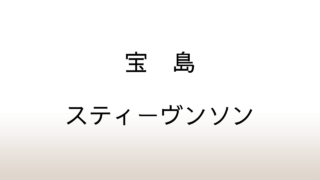
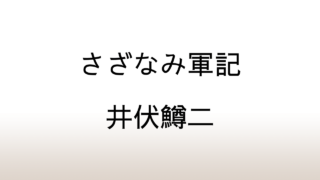
003-150x150.jpg)




