庄野潤三「蒼天」読了。
本作「蒼天」は、「新潮」昭和39年6月号に掲載された短篇小説である。
作品集では『丘の明り』(1967、筑摩書房)に収録された。
「この家から、二度も続いて葬式が出せるか」
主人公の「蓬田」は、高校一年を終わったばかりの娘「和子」と一緒に、彼の生家のある「この町」を訪れている。
蓬田の家族がこの町を離れて東京へ移ったのは、ちょうど十年前であった。
懐かしい病院の前で蓬田は、幼い和子を抱きかかえて必死に走った日の思い出を、和子に話して聞かせる。
しかし、彼の頭の中にあったのは、病院まで走った日の(そのときは一人きりで)、もうひとつの思い出のことだった。
かつて我が家だった家の前で、蓬田は「なつかしいという気持ではなくて、足早にその前を通り過ぎたい。そばにいる娘に対して、そういう気持になる」と考えている。
自分とそっくり同じ身体つきで(もっとあの頃は痩せていた)、顔も同じで、ただ皮膚や髪だけがずっと若くて、そのために別人のように見えるかもしれない男が、この二階屋に住んでいた。そうして、その男と一緒に若い妻と小さな女の子がいた。(庄野潤三「蒼天」)
「あれ」は、長兄が亡くなって一月後のことだった。
「この家から、二度も続いて葬式が出せるか」「どう云ってみんなに話せるか。あれだけ大勢の人に来て貰って、迷惑をかけておいて、また葬式ですとわしの口から云えるか」と、父は言った。
「そんなこと云ったって」「いま、生きるか死ぬかの境目にいるのに、そんなことを云ったって」と思いながら、蓬田は涙と一緒に飯を喉の奥に流し込んだ。
何が起こったのかは書かれていない。
蓬田の妻は、ただ、眠り続けた布団の湯たんぽで火傷をした足を、引きずっているだけだ。
ヒントは折々書かれている。
「母がひとり残ってからは、もうあんなことはやらなかった」
結局、彼女は生き返って、和子と一緒に動物園へ出かけることができるようにまで回復する。
まだ少しびっこをひく癖は直らなかったが。
墓石の上の平らなところに水がたまって、春の空を写した。
物語のテーマは「生と死の境目」だろう。
ひきつけをおこし、蓬田に抱えられて病院まで行く途中に正気を取り戻した幼い日の和子。
おそらくは自殺未遂をしたものと思われる長い眠りから生き返った若き日の妻。
蓬田の家族は奇跡的に「生と死の境目」から生還し、現代の東京で生きている。
「生と死の境目」を象徴するアイテムが、かつて急死した長兄が眠っている墓である。
黒い、なめらかな墓石の上から水を何度も注ぎかけていると、「もうよい。そんなに水ばかりかけるな。まわりが水浸しになってしまう」そう云う父の声が聞えて来そうであった。墓石の上の平らなところに水がたまって、春の空を写した。「ほら、空が写っている」和子は覗いてみた。(庄野潤三「蒼天」)
和子の覗いた墓石の上の水に写った空が、おそらくは作品タイトルでもある「蒼天」だろう。
墓石のいちばん端に長兄の名前と亡くなった年月が刻まれていて、その隣に父の名が、次に母の名が並んでいる。
父が亡くなったとき、母は、父の隣に自分の名前を彫らせて朱い色を塗った。
生と死の境目で、母は生きていくことを決意していたのかもしれない。
自殺未遂をした若き日の妻を素材としているという意味において、この小説は「静物」と対を成す作品と言うことができるかもしれない。
もっとも、あまりに高尚で文学的な「静物」に比べて、「蒼天」はずっと素直でピュアな小説として描かれている。
どちらが好きかと言えば、僕はきっと「蒼天」の方がずっと好きだと思う。
書名:丘の明り
著者:庄野潤三
発行:1975/4/25(新装版)
出版社:新潮社


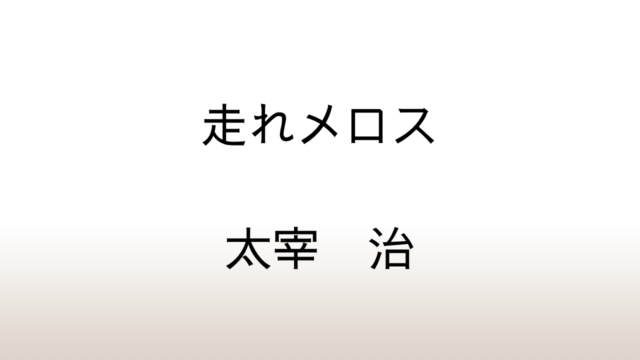

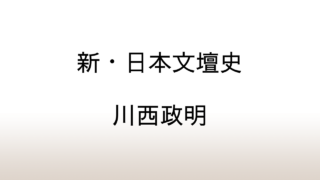
003-150x150.jpg)




