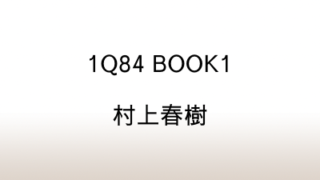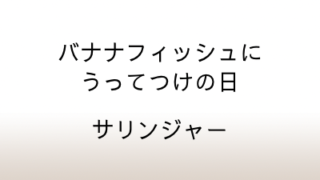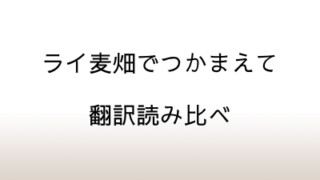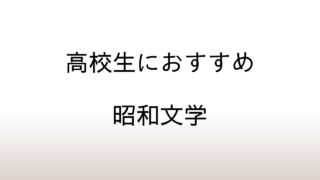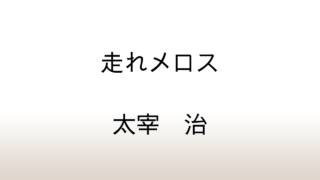庄野潤三の長篇小説「屋根」読了。
初出は「新潮」で、「屋根」が昭和45年8月号、「父と子」が昭和45年12月号、「村の道」が昭和46年7月号だが、単行本収録時は、すべてを通して「屋根」というひとつの作品となっており、「父と子」や「村の道」といった題名は残っていない。
当時の帯文には「庄野順三最新連作長編小説」「親子二代にわたる父と子の生活上の葛藤といたわり、寄り添うようにして暮す夫婦の慈しみあいを通して、平凡な一家眷族の姿を心あたたまる筆致で描く」とある。
庄野さんは、あとがきの中で「『屋根』は、牛に惹かれる私の気持を、このすぐれた家畜に寄り添うようにして暮している親子、夫婦の上に移したところから始まる小説といえばいいだろうか」と綴っている。
作風としては、昭和40年代の庄野さんが積極的に取り組んだ「聞き書き小説」である。
「忠夫君」は、物語の語り手である「茂木」の一家が利用する肉屋さんの主人で、22歳の青年だ。
茂木は忠夫君に案内されて市場を見学させてもらうようになり、肉屋さんのことや忠夫君の家庭内の事情などを詳しく知ることになる(忠夫君には23歳の妻と赤ん坊がいる)。
働き者の忠夫君の父は、田舎で家畜商を営んでいて、忠夫君も「四年たったら、田舎へ帰らないといけない」と言っている。
やがて、茂木は忠夫君の実家へ泊りがけで出かけるようになり、「忠夫君のお父さん」から、馬喰(ばくろう。かつては家畜商のことをこう呼んだ)について、たくさんの話を聞かせてもらうようになる。
物語は、忠夫君やお父さんの言葉によって、血筋の話から、馬喰の生き様まで幅広く広がりを見せていく中で、親子や家族のつながりを浮き彫りにしていくのだが、庄野さんの聞き書き小説の特徴は、語り手による補足的な解説を加えることなく、登場人物の会話によって細部を明らかにしていく手法にある。
帯に書かれた庄野潤三作品を見ると、「浮き灯台」や「流れ藻」といった聞き書き小説が並んでいて、この時期の庄野さんの文学的関心が、戦後の日本社会の中でたくましく生きる職業の人たちに向いていたことが分かる。
本作「屋根」に登場する忠夫君やお父さんにも、やんちゃで野生的なエピソードが随所で登場しており、庄野さんは、サラリーマンではない職業の人たちの暮らしや家庭の中に、人間らしい本質的な魅力を見出していたのだろう。
別に手土産の菓子の箱は妻が買ってあったが、出かける前に巻ずしをつくった。
別に手土産の菓子の箱は妻が買ってあったが、出かける前に巻ずしをつくった。先に夕食を済ませて行くには、時間が少し早い。それに、かりにこちらは食べる時間があっても。忠夫君の方はそうはゆかないだろう。おそらく夕食はいつも店がしまってからではないか。(略)それなら、どっちになってもいいように、弁当を持って行ったらいい。途中でおなかがすいたら、どこかで車をとめて二人で食べてもいい。向うへ着いてから、食べてもいい。夕食を用意してくれてある場合でも、巻ずしなら何とでもなる。
庄野さんの作品に「巻ずし」が登場すると、そのことが非常に気になってしまう。
話の筋は別にして、このおいしそうな巻ずしがどうなるのか、すごく気になる。
物語の中で、この巻ずしは忠夫君からお母さんへ手渡されるが、お母さんは「それならここで頂きましょう」と云って、小皿に取ってひと口食べて「おいしいです」と言って、お父さんにも勧める。
お母さんは三つか四つか食べて、お父さんも少し口に入れた。
食事を終えて風呂から上がった茂木は、蒲団の中で巻ずしのことを思い出し、薄暗がりの中で食べた。
さらに翌日、巻ずしが深夜の仕事に集まった人たちに振る舞われ、みんな「これはおいしいすしだ」と言って、醬油をつけながら全部食べてしまったということを、茂木はお母さんの話から知るのだが、ストーリーとは直接的な(というより伏線的にも)関係のない巻ずしのことが、ひたすら丁寧に描かれているところは、いかにも庄野さんらしいこだわりである。
朝御飯は、味噌汁と山盛りにした納豆の上に葱を納豆が見えないくらいふりかけた皿と海苔と目玉焼にキャベツ、白菜の漬物である。
朝御飯は、味噌汁と山盛りにした納豆の上に葱を納豆が見えないくらいふりかけた皿と海苔と目玉焼にキャベツ、白菜の漬物である。茂木が食べかけようとすると、お母さんがもう一つお皿を運んで来た。「これ、いま揚げたところですから、上って下さい。うちのメンチ、肉がいっぱい入っているから」メンチ・カツの大きいのが二つ、皿からはみ出しそうになっている。それに包丁を入れてくれた。(これは茂木は、一枚だけ食べた)味噌汁には菜っ葉が入っている。白味噌ではないが、いくらか白味噌に近いような味の味噌であった。茂木は御飯をお代りしたあと、お母さんにもう一杯上って下さいと云われて、味噌汁もお代りした。
この作品の中で特に好きな場面が、茂木が忠夫君の実家に初めて泊まった翌朝の朝食風景である。
これも、物語のストーリーとはほとんど関係のない場面ではあるが、庄野文学では、こうした家庭的な日常風景の積み重ねが、作品全体の印象を左右することが少なくない。
ストーリーそのものに特別の展開があるわけではないので、こうした脇の情報をいかに積み重ねていくかということが、庄野さんの作品では重要になっているのかもしれない。
「美味しかった」とは書かれていない代わりに、「茂木は御飯をお代りしたあと、お母さんにもう一杯上って下さいと云われて、味噌汁もお代りした」と書かれていて、その朝食に茂木が非常に満たされていることが伝わってくるように仕掛けられている。
食事の準備をするお母さんと茂木との間で交わされる「朝はぜんぜん飲まないのけ、旦那さん」「ええ、頂きません」「そうけ」という何気ない会話も、忠夫君の家庭の風景を映し出しているようで良い場面である。
庄野さんは特別のメニューではない食事を、本当に美味しそうに描くことのできる小説家だった。
書名:屋根
著者:庄野潤三
発行:1971/11/10
出版社:新潮社

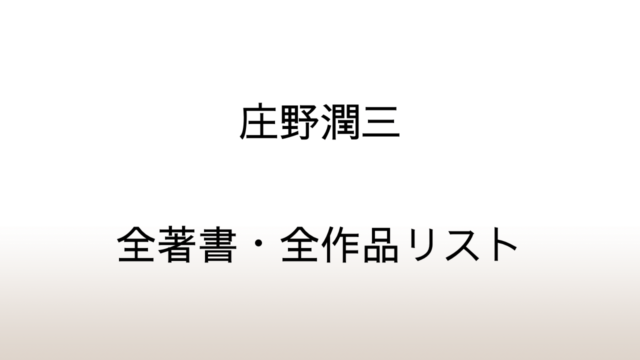
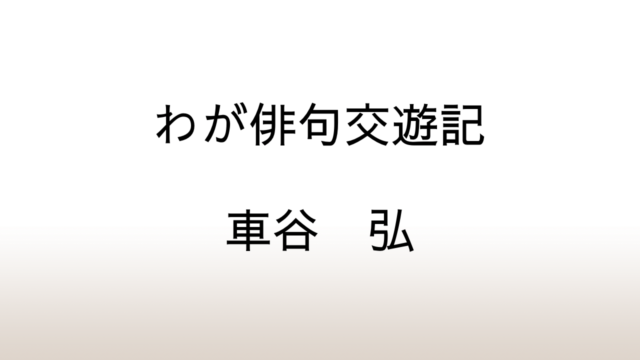
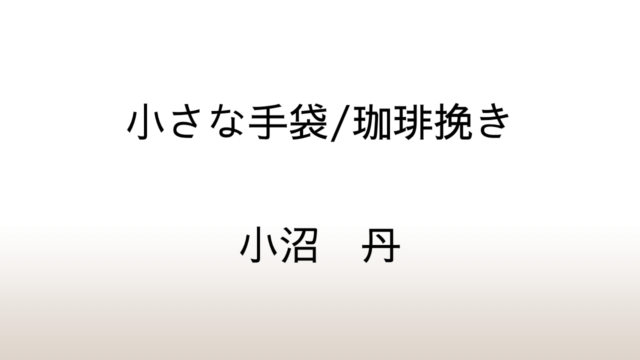
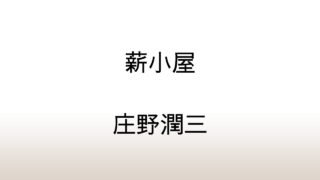
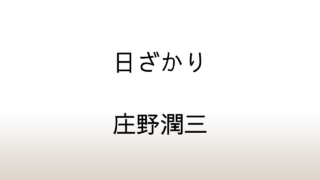
003-150x150.jpg)