庄野潤三「せきれい」読了。
本作「せきれい」は、1997年(平成9年)1月から12月まで『文学界』に連載された長篇小説である。
この年、著者は76歳だった。
単行本は、1998年(平成10年)1月に文藝春秋から刊行されている。
人生のお返し的な「よろこび」
本作「せきれい」は、いわゆる「夫婦の晩年シリーズ」として、『貝がらと海の音』『ピアノの音』に続く3作目の作品である。
作品中で、庄野さんが76歳の誕生日を迎えていることから、この物語は、1996年(平成8年)秋から1997年(平成9年)春にかけての庄野一家の日常生活を題材にしたものであることが分かる。
ちなみに、長女夏子49歳、次男の長女フーちゃんは小学4年生。
「夫婦の晩年シリーズ」の一つとして、この物語も、日記のような随筆のような、およそ小説らしくない構成で、細々とした身辺雑記が綴られている。
そして、綴られている内容は、庭に咲いた花が「きれいだ」とか、庭に野鳥がやってきて「うれしい」とか、アップルパイを食べて「おいしいなあ」、ハーモニカで唱歌を演奏して「いい歌だなあ」、近所のスーパーへ買い物に行って「よろこぶ」、お湯の沸く音が「快い」、とにかく、老夫婦が感じた(かなり些細な)「楽しいこと(ハッピーなこと)」がほとんど。
だから、この小説は「老夫婦の平穏な暮らしを描く」みたいな表現で紹介されることが多い。
それでは、老夫婦の平穏な暮らしを描いた物語が、どうしてこんなに支持を得たのだろうか。
僕は、庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」を何度も何度も繰り返し読むうちに、これらの作品は、実は平穏なだけの作品ではないと考えるようになった。
その理由のひとつは、作品タイトル「せきれい」と関係がある。
ピアノのおけいこから帰った妻に、「いかがでした?」と訊く。「せきれい、上げて下さった」「コングラチュレイションズ(おめでとう)」いつまでかかるかと思った「せきれい」が無事に上ったとは、めでたい。(庄野潤三「せきれい」)
「せきれい」は、ブルグミュラーの練習曲で、ピアノ教室に通っている妻は、この曲に手こずっている。
何度も不合格になって、とうとう合格したとき、庄野さんは妻に「コングラチュレイションズ(おめでとう)」と祝福する。
ここに描かれている「よろこび」は、偶然に得られた「よろこび」ではなく、妻の努力によって獲得した「よろこび」である。
同じような例が、もうひとつある。
冬至で今夜は柚子湯。はじめて庭で実った柚子で「自前の柚子湯だな」といって、よろこぶ。(略)いつもは八百清で買った柚子を浮べるのだが、今年は自前の柚子である。うれしい。それも庭に植えてから二十五年ぶりにはじめて実った柚子だから、めでたい。(庄野潤三「せきれい」)
柚子は「柿生のお不動さんのだるま市」で買ったものだが、何年経っても花が咲かず、夫婦はもうあきらめていたところだった。
あきらめていた花が咲いて、柚子が実り、自前の柚子湯に入ることができるのだから、こんなにうれしいことはないだろう。
「夫婦の晩年シリーズ」で描かれている老夫婦の「よろこび」は、時間によって培われた「よろこび」である。
それは、長女のアップルパイが「おいしい」という話ひとつとっても同様で、良好な家族関係を築いてきた、その先に「長女の作ったアップルパイがおいしい」という結果がある。
庭に咲いた花も、野鳥が集まる庭木も、庄野夫妻の手によって、長い年月をかけて育てられてきたものだ。
庄野夫妻の「よろこび」は、一見些細で、つまらないもののように見えても、実は「人生の結実」とも言うべき、重厚な「よろこび」という本質を持っている。
今日から、これを真似しようと思っても、実は簡単には真似することのできない時間の重みがある。
もちろん、庄野さんは、人生の楽しいところ、良いところを見て、作品に描いてきた作家だから、いつの時代の作品にも「よろこび」があった。
しかし、「夫婦の晩年シリーズ」で描かれている老夫婦の「よろこび」の本質は、まっとうな人生を送ってきた者だけが得ることのできる、人生のお返し的な「よろこび」に近い。
「不愉快なことを書かない」というコンセプトの前に、「愉快なことが多い」という老夫婦の日常生活にこそ、我々は注目すべきではないだろうか。
生きているよろこび
理由のもうひとつは、盟友・小沼丹の死に象徴されている。
夕方、吉岡達夫から電話かかり、「小沼が昨日のお昼、十二時半に病院で肺炎で亡くなった。家族だけで葬儀をすませて、小沼はもうお骨になって家に帰った。さっき、奥さんから電話があった」という。(庄野潤三「せきれい」)
文壇で、特に親交の深かった小沼丹の死は、庄野さんに大きな衝撃を与え、以降「夫婦の晩年シリーズ」では、小沼丹の思い出が繰り返し紹介される。
考えてみると、「夫婦の晩年シリーズ」では、死者(故人)の話題が少なくない。
三年前に亡くなった次兄英二(二十八日)と戦後早くに亡くなった長兄鷗一(十九日)のお命日を合せて、妻はかきまぜを作る。かきまぜは父母の郷里の阿波徳島風まぜずし。(庄野潤三「せきれい」)
「夫婦の晩年シリーズ」でおなじみとなった郷土料理「かきまぜ」も、亡くなった家族にお供えされることが多い。
恒例の大阪旅行も同様である。
春と秋にお墓参りに大阪へ行くのが、私たち夫婦の晩年の大きな楽しみとなっている。淀屋橋の橋の上から下を流れる土佐堀川にアイサツするのも、その楽しみのうちの一つである。父も母も早くに亡くなり、二人も兄もいなくなったが、こうして大阪へお墓参りに帰って来るのが何よりうれしい。(庄野潤三「せきれい」)
『井伏鱒二全集』が配本されたときに語られる井伏鱒二の思い出も、死者を偲ぶエピソードの一つと言っていいだろう。
「よろこび」の裏側に死者(故人)がいる。
そこに、「夫婦の晩年シリーズ」の特徴の一つがある。
死者の話ではないが、庄野さんが重病をしたときの話というのも、同じような意味を持っているだろう。
石川先生のテレビ出演の話を聞いて、長女は、私が救急車で運び込まれた溝口の病院から梶ヶ谷の虎の門病院分院へ移った最初の日の出来事を話す。お昼ご飯の時間になった。前の病院では、食事は全部、家族が食べさせていた。虎の門では、自分ひとりで食べなくてはいけない。(庄野潤三「せきれい」)
こっそり病室を覗いていた長女が、庄野さんがようやく箸を持って食べ始めたことを伝えたとき、妻は泣きだしたという。
こうした闘病の記憶や、死者の思い出の裏側にあるものは、「健康であることのよろこび」であり、「生きていることのよろこび」である。
本を読んで「楽しい」と感じることも、うぐいすが鳴いて「うれしい」と感じることも、ロールキャベツを食べて「おいしい」と感じることも、究極的には(つまり本質的には)「健康であることのよろこび」であり、「生きているよろこび」だ。
年寄りだから当たり前だと言われるかもしれないが、当たり前で普遍的な「よろこび」だったからこそ、夫婦の晩年シリーズは、多くの支持者を得たのではなかったか。
それは、平穏に生きたいと願う、庶民の祈りである。
夫婦の晩年シリーズは、当時、若い女性に人気となって「静かなブーム」と呼ばれた。
平穏な老後は、老後になってから得られるものではないことを(つまり、若いうちからの人生が重要であることを)、若い世代は感覚的に読み取っていたのではないだろうか。
人間が「生きているよろこび」を尊び、「平穏に生きたいと願う気持ち」を抱いているうちは、庄野さんの「夫婦の晩年シリーズ」は廃れることがないような気がする。
庄野さんは、決して作品中に「生きていてよかった」とは書かない。
「生きているよろこび」を文学によって伝えることが、この物語の大きなテーマだからだ。
そして、こうした作品は、どんな作家にも書けるというものではない。
家族を敬い、人生を大切に生きてきた老作家だからこそ描くことのできる物語がある。
経験に裏打ちされた文学というよりも、これは、人生そのものによって培われた文学なのだ。
作品名:せきれい
著者:庄野潤三
発行:2005/01/10
出版社:文春文庫

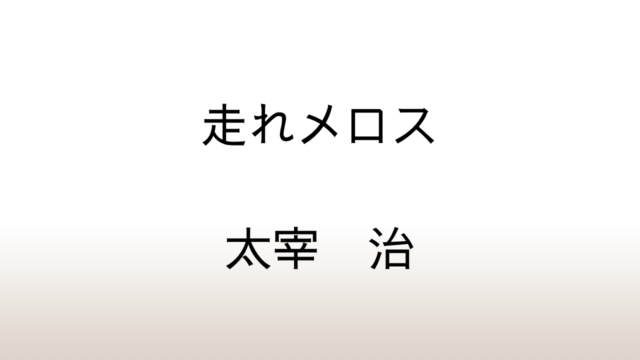
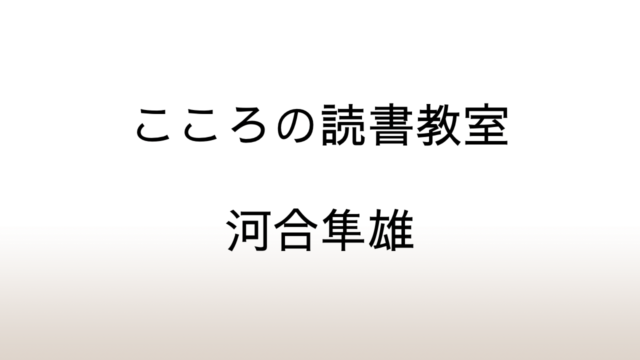



003-150x150.jpg)




